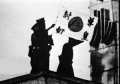
・・・・たしかに
二・二六事件の挫折によって、何か偉大な神が死んだのだった。
当時十一歳の少年であった私には、それはおぼろげに感じられただけだったが、
二十歳の多感な年齢に敗戦を際会したとき、
私はその折の神の死の恐ろしい残酷な実感が、十一歳の少年時代に直感したものと、
どこかで密接につながっているらしいのを感じた。
それがどうつながっているのか、私には久しくわからなかったが、
「 十日の菊 」 や 「 憂国 」 を私に書かせた衝動のうちに、
その黒い影はちらりと姿を現わし、又、定からぬ形のまま消えて行った。
それを二・二六事件の陰画とすれば、
少年時代から私のうちに育まれた陽画は、蹶起将校たちの英雄的形姿であった。
その純一無垢、その果敢、その若さ、その死、すべてが神話的英雄の原型に叶っており、
かれらの挫折と死とが、かれらを言葉の真の意味におけるヒーローにしていた。
十一歳のその日の朝、何も知らずに登校した私は、級友のある子爵の息子が、
「 総理が殺されたんだって 」 と 声をひそめて囁くのをきいた。
私は、「 ソーリって何だ 」 とききかえし、総理大臣のことだと教えられた。
齋藤内府の殺された私邸も学校のすぐ裏手にあり、その朝の学習院初等科は、
いわば地理的にも精神的にも 「 狙われた人たち 」のごく近くにいて、
不吉な不安に充たされていた。
授業第一時間目に、先生は休校を宣し、
「 学校からのかえり道で、いかなることに会おうとも、学習院学生たる矜りを忘れてはなりません 」
という訓示をした。
しかし私たちは何事も出会わなかった。
その雪の日、少年たちは取り残され、閑却され、無視されていた。
少年たちが参加すべきどんな行為もなく、
大人たちに護られて、ただ遠い血と哨煙の匂いに、感じ易い鼻をぴくつかせていた。
悲劇の起こった邸の庭の、一匹の仔犬のように。
少年たちはかくてその不如意な年齢によって、事件から完全に拒まれていた。
拒まれていたことが、却ってわれわれに、その宴会の壮麗さをこの世ならぬものに想像させ、
その悲劇の客人たちを、異常に美しく空想させたのかもしれない。
磯部浅一氏の 「 行動記 」 は、蹶起の瞬間を次のように述べている。
「 村中、香田、余等の参加する丹生部隊は、午前四時二十分出発して、
栗原部隊の後尾より赤坂溜池を経て首相官邸の坂を上る。
其の時俄然、官邸内に数発の銃声をきく、いよいよ始まった。
秋季演習の聯隊対抗の第一遭遇戦のトッ始めの感じだ。
勇躍する、歓喜する、感慨たとえんにものなしだ。
( 同志諸君、余の筆ではこの時の感じはとても表し得ない、とに角言うに言えぬ程面白い、
一度やって見るといい、余はもう一度やりたい。あの快感は恐らく人生至上のものであろう。) 」
( 河野司編 「二・二六事件 」 )
----この人生至上の面白さには、
しかし、あのとき少年たちの心に直感的に宿ったものと、
相照応するものがあったのではなかろうか。
戦時中は日の目を見なかった二・二六事件関係の資料が、戦後続々と刊行され、
私が 「 英霊の聲 」 を書き終った直後に上梓された。
「 木戸幸一日記 」 と 「 昭和憲兵史 」 ( 未発表の憲兵隊調書を収載 ) を以て、
ほぼ資料は完全に出揃ったものと思われる。
壮烈な自刃を遂げた河野寿大尉の令兄河野司氏の編集にかかる 「 二・二六事件 」 と、
末松太平氏の名著 「 私の昭和史 」 は、なかんずく私に深い感銘を与えた著書である。
私は集められる限りの資料に目を通していたが、それで一篇の小説を書こうという気はなかった。
たまたま昨年からかかった四巻物の長篇の、第一巻を書いているうちに、
来年からとりかかる第二巻の取材をはじめた。
たわやめぶりの第一巻 「 春の雪 」 と対蹠的に、第二巻 「奔馬」 は、
ますらおぶりの小説になるべきものであり、昭和十年までの国家主義運動を扱う筈であった。
それらの文献を渉猟するうち、
その小説では扱われない二・二六事件やさらに特攻隊の問題は、
適当な遠近法を得て、いよいよ鮮明に目に映ってきていた。
一方、私の中の故しれぬ鬱屈は日ましにつのり、かつて若かりし日の私が、
それこそ頽廃の条件と考えていた永い倦怠が、
まるで頽廃と反対のものへ向って、しゃにむに私を促すのに私はおどろいていた。
( 政治的立場を異にする人たちは、もちろんこれも頽廃の一種と考えるだろうことは目に見えている。)
私は剣道に凝り、
竹刀の鳴動と、あの烈しいファナティックな懸声だけに、ようよう生甲斐を見出していた。
そして短編小説 「 剣 」 を書いた。
私の精神状態を何と説明したらよかろうか。
それは荒廃なのであろうか、それとも昂揚なのであろうか。
徐々に、目的を知らぬ憤りと悲しみは私の身内に堆積し、
それがやがて二・二六事件の青年将校たちの、
あの激烈な慨きに結びつくのは時間の問題であった。
なぜなら、
二・二六事件は、無意識と意識の間を往復しつつ、この三十年間、たえず私と共にあったからである。
私は徐々にこの悲劇の本質を理解しつつあるように感じた。
北一輝の思想が、否定につぐ否定、
あの熱っぽい否定の颶風によって青年の心をとらえたことは、想像に難くないが、
二・二六事件の蹶起将校は、北一輝の国体観とだけは相容れぬものを感じていた。
幼年学校以来、「 君の御馬前に死ぬ 」 という務りと国体観は一体をなしていたにかかわらず、
北一輝は、 スコラ哲学化した国体観を一切否定し、
天皇を家長と呼び 民を 「 天皇の赤子 」 と呼ぶような論法を自殺論法と貶し、
君臣一家論を大逆無道の道鏡の論裡となし、
このような国体論中の天皇を、東洋の土人部落の土偶に喩えていたからである。
二・二六事件の悲劇は、方式として北一輝を採用しつつ、理念として国体を戴いた。
その折衷性にあった。
挫折の真の原因がここにあったということは、同時に、彼らの挫折の真の美しさを語るものである。
この矛盾と自己撞着のうちに、
彼らはついに、自己のうちの最高最美のものを汚しえなかったからである。
それを汚していれば、あるいは多少の成功を見たかもしれないが、
何ものにもまして大切な純潔のために、 彼らは自らの手で自らを滅ぼした。
この純潔こそ、彼らの信じた国体なのである。
そして国体とは ?
私は当時の国体論のいくつかに目をとおしたが、曖昧模糊としてつかみがたく、
北一輝の国体論否定にもそれなりの理由があるのを知りつつ、
一方、「 国体 」 そのものは、誰の心にも、明々白々炳乎として在った、
という逆説的現象に興味を抱いた。
思うに、一億国民の心の一つ一つに国体があり、国体は一億種あるのである。
軍人には軍人の国体があり、それが軍人精神と呼ばれ、
二・二六事件蹶起将校の 「 国体 」 とは、この軍人精神の純粋培養されたものであった。
そして、万世一系の天皇は同時に八百万の神を兼ねさせたまい、
上御一人のお姿は一億人の相ことなるお姿を現じ、一にして多、多にして一、
・・・・・・しかも誰の目にも明々白々のものだったのである。
この明々白々のものが、何ものかの手で曇らされ覆われていると感じれば、
忽ち剣を執って、これを討ち、明澄と純潔を回復しようと思うのは、当り前のことである。
二・二六事件将校にとって、統帥大権の問題は、軍人精神をとおしてみた国体の核心であり、
これを干犯する(と考えられた)者を討つことこそ、大御心に叶う所以だと信じていた。
しかもそれは、大御心に叶わなかたのみならず、
干犯者に恰好に口実を与え、身自ら 「 叛軍 」 の汚名を蒙らねばならなかった。
文学的意慾とは別に、かくも永く私を支配してきた真のヒーローたちの霊を慰め、
その汚辱を雪ぎ、その復権を試みようという思いは、たしかに私の裡に底流していた。
しかし、その糸を手繰ってゆくと、
私はどうしても天皇の 「 人間宣言 」 に引っかからざるをえなかった。
昭和の歴史は敗戦によって完全に前期後期に分けられたが、
そこに連続して生きていた私には、自分の連続性の根拠と、論理的一貫性の根拠を、
どうしても探り出さなければならない欲求が生まれてきていた。
これは文士たると否とを問わず、生の自然な欲求と思われる。
そのとき、どうしても引っかかるのは、「 象徴 」 として天皇を既定した新憲法よりも、
天皇御自身の、この 「 人間宣言 」 であり、
この疑問はおのずから、二・二六事件まで、
一すじの影を辿って 「 英霊の聲 」 を書かずにはいられない地点へ、私自身を追い込んだ。
自ら 「 美学 」 と称するのも滑稽だが、私は私のエステティックを掘り下げるにつれ、
その底に天皇制の岩盤がわだかまっていることを知らねばならなかった。
それをいつまでも回避しているわけには行かぬのである。
「 木戸幸一日記 」 昭和二十年九月二十九日の項には、
天皇をあたかもファシズムの指導者であったかの如く邪推する米国側の論調に対して、
陛下御自身次のごとく仰せられたことが誌されている。
「 其際、[ 天皇は ] 自分が恰もファシズムを心奉するが如く思わるることが、最も耐え難きところなり。
実際余りに立憲的に処置し来りし為めな如斯事態となりたりとも云うべく、
戦争の途中に於て今少し陛下は進んで御命令ありたりしとの希望を聞かざるには非ざりしも、
努めて立憲的に運用したる積りなり 」 ( 傍点三島 )
私が傍点を附したこの個所はもちろんこの文章の主旨ではなく、
陛下が立憲君主として一切逸脱せず振舞われたということが主旨である。
しかしこの傍点の個所に、
私は、天皇御自身が、あらゆる天皇制近代化・西欧化の試みに対する、
深い悲劇的な御反省の吐息を洩らされたようにも感じるのである。
日本にとって近代的立憲君主制は真に可能であったのか?
・・・・・あの西欧派の重臣たちと、
若いむこう見ずの青年将校たちと、どちらが究極的に正しかつたのか?
世俗の西欧化には完全に成功したかに見える日本が、
「神聖」 の西欧化には、これから先も成功することがあるのであろうか?
二 ・二六事件と私
三島由紀夫 著
英霊の聲 から
・・・リンク→などてすめろぎはひととなりたまいし















