脳トレ宇宙論 第14話
天文学と数値計算、数表、計算機械、人間の作業 ③
 アナログ式微分解析機
アナログ式微分解析機
天文学の進歩は宇宙の観測、測定、考察 理論ばかりではなく、計算に大きく依存している。そして数学、数値計算、数表、人間の作業に関連して、膨大なデータ解析のための大量の計算、および人間の骨の折れる作業から解放し少しでも効率を上げるための計算道具や計算機械を作るという工夫や努力も必要不可欠であった。
計算道具・計算機械発展の歴史から
・BC100年 古代ギリシャ アンティキテラ島の機械 (1901年、古代ギリシャの沈没船から回収された天文学用歯車式計算機)


☆初期の手廻し計算機(Early Gear Caluculators)
・ネイピア(John Napier)の計算棒

1614年のネーピアの対数の発明以来、天文学者は長い計算を行うのに対数表を頼りにしてきた。さらに航海のために天体の観測から正確に位置を計算する、大砲の弾道軌道の計算などを複雑な計算を行う計算機械の必要性が高まる。ヨーロッパでは16世紀頃から精密機械技術の発達により計算機と呼べるものが作られるようになった。機械式計算機が市場に販売されるなようになったのは19世紀末になってからである。
・1623年 シッカルト(Wilhelm Schickard)の計算器(Rechenmaschine)およびシミュレータ
・1642年 パスカル(Blaise Pascal)のパスカリーヌ(The Pascaline) 歯車式計算機 (加減算のみ。ただし減算は補数で行う) 、シミュレータおよび機構の説明、パスカルが税務官の父の計算を助けるために歯車式の計算機を作成した。

・1673年 ライプニッツ(Wilhelm von Leibniz) 機械式計算機 (Stepped Reckoner/Reconstruction:1673) (加減乗除の計算が可能)、ドイツのライプニッツはそれを改良してさらに高度な計算機を作成した。
☆UK の数学者バベッジ(Charles Babbage 1791年ー1871年)は人間の骨の折れる作業から解放すると言うライプニッツの思想を受け継ぎ、バベッジの解析機関を考えた。
1820 年 トーマス 機械式計算機の商品化
1822年 階差機関(Differential Engine )No.1

1833年ー1834年 バベジ 機械式計算機の解析機関(Analytical Engine)および機構の解析・シミュレータなど開発開始
1853年 シュッツ兄弟(George and Edwrd Schuetz)の階差機関(Differential Engine)→4次多項式まで
1898年 エドワード・モーリーはサムエル・W・ストラットンとともに,フーリエ級数の160個の係数を決定できる機械的な装置(調和解析機)を作った。
1907年 グラント(George B. Grant)の階差機関(Differential Engine)
1991年 階差機関(Differential Engine)No.2
☆計算表と計算尺(Calculation Tables and Slide Rulers)(この項、WEB”歴史上の主な計算尺”参照)
1574年 Georg Joachim Rheticus の計算表
1596年 Valentius Othoの計算表「Opus Palatinum de Triangulis」
1620年 William Oughtred の最初のSilde Rule (スライド式)
1632年 同上回転式
1902年 Carl George Lange Barth Slide Rule (テイラー展開によるもの)
☆手廻し(歯車)計算器の興隆(Modern Gear Calculators)
1821年 Charles Xavier Thomas de ColmarのアリスモメータArithmometer)
1870年 バルドウィン(Frank S. Baldwin)計算器
1875年 オドナー計算器(Willgodt Theophil Odhner)
1889年 ボレー(Leon Bollee)の計算機
1893年 シュタイガー(Otto Steiger)の ミリオネリア(Millionaire)
1903年 矢頭良一の自働算盤(Patent Yazu Arithmometer)
1907年 ティム(Baby Tim)計算器
1910年 ブルンスヴィガ計算器(Brunsiviga)→マーチャント計算器(Marchant)
1923年 大本寅治郎(1887-1961 )大正8年(1919年)国産計算器の発明考案に着手し、1923年商品として完成「虎印計算器」として販売開始した。


☆統計マシンとレジ(会計器)の登場(Statistical Machines and Acounting Machines)
1890年 ホレリス(Herman Hollerith)による国勢調査(Census)機
1895年 John K. Goreによる整列・分類機
1887年 米国海軍(開発者Dorr E. Felt)のコンプトメータ(Comptometer)
1888年 バローズ(William S. Burroughs)の会計機(Adding machine)
☆論理マシン(Boolean Logic and the successors)
1777年 Charles Earl StanhopeのDemonstrator最初の論理マシン
1869年 William Stanley JevonsによるLogical Piano
1890年 Allan Marquandによる電気式論理マシン
1910年 トレス(Leonardo Torres y Quevedo)によるLogical Automata - El Ajedrecista(The Chessplayer)
☆コンピュータ時代に向かって
・1893-1920年トレス(Leonardo Torres y Quevedo)の代数マシン(Algebraic Machines)
・1920年ヴァネヴァー・ブッシュ(Vannevar Bush)の積分器(The Product Intergraph)、続いて微分解析器(Differential Analyzer)
・1945年 米のエッカートとモークリーはフォン・ノイマンの協力の下に2進法の最初の真空管式計算機ENIACを完成

・1949年 ENIACの後継機種として初のプロミング内蔵型計算機EDVAC完成
つい最近まで、まだトランジスタの集積回路になる以前、計算機は真空管の熱の中で夥しいケーブルに繋がれ、計器の針が慌ただしく動き、パンチカードを音を立てて吐き出す機械だった。観測結果など現実のさまざまな場面で生じる課題に挑んだ理論家・技術者たち、そして彼らの試行錯誤の末に生み出されたさらにユニークな機械やアイデアの流れが交錯し、影響を及ぼし合いながら、未来に向かって進歩していく。
そして現代の電子計算機のような科学技術的進歩が、従来人間の頭と手で行なわれてきた作業を代行し、作業の能率と規模において革命的な変革を齎しており、宇宙論においてもさらなる発展が期待される。


















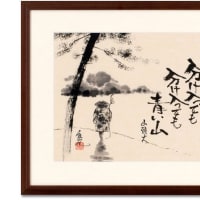

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます