この日もまったりと起床。
多分もう1時間早く起きると,もっと充実した行程となったでしょうし,食事もさっさと済ませれば良かったのかもしれませんが,家族連れではなかなかそうもいきません。
3日間ホテルの朝食を食べると飽きてきそうなものですが,食べることに拘泥しない性格なので何を食べても美味しいと感じる大雑把な性格は,こういう時だけ良かったりします・・・(逆に,私が不味いというものは,相当不味いものだということに・・・)。
都ホテルグループで近鉄系のホテルでしたが,昨年10月にオープンしたばかりということもあって,シックで小綺麗だったので私的には合格点でした。
何せ1泊朝食付きで4,000円台で,近鉄ホームの真上というロケーションも抜群でしたし・・・。
この日は,6時の新幹線で帰途に就くので,夕食とお土産物色を考えて4時半まで京都駅に戻れば・・・と,ゆったりした日程を組んでいました。
荷物は,ホテルの無料コインロッカーで預かってもらえるので,新幹線乗車の10分前までロッカーを開ければOK。
なので,まずJR奈良線に乗り,次の東福寺で京阪に乗り換えました。
このルートも多分30年ぶりでしょう。
途中,中書島まで特急に乗り換えて,本日の目的地である宇治へ向かいました。
宇治平等院を訪れるのは,それこそ高校の修学旅行以来となります。
当然団体バス(帝産バスだった)で行ったので,自力で電車で行くのは初めてで宇治橋も多分初めて渡りました・・・。
宇治橋から宇治川を見ると流れが急であることに驚かされます。
すぐ上流に天ヶ瀬ダム湖があるので,放水の状況にもよるかもしれませんが,京都防衛の拠点となったことも伺えるというものです・・・。 宇治橋上より。もろ逆光。中州の右が平等院。
宇治橋上より。もろ逆光。中州の右が平等院。 宇治橋袂。流れが急であることが分かるでしょうか・・・。
宇治橋袂。流れが急であることが分かるでしょうか・・・。
古来京都防衛戦は幾多もありましたが,有名なのは何と言っても寿永3(1184)年1月の宇治・瀬田の戦いでしょう。
京を防衛する木曾義仲軍に対して,鎌倉を進発した源範頼・義経軍が攻め入り,結果的に義仲が滅んだという源氏同士(従兄弟同士)の内訌です。
ともに生月(いけづき)・磨墨(するすみ)という頼朝拝領の名馬に乗る佐々木四郎高綱・梶原源太景季(梶原氏は平姓鎌倉一族なのに何故源太なのか不明)という板東武者2騎による有名な先陣争いは,名場面の多い「平家物語」にあっても白眉とも言うべきものですが,個人的には,その4年程前の治承4(1180)年5月の第一次宇治川合戦(というかどうか知りませんが・・・。「平家物語」では橋合戦)の方が興味深いです。 中州にある宇治川先陣之碑
中州にある宇治川先陣之碑
宇治橋の橋板を落として守るのは源三位入道頼政。
従うのは腹心とも言うべき摂津渡辺党(嵯峨天皇の子孫にして,頼政の先祖である頼光四天王の1人渡辺綱の子孫)と園城寺の僧兵勢力です。
以前述べたかも知れませんが,この頼政は頼信-頼義-義家-義親-為義-義朝-頼朝・範頼・義経と続く河内源氏とは異なり,頼信兄の頼光を祖とする摂津源氏(多田源氏とも)です。
平治の戦いの際には清盛に付き,平氏政権下で三位という高位に登り(しかも清盛の推挙で),内裏警護の任に当たると共に文字通り源氏の長老として70余年の生涯を全うしようとした矢先の反平氏挙兵でした・・・。
所謂源平の戦い(治承寿永の内乱)は,頼政が不遇を託っていた高倉宮以仁王(高倉上皇弟)
に持ちかけて,決起を呼びかける令旨を全国各地の源氏へ発したことに始まるとされています。
そこに到るまでには,治承元(1177)年の鹿ヶ谷事件(後白河院が平氏転覆を企てるも,多田行綱の讒訴にて失敗)後,後白河院と清盛の関係が悪化。
清盛が高倉帝に譲位させ外孫に当たる安徳帝が即位。
それに伴い園城寺・延暦寺・興福寺僧兵勢力の不穏な動き(後白河・高倉両院を拉致して,寺域に囲っての反平氏蜂起-後白河が平宗盛に知らせたことで頓挫)といった複雑な背景があり,反平氏の機運が畿内諸国でも高まっていたと思われます。
平氏政権下で命脈を保ってきた源氏の長老の心中は,830年を経た今となっては想像するしかありません・・・。
一説によると,頼政の嫡子仲綱は木の下という名馬を所有しており,平宗盛にそれを所望されるも,差し出すことを渋っていたところ父頼政の進言で結局差し出す。
ところが,宗盛は事もあろうに木の下の尻に「仲綱」と焼き印を入れ,「仲綱仲綱」と呼んで引き回したり鞭打ったりした。
その屈辱・恥辱が反平氏挙兵を決意させた・・・と言われてきました。
宗盛の暗愚さを示す出来事ですが,平氏政権下で生き延びてきた頼政父子がこれで暴発するとも思われません・・・。
治承4年4月,頼政は以仁王にはたらきかけ,諸国の源氏に令旨を発します。
その時,頼政は諸国の源氏の武将の名を読み上げます。
伊豆には前右兵衛佐頼朝,駿河にはその弟蒲冠者範頼,陸奥には九郎冠者義経,信濃には帯刀先生義賢遺児木曾冠者義仲,上野には新田大炊助義重,下野には足利三郎義兼・・・といった具合だったのでしょう。
その令旨は,山伏に窶した新宮十郎義盛(行家)によって,それら源氏一族に届けられます・・・。
平氏は,以仁王が反平氏の令旨を発したことを察知(密告したのは,熊野別当湛増-弁慶の父とも言われる-だったとの説あり)。
検非違使別当を務める平時忠(清盛義弟)が兵300余を率いて,以仁王の三条高倉邸に向かうも,以仁王は滝口の武者長谷部信連(子孫は能登の戦国大名の長氏)の奮戦もあって園城寺へ脱出。
この時忠の軍勢に頼政次子(養子とも)兼綱が入っていたのは,平氏が頼政を全く疑っていなかった証拠でしょう・・・。
頼政は,長子仲綱,次子兼綱,三子頼兼,四氏宗綱,養子の八条蔵人仲家(木曾義仲兄)とともに園城寺に入りますが,平氏の調略により頼みの比叡山延暦寺が中立に回り,園城寺も安全でなくなったので南都興福寺を目指します。
しかし,馬に慣れぬ以仁王はたびたび落馬。
やむなく宇治平等院にて休息しているところを,平氏の追っ手に追いつかれてしまいます。そして,宇治橋の橋板を落として平氏の大軍を迎え撃つことになります・・・。
・・・と,ここまで書いて気づくと,ワープロ2ページ半。
とんでもない分量です。
宇治は,「源氏物語」の最終章である宇治十帖(橋姫から夢の浮橋まで)の舞台であるだけに,本来ならそちらの根多で語るべきかも知れませんが,同じく「源氏物語」縁の石山寺同様,源氏は源氏でも源平の源氏について語ってしまいました・・・。
しかも「橋合戦」に関しては終わってもいませんし,明日は,一体どうなることか自分でも皆目見当が付きません・・・。
宇治の風物について何も書いていないし・・・。
取り敢えず,明日も頑張って書きたいと思いますが,果たして如何なる事に・・・。
宇治川を挟んで対峙する頼政と平氏軍の戦いの顛末は・・・










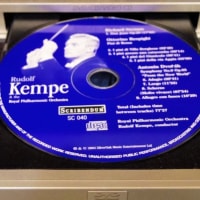
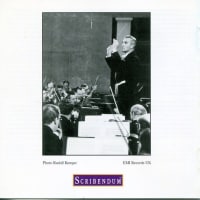
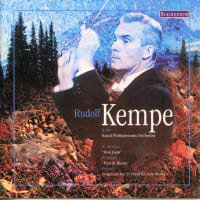







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます