ようやく原作の冒頭までたどり着きました。
見覚えのある台詞が出てくると,思わずにやりとなります。
青木大膳が金をせびりにやって来るのも勘助が彼を陥れたのも原作通りでしたが,トラップを仕掛けるとは勘助もかなり狡猾です。
原作だと,板垣信方を襲った大膳を勘助が斬って恩を売ったのが天文11年の8月で,武田家から仕官を進める使者が来たのが翌年2月ですが,あっという間に亀晴信に気に入られて仕官してしまいましたね。
破格の厚遇で仕官した後,重臣たちによるいじめが始まって,
「迷惑至極」
と言ったのも原作通りでしたが,真剣でしか勝負しないと言って墓穴を掘ったり,何故か原虎胤が相手をしよう,と出てきたりしたのはオリジナルです。
墓穴を掘ってしまった勘助は,どう切り抜けるのでしょう・・・。
一つ気になっていたのですが,冒頭で亀晴信が,
「この戦国乱世」
という言葉を使っていましたが,当時「乱世」はともかく「戦国」という言葉は使われたのでしょうか。
「戦国」と言えば中国の春秋時代を指す言葉でしょうから,我が国の「戦国」時代という呼称は江戸時代になってからのように思われるのですが,果たしてどうなのでしょう。
そう言えば山岡荘八の歴史小説でも横山光輝のコミックでも,「戦国」という言葉が使われていました。
さらに地名について。
今川家の居城は駿河の府中です。
駿河府中-即ち駿府ですが,これはいつ頃からそのように呼ばれたのでしょう・・・。
江戸期に整備された東海道五十三次では,府中-鞠子・・・と宿駅が続きます。
・・・ということは城は駿府城で宿場が府中なのか,或いは幼少期の家康が人質時代を送って太原雪齋の弟子となっていた頃から駿府と呼ばれていたのか・・・。
地元の方ならご存じかもしれません・・・。
同じことは武田の居館(断じて居城ではない)がある躑躅ヶ崎館の場所にも言えます。
甲斐の府中-即ち甲府ですが,果たして天文年間に甲府という呼称は有ったのでしょうか・・・。
後に信玄の後を継いだ勝頼によって,武田氏創業以来の城が韮崎の笛吹川の段丘上に建造されます。
対信長戦略なのか示威活動なのか諸論はあると思いますが,そこを当時新府と呼び,現在もJR中央本線の駅名として残っています。
対して,躑躅ヶ崎館のあった現在の甲府市を「古府中」と呼びました。
「風林火山」原作には「甲府」という名は一度も出ず,「古府中」で統一しています。
ただ,新府-古府中という観点で言えば,天文年間は「古府中」という呼称は変だと思いますし,「甲府」という呼称も江戸期に柳沢吉保がいた頃以降ではないでしょうか・・・。
これも地元の方やご存じの方にうかがってみたいことです・・・。
・・・ということで,ドラマの内容をそっちのけでまたしても突っ込んでしまいましたが,はっきり言って途中で眠くなってしまった「功名が辻」に比べ,ドラマとしての出来は格段に違うと思います。
来週も実に楽しみです。
・・・で,最後にまた余計なひとこと。
板垣信方の子孫は土佐出身の板垣退助・・・???。
さて,本当でしょうか。










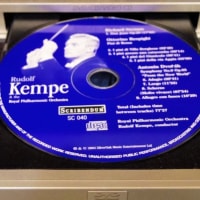
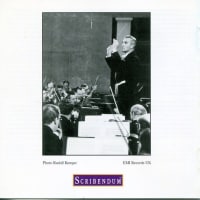
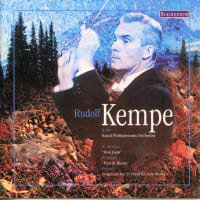







そうですよね、当時から地名はそうだったか?ってのは興味ある事柄のひとつです。
郷土資料館なんてあれば行って調べてみたいですね。
昔の地図とかあるかもしれません。
風土記みたいなのがあると、分かりやすいですね。
ところで、戦国時代って当時の人が戦国って思っていたかは疑問ですよね。
「乱世」とかはよく出てくる言葉ですが、生まれた時から世が乱れて、それが当然な人々はそう呼んだかどうかも疑問です。
それと、「風林火山」の中で亀晴信が天下を望んでる様子ですが、それって歴史的にどうかな~?と思っています。
確かに上洛しようとしていたけど、実際はどうなんでしょうね?
今週は私も感想書いてませんが、これからも突っ込んでいきましょう~!!
楽しみにしています!!
こちらにまでコメントいただいていたのですね。
見落としてしまって,ただただ謝るしかございません・・・。
甲府は,多分藩政時代以降の呼称ではないかと思われます。
多分「府中」と呼んでいたでしょうし,勝頼が新府城を築いてからは「古府中」と呼んだと思われます。
信玄が天下を見据えたのは,おそらく最後の半年だけではないでしょうか。
三方ヶ原で徳川軍を破り三河に侵攻。
野田城を包囲するまでがそれに当たり,後は無念の撤退中伊那の駒場で亡くなった,ということですので・・・。
そうした意味でも,川中島の戦いは天下の趨勢とは全く無縁で,信玄に謙信といった名将もローカルヒーローだったということでしょう・・・。
個人的には上杉より武田が好きですが・・・。