いよいよ「江戸編」のスタートとなりました。
龍馬の人生を俯瞰すると,その功績は慶応年間の3年間に集約されている訳ですが,嘉永6(1853)年から元治元(1864)年という少なからぬ年数を過ごした(勿論その間に土佐に帰ったり脱藩したり神戸海軍塾の塾頭を務めたり,勝と長崎に行ったりしていましたが)江戸での生活は,その生涯の中でも最も明るく活気に満ちた時期ではなかったでしょうか・・・。
当時江戸と土佐は片道30日と言われましたが,TVは便利です。
先週,弥太郎を讃岐(仁尾?)か阿波(鳴門?)の何処かに置いて江戸に向かった龍馬と溝渕ですが,一週間で着いてしまいましたね。
途中大坂や京を見たり,東海道筋で冨士を見たり(「篤姫」にそんな場面がありました)・・・といった余計なエピソードは無く,あっさり江戸入りとなってしまいました。
・・・で,この2人はどこに居を構えたのでしょう・・・???
そのあたりが全く触れられませんでした。
おそらく土佐藩邸に寄宿したと思われますが,もしかすると道場に直接住んだ・・・というのも有りかもしれません。
土佐編のヒロインが加尾なら,「江戸編」は何と言っても千葉の鬼小町と言われた道場主定吉の長女佐那です。
龍馬の生涯を彩る3人のヒロインのうち,個人的に最も魅力的なのは何と言ってもこの佐那ですので(笑),ついつい期待してしまいますが,配役発表の際,貫地谷しほり嬢と知って???と思ってしまいました。
どうしても「風林火山」のおみつのイメージが有ったからでしょう・・・。
しかし,本日実際に見てみると凛然とした節度だった美しさが感じられ,嬉しいことに???が杞憂に終わりました。
これで来週が楽しみになります・・・(をい・・・)。
只,相変わらず話の展開には無理があったように思われました。
北辰一刀流千葉道場-つまり玄武館は,当時神田於玉ヶ池にあった千葉周作(我が県出身なのに殆ど知られていない・・・)の道場に対して,周作弟で龍馬の師となった定吉の道場は桶町にあり,周作の道場と区別して小千葉道場と呼ばれました。
龍馬が,入門した嘉永6年当時,定吉は鳥取藩の剣術師範として江戸屋敷詰となっていたので,龍馬と立ち会ったのは息子の重太郎だったことになります(後に重太郎も鳥取藩に仕官します)。
ですから,最初に佐那と立ち会わせて龍馬が負けたという展開は良いと思うのですが,どうもこの龍馬は達観しているのか,女に負けた・・・という悔しさを微塵も持っていないようです・・・。
或いは,土佐の田舎剣法と江戸の大流儀との相違をまざまざと見せつけられて,どん底に叩き込まれるぐらいの描写があっても良かったのでは,と思いました。
実際,千葉道場の稽古の凄まじさは相当なものであったようで,千葉周作の長男と次男が夭折したのは,あまりに激しい稽古のため,という話を聞いたことがあります。
最初に龍馬と立ち会った佐那の激しい竹刀裁きにその片鱗を見ることができましたが(代役だったのでしょうか),その後定吉が佐那に対して
「お前は龍馬に勝てん」
といったことを言った必然性が,私には理解できませんでした。
だって,現時点で龍馬の一敗ですよ。
今一度立ち会って龍馬に圧倒されたなら分かりますけど・・・。
それに龍馬の入門は嘉永6年の4月でしょうから,6月のペリー来航前ということは二ヶ月しかたっていません。
その間龍馬の剣技が飛躍的に向上したとしても,その描写は有りませんでした。
女子どもに稽古を付けて,何故か太鼓を打っていましたが・・・。
因みに,龍馬が北辰一刀流の免許を貰ったのは,その5年後になります。
さて,どう考えても偽手形で打ち首の筈の弥太郎は無事本国に帰り,相変わらずの暮らしをしておりました。
で,半平太と遭って散々毒づいておりましたね。
半平太と弥太郎の接点はどの程度だったのか分かりませんが,地下浪人と藩士の差は歴然としていたでしょうから,タメ口は勿論毒づいたりしたら切り捨て御免ではないでしょうか・・・。
さらに述べるならば,半平太は郷士とはいえ上士同様日傘を差すことを許された「白札」なる階級でした(このあたりに全く本編では触れられていませんが)。
ですから,今回のようなことは有り得ないと思います。
尤も半平太は土佐勤王党の首魁として人望のあった人格者ですから,鷹揚で偉ぶったりはしなかったことでしょうが・・・。
半平太の私塾には,後の土佐勤王党の面々が集っていました。
以蔵にも学問を教えてやるという半平太ですが,どうも私には魅力的な人物に映りません。
後に池田屋で命を落とす望月亀弥太も居るようなのですが,どこに居るのか分かりませんでした・・・。
どうもこのように各々のキャラが立ってこないきらいがある,と思うのは私だけでしょうか。
龍馬,弥太郎,弥太郎父,加尾以外の土佐者は何か埋没しています・・・。
・・・で,弥太郎が半平太に対抗して私塾を開く・・・。
このあたりで既に???なのに,訪ねて来た加尾(もう出番は無いと思ったのに)。
で,
「私に学問を・・・」(絶句)
そんでもって,
「これは夢じゃあ~」
と喜ぶ弥太郎。
波がどっぱーん・・・・・・(抱腹絶倒)
いや,面白かったです。
あっと言う間の45分でした。
かなりの突っ込みどころ満載でしたが・・・。
弥太郎に関して少し付け加えると,実は幼少時に既に文才は相当なものだったらしく,14歳で当時の藩主の前で漢詩を披露したと言われています。
ですから,間違っても裕福ではなかったにせよ果たして鳥籠を売り歩いていたという設定はどんなものかと思います。
江戸に出たのは龍馬より遅く確か安政年間で,昌平黌の安積艮斎に付いたということですので(今なら東大教授に付いたことに),相当な才能・・・ということになりそうです・・・。
千葉重太郎役の渡辺いっけいは,変な役をやらせたらピカイチと思ってきましたが(女房の尻に敷かれる駄目夫,女子高生と援助交際する危ない中年・・・),こんなまともな役柄は初めて見ました。
ちょっと年がいきすぎている感もありますが・・・(どうも千葉重太郎というと,明朗な好青年で江戸っ子というイメージが有るので・・・)
ダークサイドに陥った今川義元とマザコン駄目夫を同時期に好演していた谷原章介の桂はどうなんでしょうね・・・。
怜悧なイケメンというイメージの桂ですが,後年祇園の芸者だった幾松といい仲になっただけあって,朴念仁ではなかったということでしょう・・・。
それにしては,ちくと(土佐弁)饒舌に過ぎるような気もしましたが・・・。
饒舌と言えば,龍馬もこの時点ではあっちのことを知らない割に,佐那に対しては妙に饒舌でしたね。
父の訓辞を守って女色にふけらず・・・と,おねいさんの前で言ったらどん引きされるでしょうけど・・・。
・・・ということで,ぺりーがやってきました。
道着のまま飛び出した龍馬は,来週そのまま浦賀に行くのでしょうか・・・。
江戸から浦賀までは17里は有りますので,一度藩邸から招集がかかって武装して・・・ということになるのでしょうか・・・。
楠木流軍学-大筒に見せかける釣り鐘の話は出てくるのかどうか・・・。

龍馬の人生を俯瞰すると,その功績は慶応年間の3年間に集約されている訳ですが,嘉永6(1853)年から元治元(1864)年という少なからぬ年数を過ごした(勿論その間に土佐に帰ったり脱藩したり神戸海軍塾の塾頭を務めたり,勝と長崎に行ったりしていましたが)江戸での生活は,その生涯の中でも最も明るく活気に満ちた時期ではなかったでしょうか・・・。
当時江戸と土佐は片道30日と言われましたが,TVは便利です。
先週,弥太郎を讃岐(仁尾?)か阿波(鳴門?)の何処かに置いて江戸に向かった龍馬と溝渕ですが,一週間で着いてしまいましたね。
途中大坂や京を見たり,東海道筋で冨士を見たり(「篤姫」にそんな場面がありました)・・・といった余計なエピソードは無く,あっさり江戸入りとなってしまいました。
・・・で,この2人はどこに居を構えたのでしょう・・・???
そのあたりが全く触れられませんでした。
おそらく土佐藩邸に寄宿したと思われますが,もしかすると道場に直接住んだ・・・というのも有りかもしれません。
土佐編のヒロインが加尾なら,「江戸編」は何と言っても千葉の鬼小町と言われた道場主定吉の長女佐那です。
龍馬の生涯を彩る3人のヒロインのうち,個人的に最も魅力的なのは何と言ってもこの佐那ですので(笑),ついつい期待してしまいますが,配役発表の際,貫地谷しほり嬢と知って???と思ってしまいました。
どうしても「風林火山」のおみつのイメージが有ったからでしょう・・・。
しかし,本日実際に見てみると凛然とした節度だった美しさが感じられ,嬉しいことに???が杞憂に終わりました。
これで来週が楽しみになります・・・(をい・・・)。
只,相変わらず話の展開には無理があったように思われました。
北辰一刀流千葉道場-つまり玄武館は,当時神田於玉ヶ池にあった千葉周作(我が県出身なのに殆ど知られていない・・・)の道場に対して,周作弟で龍馬の師となった定吉の道場は桶町にあり,周作の道場と区別して小千葉道場と呼ばれました。
龍馬が,入門した嘉永6年当時,定吉は鳥取藩の剣術師範として江戸屋敷詰となっていたので,龍馬と立ち会ったのは息子の重太郎だったことになります(後に重太郎も鳥取藩に仕官します)。
ですから,最初に佐那と立ち会わせて龍馬が負けたという展開は良いと思うのですが,どうもこの龍馬は達観しているのか,女に負けた・・・という悔しさを微塵も持っていないようです・・・。
或いは,土佐の田舎剣法と江戸の大流儀との相違をまざまざと見せつけられて,どん底に叩き込まれるぐらいの描写があっても良かったのでは,と思いました。
実際,千葉道場の稽古の凄まじさは相当なものであったようで,千葉周作の長男と次男が夭折したのは,あまりに激しい稽古のため,という話を聞いたことがあります。
最初に龍馬と立ち会った佐那の激しい竹刀裁きにその片鱗を見ることができましたが(代役だったのでしょうか),その後定吉が佐那に対して
「お前は龍馬に勝てん」
といったことを言った必然性が,私には理解できませんでした。
だって,現時点で龍馬の一敗ですよ。
今一度立ち会って龍馬に圧倒されたなら分かりますけど・・・。
それに龍馬の入門は嘉永6年の4月でしょうから,6月のペリー来航前ということは二ヶ月しかたっていません。
その間龍馬の剣技が飛躍的に向上したとしても,その描写は有りませんでした。
女子どもに稽古を付けて,何故か太鼓を打っていましたが・・・。
因みに,龍馬が北辰一刀流の免許を貰ったのは,その5年後になります。
さて,どう考えても偽手形で打ち首の筈の弥太郎は無事本国に帰り,相変わらずの暮らしをしておりました。
で,半平太と遭って散々毒づいておりましたね。
半平太と弥太郎の接点はどの程度だったのか分かりませんが,地下浪人と藩士の差は歴然としていたでしょうから,タメ口は勿論毒づいたりしたら切り捨て御免ではないでしょうか・・・。
さらに述べるならば,半平太は郷士とはいえ上士同様日傘を差すことを許された「白札」なる階級でした(このあたりに全く本編では触れられていませんが)。
ですから,今回のようなことは有り得ないと思います。
尤も半平太は土佐勤王党の首魁として人望のあった人格者ですから,鷹揚で偉ぶったりはしなかったことでしょうが・・・。
半平太の私塾には,後の土佐勤王党の面々が集っていました。
以蔵にも学問を教えてやるという半平太ですが,どうも私には魅力的な人物に映りません。
後に池田屋で命を落とす望月亀弥太も居るようなのですが,どこに居るのか分かりませんでした・・・。
どうもこのように各々のキャラが立ってこないきらいがある,と思うのは私だけでしょうか。
龍馬,弥太郎,弥太郎父,加尾以外の土佐者は何か埋没しています・・・。
・・・で,弥太郎が半平太に対抗して私塾を開く・・・。
このあたりで既に???なのに,訪ねて来た加尾(もう出番は無いと思ったのに)。
で,
「私に学問を・・・」(絶句)
そんでもって,
「これは夢じゃあ~」
と喜ぶ弥太郎。
波がどっぱーん・・・・・・(抱腹絶倒)
いや,面白かったです。
あっと言う間の45分でした。
かなりの突っ込みどころ満載でしたが・・・。
弥太郎に関して少し付け加えると,実は幼少時に既に文才は相当なものだったらしく,14歳で当時の藩主の前で漢詩を披露したと言われています。
ですから,間違っても裕福ではなかったにせよ果たして鳥籠を売り歩いていたという設定はどんなものかと思います。
江戸に出たのは龍馬より遅く確か安政年間で,昌平黌の安積艮斎に付いたということですので(今なら東大教授に付いたことに),相当な才能・・・ということになりそうです・・・。
千葉重太郎役の渡辺いっけいは,変な役をやらせたらピカイチと思ってきましたが(女房の尻に敷かれる駄目夫,女子高生と援助交際する危ない中年・・・),こんなまともな役柄は初めて見ました。
ちょっと年がいきすぎている感もありますが・・・(どうも千葉重太郎というと,明朗な好青年で江戸っ子というイメージが有るので・・・)
ダークサイドに陥った今川義元とマザコン駄目夫を同時期に好演していた谷原章介の桂はどうなんでしょうね・・・。
怜悧なイケメンというイメージの桂ですが,後年祇園の芸者だった幾松といい仲になっただけあって,朴念仁ではなかったということでしょう・・・。
それにしては,ちくと(土佐弁)饒舌に過ぎるような気もしましたが・・・。
饒舌と言えば,龍馬もこの時点ではあっちのことを知らない割に,佐那に対しては妙に饒舌でしたね。
父の訓辞を守って女色にふけらず・・・と,おねいさんの前で言ったらどん引きされるでしょうけど・・・。
・・・ということで,ぺりーがやってきました。
道着のまま飛び出した龍馬は,来週そのまま浦賀に行くのでしょうか・・・。
江戸から浦賀までは17里は有りますので,一度藩邸から招集がかかって武装して・・・ということになるのでしょうか・・・。
楠木流軍学-大筒に見せかける釣り鐘の話は出てくるのかどうか・・・。











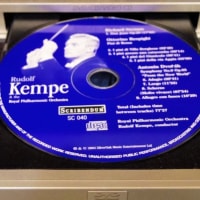
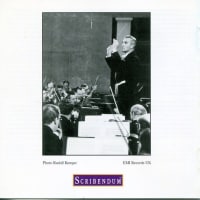
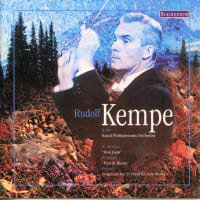







TBありがとうございます。
私も同じような事感じました~。たった2ヶ月くらいで佐那を負かせるようになったのなら、その描写が欲しかったですよね。
ちょっと唐突でした。
加尾の言動も意味不明ですね。
毎週・・・・は無理かもしれないけど、感想を書いていこうと思ってます。これからもよろしくお願いします。
そして,初めまして。
エントリとHNから察して,主人公のご縁の方かと緊張してしまいました・・・(汗)
前作に比して極めて評判の良い「龍馬伝」ですが,どうしても食い足りない部分が感じられ,ついつい突っ込みを入れてしまいます・・・。
加尾と弥太郎のエピソードは余計と思いましたが,
「夜明けじゃ~」(ざっぱ~ん)
は個人的にツボでした・・・(爆)
ぜひ又のお越し,そしてご感想をお待ちしています。
そちらにも伺いたいと思いますので・・・。