
半世紀ほど前に西の国から東の国東京にやって来た。
東の国にはいろんな乗り物がある、階段が一段一段あらわれ立っているだけで人混みを抜き先に移動する。乗る時は最初はタイミングが合わなくて乗り遅れてバランスを崩してよろめいた。慣れればこれほど楽なものはない。
東京もモグラのような街で地下に潜っている。だからこの乗り物には重宝する。神社にお参り何百段もある階段を、富士山に登る険しい道のりを登る達成感とは違って、急いでいる時は長い階段をのぼる時間がない。
エスカレータの幅が2人が並んで立つ幅もあり、3人並んで立つ幅もある。
"Escalator"という語は元々、
アメリカのオーチス・エレベータ・カンパニーの商品名だそうだ。
せっかちな日本人だけだと思ったらアメリカに行ってもエスカレータ上を足早に歩いていた。私も歩くのが速いと思ったらニューヨークでは人は飛ぶように歩いていた。人が右側に立っていたら左側を歩いていた。
アメリカ、イギリス、香港、台湾は、先を急ぐ人のために左側を空ける習慣・マナーとなっている。
逆に、オーストラリア、ニュージーランドは右側を空けるようだ。
いずれにしてもエスカレータを歩くと転んだり落下の危険があるのでカナダや日本ではところによつて条例でエスカレータ上を歩きを禁止しているところもある。
車は日本では左通行で追い越し車線は右側だから、エスカレータを急いでいる方は人が左側に立って場合は右側を通行するのが習慣、マナーだ。
そうすると、アメリカ、イギリス、台湾、香港は右側通行だから、エスカレータを急いでいる方は人が右側に立っている場合は左側を通行するのが習慣だ。
日本では、車は、左通行だから、右側通行は逆走になる。道路の複雑になって、間違って逆走に気づかず正々堂々と走って、最近のニュースでは高齢者ばかりではなく中年の方も逆走している。
第二次世界大戦の敗戦後アメリカ連合国は車を右側通行に直されなかった。日本はバスの停留所も道路の左側にあった。乗り降りも当然、左側だ。
侍が左側の腰に刀を差していたので、右側通行だとサヤとサヤがガチィンとふれるので因縁をつけられ喧嘩を避けるのに左側通行にしたとか、習慣はすぐには直せない。
別に喧嘩を売るつもりはないが、箸が右手、お茶碗は左手だったのに、どうしても、他人が箸を左手に持っていると味まで変わる。習慣っておかしいね。
エスカレータに感謝する。地下鉄から国鉄に乗り換えるのに、地下から長―い階段を上るのが無理でエスカレータのおかげで地上の明かりを見えてJRに乗り換えることが出来た。
エスカレータは混雑を避けるため、足のご不自由な方、お年寄りの方がいらっしゃれば流れが多少違ってくる。駅などの人混み解消にはエスカレータの役割を果たしたのだろう。
ところが、西の国の大坂、兵庫、奈良、和歌山ではエスカレータは利用の立て看板にはエスカレータは右寄りに立って乗り、急いでいる方の為に左側を空けるようにとエスカレータの利用の立て看板があって、関西では東の国東京とは反対になったとか
このような経緯により、関西では左側空けが定着した。
一方、同じ関西でも京都は右側空けの立て看板で設置で右側空けが定着した。
滋賀県は京都に習って右側空けが定着した。
習慣、マナーで東京都と大阪の違いがうまれた。
法律で左右の決まりはないがその地の実情によって、日本では左側空けの、右側空けの習慣、マナーがあるようだ。駅などの券売機の位置、乗り換えの混雑を避けるため、エスカレータは人の流れを見て、人と人の交差がスムーズいくよう危険のないよう考えているのだろう。
ところ変われば、習慣もマナーも変わるんだね。
東の国にはいろんな乗り物がある、階段が一段一段あらわれ立っているだけで人混みを抜き先に移動する。乗る時は最初はタイミングが合わなくて乗り遅れてバランスを崩してよろめいた。慣れればこれほど楽なものはない。
東京もモグラのような街で地下に潜っている。だからこの乗り物には重宝する。神社にお参り何百段もある階段を、富士山に登る険しい道のりを登る達成感とは違って、急いでいる時は長い階段をのぼる時間がない。
エスカレータの幅が2人が並んで立つ幅もあり、3人並んで立つ幅もある。
"Escalator"という語は元々、
アメリカのオーチス・エレベータ・カンパニーの商品名だそうだ。
せっかちな日本人だけだと思ったらアメリカに行ってもエスカレータ上を足早に歩いていた。私も歩くのが速いと思ったらニューヨークでは人は飛ぶように歩いていた。人が右側に立っていたら左側を歩いていた。
アメリカ、イギリス、香港、台湾は、先を急ぐ人のために左側を空ける習慣・マナーとなっている。
逆に、オーストラリア、ニュージーランドは右側を空けるようだ。
いずれにしてもエスカレータを歩くと転んだり落下の危険があるのでカナダや日本ではところによつて条例でエスカレータ上を歩きを禁止しているところもある。
車は日本では左通行で追い越し車線は右側だから、エスカレータを急いでいる方は人が左側に立って場合は右側を通行するのが習慣、マナーだ。
そうすると、アメリカ、イギリス、台湾、香港は右側通行だから、エスカレータを急いでいる方は人が右側に立っている場合は左側を通行するのが習慣だ。
日本では、車は、左通行だから、右側通行は逆走になる。道路の複雑になって、間違って逆走に気づかず正々堂々と走って、最近のニュースでは高齢者ばかりではなく中年の方も逆走している。
第二次世界大戦の敗戦後アメリカ連合国は車を右側通行に直されなかった。日本はバスの停留所も道路の左側にあった。乗り降りも当然、左側だ。
侍が左側の腰に刀を差していたので、右側通行だとサヤとサヤがガチィンとふれるので因縁をつけられ喧嘩を避けるのに左側通行にしたとか、習慣はすぐには直せない。
別に喧嘩を売るつもりはないが、箸が右手、お茶碗は左手だったのに、どうしても、他人が箸を左手に持っていると味まで変わる。習慣っておかしいね。
エスカレータに感謝する。地下鉄から国鉄に乗り換えるのに、地下から長―い階段を上るのが無理でエスカレータのおかげで地上の明かりを見えてJRに乗り換えることが出来た。
エスカレータは混雑を避けるため、足のご不自由な方、お年寄りの方がいらっしゃれば流れが多少違ってくる。駅などの人混み解消にはエスカレータの役割を果たしたのだろう。
ところが、西の国の大坂、兵庫、奈良、和歌山ではエスカレータは利用の立て看板にはエスカレータは右寄りに立って乗り、急いでいる方の為に左側を空けるようにとエスカレータの利用の立て看板があって、関西では東の国東京とは反対になったとか
このような経緯により、関西では左側空けが定着した。
一方、同じ関西でも京都は右側空けの立て看板で設置で右側空けが定着した。
滋賀県は京都に習って右側空けが定着した。
習慣、マナーで東京都と大阪の違いがうまれた。
法律で左右の決まりはないがその地の実情によって、日本では左側空けの、右側空けの習慣、マナーがあるようだ。駅などの券売機の位置、乗り換えの混雑を避けるため、エスカレータは人の流れを見て、人と人の交差がスムーズいくよう危険のないよう考えているのだろう。
ところ変われば、習慣もマナーも変わるんだね。


























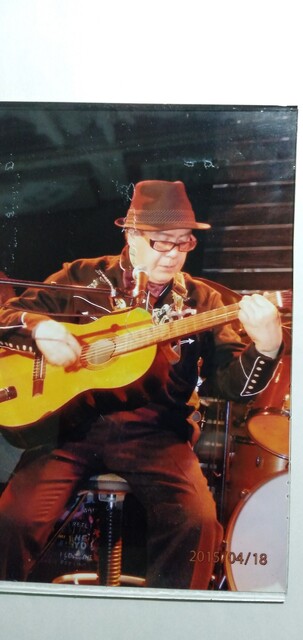
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます