<司法試験>「予備試験」始まる 初の1万人超え
毎日新聞 5月19日(日)19時10分配信
法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格
が得られる「予備試験」が19日、全国8会場で
始まった。出願者は1万1255人(前年9118人)
で、2011年の制度開始から2年連続で増加し、
初めて1万人を超えた。一方、法科大学院の今年度
の入学者は過去最低の2698人にとどまり、法科
大学院離れが進んでいる
予備試験は、経済的事情などから法科大学院に通え
ない人に門戸を開くため、合格すれば司法試験を受
けられる「例外ルート」として設けられた。
受験資格に制限がなく、司法試験の合格率も
法科大学院修了者より高い結果が出ていることもあり、
出願者数は年々増加している。
これに対し、「原則ルート」である法科大学院の
入学者数は、06年度にピークの5784人に達したが、
司法試験合格率の低迷などにより、その後は減少し
続けている。
政府の有識者会議は4月、「法科大学院教育の改善
状況も見ながら、予備試験を見直す必要があるか
どうか検討すべきだ」との中間提言をまとめている。
19日は短答式の試験があり、その後、論文式や口述
の試験を経て、11月7日に合格者が発表される。
合格すれば、5年以内に3回まで司法試験を受験する
ことができる。
法科大学院協会事務局長の中山幸二・明治大法科
大学院教授の話 受験技術に走る人が増え、視野の
狭い法律家を生むと批判された旧司法試験の反省から、
原則3年かけて幅広い法的素養を身につける法科大学
院制度が導入されたのに、予備試験組がエリート視
されるゆがんだ風潮が広がりつつある。予備試験に
年齢制限を設けるなど、早急な見直しをしなければ、
法科大学院制度は破綻する。
・・・
法科大学院の制度自体、無理があったように思います。
幅広い法的素養を身につけるという考え方は、正しい
とは思いますが、
「司法試験に合格して、弁護士という資格を取らなけ
れば、ただの人」なわけですから、試験合格に受験生
の主眼が行くのは避けられないものだと思いますね。
それに、「法科大学院」まで行かないと受験できない
という仕組みにすること自体、
おカネ(学費)、時間、早く社会人となり稼ぐ
という面で、法学既修者で2年、未修者で3年も
かかるというのは、経済的負担が大きすぎるのもネック
だと思います。
ほとんどの人は、社会人掛け持ちではなく、親に学費
を頼っての勉強への集中ですから。
現役、ストレートで修了しても24歳、25歳。
いい歳して、いつまでも親に学費を出させるのか
という問題もあります。
・・・
また、大学院を修了すれば「視野が広い人物になれる」
かどうかというのも疑問です。
結局は、「司法試験」という試験で篩いにかけられ、
その中で合格を掴まないといけないわけですから、
どのルートを通りましても、受験生の頭の中は、最終的
には「司法試験に合格」がもっとも重要で、それ以上も
それ以下も関係ない話ですもんね。
本当に視野が広くなったか否かは別として、
大学院へ行き、視野が広くなったが、新司法試験に
3度落ちて受験資格が無くなった法務博士号取得者と
予備試験に合格して、司法試験にも合格した人とでは
司法試験に合格しなければどうにもなりませんので
やはり、無駄なく合格できる道(専門学校で学ぶ等)
を進もうとするのは自然の流れだと思います。
どうしても法科大学院へ進むことを原則ルートと
したいのであれば、修了者には免除科目を与える
など、法科大学院に進んだのに受験、受験、と勉強
ばかりにならないよう大学院で視野を広くする時間
を設ける分、進学するメリットを創ればよいと思います。
ただし、司法試験の合格者のレベルを落とさないように。
大体、大学院側がそこが出来ていないから予備試験
を通り司法試験に合格した人のほうが優秀と言われる
のだと思います。
大学院も所詮は、学生集めの金儲け。
そこが間違いの元と気づくべきでしょうね。
・・・
しかし、私は、
受験資格の制限を設けない、例外ルートのほうが
「平等」な姿で、極当たり前の試験方法だと思い
ますね。
年齢制限や受験に規制をかける?もってのほか
の大間違いです。
合格できる出来ないは別として、受けること自体は、
誰にでも機会を与えるべきです。
どうしても、勉強、勉強、と受験勉強、司法試験
に合格するためだけの勉強になることを懸念する
のであれば、合格後に教育すればよいと思います。
まずは、司法試験へ合格しないと受験生は落ち着
かない、他の事に気を向けている暇など無いという
心理でしょうから。
合格後に、ほっとした合格者の視野を広げるために、
専門家による教育施設を公費で設け、その機関を
修了することを義務づけすれば良いと思います。
やはり、当初から「弁護士、裁判官になりたい
なら大学院(法科)へ行きなさい」ということ
自体無理があったように思います。
授業料が無料ならいいですけどね。
また、法科大学院を修了したという肩書きや
法務博士号など要らない、司法試験に合格して
弁護士、裁判官になりたいだけだ!という人が
大半なのが、司法試験受験者ということ自体
分かっていないのでしょうね。
高卒で弁護士になりました。
通信制大学を出て弁護士になりました。
法科大学院を出て弁護士になりました。
弁護士の世界では、「弁護士」という資格自体
が絶大であって、どこを出た、学歴がどうこう
という世界ではないですからね。
学閥のあるような大きな弁護士法人は別で
しょうけど、そんなところは極一部でしょう。
司法試験に合格し、弁護士、裁判官になったという
ことで、超一流の大学を出たのと同じ価値が
合格と共に一緒に付いて来るものですからね。
・・・
米国をマネして法科大学院制度を創ったこと
自体、日本ではその制度が合っていなかった
ということでしょうね。
毎日新聞 5月19日(日)19時10分配信
法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格
が得られる「予備試験」が19日、全国8会場で
始まった。出願者は1万1255人(前年9118人)
で、2011年の制度開始から2年連続で増加し、
初めて1万人を超えた。一方、法科大学院の今年度
の入学者は過去最低の2698人にとどまり、法科
大学院離れが進んでいる
予備試験は、経済的事情などから法科大学院に通え
ない人に門戸を開くため、合格すれば司法試験を受
けられる「例外ルート」として設けられた。
受験資格に制限がなく、司法試験の合格率も
法科大学院修了者より高い結果が出ていることもあり、
出願者数は年々増加している。
これに対し、「原則ルート」である法科大学院の
入学者数は、06年度にピークの5784人に達したが、
司法試験合格率の低迷などにより、その後は減少し
続けている。
政府の有識者会議は4月、「法科大学院教育の改善
状況も見ながら、予備試験を見直す必要があるか
どうか検討すべきだ」との中間提言をまとめている。
19日は短答式の試験があり、その後、論文式や口述
の試験を経て、11月7日に合格者が発表される。
合格すれば、5年以内に3回まで司法試験を受験する
ことができる。
法科大学院協会事務局長の中山幸二・明治大法科
大学院教授の話 受験技術に走る人が増え、視野の
狭い法律家を生むと批判された旧司法試験の反省から、
原則3年かけて幅広い法的素養を身につける法科大学
院制度が導入されたのに、予備試験組がエリート視
されるゆがんだ風潮が広がりつつある。予備試験に
年齢制限を設けるなど、早急な見直しをしなければ、
法科大学院制度は破綻する。
・・・
法科大学院の制度自体、無理があったように思います。
幅広い法的素養を身につけるという考え方は、正しい
とは思いますが、
「司法試験に合格して、弁護士という資格を取らなけ
れば、ただの人」なわけですから、試験合格に受験生
の主眼が行くのは避けられないものだと思いますね。
それに、「法科大学院」まで行かないと受験できない
という仕組みにすること自体、
おカネ(学費)、時間、早く社会人となり稼ぐ
という面で、法学既修者で2年、未修者で3年も
かかるというのは、経済的負担が大きすぎるのもネック
だと思います。
ほとんどの人は、社会人掛け持ちではなく、親に学費
を頼っての勉強への集中ですから。
現役、ストレートで修了しても24歳、25歳。
いい歳して、いつまでも親に学費を出させるのか
という問題もあります。
・・・
また、大学院を修了すれば「視野が広い人物になれる」
かどうかというのも疑問です。
結局は、「司法試験」という試験で篩いにかけられ、
その中で合格を掴まないといけないわけですから、
どのルートを通りましても、受験生の頭の中は、最終的
には「司法試験に合格」がもっとも重要で、それ以上も
それ以下も関係ない話ですもんね。
本当に視野が広くなったか否かは別として、
大学院へ行き、視野が広くなったが、新司法試験に
3度落ちて受験資格が無くなった法務博士号取得者と
予備試験に合格して、司法試験にも合格した人とでは
司法試験に合格しなければどうにもなりませんので
やはり、無駄なく合格できる道(専門学校で学ぶ等)
を進もうとするのは自然の流れだと思います。
どうしても法科大学院へ進むことを原則ルートと
したいのであれば、修了者には免除科目を与える
など、法科大学院に進んだのに受験、受験、と勉強
ばかりにならないよう大学院で視野を広くする時間
を設ける分、進学するメリットを創ればよいと思います。
ただし、司法試験の合格者のレベルを落とさないように。
大体、大学院側がそこが出来ていないから予備試験
を通り司法試験に合格した人のほうが優秀と言われる
のだと思います。
大学院も所詮は、学生集めの金儲け。
そこが間違いの元と気づくべきでしょうね。
・・・
しかし、私は、
受験資格の制限を設けない、例外ルートのほうが
「平等」な姿で、極当たり前の試験方法だと思い
ますね。
年齢制限や受験に規制をかける?もってのほか
の大間違いです。
合格できる出来ないは別として、受けること自体は、
誰にでも機会を与えるべきです。
どうしても、勉強、勉強、と受験勉強、司法試験
に合格するためだけの勉強になることを懸念する
のであれば、合格後に教育すればよいと思います。
まずは、司法試験へ合格しないと受験生は落ち着
かない、他の事に気を向けている暇など無いという
心理でしょうから。
合格後に、ほっとした合格者の視野を広げるために、
専門家による教育施設を公費で設け、その機関を
修了することを義務づけすれば良いと思います。
やはり、当初から「弁護士、裁判官になりたい
なら大学院(法科)へ行きなさい」ということ
自体無理があったように思います。
授業料が無料ならいいですけどね。
また、法科大学院を修了したという肩書きや
法務博士号など要らない、司法試験に合格して
弁護士、裁判官になりたいだけだ!という人が
大半なのが、司法試験受験者ということ自体
分かっていないのでしょうね。
高卒で弁護士になりました。
通信制大学を出て弁護士になりました。
法科大学院を出て弁護士になりました。
弁護士の世界では、「弁護士」という資格自体
が絶大であって、どこを出た、学歴がどうこう
という世界ではないですからね。
学閥のあるような大きな弁護士法人は別で
しょうけど、そんなところは極一部でしょう。
司法試験に合格し、弁護士、裁判官になったという
ことで、超一流の大学を出たのと同じ価値が
合格と共に一緒に付いて来るものですからね。
・・・
米国をマネして法科大学院制度を創ったこと
自体、日本ではその制度が合っていなかった
ということでしょうね。












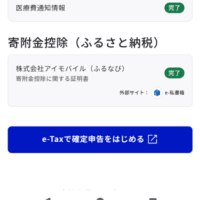
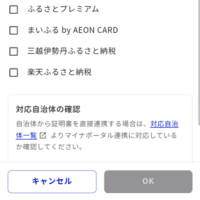


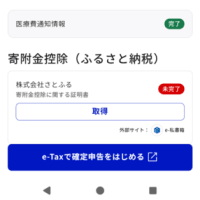
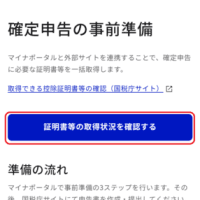




 耕三寺・善通寺
耕三寺・善通寺

 国分寺・厳島神社五重塔
国分寺・厳島神社五重塔


 祖母とよく訪れた四国八十八ヶ所霊場第51番札所石手寺
祖母とよく訪れた四国八十八ヶ所霊場第51番札所石手寺

 2024/9/20相変わらず仕事に追われた生活をしています。
2024/9/20相変わらず仕事に追われた生活をしています。





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます