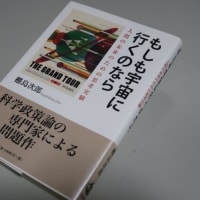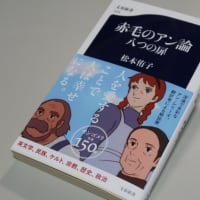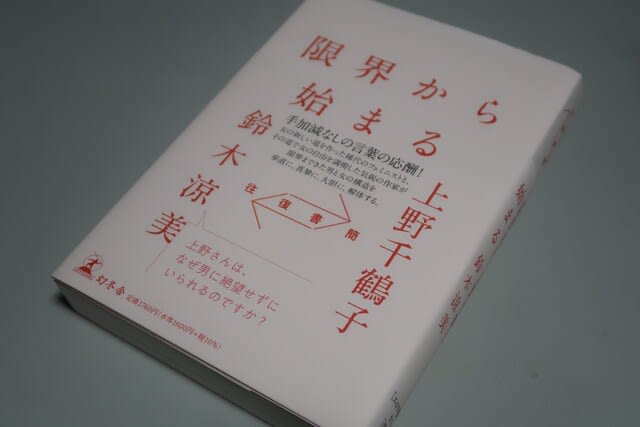
☆『限界から始まる』(上野千鶴子、鈴木涼美・共著、幻冬舎、2021年)☆
こんなにおもしろい本はめったにない。年齢差35歳の女性社会学者と女性作家による往復書簡。著者たちのことを何も知らずに読んでもおもしろいかもしれないが、書簡のやり取りに伴うスリリングな展開は、お二人の経歴や仕事を知っているか否かに左右されそうに思う。
幸いにもお二人の著作は、そのデビュー作から読んでいたので、おもしろさが倍加したのはまちがいない。もちろんお二人の著作のすべてを読んできたわけではないし、とくに上野さんの著作は膨大である。
思えば、上野さんのデビュー作『セクシィ・ギャルの大研究』(カッパブックス、1982年、現在は岩波現代文庫、2009年)を買ったのは、そのタイトルと掲載画像が当時まだ二十代だった男にとって刺激的だったことと、当時は金沢に住んでいたのだが、著者の経歴がお隣の富山県生まれで金沢市内の県立高校卒業だったこともあったはずだ。当時、上野さんは平安女学院短期大学に所属していたが、平安女学院短期大学なんて聞いたこともなかったし、上野千鶴子とはいったい何者なのかと思っていた。しかし、読み進めるうちに、一種の動物行動学的、あるいは記号論的な研究手法に興味を持ったのも本書のお陰である。
鈴木さんのデビュー作『「AV女優」の社会学』(青土社、2013年)は、その経歴とともにセンセーショナルに宣伝されたが、買ったのは出版1年後くらいだった。ちょうど母親の遠距離介護から解放され、良くも悪くもセンセーショナルな本にも手を出す余裕が出てきた頃だったと思う。しかし、実際に読んでみるとわかるが、東大の修士論文が元になっていることもあって、実にマトモな社会学書だった。たんなる「性の商品化」論に追随するものではないことも、一言付け加えておきたい。
この手の本に興味を持つ人ならば、いまは両者とも知らないという人は少ないはずだ。しかし、たぶんよくありがちだと思うのは、上野千鶴子は知っているが、鈴木涼美なんて知らない(あるいは知りたくもない)とか、鈴木涼美の書いたものは読んできたが、上野千鶴子の本など読んだことがない(あるいは読みたくもない)とか。どちらの思い込みも理解できるが、陳腐な独断は得策ではないのではないか、と個人的には思う。
一応、女性に向けて書かれた体裁をとっているが、ヘテロセクシュアリティの男性からすれば、まずは同類にこそ読んでほしいと思う。読めば痛みを伴うのはまちがいない。それでも、いや、だからこそ自らのジェンダー観を省みる試金石となるかもしれない。
卑近な(ひょっとしたら陳腐な)例えに言い換えれば、一種のリトマス試験紙の役割を果たすのではないか。リトマス試験紙は一次元的にPH(水素イオン濃度)を測るにすぎないが、もっと多次元的に自らの「男性性」が判定される。その判定結果から自らの「男性性」が問い詰められ、苦悶の読書体験となるかもしれない。読んだからといって、男性として免罪はされるわけでは全くないが、女性との関係性を捉え直すきっかけになる可能性がある。
自分がヘテロセクシュアルであることは確かだと思っているが、生まれながらに身体的に弱者だったからか、世間一般に通用しているような男性性にはついていけず、むしろ嫌悪に近い感情をずっと抱いてきた。だから、ふつうの(この定義は難しいが)男性とはちがって、男なのに男と居る方が緊張し、女と居る方が気持ち的に楽だったりする。教える仕事でも女の子を教える方がたいていは楽だった。
こういうふうに書くと、変態とまでは誤解されなくても、それって女性に対する幻想の裏返しじゃないのかと言われれば、それを否定するのは困難だ。男はよく、女は複雑でわからないと口にするが、男は男にとってわかりやすいのかと男に聞いてみたくなる。
中年になって大学に再入学したとき、大学で学ぶ学問的な興味とはまったく別に、男性性を問いなおすサークルのような集まりに入って(怪しげな宗教的サークルなどではないので、これも誤解しないように)しばらく通っていた。いまでいうLGBTQのような人たちもいて、けっこうこころが和んだものだった。それで男がわかったわけではないが、男がわかりたい男もいることがわかったのは収穫だった。
結局のところ、男は男性性を相対化して男を論じるのを避けたがるので(そうではないように見せかける男もいるが、たいていどこかでバレる)、男の書いた本を読んでも、自らの内なるミソジニー(女性蔑視)を直視できない。男性が書いたフェミニズムやジェンダーに関する本はたいていつまらない。
だから、上野さんや鈴木さんの本を読むことで、自らの内なる気持ち悪さをえぐり出し、痛みを伴う快感に浸ることができる。だからといって、どれだけえぐりだしたところで、ゼロベースになるわけではないし、罪と表現するものがあるとすれば、罪が免じられるわけでもない。
本書の「エロス資本」から始まって「男」で終わる12回(+「あとがき」)の往復書簡は、「性」だの「愛」だのが話題の中心のように見えるが、実際は生きていく上で考えたり悩んだりする事項について論じられている。親子や家族も大きなテーマになっているように思う。
そして最終的には「男」に収斂していく。さらに、上野さんなり鈴木さんなりが単独で論じているのではなく、大きな年齢差のあるお二人が、自らの経験も俎上に載せて語り合っているところに、本書の妙味があるのだと思う。本書は「フェミニズム」の範疇に入るのだろうが、その枠を大きく超えた読み応えのある良書だった。

本書は、鈴木さんの近著『娼婦の本棚』(中公新書ラクレ、2022年)といっしょに6月頃に買った。『娼婦の本棚』も、その刺激的なタイトルとは裏腹に、鈴木さんの読書体験を垣間見ることで、幅広い知的な側面を読者は知ることができるにちがいない。
その直後、鈴木さんの小説『ギフテッド』(未読)が芥川賞候補作になり正直驚いてしまった(結果的に落選したが)。『ギフテッド』はともかく、本書より先に読み終えた『娼婦の本棚』は一種の書評集だが、帯にも書いてあるように「世界に繋がって生き延びるため」に本は有用なものだと思わせてくれる。
数年前、林芙美子の『放浪記』を読んだときも同じような感想を持ったことを思い出した。本がなかったら林芙美子はきっと存在しなかったように、本がなかったら、いまの鈴木涼美はきっと存在しなかったはずだ。
こういった性にまつわることを書くと、露悪趣味だと思う人がいるかもしれない。さらにいえば、多くの人はこういったことを書いたり話したりするのをいまだにタブー視している。しかし、齢ン十年になり、いつ死んでもおかしくないという歳になると、自分が何を考えていたか、どんな思いで生きてきたか、生きてきた証みたいなものを残したくなるものだ。
このブログはいずれなくなるだろうが、この文章(だけに限らないが)を読んだ(読まされた)人のこころの内に、ほんの砂粒ほどでも自分という人間についての何かが残れば(たとえそれがマイナス感情だったとしても)満足だと思って書いている。

こんなにおもしろい本はめったにない。年齢差35歳の女性社会学者と女性作家による往復書簡。著者たちのことを何も知らずに読んでもおもしろいかもしれないが、書簡のやり取りに伴うスリリングな展開は、お二人の経歴や仕事を知っているか否かに左右されそうに思う。
幸いにもお二人の著作は、そのデビュー作から読んでいたので、おもしろさが倍加したのはまちがいない。もちろんお二人の著作のすべてを読んできたわけではないし、とくに上野さんの著作は膨大である。
思えば、上野さんのデビュー作『セクシィ・ギャルの大研究』(カッパブックス、1982年、現在は岩波現代文庫、2009年)を買ったのは、そのタイトルと掲載画像が当時まだ二十代だった男にとって刺激的だったことと、当時は金沢に住んでいたのだが、著者の経歴がお隣の富山県生まれで金沢市内の県立高校卒業だったこともあったはずだ。当時、上野さんは平安女学院短期大学に所属していたが、平安女学院短期大学なんて聞いたこともなかったし、上野千鶴子とはいったい何者なのかと思っていた。しかし、読み進めるうちに、一種の動物行動学的、あるいは記号論的な研究手法に興味を持ったのも本書のお陰である。
鈴木さんのデビュー作『「AV女優」の社会学』(青土社、2013年)は、その経歴とともにセンセーショナルに宣伝されたが、買ったのは出版1年後くらいだった。ちょうど母親の遠距離介護から解放され、良くも悪くもセンセーショナルな本にも手を出す余裕が出てきた頃だったと思う。しかし、実際に読んでみるとわかるが、東大の修士論文が元になっていることもあって、実にマトモな社会学書だった。たんなる「性の商品化」論に追随するものではないことも、一言付け加えておきたい。
この手の本に興味を持つ人ならば、いまは両者とも知らないという人は少ないはずだ。しかし、たぶんよくありがちだと思うのは、上野千鶴子は知っているが、鈴木涼美なんて知らない(あるいは知りたくもない)とか、鈴木涼美の書いたものは読んできたが、上野千鶴子の本など読んだことがない(あるいは読みたくもない)とか。どちらの思い込みも理解できるが、陳腐な独断は得策ではないのではないか、と個人的には思う。
一応、女性に向けて書かれた体裁をとっているが、ヘテロセクシュアリティの男性からすれば、まずは同類にこそ読んでほしいと思う。読めば痛みを伴うのはまちがいない。それでも、いや、だからこそ自らのジェンダー観を省みる試金石となるかもしれない。
卑近な(ひょっとしたら陳腐な)例えに言い換えれば、一種のリトマス試験紙の役割を果たすのではないか。リトマス試験紙は一次元的にPH(水素イオン濃度)を測るにすぎないが、もっと多次元的に自らの「男性性」が判定される。その判定結果から自らの「男性性」が問い詰められ、苦悶の読書体験となるかもしれない。読んだからといって、男性として免罪はされるわけでは全くないが、女性との関係性を捉え直すきっかけになる可能性がある。
自分がヘテロセクシュアルであることは確かだと思っているが、生まれながらに身体的に弱者だったからか、世間一般に通用しているような男性性にはついていけず、むしろ嫌悪に近い感情をずっと抱いてきた。だから、ふつうの(この定義は難しいが)男性とはちがって、男なのに男と居る方が緊張し、女と居る方が気持ち的に楽だったりする。教える仕事でも女の子を教える方がたいていは楽だった。
こういうふうに書くと、変態とまでは誤解されなくても、それって女性に対する幻想の裏返しじゃないのかと言われれば、それを否定するのは困難だ。男はよく、女は複雑でわからないと口にするが、男は男にとってわかりやすいのかと男に聞いてみたくなる。
中年になって大学に再入学したとき、大学で学ぶ学問的な興味とはまったく別に、男性性を問いなおすサークルのような集まりに入って(怪しげな宗教的サークルなどではないので、これも誤解しないように)しばらく通っていた。いまでいうLGBTQのような人たちもいて、けっこうこころが和んだものだった。それで男がわかったわけではないが、男がわかりたい男もいることがわかったのは収穫だった。
結局のところ、男は男性性を相対化して男を論じるのを避けたがるので(そうではないように見せかける男もいるが、たいていどこかでバレる)、男の書いた本を読んでも、自らの内なるミソジニー(女性蔑視)を直視できない。男性が書いたフェミニズムやジェンダーに関する本はたいていつまらない。
だから、上野さんや鈴木さんの本を読むことで、自らの内なる気持ち悪さをえぐり出し、痛みを伴う快感に浸ることができる。だからといって、どれだけえぐりだしたところで、ゼロベースになるわけではないし、罪と表現するものがあるとすれば、罪が免じられるわけでもない。
本書の「エロス資本」から始まって「男」で終わる12回(+「あとがき」)の往復書簡は、「性」だの「愛」だのが話題の中心のように見えるが、実際は生きていく上で考えたり悩んだりする事項について論じられている。親子や家族も大きなテーマになっているように思う。
そして最終的には「男」に収斂していく。さらに、上野さんなり鈴木さんなりが単独で論じているのではなく、大きな年齢差のあるお二人が、自らの経験も俎上に載せて語り合っているところに、本書の妙味があるのだと思う。本書は「フェミニズム」の範疇に入るのだろうが、その枠を大きく超えた読み応えのある良書だった。

本書は、鈴木さんの近著『娼婦の本棚』(中公新書ラクレ、2022年)といっしょに6月頃に買った。『娼婦の本棚』も、その刺激的なタイトルとは裏腹に、鈴木さんの読書体験を垣間見ることで、幅広い知的な側面を読者は知ることができるにちがいない。
その直後、鈴木さんの小説『ギフテッド』(未読)が芥川賞候補作になり正直驚いてしまった(結果的に落選したが)。『ギフテッド』はともかく、本書より先に読み終えた『娼婦の本棚』は一種の書評集だが、帯にも書いてあるように「世界に繋がって生き延びるため」に本は有用なものだと思わせてくれる。
数年前、林芙美子の『放浪記』を読んだときも同じような感想を持ったことを思い出した。本がなかったら林芙美子はきっと存在しなかったように、本がなかったら、いまの鈴木涼美はきっと存在しなかったはずだ。
こういった性にまつわることを書くと、露悪趣味だと思う人がいるかもしれない。さらにいえば、多くの人はこういったことを書いたり話したりするのをいまだにタブー視している。しかし、齢ン十年になり、いつ死んでもおかしくないという歳になると、自分が何を考えていたか、どんな思いで生きてきたか、生きてきた証みたいなものを残したくなるものだ。
このブログはいずれなくなるだろうが、この文章(だけに限らないが)を読んだ(読まされた)人のこころの内に、ほんの砂粒ほどでも自分という人間についての何かが残れば(たとえそれがマイナス感情だったとしても)満足だと思って書いている。