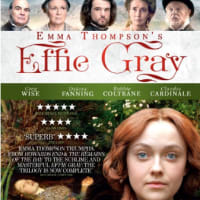「ナショナル・ギャラリー 英国の至宝」
[原題:'National Gallery']
監督 フレデリック・ワイズマン
2014
(IMDb)
いま、「美術館映画」が熱い。
先日、公開になったばかりの「みんなのアムステルダム国立美術館へ」。
来年の2月に公開される「ヴァチカン美術館4K3D天国への入口」。
そして、「ナショナル・ギャラリー 英国の至宝」(2015年1月17日公開予定)。
19世紀初頭に設立された、英国の誇る美の殿堂。
今日、この映画を試写会で鑑賞してきた。
会場は国立西洋美術館(上野)。
上映後には、馬渕明子氏(国立西洋美術館館長)や岩井希久子氏(絵画修復家)らによるトークセッションも行われた。
この映画、なんと上映時間181分(3時間)。
「みんなのアムステルダム国立美術館へ」が90分、「ヴァチカン美術館4K3D天国への入口」が66分なのと比べても、その長さには驚く。
観終わった感想としては、長さを感じさせないほど、とまではいかずとも、長さに相応しい、充実した内容の作品だと思った。
「みんなのアムステルダム国立美術館へ」の「前編」にあたる、「ようこそ、アムステルダム国立美術館へ」を観たときに思ったのだが、私はどうも、いわゆる「ドキュメンタリー映画」というのが苦手である。
テレビの特番でドキュメンタリーを観る分にはなんとも思わないのだが、映画のドキュメンタリーとなると、なんだか消化不良というか、本質的な意味での満足感を得られることが少なかった。
そんな感じで観に行った、今日の「ドキュメンタリー映画」。
この映画、ただの「ドキュメンタリー映画」ではない。
独特の音響効果。
いわゆる「インタビュアー」の存在を感じさせない、"selfless"な視点。
「心地よい違和感」を観客に与えながら、話は進行してゆく。
"documentary"というよりは、"dialogue"。
館長や専門家、有識者らによる会議の現場。
美術館の職員による一般向けの作品レクチャーの一コマ。
手に汗握る、修復家の一挙手一投足。
観客は、彼らの語りに誘われ、いつのまにか、その"dialogue"に加わっている。
映画の最後で二人のダンサーが出てきて、美術館内で踊っている場面に関しては、鑑賞後のトークセッションでも議論になっていたが、私個人としては、面白い演出だと思って観ていた。
あの場面は、(たしか)ディアナ(ダイアナ)とカリストだったり、ディアナとアクタイオンだったりといった、神話の物語に関連した絵画の解説がなされたあとに、二人が登場するという流れだったと記憶している。
カリストの前に登場したディアナとは、実際には、ゼウスが変身した姿であった。
この意味において、映画の最後に登場するダンサーの二人(男性と女性)は、ゼウスとカリスト、また、アクタイオンとディアナという男女の関係とパラレルになっているように、私には思えた。
(去りゆく二人の恋の行方は、誰にも分からない。)
また、細かいところでいえば、美術館の学芸員が、フェルメールの作品の特質を、「写実と抽象の間をとっているところ」と解説していたのが印象に残った。
私もそう思う。
《デルフト眺望》のような、現実の風景に取材してはいるが、だからといって「写実」の域には留まらず、有限の世界を越えたところに住まう、「超越」的な存在の影をも写し取っているように思われる作品などは、まさにその最たるものではないか。
プルースト(『失われた時を求めて』)がこの作品に言及したり、後世の人間が、フェルメールとスピノザとを結びつけようと試みたりするのも(参考)、この画家の作品に、たんなる「写実」の域を超えた、「なにか」をみてとっているからではないだろうか。
「時を越えて、美と出逢う」―。
ワイズマン(監督)の力作が、これだ。