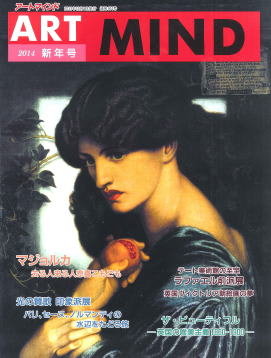CREA(クレア) 2014年7月号
(特集:「アート、足りてる? 人生にアートを! No Art, No Life 知る、観る、そして買う!」)
文藝春秋
2014
六本木の森美術館には折に触れてよく行くのだが、以前、入口の表記をみて一瞬驚いたことがあった。
「・・・モリアーティー美術館!?」
ホームズ物語にかぶれすぎといわれそうだが、"MORI ART MUSEUM"を"MORIARTY MUSEUM"に空目したのだ(モリアーティー教授はホームズの宿敵)。
そういわれると、"MORIARTY"にみえてこないだろうか(みえてこないか)。
閑話休題。
女性向け月刊誌CREA(クレア)のアート特集が昨日(6月7日)発売された。
そこまで突っ込んだ内容ではないが、中野京子氏や原田マハ氏、橋本麻里氏ら著名な方々が多く寄稿されている。
62-63頁の見開きで解説されている、四つの作品だけで日本と西洋の美術史をそれぞれ概観するという(やや乱暴な)まとめは、しかし、なかなか興味深かった。
少なからず、本質をついている。
西洋美術に関していえば、扱われていたのは次の四つの作品。
1.プラクシテレス《クニドスのアフロディーテ》

2.ラファエロ《アテネの学堂》

3.ダヴィッド《皇帝ナポレオン1世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠式》

4.デュシャン《泉》

それぞれ、古代ギリシア(ローマ)、ルネサンス、新古典主義、20世紀(ダダ)を代表する傑作群である。
個人的には3のダヴィッドと4のデュシャンの間に、印象派の作品をひとつ入れておいてほしかった。
印象派は、西洋美術史上で最大のパラダイム・シフトといって過言ではない。
さしあたり、モネの《印象・日の出》かルノワールの《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》といったところか。
あと、興味深かったのは105頁の原田マハ氏の寄稿文。
モネの使っていたパレットには、それこそ抽象画のように絵の具の色彩が配置されていた。
なんとも原田氏らしい細やかな視点である。
もう一点気になったのだが、123頁に、今年の秋から東京都美術館(上野)で開催される「ウフィツィ美術館展」の紹介記事があった。

その解説文のなかで、「日本初のウフィツィ美術館展」といった言い方がされていたが、本当なのか。
2010年には東郷青児美術館(新宿)で「ウフィツィ美術館―自画像コレクション」が開かれている。

細かいことだが、どうなのだろうか。
しかし(ホームズの話で始まり、ホームズの言葉で締めるのもなんだが)ホームズは言う。
"It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important."
(Conan Doyle 'A Case of Identity')
さぁ、「人生にアートを」。