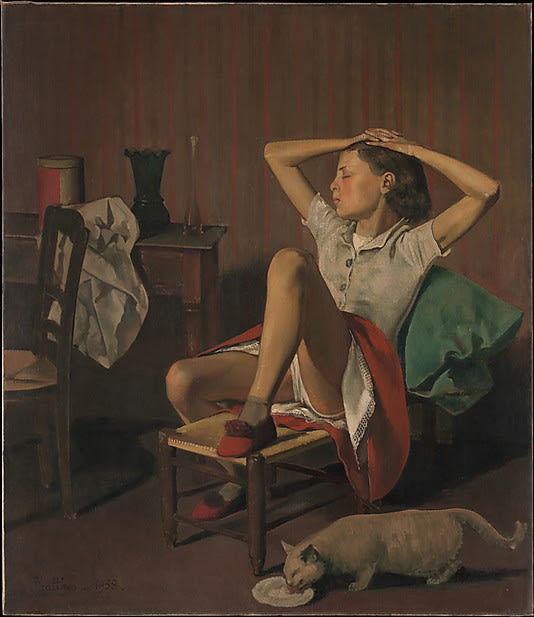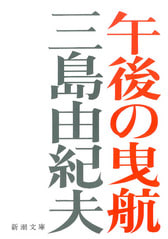“The smallest point may be the most essential.”
―Sherlock Holmes
―Sherlock Holmes
「都の西北」早稲田大学のシンボルともいえる大隈講堂。
この記念講堂が完成したのは1927年。
大学の創立者にして初代総長の大隈重信の逝去から5年後のことだった。
学内の学生向け週刊広報紙(WASEDA WEEKLY)の特集記事によれば、当時総長だった高田早苗は建設に際して二つの注文を寄せたという。
ひとつは「ゴシック様式であること」、もうひとつは「演劇に使えること」であった。
後者についてはともかく、前者についてはややひっかかる。
大隈講堂は、本当に「ゴシック建築」なのだろうか。
たしかにウィキペディアには「チューダー・ゴシック様式」とある。
しかし、出典がわからない。
ざっとネット検索をかけたところでは、大隈講堂が「チューダー・ゴシック様式」であると明言しているのはこのウィキペディアページ以外ほぼ皆無といっていい。
この点についてひとつ考えられるとすれば、おそらくウェストミンスター寺院との関連であろう。
大隈講堂の鐘の音は、この由緒ある英国の寺院のそれにならっている。(→参考)
そしてこのウェストミンスター寺院は、すべてではないにせよ、大部分はチューダー王朝期のゴシック様式で作られているのだ。(参考:"Tudor architecture")

ウェストミンスター寺院
とはいえ、まだすっきりしない。
大隈講堂には、いわゆる「純粋な」ゴシック建築の〈クオリア〉が欠けているような気がしてならない。
それこそ、19世紀英国の美術批評家ラスキンが、「純粋な」ゴシック様式の荘厳な美を手放しで称賛した一方で、彼にとっては「亜流」に過ぎない「ゴシック・リヴァイバル」の建造物については手厳しかったように。
「ゴシックの本質」の章が挿入されている著書『ヴェネツィアの石』でも知られる彼は、たとえばこうした「復興期」の建築の代表例ウェストミンスター宮殿の様式をみて激しく嫌悪したという。

ウェストミンスター宮殿
さて、大隈講堂の建設に大きく携わったひとりが、早稲田大学建築科を創設した人物でもある佐藤功一であった。
ここに、彼の手掛けた建築のひとつ「岩手県公会堂」の建築様式について書かれた一本の論文がある。(参考:「岩手県公会堂の建築様式に関する研究」)
この論文のなかでは、大隈講堂を含む複数の「佐藤建築」についても言及されている。
論者は、佐藤功一の建築の多くが「ネオ・ゴシック」と評されていることをふまえたうえで、この岩手の公会堂が、「ネオ・ゴシックを下敷きとした表現主義の建築」であると述べている(60頁)。
ちなみに「ネオ・ゴシック」という用語については、「ゴシック・リヴァイバル」とほとんど同義といっていいだろう。
岩手県公会堂については実物を見たことがないので何とも言えないが、少なくとも、佐藤の建築の多くが「ネオ・ゴシック」と呼ばれ、それゆえ「純粋な」ゴシック建築とは一線を画していることだけは確実に言えると思われる。
「表現主義」うんぬんについては何とも言い難いが、よくよく考えてみれば、そもそも、「グリーク・リヴァイバル」にせよ「ゴシック・リヴァイバル」にせよ、復興期の建築の特質のひとつはその「折衷主義」ではなかったか。
『西洋建築様式史』(美術出版社)には次のようにある。
「[19]世紀の後半は諸様式のリヴァイバル(復興)の時代となった。復興様式はさらにそれぞれの国の伝統と混ざり合い、ひとつの建物に複数の様式が折衷されることもあったが、建築の格付けのための重要な表現媒体として生き続けた」(142頁)。
それゆえ、「表現主義」の要素があるかどうかはともかく、「純粋な」ゴシック建築に様々な様式を混ぜ合わせるという「折衷主義」の気風が、復興期の建築、ひいては佐藤の建築の精髄であったことは間違いないだろう。
文化遺産に関するこちらのHPでは、「ロマネスク様式を基調としてゴシック様式を加味した我が国近代の折衷主義建築の優品」として、大隈講堂が紹介されている。
また、早稲田大学のHPでも、この記念講堂は「入り口の尖頭アーチや鐘楼デザインなど建物全体はゴシック様式を基調とし、大隈庭園側の半円アーチが連続した回廊にはロマネスクのエッセンスを加えるなど、2つの様式を巧みに折衷した日本近代建築の名作」であると評されている。

大隈講堂(回廊)
したがって、結論としては、大隈講堂は「純粋な」ゴシック建築ではない。
その基盤にみられるのは、あくまで「ネオ・ゴシック」的な折衷主義の理念である。
ロマネスク、ゴシック、そしてあるいは表現主義。
そうした多様な様式の結晶として、大隈講堂は都の西北に息づいている。