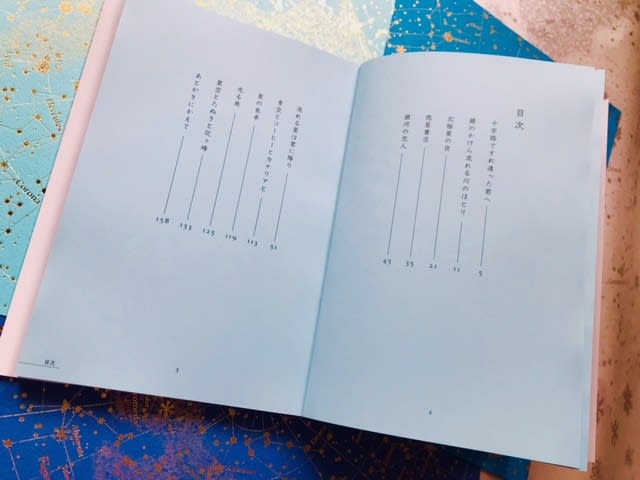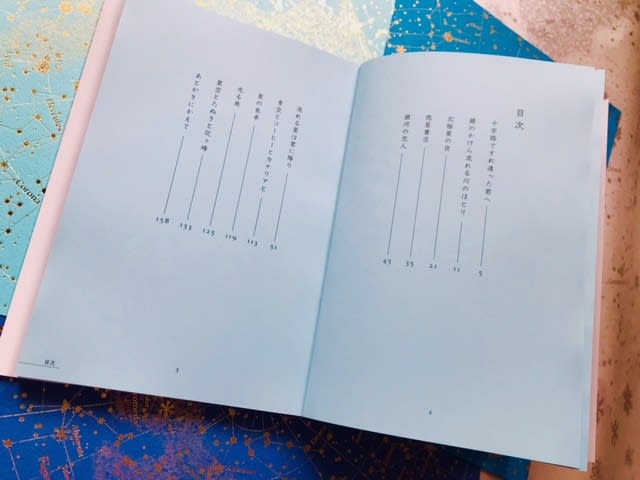『つばさ屋』
第二章 出会いのつばさ
ぼくが、「その人」と出会ったのは、兵舎に入って、しばらくたった日のことです。
「その人」の名前は、「ツバサ」といいました。
この基地から、前線となっている、南の国へと発つ予定のために、他の基地からうつってきたのです。
ぼくの部屋に、いく日か、滞在することになりました。
なぜなら、さいしょは、五人いたぼくの部屋の仲間たちは、みな、行方不明になっていて、
今、部屋には、ぼくひとり。もちろん、ベッドは空いていました。
「ツバサ」という名前を聞いたとき、まるで、飛ぶために生まれてきたような名前だなあ、と思いました。
そう言うと、ツバサさんは、人なつこく笑い、うなずきました。
「いい名前だと、自分でも、思っています。空がね、好きなんです。飛ぶのが、好きなんです」
「空が好きなんです」と、ツバサさんは、どこまでもすきとおる世界を夢中で飛ぶ中で見つけた、
どこにもないのだけれども、たしかに自分の心にはある、そんな宝ものをいつくしむような、
いとおしくだきしめるような、なんともいえない、すてきな表情で、そう言いました。
―空が好き―
―飛ぶのが好き―
ああ、そうです。ぼくもなんです。
ぼくも、空が好きなんです。飛ぶのが、大好きなんです。
思わず、そう答えていました。
さつばつとした兵舎の生活で、ぼくは、すっかりそんな(何かを「好き」である、と、なんのてらいもなく言うような)
感情も表現も、なくしてしまっていることに、気がつきました。
「ツバサ」という名前と「空が好き」「飛ぶのが好き」という、心ひかれる言葉たちに、
ずいぶん長いこと、心のいちばん、おくの、おくの、目につかないところに、おきざりにしてしまい、
そのまま忘れてしまっていた、きらきら光るものを、ふたたび見つけたような、そんな気分がよぎり、
かがやいていた夢を思い出しかけていました。
ツバサさんは、ぼくより、ずいぶん、年上の男の人でした。
すらっとした体型のツバサさんは、飛行士の制服を、とてもおしゃれに、着こなしていました。
聞けば、飛行士の養成所を卒業したのちは、家業の、紳士服の仕立て屋をついで、
紳士服をデザインしたり、仕立てたりしているということでした。
なるほど、となっとくしました。
服のデザイン、仕立てをやっているという、そのせいなのか、制服もそうですが、
飛行士が首にまくスカーフのまきかたひとつにしても、とてもスマートで、かっこうがよくて、
自分に似合う身につけ方を知っているような、そんな感じにみうけられました。
ツバサさんが、出発(「出撃」という言葉は、ぼくは好きではないので、使いたくありません)
するまで、ぼくたちは同じ部屋で寝起きすることになりました。
出発の命令は、いつ出されるかわかりません。
もしかしたら、ぼくのほうが先かもしれません。
それまで、ぼくたちは、いっしょです。
目を閉じても、どうしても眠れないある晩のこと。
ツバサさんも、そんなようすでした。
となりのベッドで、いくどもねがえりをうっているようでした。
月あかりが、まどから、差しこんでいて、夜もおそいというのに、部屋の中は決して暗くはなく、
やわらかい色の電球に、ふんわりと包まれているような明るさでした。
「写真を見ているのですね。まいばん、見ているようですが」
ぼくが、毎夜毎夜、妻と子どもの写真をなでては、なにやらぶつぶつと
となえているのが、ツバサさんにも、わかったみたいです。
同じ部屋で、夜を過ごすのですから、そっと流したつもりの涙も
もしかしたら、気づかれているのかもしれません。
「妻と子どもです」
ぼくは、ツバサさんに、写真を見せました。
「やさしそうなおくさまと、かわいらしい子どもさんですね」
「ツバサさん、ご家族は?」
ツバサさんは、うなずきました。
彼も、ぼくと同じように、胸ポケットに写真をしのばせていました。
とりだして見せてくれました。
「つばさ屋」という、かんばんを、かかげた店の前で、三人家族が
ほほえみ、肩をよせあい立っていました。
「妻と息子です。息子は、今、店をつぐために修行中ですよ。やはり、わたしとおなじように
飛行士養成所へ通っていましてね、やっと卒業したところです。
もうすぐ、戦争への出動命令が出るかもしれませんね」
「そうですか」
と返事をして、ぼくはひとつ、ぎもんに思いました。
仕立て屋さんをつぐのに、飛行士養成所へ? なぜ?
「どうも今夜は月がまぶしくて、眠れませんね。
どうです。ふたりで、こっそり、外で、お月見でもしませんか」
ここへツバサさんがやってきてから、空が大好きだった自分を思い出していたぼくは
むしょうに、じっくりと、空をながめたくなっていました。
すぐにうなずきました。
外へ出たツバサさんとぼくは、兵舎からは見えないように
走路のわきの木かげに、こしをおろしました。
「満月ですね」
ツバサさんがしみじみとした声で言いました。
「ええ。月のあかりがこんなにまぶしい」
「いい夜空だ」
「ええ、いい夜空です」
「こんなにいい空を、戦闘機に乗って飛びたくはないものです」
「ぼくも、そう思います」
やはり。ツバサさんも、ぼくと同じ気持ちだったのです。
争うためではなく、飛びたい。空の無限の広さにまけないくらいの
夢をもって、空を、飛びたい。
ぼくが、そんなことを伝えると、
「いつか、戦争が終わったら―そういう日がきますよ。いや来なければならない」
ツバサさんは、月を見つめたまま、自分に言い聞かせるように
「きっと」と、力強く、言いました。
実は、ツバサさんには、明日の朝、出発の命令が出ていました。
行き先は、最前線の、南の島でした。
島の近辺の海にうかんでいる「敵国」の艦隊への爆撃を、命じられていました。
「わたしは、もう、帰ってこられないでしょう」
「ツバサさん、なにをおっしゃるんですか。きっと、帰ってきてください。
おくさんや子どもさんも、待っていらっしゃるでしょう」
「この島へ向けて飛び立った飛行機が、帰ってきたためしがありますか」
ぼくには、こたえようがありませんでした。
どの飛行機も、いや、飛行士も、片道の燃料だけで行き
二度と基地にもどってくることはありませんでしたから。
「さいごに、同じ部屋になったよしみで、ひとつ、話を聞いてくれませんか」
「はい。なんなりと」
「実は、これなんですが」
ツバサさんは、ズボンのポケットから何やらとりだし、地面に広げてみせました。
「こ、これは?」
それは、どうみても、鳥のつばさのような形をしていました。
透明感のある青色です。月のあかりをうけて、金色の粉をまぶしたように、きらめいていました。
「さわってみてください」
おそるおそるさわってみました。
布だということがわかりましたが、なんという、手ざわりでしょう。
今までにさわったことのない、ぼくの知らないかんしょくでした。
やわらかくふんわりとして、肌にすこぶるなじみのいい、そんな感じでした。
「こ、これは、なんですか?」
「ごらんのとおり、つばさです。わたしは、つばさの仕立ても、やっているんですよ」
「つばさの仕立て……」
「ええ、人がそれを背中につけて、空を飛べるつばさです」
そんなばかな、とぼくは思いました。
人がつばさをつけて空を飛べるなんて。
「信じられませんか?」
ぼくはうなずきました。
そんなりくつや理論は、飛行士養成所では学びませんでした。
「理論より実践です。やってみましょう」
ツバサさんは、地面においたつばさを、ぼくの背中に当てました。
つばさがぼくの背中にあたったしゅんかん、ぼくは、またおどろきました。
あまりにも背中やうでの骨や筋肉に、しっくりとなじんだからです。
ツバサさんが、後ろでなにやら、くくりつけたり、こすったりしているようでしたが
ぼくには見えません。
「飛んでみてください」
「え」
あっという間に、ぼくのからだは、重力などまるでないかのように
うかんでいました。
うでにそって、つばさがのびているので、うでを、ぱたぱたとすれば
飛べるのがわかりました。
気がつくと、ぼくは、夢中で、満月の夜空を飛んでいました。
月が近づきました。
星が近づきました。
ビロードのような夜の空が、目の前に広がりました。
味わったことのない、気持ちのよさでした。
夢のようだ。
夢を見ているのではないか。
どのくらい、飛んだでしょうか。
時間がわからないくらい、夢中でした。
下で、ツバサさんが手をふっているのが見えたので
ずいぶん、自分は飛んだのだと思い、やっと着地しました。
ぼくの心臓は、どきどきと波打っていました。
「どうでしたか?」
「ええ、すばらしい。夢なら覚めないでほしいなあ」
「これで信じてもらえましたか」
ツバサさんは、ぼくの背中から、つばさをはずし、ふたたび小さくおりたたみました。
「実は、あなたに、お願いがあるのです」
ぼくは、まだ夢をみているようでした。
つばさをつけて空を飛んだという、心地よさの冷めないまま、なかば、上の空で
なんでしょうか、とツバサさんにたずねました。
「これをわたしの形見として、妻と息子に届けてもらえないでしょうか」
「形見……」
「ええ、これは、わたしの中でも自信作です。息子には、もっともっと、おしえたいことがありました。
わたしと息子が飛行士養成所へ通ったのは、飛ぶ、ということについて、理論を学ぶためと、深く考えるためです。
つばさ屋は、わたしの家だけで、代々つづいている老舗なのです。わたしが帰らなかったら
息子はさぞ、ざんねんがることでしょう。わたしの知識は、書き置きして、手わたしてあるのですが……
できることなら、いっしょに、いいつばさを作りたかったなあ」
ぼくは、すっかりわれにかえりました。
そうです。
ツバサさんは、明日、二度ともどってこられないかもしれないところへ、発つのです。
「これが地図です。つばさ屋への地図です。どうかよろしくお願いします。夢を持って飛べる日はきっ来ると思います」
ツバサさんは、事前に用意していたのか、鉛筆でていねいに書かれた、つばさ屋への地図と
おりたたんだつばさを、深々とおじぎをしながら、ぼくに、さしだしました。
次の日の朝早く、ツバサさんは、飛び立って行きました。
そうして、ツバサさんの消息は絶たれました。
それからしばらくして、ぼくにも出発の命令が下されました。
行き先は、ツバサさんと同じ、南の島沖でした。
幸い、ぼくの上官は、とても情けの深い人でした。
出発の前、妻と息子が面会にきてくれることを、許してもらいました。
二度ともどれないかもしれない最前線に行くことは秘密です。
妻は、この再会を飛び上がるようにして喜んでくれました。
息子も笑顔でした。
ツバサさんとの約束が頭をよぎります。
果たさねばなりません。
が、明日出発するぼくに、約束を果たす望みは、うすそうです。
あずかったつばさと地図は、理由を言って二人にたくしました。
妻と息子の笑顔を胸に、ぼくは次の日、飛行機に乗りこみました。
夢をもって飛べる日は、きっと来る。
ぼくに、消えそうだった夢を思い出させてくれた、ツバサさんのことばを
口に出し、操縦桿をにぎりました。
―行ってきます。
ぼくの飛行機は、朝焼けの中、離陸しました。
……………… ……………… ……………
ぼくの話は、ここまでです。
この続きは、子どもたちが、つむいでくれることを、信じています。
つばさの物語のとびらを、
未来の、きみが開いてくれることを願って。
(第三章に続く)