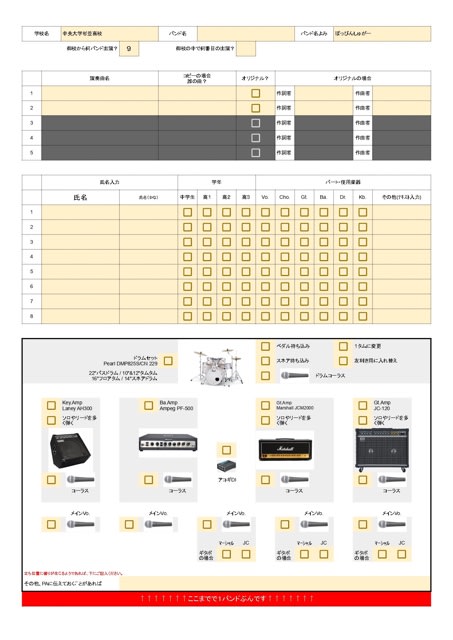当初、この記事は2024年緑苑祭のふりかえり記事の一部として書き始めたのですが、「もはや文化祭関係ないな」と思いまして、当ブログ「雑」カテゴリの記事に回ることになりました。
こんな記事を吹奏楽部さんが読んでくれるとは思いませんが、音楽部の1年生の勉強用+「今後に向けて」ということで…。
1.本記事執筆の背景
後夜祭の吹奏楽部とのコラボについては、例年コミュニケーションに苦労しており、今年もまた然りだったようです。
今年は、例年以上に「吹奏楽部の音が聞こえない問題」が前景化することになりました。(過去は、吹奏楽部さんが「聞こえないのは承知の上」という形での出演だったので、前景化することはありませんでした。)
「マイクを立てたとしても、吹奏楽部の音をスピーカーから出すのはかなり難しいーーということを、吹奏楽部さんにも十分に説明するんですよ」ということを3年生にはしつこく伝えましたし、3年生なりにその努力はしたのだと思います。ただ、なかなかそれは簡単ではなかったようです。
2.マイクのこと
私達がやっているように、マイクで音を録り、それをスピーカーで増幅して流す作業のことを”PA”と呼んでいます。これは”Public Adress”の略で、「広く公衆に伝達すること」の意です。
(軽)音楽部にでも居ないと、ロックバンドのPAが何をしているのかーーなんて考えたこともないと思いますが、基本的なことは
・演奏者の音をマイク等で集音する
→ミキサーで個々の演奏者の音量や音質(後述)を調整する
→音を大きくしてスピーカーから流す
というプロセスです。ドラムセットやギターアンプはそれ単体でも相当大きな音を出すことができますが、ギターアンプから出ている音もドラムセットの音もマイクで拾い、音量音質をミキサーで調整しています。
そういうわけで、ドラムやエレキギターほど大きな音が出ない管楽器は、マイクで音を録らないと、聴衆に音を届けることはできません。
ただ、この「マイク」への理解がまた曲者です。「吹奏楽部全体の音をスピーカーから流したいのなら、吹奏楽部全体の音が聞こえる位置にマイクを立てて集音すれば良いのでは?」と思いますよね。これが、そういうわけにはいきません。マイクには「感度」があります。「音を拾いやすい/拾いにくい」という感度です。
吹奏楽部の「全体の」音を拾うとなるとマイクの感度を上げて音を拾いやすくする必要があります。(カラオケのマイクだって、マイクから口を離すと音を拾いにくくなりますよね?)しかし、「音を拾いやすくする(我々は「Gainを上げる」と言います)」ということは、スピーカーから出る音も拾いやすくなります。つまり、マイクで音を拾う→スピーカーから流す→スピーカーから出る音をマイクで拾う→スピーカーから流す…というループが起こります。これがハウリングです。つまり、「吹奏楽部の全体の音を空間で集音する」ということは不可能に近いのです。
実際にボーカルはマイクにほぼ口が付くくらいの位置で歌いますし、ギターアンプにマイクを立てるときも、音が出る場所に直にマイクを当てています。マイクによる音の集音は(多くの場合)空間を介さず直接音がマイクに入ることが理想となります。今回も、吹奏楽部さんに「できる限りマイクとゼロ距離で演奏をしてくれ」とお願いしたのはそういう理由です。
3.耳の問題
そういうわけで、今回は吹奏楽部用に5回線(=マイク5本)用意したわけですが、「その5つの楽器の音だって聞こえないじゃないか」という声が吹奏楽部さんから聞こえてきました。
方や音楽部員の感覚としては「思っていたよりも聞こえる」でした。これは、それぞれの部活エゴの問題ではなく、「耳の問題=音の聞き方」に問題があります。
音楽部は普段から「音の棲み分け」を意識した「音作り」をしています。後述しますが、音量とは別に音質を工夫しないと音はグチャグチャして、「何かが鳴っているけど、うるさいだけで音楽としては聞きづらい」ということが起こります。
吹奏楽部さんの場合は(おそらくですが)、全体の音の調和とか融合をめざしていますよね。吹奏楽のアレンジは、Aの楽器とBの楽器が同じ旋律を奏でる場面が多いと聞きますが、それもAとBの楽器それぞれを聞いて欲しいのではなく、それらの混じり合った音を聞いてもらうことを目指しているのだと思います。
一方、PAを介した音楽をやっているロックバンドなどは、あまりそういうことはしません。仮にXの楽器とYの楽器がユニゾンフレーズを弾いたとしてもそれぞれの音が分離して聞こえることを目指します。(テンポからズレた演奏する、という意味ではありません!)
そのために行うことがイコライザー(=EQ≒音質)の調整です。例えばベースという楽器は、音階の上では低音を担っているわけですが、アンプから出る音は低域の周波数もあれば、高音の周波数も含みます。(一般に人間が聞こえる周波数帯は20Hz〜20000Hz(20kHz)だそうです。)このベースの高音域があまり出力されると、ギターやボーカルなどの音を出力する際に邪魔になってしまいます。ですので、それぞれの楽器や歌をEQ上で棲み分けるという操作をします。ギター・ベース・キーボードは楽器側(それぞれのアンプ含む)でもEQの調整をしますし、さらにそれらをミキサーの側で調整します。歌やドラムなど楽器側(演奏者側)でEQ調整できないものは、当然ミキサー側での調整となります。
…ということを日常的に意識を向けているがゆえ、音楽部は「スピーカーからどの帯域が出力されているか」「どの帯域(周波数)が音が被っているか」を聞き分けるを訓練をしています(顧問も含め全員その「道半ば」です)。ですので、そういう訓練をしている音楽部の立場から言うと、今回のコラボ演奏の吹奏楽部の音は「けっこう出力されていた」ということになります。(「それをもっと聞きやすくできないのかよ!」という疑問については後述。)
これは、別にそういう訓練をしている音楽部員の耳が優れている、とかそういう話ではなく、調和を聞く訓練をしている吹奏楽部、分離を聞く訓練をしている音楽部、という特性の違いなのです。
3.音量を絞れば良いのか?ーーDead or Live
「それにしたって、音楽部の音はあまりに大きすぎるじゃないか!」ーーそう思いますよね。私も中学生の時に始めて西武球場(現ベルーナドーム)でロックバンドのライブを観に行ったときに「なんじゃ!この音量は!!」と思ったのをよく覚えています。ライブハウスもそうですが、まあとにかく音が大きいですよね。
もちろんこの理由の一つに「ロックならではの迫力を求めて」ということもあるのですが、じゃあその音量を絞ることが簡単なのかーーというと一筋縄ではいきません。
ロックバンドでもDJイベントでもそうですが、大きい会場になると、会場の壁や天井による反響が生まれます。音は跳ね返れば跳ね返るほどグチャグチャしますし、先述のようなハウリングの原因にもなります。ですので、「反響した音ではなくスピーカーからダイレクトな音を観客に聞かせる」ということが求められます。そのためには、あの音量が必要なのです。
ですから、今回、「音楽部の音をもっと絞って吹奏楽部の音を出すことができたのでは?」という疑問もあったかと思いますが、音量を絞ったところで客席からは反響音を聞くことになってグチャグチャするだけで、結局吹奏楽部の音も音楽部の音も聞こえない、という事態を招くことになるのです。
(合唱や吹奏楽のように生の音を観客に聞かせたい場合は、会場の響きが重要になりますよね。PAの場合はこれが全く逆でして、響かない会場であればあるほど良い、ということになります。こういう響かない会場のことを我々は「デッド(Dead)な会場」と呼んだりします。中杉の視聴覚室は、かなりデッドです。)
4.アレンジの問題
「たくさんの音を出してその調和を聞かせる吹奏楽」と「限られた音数を周波数帯ごとに分散させて個々の音の分離を目指すPA」は、そもそも食い合わせがかなり悪いーーということを、ここまで説明してきました。例えるなら、「サッカー選手もアメフト選手もフットボール選手だから、一緒にラグビーができるよね?」と言っているようなものです。「同じ音楽」「同じ合奏」「同じポップス」だからといって、何でも一緒にやってうまくいくわけではありません。
これに加え、今回の演奏の場合、「吹奏楽だけで成立するアレンジ」と「バンドだけで成立するアレンジ」を一斉に演っているのが致命的でした。
PAのことを知らないと、「全部鳴ると全部聞こえる」ような気がしますが、PA的には「全部鳴る=全部聞こえない」です(ノイズキャンセリングのイヤフォン&ヘッドフォンもこの仕組みを利用して、外部の音と逆位相の同じ音をぶつけることで外部の音を消しているのです)。今回の場合、例えばトランペットの出す周波数はフルートの周波数を網羅してしまうため、フルートが聞こえるようなPAをするためには、他の音を犠牲にするしかないのです。そういう「同居し得ない」組み合わせがたくさんあった、ということなのです。
ボーカルのメロディラインをなぞる楽器がありましたが、「歌もの」である以上、歌が優先されます。繰り返しますが、それを両方聞こえるようにすることはできないのです。いや、できるのですが、その「歌」と「歌メロをなぞる楽器」を両方とも聞こえるようにするために、今度は他の楽器の音を犠牲にする必要があるのです。
5.合同演奏は可能か
以上を踏まえた上で、それでも音楽部と吹奏楽部が一緒に演奏するとしたら、どういう形があり得るでしょうか。
案1)もともとホーンセクションが入っている楽曲をカバーする。(音楽部>吹奏楽部)
スカやファンクのようなホーンセクションのいる音楽は原則として、ギターや鍵盤が鳴っている瞬間とホーンセクションが鳴っている瞬間を分けたアレンジになっています。
一般的に、スカやファンクなどのジャンルに入るホーンセクションというと、サックス・トランペット・トロンボーンです。低音域はエレキベースが担うことになりますし、楽曲のコード感はギターやキーボードが担うことになります。
この形なら、吹奏楽部(ホーンセクション)をバッチリ聞こえるように調整することが可能です。ただし、それ以外の吹奏楽の低音楽器や木管楽器の人に出番はありません。
案2)吹奏楽部のアンサンブルにギター、ベース、(ドラム)として音楽部が参加する(吹奏楽部>音楽部)
上の案では、吹奏楽部がせいぜい3人しか出演できませんから、納得がいかないですよね。ということで、こちらの提案です。吹奏楽部の演奏する楽曲の中には、ドラムセットやエレキベースを使用する楽曲がありますよね。こうしたリズム隊だけ音楽部が参加するやり方です。PAは利用せず、普段の吹奏楽部さんがやっているように、ドラムは生音、ベースはベースアンプから出力します。加えて、吹奏楽部さんがソロ回しをするついでに、ギターソロの場面を作ってもらう、なんていうのはどうでしょう。(こちらもPAを介さず、ギターアンプの音を観客に届けることになります。)
ただ、音楽部のドラムの演奏は、吹奏楽部よりもかなり音量・音質の面で主張が強いので、「このドラム、うるさいな…」ということが起こるかもしれません。
当然のことながら、こちらの案の場合、音楽部員は最大でも3人混ぜてもらうのが限界です。また、演奏全体の音量としては案1よりも小さくなってしまうため、案1→案2の順で演奏すると、会場は盛り下がることになるので注意が必要です。
いかがだったでしょうか。いずれにしても、「音楽部員大勢+吹奏楽部員大勢」という形態でのコラボ演奏は無理だということがご理解いただけましたか。また、(きっと読んではくれないでしょうが…)「別に音楽部がエゴで大きな音を出して吹奏楽部の演奏をかき消そうとしていた」というわけではないことをご理解いただけたら嬉しい限りです。