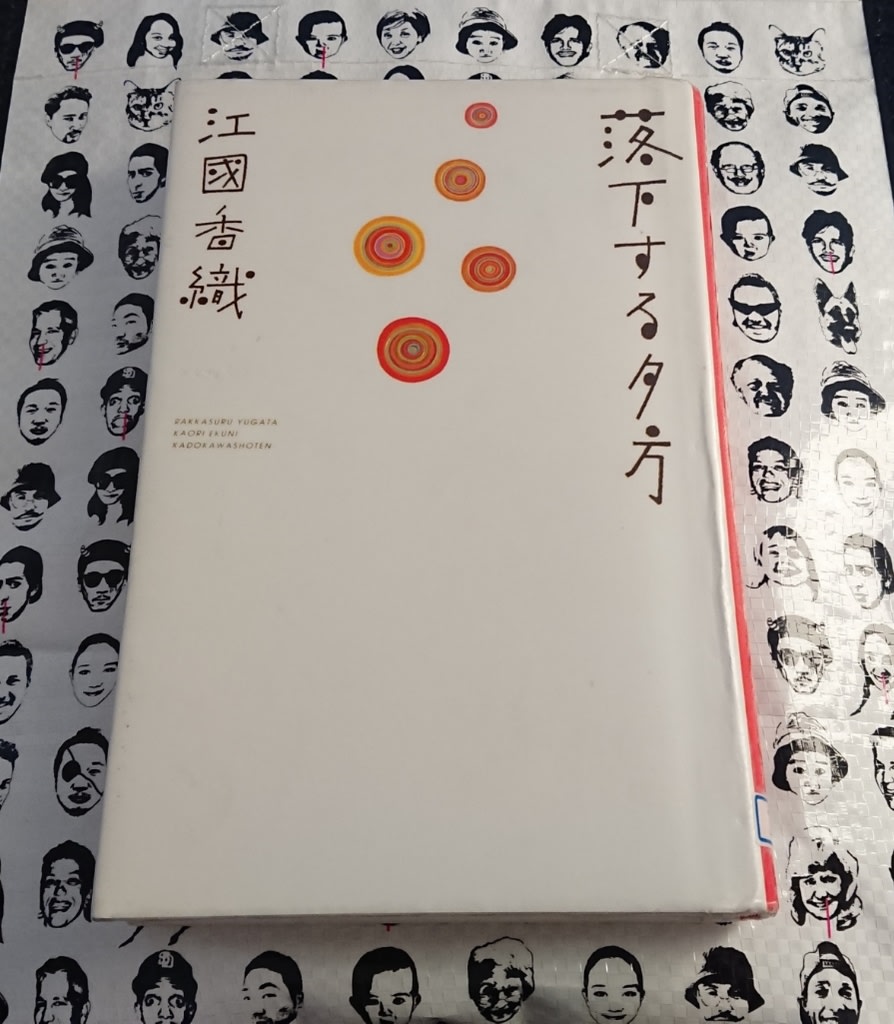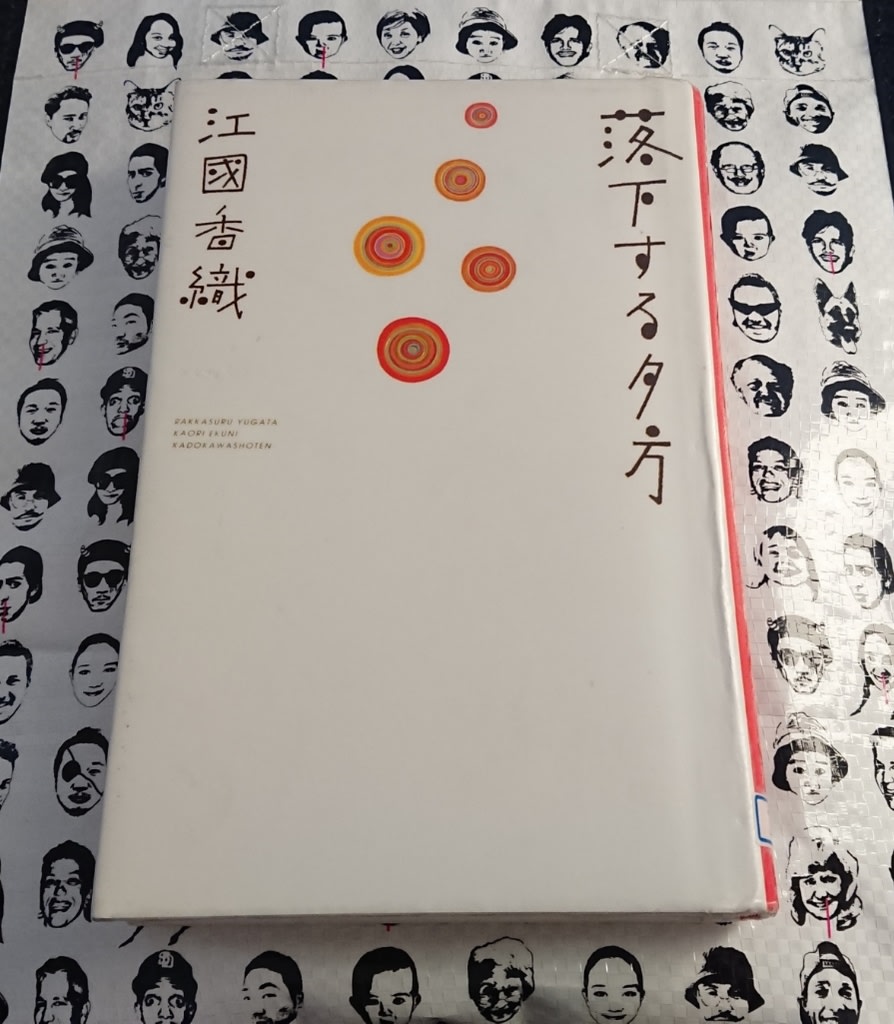江國香織
『落下する夕方』★★★★
未読本発見☆
金曜の夜から体調不良が続き、
我が身体なのに何も分かっていないなと嘆く・・
一つ一つ順番にどこかが壊れてゆく。
今はまだ気力でカバー出来るけど、この先のことを思うと暗澹たる気持ちに。
頼れる支えが必要だと実感
そんな暗い気持ちになった真夜中
早寝したせいで目が冴えてしまってこの本を手に取った。
で・・ラストのまさかの衝撃で気づくと明け方の4時!
(もちろんその日はお仕事です)
いやー徹夜読書なんて久々
身体のつらいことも忘れ、世界に没頭してしまった(笑)
この話「ヤバイ」ね(20代女子と仲良くしていると口から自然に出てしまう)
感化されやすいのか、今年出逢った年上のおじさまを思い出し、
机の中から名刺を引っ張り出して、電話番号に名前を登録した。
そうよ。いつの間にか仲良くなってるパターン?
来るもの拒まず去るもの追わず。
華子 強烈だけど愛おしい。
---
「なんでもいいけど、必要なものははなしちゃだめよ」
空にはピンクグレープフルーツそっくりの、もやもやと赤くまるい大きな月が浮かんでいる。
「これからうちに遊びに来ない?」
きっぱりと、私はそう言っていた。
夏の夜は虫の匂いがする。草と虫と空気の混ざり合ったような匂い、ひどく子供っぽい匂いだ。
私ははな歌をうたう。
私はといえば変わったことはなにもなく、平和な日々でお茶漬けばかり食べている。秋は、一年じゅうでいちばんお茶漬けのおいしい季節だと思う。
このとき私は確信した。一人の男と人生を共有しているときの、ありふれた日常の信じられないような幸福、奇跡のような瞬間の堆積
眠りながら暮らすのなんて、わけのないことだ。毎日お昼近くに起きて食事をし、窓の外でも眺めてぼんやりしているうちに、また眠くなって少しうとうとし、途中でたぶん一、二度目をさます。トイレに立ち、お腹がすいていれば口になにか入れ、場合によっては雑誌をぱらぱらめくったりするかもしれないが、結局またソファにねそべって、浅く淀んだ眠りを眠る。目をさますとすっかり暗くなっている。起きあがってカーテンをしめ、電気をつけテレビをつけ、とりあえず冷蔵庫からセブンアップでもだしてのむ。あとは、食事をしてお風呂に入ればそれでもう一日がおわる。
三人ともほとんど話をしなかった。そうしてそれは、不思議と心地のいいしずかさだった。大きなガラス窓に雨粒が流れ、無数の点線になったその雨粒ごしに、大通りと車と青い歩道橋、傘をさして歩いている人がみえる。
「惣一は私を愛してるの」
華子が言った。写真の学校にいってるの、と言うのとおなじ口調だ。
私たちは駅までぶらぶら歩いた。何かのかけらと呼びたいような、紡錘形の月が輪郭をぼやかせ、湿った夜空に白く光っていた。
私はしばらくおしいれの前に立っていたが、のろのろ歩いてワンピースのハンガーを鴨居にかけ、それから窓をあけた。すりガラスのはまった格子窓だ。ねじ式の鍵がついている。あけると、きゅるきゅると木枠のきしむ音がした。
夜は濃く、深く、しずかだった。黒々とした木立ち。葉のざわめく気配がしたが、錯覚だったのかもしれない。そよとも風がないのだから。のりだして見下ろすと、街灯にブロック塀がみえた。
「恋愛っていうんじゃないことは、自分でももうわかってるんだ。
とぷちゃぷととぷちゃぷととぷちゃぷと。私たちのまわりで、雨が際限なく単調でやわらかな音をたてていた。
「恋愛じゃなかったらなんなの?」
いちめんに水をたたえたアスファルトの道は、街灯のあかりで黒々と光っている。
「執着」
「私ね、空は好きよ。海よりずっといい」
---