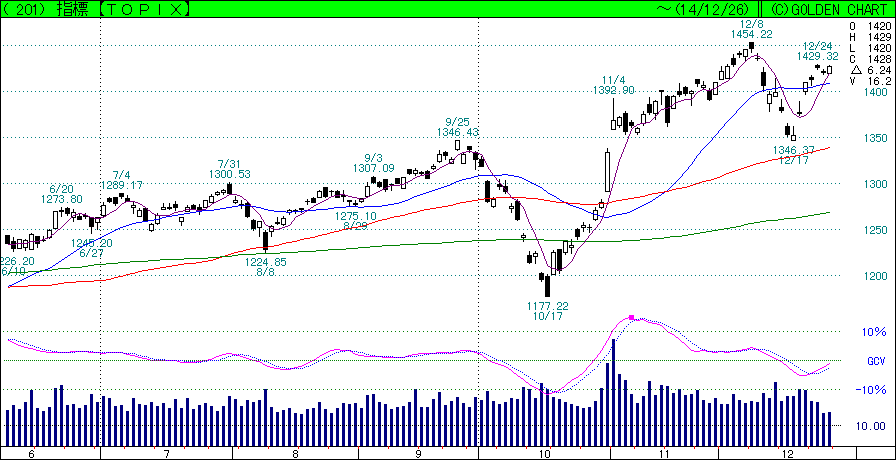2014年 12月 25日 11:00 JST ロイター
[モスクワ/アブダビ 24日 ロイター] - ロシアの有力農業ロビー団体、ロシア穀物連盟のズロチェフスキー会長は24日、同国の穀物輸出が政府の事実上の規制によって停止したことを明らかにした。大口契約が不履行になる恐れがあり、ロシア産小麦の有力な買い手であるエジプト、トルコ、イランの調達に支障が生じることが懸念される。
ロシアは12月に入り、輸出穀物の品質検査を厳格化するなど、国内供給を確保する目的とみられる事実上の輸出規制措置を導入した。
ズロチェフスキー会長によると「18日以降、契約に基づいて航行予定だった(穀物輸送)船舶が一隻も出港していない」。
ロシア当局は穀物輸出税の適用も計画している。ズロチェフスキー会長は、輸出税は事実上の禁輸措置になると確信しており、具体的な税率は重要でないとし「積み込みは全面的に中断している。あとは(輸出停止が)正式に法制化されるだけだ」と述べた。この発言で、世界各地の小麦先物は上昇した。
穀物輸出税導入案を策定すると表明したドボルコビッチ副首相の報道官のコメントは得られていない。
<エジプト向け輸出が不履行の恐れ>
ズロチェフスキー会長は、出荷期限が1月末の穀物約300万トンの輸出が滞っていると述べ、世界最大の小麦買い付け国であるエジプトの商品供給公社(GASC)への供給が来年1月に不履行となる可能性もあると付け加えた。
この日GASCのアブデル・ファタハ副会長はロイターに対し、トレーダー各社がロシア産小麦のエジプト向け輸出契約を履行する義務を負っていると語った。
今年のロシア穀物輸出量は、1億0500万トンの記録的豊作を踏まえて世界4位の規模に膨らむと予想されている。ただ、欧州のトレーダーは「(ロシアが)今後穀物売却を中断するのは明らかだ」との見解を示し、「(ロシア)政府が具体的にどのような措置を取るか、市場が現在知りたいのはその詳細だ」と強調した。
[モスクワ/アブダビ 24日 ロイター] - ロシアの有力農業ロビー団体、ロシア穀物連盟のズロチェフスキー会長は24日、同国の穀物輸出が政府の事実上の規制によって停止したことを明らかにした。大口契約が不履行になる恐れがあり、ロシア産小麦の有力な買い手であるエジプト、トルコ、イランの調達に支障が生じることが懸念される。
ロシアは12月に入り、輸出穀物の品質検査を厳格化するなど、国内供給を確保する目的とみられる事実上の輸出規制措置を導入した。
ズロチェフスキー会長によると「18日以降、契約に基づいて航行予定だった(穀物輸送)船舶が一隻も出港していない」。
ロシア当局は穀物輸出税の適用も計画している。ズロチェフスキー会長は、輸出税は事実上の禁輸措置になると確信しており、具体的な税率は重要でないとし「積み込みは全面的に中断している。あとは(輸出停止が)正式に法制化されるだけだ」と述べた。この発言で、世界各地の小麦先物は上昇した。
穀物輸出税導入案を策定すると表明したドボルコビッチ副首相の報道官のコメントは得られていない。
<エジプト向け輸出が不履行の恐れ>
ズロチェフスキー会長は、出荷期限が1月末の穀物約300万トンの輸出が滞っていると述べ、世界最大の小麦買い付け国であるエジプトの商品供給公社(GASC)への供給が来年1月に不履行となる可能性もあると付け加えた。
この日GASCのアブデル・ファタハ副会長はロイターに対し、トレーダー各社がロシア産小麦のエジプト向け輸出契約を履行する義務を負っていると語った。
今年のロシア穀物輸出量は、1億0500万トンの記録的豊作を踏まえて世界4位の規模に膨らむと予想されている。ただ、欧州のトレーダーは「(ロシアが)今後穀物売却を中断するのは明らかだ」との見解を示し、「(ロシア)政府が具体的にどのような措置を取るか、市場が現在知りたいのはその詳細だ」と強調した。
AFP=時事 12月27日(土)16時46分配信
【AFP=時事】ロシアの通貨ルーブル暴落の衝撃は、ロシア国民だけではなく、同国に暮らす外国人たちにも広がっている。黄金郷から金融ブラックホールへと化した首都モスクワ(Moscow)では、外国人労働者たちが国外への脱出時期を計りはじめている。
出国したがっている外国人の数は定かではないし、実際に外国人が大挙してロシアから脱出していることを示す具体的な事例もない。それでも先週、ルーブルが数日間で25%も急落したことを受けて、そろそろロシアを去る潮時と考え始めたと明かす外国人は少なくない。
多少は持ち直したもののルーブルは今年に入って対ドル、対ユーロとも40%も下げており、多くの人々が財政的に不安定な状況に追い込まれている。
■半年余りで収入半減
ジョイさん(28)は今年4月、子ども3人をフィリピン・マニラ(Manila)に残してロシアに出稼ぎに来た。モスクワの富裕層向けアパートで、清掃スタッフとして働く。賃金は4時間で1500ルーブル。
「こちらに来た当初は、換算すれば42ドル(約5000円)くらいになった。今は、同じ仕事なのにせいぜい20ドル(約2400円)程度にしかならない」とジョイさん。
家族を支えるため、ジョイさんは収入の3分の2をフィリピンに仕送りしていた。長男の進学費用と、夫がバイクタクシーの仕事に就くためのオートバイ購入資金を貯めるのが、出稼ぎの目標だった。両親の家の屋根の修繕もしたいと考えていたが、もはや、かなわぬ夢だ。
「今では家族の生活費さえ、満足に仕送りできない。でも、両親は状況を理解してくれなくて、私が以前より真面目に働かなくなったと思っている。心苦しいです」
とはいえ、賃金が支払われているだけジョイさんは幸運なほうかもしれない。多くの移民労働者たち、とりわけ旧ソビエト連邦圏出身の建設作業員らの間では、給料が全く支払われない例も増えている。
だが、帰国しようにも航空運賃はドル建てだ。「航空券はどんどん高騰しているのに、私の稼ぎは減る一方。すぐにでも出国を決意しないと、モスクワに取り残されてしまう」とジョイさんは話した。
■「去るときが来た」
一方、30代のフランス人トレーダー、オリビエさんは、9月末にモスクワにあるロシアの銀行に転職したことを後悔している。転職の条件として提示された給与と賞与の額面は、申し分ないものだった。
「こいつは良い機会だ、と自分に言い聞かせたんだ。4年間ずっと成長し続けている活気に満ちた市場で活躍できるぞ、停滞しきった欧州におさらばするのも悪くないってね」
しかし、オリビエさんの着任後わずか2週間で、高額の給与も多額のボーナスも幻想となってしまった。ルーブル建ての給与の価値は、対ユーロで瞬く間に下がってしまったのだ。
2桁インフレで定期昇給分が相殺される可能性は想定していたかもしれないオリビエさんも、「毎日がブラックマンデーなんて事態は全く予期していなかった」と悲鳴を上げる。
「ロシア人が手持ちのルーブルを丸ごと売却しているのは確かだ。その国の人たちが自国の通貨を見捨てたら、外国人にとっては去るときが来たということだ」。そう語るオリビエさんは既に、帰国便を手配する用意があるという。
「帰国するのは僕が最初だろう。僕は独身で、子どももいないから。でも、他の人たちが出国し始めるのも、そう遠い先の話ではないと思うよ」 【翻訳編集】 AFPBB News
【AFP=時事】ロシアの通貨ルーブル暴落の衝撃は、ロシア国民だけではなく、同国に暮らす外国人たちにも広がっている。黄金郷から金融ブラックホールへと化した首都モスクワ(Moscow)では、外国人労働者たちが国外への脱出時期を計りはじめている。
出国したがっている外国人の数は定かではないし、実際に外国人が大挙してロシアから脱出していることを示す具体的な事例もない。それでも先週、ルーブルが数日間で25%も急落したことを受けて、そろそろロシアを去る潮時と考え始めたと明かす外国人は少なくない。
多少は持ち直したもののルーブルは今年に入って対ドル、対ユーロとも40%も下げており、多くの人々が財政的に不安定な状況に追い込まれている。
■半年余りで収入半減
ジョイさん(28)は今年4月、子ども3人をフィリピン・マニラ(Manila)に残してロシアに出稼ぎに来た。モスクワの富裕層向けアパートで、清掃スタッフとして働く。賃金は4時間で1500ルーブル。
「こちらに来た当初は、換算すれば42ドル(約5000円)くらいになった。今は、同じ仕事なのにせいぜい20ドル(約2400円)程度にしかならない」とジョイさん。
家族を支えるため、ジョイさんは収入の3分の2をフィリピンに仕送りしていた。長男の進学費用と、夫がバイクタクシーの仕事に就くためのオートバイ購入資金を貯めるのが、出稼ぎの目標だった。両親の家の屋根の修繕もしたいと考えていたが、もはや、かなわぬ夢だ。
「今では家族の生活費さえ、満足に仕送りできない。でも、両親は状況を理解してくれなくて、私が以前より真面目に働かなくなったと思っている。心苦しいです」
とはいえ、賃金が支払われているだけジョイさんは幸運なほうかもしれない。多くの移民労働者たち、とりわけ旧ソビエト連邦圏出身の建設作業員らの間では、給料が全く支払われない例も増えている。
だが、帰国しようにも航空運賃はドル建てだ。「航空券はどんどん高騰しているのに、私の稼ぎは減る一方。すぐにでも出国を決意しないと、モスクワに取り残されてしまう」とジョイさんは話した。
■「去るときが来た」
一方、30代のフランス人トレーダー、オリビエさんは、9月末にモスクワにあるロシアの銀行に転職したことを後悔している。転職の条件として提示された給与と賞与の額面は、申し分ないものだった。
「こいつは良い機会だ、と自分に言い聞かせたんだ。4年間ずっと成長し続けている活気に満ちた市場で活躍できるぞ、停滞しきった欧州におさらばするのも悪くないってね」
しかし、オリビエさんの着任後わずか2週間で、高額の給与も多額のボーナスも幻想となってしまった。ルーブル建ての給与の価値は、対ユーロで瞬く間に下がってしまったのだ。
2桁インフレで定期昇給分が相殺される可能性は想定していたかもしれないオリビエさんも、「毎日がブラックマンデーなんて事態は全く予期していなかった」と悲鳴を上げる。
「ロシア人が手持ちのルーブルを丸ごと売却しているのは確かだ。その国の人たちが自国の通貨を見捨てたら、外国人にとっては去るときが来たということだ」。そう語るオリビエさんは既に、帰国便を手配する用意があるという。
「帰国するのは僕が最初だろう。僕は独身で、子どももいないから。でも、他の人たちが出国し始めるのも、そう遠い先の話ではないと思うよ」 【翻訳編集】 AFPBB News
ロイター 12月25日(木)13時56分配信
[東京 25日 ロイター] - 日銀の黒田東彦総裁は25日午後、都内で開かれた日本経団連審議員会で講演し、出席した企業経営者に対して「収益を使っていく」ことが日本経済や自社のメリットになるとし、賃上げや投資の積極化などデフレ脱却を前提とした行動の重要性を強調した。
2%の物価安定目標が実現すれば内外価格差に基づく円高リスクが小さくなると明言し、2%実現の意義にも理解を求めた。
<賃金交渉に強い関心、脱デフレでルールブック変わる>
総裁は、現在の日本経済はデフレマインドからの転換が着実に進んでいるとし、こうした変化が今年の春闘でのベースアップ(ベア)や低価格戦略からの転換など「企業の賃金設定や価格戦略にも影響を与えている」と語った。
特に久しぶりのベア実現は、日銀による2%の物価目標が「労使間の賃金交渉において意識されており、注目すべき動き」と評価。日銀として「強い関心をもって、今後の交渉の帰すうを見守っていきたい」と述べ、引き続き来年の春闘でもベアが実現することに期待感を表明した。
そのうえで来年の日本経済について、企業にとっては「資源価格の下落と円安で収益環境は良好」とし、家計も賃上げが行われる一方、消費税率引き上げの物価上昇率への影響が前年比でみて来年4月にはく落することから、「実質賃金は回復する。景気面ではフォローの風が吹いている」と楽観的な展望を示した。
企業経営者に対し、経済の好循環の実現には「高い収益をあげている企業が積極的に収益を使っていくことが求められている」と指摘。デフレ下の「縮小均衡」の経済と、物価2%の「拡大均衡」の経済とでは「企業経営のルールブックが変わる」とし、デフレ脱却の過渡期にある今の状況を利用することが、人材確保などで当該企業自体にも「メリットをもたらす」と訴えた。
<物価2%で円高リスク縮小、追加緩和は決意示した>
日銀が掲げる2%の物価目標は、消費者物価指数に下方バイアスがあるため、「決して物価が大きく上がっている状況でない」と強調。他の先進国が2%程度の物価上昇率であったにもかかわらず、日本ではデフレが続いたため「すう勢的に円高が進行してきた」とし、「今後2%の物価上昇率が実現すれば、少なくとも内外価格差に起因する円高進行リスクは小さくなる」との見解を示した。
10月末に決めた追加緩和については「原油価格下落そのものに対応したものではない」と述べ、原油価格急落に伴うさらなる追加緩和期待をけん制した。追加緩和によって「物価2%の早期実現の決意に揺らぎないこと行動で示した」とし、「追加緩和後の市場反応をみると、日銀の決意はしっかり伝わった」と評価した。
同時に、中期的に原油安が日本経済にプラスであるにもかかわらず追加緩和に踏み切った理由として「実際の物価上昇の足踏みが長引く場合、デフレマインドから転換するエンジンのひとつが弱まる可能性があるため」と説明。原油価格の下落は「今回のように産油国の事情など供給面の要因に強く反応しているケースでは、資源輸入国である日本経済は大きなメリットを受ける」とし、物価に対しては短期的な下押し要因になるものの、「やや長い目でみれば、需給ギャップの改善をもたらし、物価の基調的な上昇につながる」との認識を示した。
(伊藤純夫 竹本能文 編集:山川薫)
[東京 25日 ロイター] - 日銀の黒田東彦総裁は25日午後、都内で開かれた日本経団連審議員会で講演し、出席した企業経営者に対して「収益を使っていく」ことが日本経済や自社のメリットになるとし、賃上げや投資の積極化などデフレ脱却を前提とした行動の重要性を強調した。
2%の物価安定目標が実現すれば内外価格差に基づく円高リスクが小さくなると明言し、2%実現の意義にも理解を求めた。
<賃金交渉に強い関心、脱デフレでルールブック変わる>
総裁は、現在の日本経済はデフレマインドからの転換が着実に進んでいるとし、こうした変化が今年の春闘でのベースアップ(ベア)や低価格戦略からの転換など「企業の賃金設定や価格戦略にも影響を与えている」と語った。
特に久しぶりのベア実現は、日銀による2%の物価目標が「労使間の賃金交渉において意識されており、注目すべき動き」と評価。日銀として「強い関心をもって、今後の交渉の帰すうを見守っていきたい」と述べ、引き続き来年の春闘でもベアが実現することに期待感を表明した。
そのうえで来年の日本経済について、企業にとっては「資源価格の下落と円安で収益環境は良好」とし、家計も賃上げが行われる一方、消費税率引き上げの物価上昇率への影響が前年比でみて来年4月にはく落することから、「実質賃金は回復する。景気面ではフォローの風が吹いている」と楽観的な展望を示した。
企業経営者に対し、経済の好循環の実現には「高い収益をあげている企業が積極的に収益を使っていくことが求められている」と指摘。デフレ下の「縮小均衡」の経済と、物価2%の「拡大均衡」の経済とでは「企業経営のルールブックが変わる」とし、デフレ脱却の過渡期にある今の状況を利用することが、人材確保などで当該企業自体にも「メリットをもたらす」と訴えた。
<物価2%で円高リスク縮小、追加緩和は決意示した>
日銀が掲げる2%の物価目標は、消費者物価指数に下方バイアスがあるため、「決して物価が大きく上がっている状況でない」と強調。他の先進国が2%程度の物価上昇率であったにもかかわらず、日本ではデフレが続いたため「すう勢的に円高が進行してきた」とし、「今後2%の物価上昇率が実現すれば、少なくとも内外価格差に起因する円高進行リスクは小さくなる」との見解を示した。
10月末に決めた追加緩和については「原油価格下落そのものに対応したものではない」と述べ、原油価格急落に伴うさらなる追加緩和期待をけん制した。追加緩和によって「物価2%の早期実現の決意に揺らぎないこと行動で示した」とし、「追加緩和後の市場反応をみると、日銀の決意はしっかり伝わった」と評価した。
同時に、中期的に原油安が日本経済にプラスであるにもかかわらず追加緩和に踏み切った理由として「実際の物価上昇の足踏みが長引く場合、デフレマインドから転換するエンジンのひとつが弱まる可能性があるため」と説明。原油価格の下落は「今回のように産油国の事情など供給面の要因に強く反応しているケースでは、資源輸入国である日本経済は大きなメリットを受ける」とし、物価に対しては短期的な下押し要因になるものの、「やや長い目でみれば、需給ギャップの改善をもたらし、物価の基調的な上昇につながる」との認識を示した。
(伊藤純夫 竹本能文 編集:山川薫)
2014年 12月 23日 23:47 JST ロイター
[ワシントン 23日 ロイター] - 米商務省が発表した第3・四半期の国内総生産(GDP)確報値は、前期比年率で5.0%増と、市場予想の4.3%増を上回り、2003年第3・四半期以来11年ぶりの大幅な伸びとなった。経済成長の勢いが確実に強まったことが改めて鮮明になった。
改定値は3.9%増だった。消費支出や企業設備投資が従来推計より堅調だった。速報値からは計1.5%ポイントの上方修正となった。
第2・四半期の成長率は4.6%。2四半期連続の伸びとしては2003年以来の大きさとなった。
第4・四半期の成長率は鈍化が予想される。一方で、労働市場が急速に堅調さを増し、ガソリン価格が低下しており、来年の景気を十分後押しするとみられる。引き続き、連邦準備理事会(FRB)が来年半ばまでに利上げする見通しだ。
国内最終需要が4.1%に上方修正され、2010年第2・四半期以来の高水準となった。
個人消費支出は3.2%増、2013年第4・四半期以来の高水準だった。
民間設備投資も上方修正された。機器や知的財産製品などが従来推計より堅調だった。
在庫変動も上方修正された。GDPの押し下げ要因ではなく、中立となった。輸出の下方修正分も補った。
民間住宅投資や政府調達も上方修正された。一方で輸出、輸入はともに下方修正された。
[ワシントン 23日 ロイター] - 米商務省が発表した第3・四半期の国内総生産(GDP)確報値は、前期比年率で5.0%増と、市場予想の4.3%増を上回り、2003年第3・四半期以来11年ぶりの大幅な伸びとなった。経済成長の勢いが確実に強まったことが改めて鮮明になった。
改定値は3.9%増だった。消費支出や企業設備投資が従来推計より堅調だった。速報値からは計1.5%ポイントの上方修正となった。
第2・四半期の成長率は4.6%。2四半期連続の伸びとしては2003年以来の大きさとなった。
第4・四半期の成長率は鈍化が予想される。一方で、労働市場が急速に堅調さを増し、ガソリン価格が低下しており、来年の景気を十分後押しするとみられる。引き続き、連邦準備理事会(FRB)が来年半ばまでに利上げする見通しだ。
国内最終需要が4.1%に上方修正され、2010年第2・四半期以来の高水準となった。
個人消費支出は3.2%増、2013年第4・四半期以来の高水準だった。
民間設備投資も上方修正された。機器や知的財産製品などが従来推計より堅調だった。
在庫変動も上方修正された。GDPの押し下げ要因ではなく、中立となった。輸出の下方修正分も補った。
民間住宅投資や政府調達も上方修正された。一方で輸出、輸入はともに下方修正された。
12月23日 11時58分 NHKニュース
日本郵政グループは来年秋以降に持ち株会社の日本郵政と、傘下にあるゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式を同時に東京証券取引所に上場する方針を固めました。
日本郵政は政府が株式を100%保有する会社で、傘下のゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式のすべてを保有しています。
関係者によりますと、日本郵政は、市場の環境などを見極めたうえで来年秋以降に、東京証券取引所に株式を上場し、傘下のゆうちょ銀行とかんぽ生命の金融2社の株式も同時に上場する方針を固めました。
日本郵政は金融2社の株式売却について複数回に分けて行い、当面50%以上の売却を目指すことにしています。上場によって金融2社はこれまで政府の認可が必要だった新規業務の参入が届け出だけで済むようになり、経営の自由度を高めるねらいがあります。一方、政府は今回の株式の売却益を東日本大震災の復興財源に充てることにしています。
日本郵政は、平成17年、当時の小泉総理大臣が衆議院の解散・総選挙に踏み切ったあと成立した法律によりその2年後の平成19年に民営化されましたが、その後の民主党政権の下で成立した法律で株式の売却が一時凍結されたこともあり、株式上場にたどり着くまでに時間がかかりました。今後は上場によってどこまでグル-プ全体の収益力向上につなげられるかが注目されます。
日本郵政はこうした上場計画について、今月26日に西室社長が記者会見を開き、正式に発表することにしています。
<コメント>
NTT上場を思い出す
1987年2月 NTT 上場
1987年10月 ブラックマンデー
1989年12月 日経 史上最高値
当時のことがわからない人へ ⇒ ご参考

★★★
時事通信 12月26日(金)16時32分配信
日本郵政は26日、持ち株会社である同社と完全子会社のゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の金融2社が、2015年秋にも株式を東京証券取引所に同時上場すると発表した。親会社と子会社が同時に上場するのは日本初。日本郵政は金融2社の株式を、保有比率50%程度になるまで順次売却。残りはその後、改めて売却し、2段階で完全民営化する。
小泉政権が2005年に道筋を付けた郵政民営化は、10年を経て具体化する局面に入る。日本郵政の西室泰三社長は「本当の意味の民営化に向け、ようやく第一歩を踏み出す」と意義を強調した。
西室社長は、上場時期について「来年の8月から12月ぐらいまで」との見通しを示した。親子同時上場の理由は「金融2社の経営の自由度を確保し、3社の企業価値を市場で適正に評価してもらうため」と説明した。金融2社の株式の売り出し規模や、完全に売却する時期は明言しなかった。
日本郵政は、持ち株会社と金融2社の早期上場を目指してきた。また、異なるタイミングで上場させた場合、投資家から2回にわたって資金を集めると指摘されかねない点にも配慮し、同時上場という方法を選んだ。
現在は政府が日本郵政の全株を握っているため、ゆうちょ銀やかんぽ生命が住宅ローンなどの新規業務に参入するには国の認可が必要だ。西室社長は、金融2社を早期に上場させて新たな事業に取り組みやすくすることが必要との考えを示した。一方、民業圧迫との批判が根強い中で、地方銀行や保険会社など民間金融機関との提携について「積極的に進めていきたい」と語った。
政府は日本郵政の上場後、少なくとも3分の1超の株を保有し続ける。同社は上場後、郵便事業を行う日本郵便を100%子会社、金融2社を連結子会社として傘下に置き、グループとして事業を進める。
日本郵政グループは来年秋以降に持ち株会社の日本郵政と、傘下にあるゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式を同時に東京証券取引所に上場する方針を固めました。
日本郵政は政府が株式を100%保有する会社で、傘下のゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式のすべてを保有しています。
関係者によりますと、日本郵政は、市場の環境などを見極めたうえで来年秋以降に、東京証券取引所に株式を上場し、傘下のゆうちょ銀行とかんぽ生命の金融2社の株式も同時に上場する方針を固めました。
日本郵政は金融2社の株式売却について複数回に分けて行い、当面50%以上の売却を目指すことにしています。上場によって金融2社はこれまで政府の認可が必要だった新規業務の参入が届け出だけで済むようになり、経営の自由度を高めるねらいがあります。一方、政府は今回の株式の売却益を東日本大震災の復興財源に充てることにしています。
日本郵政は、平成17年、当時の小泉総理大臣が衆議院の解散・総選挙に踏み切ったあと成立した法律によりその2年後の平成19年に民営化されましたが、その後の民主党政権の下で成立した法律で株式の売却が一時凍結されたこともあり、株式上場にたどり着くまでに時間がかかりました。今後は上場によってどこまでグル-プ全体の収益力向上につなげられるかが注目されます。
日本郵政はこうした上場計画について、今月26日に西室社長が記者会見を開き、正式に発表することにしています。
<コメント>
NTT上場を思い出す
1987年2月 NTT 上場
1987年10月 ブラックマンデー
1989年12月 日経 史上最高値
当時のことがわからない人へ ⇒ ご参考

★★★
時事通信 12月26日(金)16時32分配信
日本郵政は26日、持ち株会社である同社と完全子会社のゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の金融2社が、2015年秋にも株式を東京証券取引所に同時上場すると発表した。親会社と子会社が同時に上場するのは日本初。日本郵政は金融2社の株式を、保有比率50%程度になるまで順次売却。残りはその後、改めて売却し、2段階で完全民営化する。
小泉政権が2005年に道筋を付けた郵政民営化は、10年を経て具体化する局面に入る。日本郵政の西室泰三社長は「本当の意味の民営化に向け、ようやく第一歩を踏み出す」と意義を強調した。
西室社長は、上場時期について「来年の8月から12月ぐらいまで」との見通しを示した。親子同時上場の理由は「金融2社の経営の自由度を確保し、3社の企業価値を市場で適正に評価してもらうため」と説明した。金融2社の株式の売り出し規模や、完全に売却する時期は明言しなかった。
日本郵政は、持ち株会社と金融2社の早期上場を目指してきた。また、異なるタイミングで上場させた場合、投資家から2回にわたって資金を集めると指摘されかねない点にも配慮し、同時上場という方法を選んだ。
現在は政府が日本郵政の全株を握っているため、ゆうちょ銀やかんぽ生命が住宅ローンなどの新規業務に参入するには国の認可が必要だ。西室社長は、金融2社を早期に上場させて新たな事業に取り組みやすくすることが必要との考えを示した。一方、民業圧迫との批判が根強い中で、地方銀行や保険会社など民間金融機関との提携について「積極的に進めていきたい」と語った。
政府は日本郵政の上場後、少なくとも3分の1超の株を保有し続ける。同社は上場後、郵便事業を行う日本郵便を100%子会社、金融2社を連結子会社として傘下に置き、グループとして事業を進める。
Bloomberg 12月19日(金)14時52分配信
著名投資家ウォーレン・バフェット氏はこの2年間、米投資・保険会社バークシャー・ハサウェイの株主に年1回送付する書簡で、同氏を補佐する2人の前年の運用成績を誇らしく語ってきたが、来年の書簡ではそれは難しそうだ。
.
トッド・コーム、テッド・ウェシュラー両氏が選んだとみられる銘柄のうち、少なくとも6つが今年1年間で株価を下げる見通し。具体的には、原油値下がりで低迷するエネルギー株や、リコール(無料の回収・修理)に苦しむゼネラル・モーターズ(GM)、株価が昨年末から50%強下落したエンジニアリング・建設会社シカゴ・ブリッジ・アンド・アイアン(CB&I)などだ。
.
バークシャーのポートフォリオを分析しているメリーランド大学ロバート・H・スミス・ビジネススクールのデービッド・カシュ教授は「ざっと見たところ、コーム、ウェシュラー両氏の運用成績はS&P500種株価指数の実績を下回っているようだ」と述べた。
.
バフェット氏は自身の後継者育成計画の要として、コーム氏とウェシュラー氏をそれぞれ2010、11年にポートフォリオ運用の補佐役に起用。この2年間の株主向け書簡でバフェット氏は、2人の運用成績がS&P500種だけでなく、自分の選んだ銘柄をも上回ったと述べていた。将来的には2人がバークシャーのポートフォリオ全てを運用することになる。9月末時点では同ポートフォリオには約1200億ドル(約14兆3000億円)相当の株式が含まれていた。
著名投資家ウォーレン・バフェット氏はこの2年間、米投資・保険会社バークシャー・ハサウェイの株主に年1回送付する書簡で、同氏を補佐する2人の前年の運用成績を誇らしく語ってきたが、来年の書簡ではそれは難しそうだ。
.
トッド・コーム、テッド・ウェシュラー両氏が選んだとみられる銘柄のうち、少なくとも6つが今年1年間で株価を下げる見通し。具体的には、原油値下がりで低迷するエネルギー株や、リコール(無料の回収・修理)に苦しむゼネラル・モーターズ(GM)、株価が昨年末から50%強下落したエンジニアリング・建設会社シカゴ・ブリッジ・アンド・アイアン(CB&I)などだ。
.
バークシャーのポートフォリオを分析しているメリーランド大学ロバート・H・スミス・ビジネススクールのデービッド・カシュ教授は「ざっと見たところ、コーム、ウェシュラー両氏の運用成績はS&P500種株価指数の実績を下回っているようだ」と述べた。
.
バフェット氏は自身の後継者育成計画の要として、コーム氏とウェシュラー氏をそれぞれ2010、11年にポートフォリオ運用の補佐役に起用。この2年間の株主向け書簡でバフェット氏は、2人の運用成績がS&P500種だけでなく、自分の選んだ銘柄をも上回ったと述べていた。将来的には2人がバークシャーのポートフォリオ全てを運用することになる。9月末時点では同ポートフォリオには約1200億ドル(約14兆3000億円)相当の株式が含まれていた。