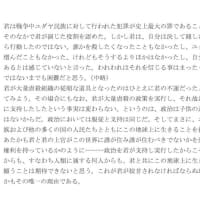ドイツ人はなぜヒトラーを選んでしまったのか?
アメリカはなぜ大統領としてトランプを選んでしまったのか?
ロシアはなぜプーチンを大統領として選んでしまったのか?
ベラルーシはなぜルカシェンコを大統領地位にとどまらせているのか?
それぞれの国のそうなるをえない実情は理解できていないが
実質的に独裁に近い形で権力を行使する姿は
国外から見ればとても不思議に見える
彼らをその地位に就かせたのは選挙という民主的なシステムで
それらが実際にはどのように行われたのかは部外者には不明なところだが
一般論として、選挙は大衆の声を反映したものとすれば、そもそも大衆は
正しい判断を行うことができるのか?
とつい考えてしまうのは当然のことだ
以前読んだ本「多数決を疑う」には、人の判断は完全ではないが
半分以上は正しい判断をしうると仮定して
例えば0.6の確率で正しい判断をするとしたら、ひとりだけだったら0.6のままだが
人数が増えると0.6よりは正しい判断の確率が上がることが数学的に示されていた
これは多くの人の判断はベターな判断をしうることを表しているように見えるが
ここには前提条件があった
それらの判断について、人は案件に対して完全にフリーの立場で情報に接し
他人に左右されることなく自己判断を示すことができることがあげられていた
だが、実社会ではこれは不可能だ
情報は必ずと言えるほど偏っているし、個々の損得も違う
また判断については人の影響を受ける
つまりは民主的な選挙というシステムは
必ずしも正しい判断を生み出すものではないということだ
話は変わるが日本では憲法を変える時には
国民投票での一定数以上の賛意を必要とするが
ドイツではかつて国民(大衆)がその時の空気に飲まれてヒトラーを選んだことから
大衆は的確な判断をなし得ない、、と判断し、憲法改正には専門家の判断による方法を
とることにしたという話を耳にしたことがある
(出典は忘れてしまったが、とにかく大衆は正しい判断を下すことができない
との判断をしたということ、違っているかもしれない)
一見、みんなの声が反映されるのは良いことのように見えるが
みんなの声の危うさというものもある
それは感情的であったり近視眼的であったり、その時の空気に振り回されたり、、
それならば、どのようなシステムが良いのか?
となるところだが、人の考えることはどこか抜けていて、完全な方法は見つからない
ただ言えることは、多数決で決まったことは正しい!
とばかりは言えないということ
正しいのではなく、肯定された方を不完全な人間たちが選んだに過ぎない
大衆は正しい判断を下しうるか?
選挙結果を見る度に、いつもこれを考えてしまう
いつものように、まとまらない話!