
ショパンの初恋の女性、コンスタンチア・グラドコフスカ。
19歳になったショパンにその年齢にふさわしく恋人ができた。
~これはぼくにとっておそらく不幸なことだろうが、ぼくにはすでに理想の
女性があるのだ。まだ直接話したことはないが、6か月も前からぼくは心
の中で彼女へつかえてきた。彼女への想い その夢にかられてぼくの協奏曲
のアダージョが書かれたのだ。今朝はまた、彼女への霊感から小さなワルツを
作曲した。それを君に送る・・・このことは君以外だれもしらないのだ~
これはワルシャワ時代の親友ティトゥスに書いた手紙。
このショパンの理想へのあこがれを託した「ピアノ協奏曲 へ短調」の第2楽章
ラルゲット、「ワルツ 変ニ長調」はショパンの初恋の名残である。
下の写真は、ショパン 3月号に載っていた美しいノアンのサンドの部屋。

ショパンが祖国ポーランドをあとにして、パリへ向かうあいだ、
1831年9月8日、ワルシャワがロシアに陥落の知らせを受けてシュトゥットガルト
で書いた手記。
~ぼくはここではなんの役にも立たない。しかも空しく手をこまねいているだけなのだ。
ぼくは時々 うなったり、苦悶したり、絶望をピアノにたたきつけたりするだけだ。
神よ!この時代の人間どもを、一人残らず地の中にのみこませたまえ!我々に
援助の手をさしのべないフランスの上に、重い罰を与えたまえ!~
乱れた筆致で書かれたショパンの慟哭の声。

ショパンがパリに出てから、ドイツの温泉地で懐かしい父母と再会し、
パリへの帰途の途中ドレスデンにたちよった。
ポーランドにいたころ親しく付き合っていたウォジンスキ伯一家を訪ね、
その妹のマリアと恋におちてしまった。
ショパンの人生の中で、このマリアへの想いが、唯一真実の恋だったといわれる。

別れの時、ショパンはマリアのために「ワルツ ロ短調」(別れのワルツ)を弾き
マリアは一輪の薔薇をショパンにささげた。
マリアから贈られた何通かの手紙と、その薔薇が一つの包みにおさめられ、
ポーランド語で《わが悲しみ》と記してある。
これだけでも芸術作品のよう。美しい!

ショパンが初めてサンドに会った時は、印象がよくなかった。
でも、ショパンの心が傾いて行った時に書かれたショパンの日記。
~三度あの人と会った。ピアノをひいている間、目の中まで深く見つめるのだ。
私の目の中にあの人の目が、暗く不可思議な目が何を囁くのか。
燃えた瞳が私を包んだ・・・私たちの周りの花。私の心は奪われてしまった。
それからニ回会った・・・・彼女は私を愛している・・・オーローラ、何と美しい
名か!~
音楽がきこえてきそうな文章。情熱的。
マリアとの関係がこわれて、サンドとの急速な展開があったころ。

手紙は大切。現代のメールでは、本当の気持ちが伝えられない気がする。
私は、美術館へ絵を見にいったら、気に入った絵のはがきを何枚も買ってくる。
いただきもののお礼に、カードのお礼に、一言気持ちを送りたくて、
はがきを書く。
大切な人には手紙。季節にあった便せんとか探すのが大好き。
アムステルダムの街角の文房具屋さんで見つけたレターセット、美しかった。
シエナで買った日記帳、トスカーナの独特の紙の表紙。
少しずつ書いてるので、15年以上も使っている。
ショパンの手紙、もう少し、書きたいので次回また。
それに加えて、今度は大好きなシューマンのことも書きたいし、
女性遍歴を並べたら1冊の本でも足りないリスト、意外な死因のシューベルト、
殺人までおかしたパガニーニ・・・とかきたいことが次々あります
少しずつかいていこう













 わたしにとっては大歓迎のスタイルで、始まったプログラム。
わたしにとっては大歓迎のスタイルで、始まったプログラム。



 東京ドームも行ったなあ。
東京ドームも行ったなあ。










































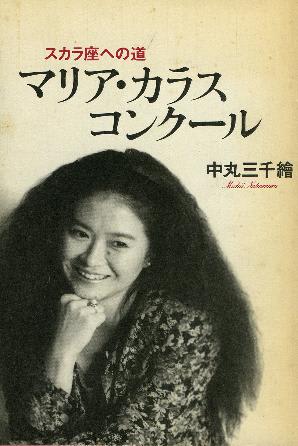











 ト音記号とOEKという文字が印してある、チョーか
ト音記号とOEKという文字が印してある、チョーか