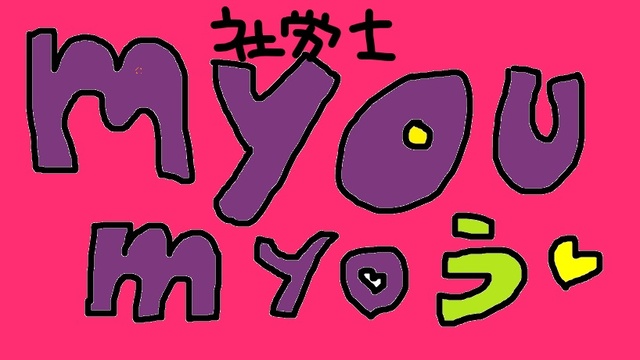企業買収を描いた「ハゲタカ」でおなじみの小説家真山仁さんが、最近の若者の特徴を述べてました。
何事も諦めが早く、失敗を嫌う人が多いと感じる。
資料の下読みを手伝ってもらってる学生アルバイトから「どうやったら真山さんみたいになれますか?」と聞かれたので、「若いときに多くの挑戦を重ねて挫折し、乗り越えることが大事だ」と伝えたところ、「挫折なしの方法を教えてください」と言われてしまったらしい。
「私ではなく、挫折しなかった人に聞いて」と諭したそうです。
苦笑いでした。
このはなし最初、挫折しなかった人なんている?と思ったんですが、自分も挫折してないなとすぐに思い至りました。
挫折してない人、挫折しててもその実感がない人はけっこういるかもと思いました。
そこそこの身の丈にあったことしかしてなければたいした挫折もないですから。
ちょっとぐらいの失敗はその場の言い訳で切り抜けられますから。
真山さんは若い人を批判してますが、失敗や挫折を許さないのは世間です。
若者はそれをちゃんと感じとってるだけです。
苦節何年で弁護士に!とかいうのは最終的に試験合格してるので、ストーリーはいかようにも色付けできますが、結局なれなかった人、こういう人の体験というのを聞きたいものです。
挫折なしの方法教えてくださいか…言いたくもなるわ。
何事も諦めが早く、失敗を嫌う人が多いと感じる。
資料の下読みを手伝ってもらってる学生アルバイトから「どうやったら真山さんみたいになれますか?」と聞かれたので、「若いときに多くの挑戦を重ねて挫折し、乗り越えることが大事だ」と伝えたところ、「挫折なしの方法を教えてください」と言われてしまったらしい。
「私ではなく、挫折しなかった人に聞いて」と諭したそうです。
苦笑いでした。
このはなし最初、挫折しなかった人なんている?と思ったんですが、自分も挫折してないなとすぐに思い至りました。
挫折してない人、挫折しててもその実感がない人はけっこういるかもと思いました。
そこそこの身の丈にあったことしかしてなければたいした挫折もないですから。
ちょっとぐらいの失敗はその場の言い訳で切り抜けられますから。
真山さんは若い人を批判してますが、失敗や挫折を許さないのは世間です。
若者はそれをちゃんと感じとってるだけです。
苦節何年で弁護士に!とかいうのは最終的に試験合格してるので、ストーリーはいかようにも色付けできますが、結局なれなかった人、こういう人の体験というのを聞きたいものです。
挫折なしの方法教えてくださいか…言いたくもなるわ。