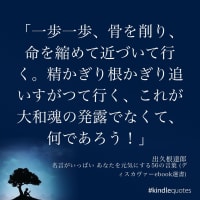【執筆原稿から抜粋】
武士道とはやせ我慢
論語のみならず、武士道もやせ我慢です。
武士は、士農工商の最上級に君臨し、他の身分から「見られる」立場にありました。人として美しいことが要求され、美しいことが存在意義ですらありました。私利に奔る醜さは不名誉とされました。私利のための誘惑に、公共心・公徳心が歯止めを掛けていました。
この「公徳心に基づく歯止め」はやせ我慢と等しく、戦後の有名な評論家・小林秀雄も「(武)士道とは痩せ我慢だ」と考えていました。
彼はやせ我慢を「私情と公道の緊張関係の自覚」と呼び、高く評価していました(『考えるヒント』)。
自分の私的な願望が公共の利害・公徳心と衝突する場合に自らを自発的に律するのがやせ我慢なのです。
____________
武士ではありませんが、理想的な軍人とされる連合艦隊の司令長官・山本五十六は、海軍兵学校の入学試験で「貴様の信念は何だ」と問われた際、一言「やせ我慢」と答えました。
信念がやせ我慢というのは現代人には伝わりにくいですが、雪害を耐え忍ぶ明治の長岡人の気概と気骨を示しています。
山本五十六に、論語や武士道から連綿と伝わるやせ我慢のエキスが凝縮していたようです。