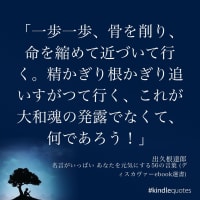朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり。
この論語の文句がとてもインテグリティ的。これは先日書きました。
こちら(過去記事)
その続き。この句は、「武道的」ともいえる。
ちなみにこの句の訳が、五十沢二郎さんによれば
真に生きる道を知りさえすれば、肉体の死のごときは、もはやなにものでもありはしない。
ってブッ飛んだ訳になる。
「朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり」は、反対解釈して、「道」にはゴールはない、永遠に道は続く。だから絶対に満足してはいけない、って意味に解釈している。
だから「道」はとてもインテグリティ的。
____________
スポーツと武道との違いで考えるとわかりやすい。
スポーツでは勝ったら喜んでよろしい。
武道では勝っても喜んではならない。
柔剣道で、全国大会とかの決勝あたりで勝ってガッツポーズして、勝利を取り消された例とかある(2012年全日本剣道大会の準決勝?)。
私も空手の黒帯を締めて極真指導員の末席を怪我しているため、「勝敗を度外視する」呼吸は身につけているつもり。
空手の試合では、試合時間終了直後に、「判定!」の号令とともに、主審+四隅にいる副審が旗を上げる。
その際、私は正面のみを見つめ、主審や副審が上げる「旗(の色、自分か相手か)を見ない」ことを美学としている。
試合では、日々の稽古の成果が出ているにすぎない。この試合の勝敗は単なる私の空手修行の過程にすぎず、勝とうが負けようが私の空手修行はずっと死ぬまで続く。
なのに自分がたかが一試合でキョロキョロして旗の上げ下げを観るのはみっともない、という痩せ我慢からです。
私の空手道における「道」において、審判員が旗を上げるか上げないかは関係ない、という強がりからです。
空手道における修行において、「道を聞く」(道を知る、目標を達成する)ということはあり得ない。永遠に果てしない道を歩み続ける。それが武道であり空手道。
こういうふうに、私の空手道、武道修行と、インテグリティにはつながりがあります。