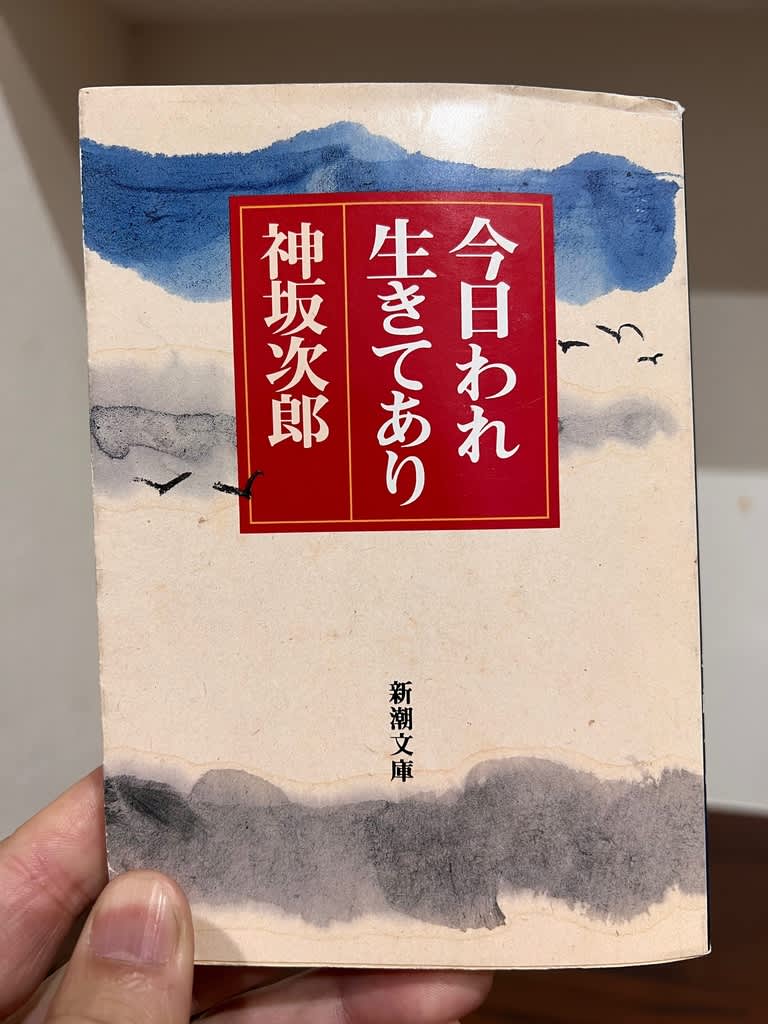『現代の考察』 執行草舟から取り急ぎ抜粋:
◆ 相克しているものが自分の中にドーンと落ちるのが核融合
◆ 死ぬほどの体当たりで全力を費やせ
私は、結果は考えていないです。
◆ ファウスト 不可能を欲する人間を私は愛する
◆ 人生とその自由は、日々これを戦い取る人にのみ与えられる。 努力しているうちに苦悩するものだ
◆ 人にものを教えることなどは、根源的にできない。 人というのは、親もそうですが、先生も感化しかしない。
◆ 小島直記の書いた本は、すべて不良の極道ですよ。
◆ 二時間で六万人にも及ぶほどの人が亡くなる ソンムの戦い、第一次世界大戦
◆ 自分の人生が本当に下らないと思うぐらいの人生を送らないと、私は人間的に生きたとは思わない
◆ 十三世紀のイランの、イスラム教徒の詩人でサアディー
徳高き人は、たとえ無頼の徒に辱めらるるとも、悲しむことなし。性悪き石、黄金の盃を砕くとも、石の価値は増さず。黄金の価値は減ぜず。
◆ 自分の人生で、ただ一つでも、他人のせい、または親のせいとかね、思うんだったら 何もわからない すべて自分のせい。
ただの一つも、人のせいにしたら終わりだ。
今は何でも人のせいにする時代だけど
◆ 機関銃に向かって突撃できる国は日本とヨーロッパしかない。なぜかというと武士道精神が国民に浸透していたから。つまり、自己犠牲ということです。
◆ 日清戦争のときに清国の軍隊なんかはご存知の通り、足を鎖で縛られていた
◆ 民主主義の一番の国が一番の戦力を保持して、一番好戦的な国になっている。
◆ 宿命は受け容れる
◆ うだつが上がらない人を見てくださいよ。必ず自分が持って生まれてきたなにかに文句を言っているから。自分が損したと思ってる。そういうケチくさい魂を持っているから。一生うだつが上がらない。宿命を受け容れていないということ。
◆ 成功した奴が一番人生は駄目ですよ。失敗に次ぐ失敗の人間が、尊い人生を送る可能性がある。
◆ 人間としての肉体や精神を鍛えることに繋がる事柄を、私は「毒」という概念に纏めて考えている
◆ 毒を食らわなかったら、自分が幸せになりたい、自分が成功したい、自分が仲良くなりたいという欲望だけになる。そのように生きた場合はどういう人間になるかというと、動物になるということです。
◆ 男は子どもに嫌われるのが役目だった。
◆ シェイクスピア リア王 Thou must be patient.
死ぬまで耐え抜かなければ駄目だということです。耐えねばならないという思想はどこまでやるのかというと、人間は死ぬまでだということです。途中で一休みしようと思うのが現代思想なのです。それでこのひと休みが動物を作ると思ってください。
◆ 六十万人の死ぬ人間を助けたのが原爆だ
…アメリカから見たら。正義はいつも相対的。
今の人間がやることは、それこそ「人間のため」というお墨付きがあればすべて正しいのだから、原爆もできてしまう。
◆ 良い芸術には祈りがある
◆ 「ただ独りで死ぬ」というのは有名なパスカルの言葉です。
◆ 後世のためにといっても本当は駄目なのです。魂を磨くのは「今、ここで」ということです
◆ 本も、その文によって決まる。文に力がなければ、人間論はすべて説教になる。文が体当りするかどうかで決まる。
◆ 自分の考え方に一人賛同してくれる人がいたら、もう本当に御の字だと思わなければなりません。歴史上色々な人を見ていて、物事をある程度成した人というのは、みんなただ一人でやった人です。
◆ 武道なんかを好きな人間は、地獄にいかなければ駄目です。
だから、私は地獄に行くに決まってる。
◆ 古代ギリシャにおいて初期の民主主義政治を樹立したソロンは。「人間のため・・・・・」という考え方を信じてはならなと言っていた。
◆ ホセ・オルテガ・イ・ガセットの『大衆の反逆』という有名な本
エリートとは何かというと、「自らに困難と義務を負う者」です。
◆ 義が最大の美徳なのが社会で、家族というのは、仁が最大の美徳なのです。
◆ 不良を定義するならば、それは「損害を一顧だにしない人間性」ということです。
◆ キルケゴール 信仰とは「自己自身を獲得するために、自己自身を喪失することである」と書いてある。
◆ 自己満足が民主主義社会の敵
民主主義というものを生み出した人間たちが、今の人間が見たら考えられないほど厳格な生活を、神の下でしていた人たちだった。
◆ 人間のことを思わなければならないと言う人たちに従ってはならない」―ソロン
絶対者を見つけ出した人は、ソロンに言わせればエリート、一方見出せなければ大衆
◆ 絶対者を見出した人の人生というのは、オルテガが書いているように、義務を重んじ、国に命を捧げ、そういう生き方をする人に自ずとなっていく。
◆ ニュートンはキリスト教の狂うほどの信仰心の持ち主で、一日じゅう時間近く祈っていた
著作の三分の二は神秘思想とキリスト教と錬金術の書物しかない。
ニュートン自身は一生涯孤独で 強烈な狂信者
◆ 小学校で学級委員とか何かを選挙しているのか、低俗なゴマすり根性
◆ 私は死ぬまで「不良」で生き、そして死ぬつもりです
◆ 社会に枯渇感と同時に向上心があるのがいい
◆ クリストファー・ドーソン 偉大なる文明は、その基礎を偉大なる宗教に負っている
(The great religions are the foundations on which the great civilizations rest.)
◆ シモーヌ・ヴェーユ
恩寵は満たすものである。だが、恩寵を迎え入れる真空のあるところにしか、入って行けない
◆ 本当の自己自身を獲得するために、自己自身を喪失しなければならない」というのが、キルケゴールによる信仰の定義
◆ 芸術作品というのは、できた原初にはそのすべてが呪物だった
◆ パウル・クレー 芸術とは、見えるものを再現するのではなく、見えないものを見えるものにするものである
◆ 私は文学作品を読むときには、呪物や供物として読んでいる
すべての文字は甲骨文字であり、すべての本を私は石碑だと思っている。
人類の石碑が書物だと思っているから、尊敬心が理解力を助けてくれている
私は本というのは紙だと思っていない
◆ 本を本だと思っている人は駄目です。本は人類の石碑であり、遺産つまりストーンヘンジや何かと一緒です
◆ 一冊の本といえども、本人が本当にその本を愛し、中にか、神の顕現を見れば、その本は芸術作品に変容していく
◆ 高村光太郎の「義ならざるものは、結局、美ではない」
◆ エドマンド・バーク 固辞で量感がある。人間に畏れを抱かしめるものであり・・・・・ごつごつしてて荒々しく、直線的で暗く陰鬱である
これが崇高の定義
◆ ヴァレリー 発見は何ものでもない 困難は発見したものを血肉化することにある
◆ 持続した人生というのは、空気と流行を拒絶した人間に与えられる恩寵だと断言できる
◆ すでに善人になってしまった人というのは人類をやめたということ
善を行いたい、善人にならなければいけないというのが人類
◆ 西田幾多郎 善を行う努力そのものを宇宙的実存の実行として捉えている
文明を担うのが人間の役割なのですから、文明を受け取る力が強いほど、人間としては価値が高いのです。
◆ 労働時間などというのは、マルクス主義の物質至上主義から生まれた考え
◆ 人間として価値のある人生を送りたかったら、誰にもわかってもらわなくていいと思わなければいけません。
ただ独りで生き抜くということは何かと言うと、幸福も成功も求めないということ
◆ 失敗ばかりの人生だったけれども、失敗そのものが成功の母になってくる。でも、失敗が成功の母にならない人は、みんな知っていると思うけれども、その人のせいにしている人です。
◆ 「土百姓とは自分は違う」という、そういう心持ちが武士道を遂行する。
◆ 諦めて、仕事を淡々と体当たりでやっていくだけなのでしょうか。最初に言っておきますが、体当たりに淡々はありません。体当たりとは、すべて全身全霊をもって、死ぬ気でぶち当たることを言います。
◆ 周りのことを気にしている人間は、永久に自分の生命が燃焼しないので、感化力がありません。体当たりで生きて、ただ独りで死ぬというつもりでいれば、運が良ければ、周りにいる人が感化を受けることもある。
感化を受ける人が現われることを期待するしか人生はない
◆ カントを読んでから、哲学書でわからない本が一冊もなくなってしまった。これは経験しないと分かりません。命懸けで体当たりすると、自分の脳回路が変わってくるのだと私は思います。
◆ 大体みんな、不幸です。私はああいう歴史的に不幸だった人に憧れています。
◆ 内村鑑三 日本の多くのキリスト教徒は、人に親切にしたりすることがキリスト教だと思っているということを嘆いている
◆ 「般若心経」が歴史的に言うと、仏教を救った
◆ 死が決まっていなかったら絶対に、体当たりや突進はできないです。 死を決めていないと必ず怯みます。そして周りに合わせるということになってしまう
◆ モンテーニュ 哲学を学ぶとは、死を学ぶということ
◆ 亀井勝一郎 『愛の無常について』
「生は未完の死である」
◆ 幸福になりたいと思っている人が一番駄目
生きている間、楽しもうでは 餓鬼道
◆ 『我と汝』 マルチン・ブーバー
人生は一回性の恐るべき眼差しにさらされなければならない
◆ 大西瀧治郎 わが声価は棺を覆うて定まらず。百年ののち、また知己なからんとす
◆ 西洋文明というのは、ゲルマン民像が造り上げたキリスト教との融合なので、キリスト教というのは知っての通り砂漠で生まれた宗教から、裁きが厳しいわけです。
◆ 教師の人格がどうかということだけが問題で、 人格が無ければ何を教えても駄目
◆ 無限経済成長に生きる人は、私から言わせれば、これは戦前の軍国主義と何も変わらない。みんな揃ってインパール作戦を敢行しているというやつです。
◆ 唾面自乾
顔に唾を吐かれても乾くまで待てばいいではないか
◆ 大体、利他なんてことは、言っていると駄目なんですよ。 もう少し具体的でなければ駄目 逃げ道があるのは駄目なのです
◆ ダグラス・マレーの『西洋の自死』がいい