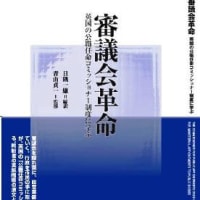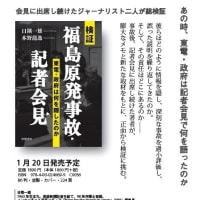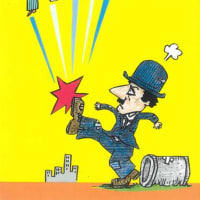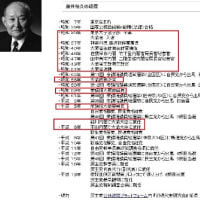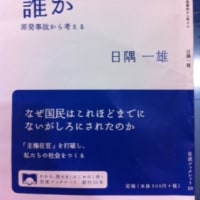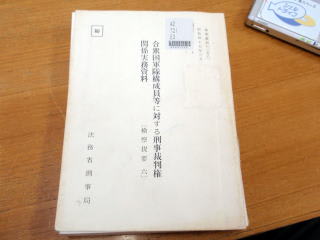
【駐留米兵らによる事件の捜査や公判の実務に関する「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」について、国立国会図書館が2月、一部閲覧禁止としていた処分をほぼ全面的に解除し、一般に公開していたことが(4月)1日、関係者への取材で分かった。】(共同、http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010040101000926.html)という報道がされてもうずいぶん時間が経ちましたが、あなたが読んでいる新聞はこの件、報道しましたか?
琉球新報(http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-160278-storytopic-1.html)が同じ4月2日に報じたほか、毎日新聞(http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100501k0000m040109000c.html)が5月1日に報じたくらいではないかな~と思う。
いつまで経っても報道されないので、そろそろ、ここでもご報告と思ってご紹介します。
この事件はもともと、駐留米軍に対する裁判権放棄に関する密約があるということが報道されたり、国会で議論された直後に、国会図書館が所蔵している検察官向けの刑事裁判権放棄に関するマニュアルを法務省が閲覧禁止にするよう国会図書館に依頼し、2008年6月、これを国会図書館が受け入れたというもの。その閲覧禁止自体が報道された後、8月にジャーナリストの斎藤貴男さんが、閲覧を申し込んだが、それを拒否されたため、2009年2月、閲覧禁止処分の取り消しを求めて訴訟を起こしていた。
私は斎藤さんの申し込みに同行し、情報公開訴訟、表現の自由に関する訴訟に詳しい先輩や仲間たちと斎藤さんの代理人として、活動してきた。
閲覧禁止とした【資料は法務省刑事局が1972年に発行。「実質的に重要であると認める事件のみ第1次裁判権を行使するのが適当」と各地検などに指示した53年の刑事局長通達も含まれている】(共同)。
閲覧禁止を要請した法務省の理由は、【(1)米軍関係者らの犯罪に関する捜査、公判の担当検事が執務の参考とするための内部資料(2)米側の信頼を損なう恐れがある―など】(共同)であった。2008年6月に閲覧が禁止された。
その後、2009年2月までの間に、一部開示されたうえ、段階的に開示範囲が広がったが、斎藤さんは全面開示を求めて提訴した。
一部は法務省と外務省の協議で同年11月から開示されたが、ジャーナリスト斎藤貴男さんが09年2月、国に全面開示を求めて東京地裁に提訴していた。
訴訟では、国側は、その後に部分的に開示しているにもかかわらず、斎藤さんに対して全面禁止にした理由について合理的な回答ができないなど厳しい立場に追い込まれた。(【国会図書館閲覧禁止事件で国打つ手なし?~次回1月19日11時要チェック】http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/792c65274e627925332639fb009d7a90)
その結果、ついに、【国会図書館内にこの資料のマイクロフィルムが所蔵され、一般にも利用可能だったことが判明。「閲覧禁止の継続は保有図書、資料の矛盾した取り扱いになる」として、個人情報部分を除き、全面解除された】(共同)わけだ。
しかし、本来、閲覧禁止にする必要があったならば、マイクロフィルム側を同様に閲覧禁止とすればよかったのであり、マイクロフィルムが閲覧されているから、本体も閲覧させるというのは、まぁ、おかしな感じはする。
訴訟もあるため、形式的には当初の判断を維持しつつも、事実上、その判断を修正したということだろう。
で、問題は、このことをいまだに報道していない社があることだ。
国会図書館が資料を合理的な理由もなく、閲覧禁止にしたうえ、政権交代後、それが解除されたのだから、本来、政権交代との関係も含めて、大きく報道されるべきだろう。表現の自由に対する過去の政権と現在の政権の違いが明確になる事実であるからだ。そして、表現の自由に対する政権の姿勢は、ただちに、報道の自由に基づいてビジネスをしている報道機関にとって、極めて関心が高いことであるはずだからだ。
本来であれば、斎藤さんに任せるのではなく、自らの記者に訴訟を提起させ、それをレポートしてもよいくらいの話だ。
しかし、そんな話になるどころか、いまだに、閲覧禁止が解除されたことを報道していないところが多いはずだ。
今後、明らかに新聞は衰退するし、テレビも現在のような制作と放送をテレビ局が一緒に行うようなシステムではなくなるだろう。
そのとき、新聞を支え、テレビニュースを支えるのは、比較的意識の高い層になることだろう。もちろん、この層ができるだけ広くなることを期待するが、現実には、惰性で購読している層は、確実に新聞の購読を中止するだろう。無駄だと感じる新聞代を支払う余裕が普通の世帯にはなくなっているからだ。
皮肉をいえば、中間層を破壊した小泉改革を支持した新聞の自業自得だが、個人的には、プロの報道機関に対する期待は捨てきれない。
近い将来、新聞(制作が分離した後のテレビニュースを含む)を支えるのは、意識的にその新聞を購読する人となるだろう。そして、それらの人は、どの新聞を選択するか迫られる。
その時、もちろん、新聞の政治的スタンスによって判断する人もいるだろう。
しかし、政治的スタンスの決まっていない多くの市民は、新聞が事実をどこまで伝えようとしているかによって判断するのではないだろうか。
たとえば、国会図書館閲覧禁止事件があったときに、どこまで真剣に国の矛盾を追及し、閲覧させる方向での紙面をつくるか?
あるいは、自らの記者が情報公開などの訴訟を提起し、それをルポとして伝えるか?
情報公開制度の拡充にどこまで真剣に取り組むか?
記者会見・クラブの開放を率先して行うか?
はたまた、抑止力があるというマジックワードに満足せず、なぜ、それが抑止力になるのかを追求し、レポートするか?
新聞が本来の権力監視機能を発揮できるかどうか、それが問われるはずだ。
まずは、国会図書館事件を報道していないところはそれを報道することから始めてみませんか、そして、読者の方は報道したかどうかを尋ね、まだだったらなぜ掲載しないのか、市民の閲覧の権利を軽視しているのか、と尋ねてみませんか?
●沖縄への連帯ツイッターキャンぺーン●
【ツイッターアカウント】@BarackObama
【メール】→http://www.whitehouse.gov/contactから
【ツイッター例文】
JAPAN IS NOT US'S COLONY! We won't support US BASE. All US BASE OUT! from our country.
Please HELP Okinawa. 75% of the American bases in JP is in the islands, only 0.6% of JP land. Relocate #Futenma base outside.
Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.
Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko
At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8
【ツイッターアカウント】yamebun
【PR】

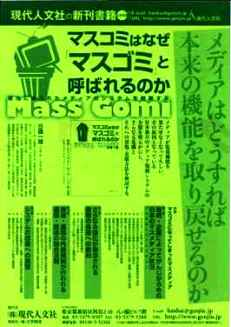
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。なお、多忙につき、試行的に、コメントの反映はしないようにします。コメント内容の名誉毀損性、プライバシー侵害性についての確認をすることが難しいためです。情報提供、提案、誤りの指摘などは、コメント欄を通じて、今後ともよろしくお願いします。転載、引用はこれまでどおり大歓迎です。
琉球新報(http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-160278-storytopic-1.html)が同じ4月2日に報じたほか、毎日新聞(http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100501k0000m040109000c.html)が5月1日に報じたくらいではないかな~と思う。
いつまで経っても報道されないので、そろそろ、ここでもご報告と思ってご紹介します。
この事件はもともと、駐留米軍に対する裁判権放棄に関する密約があるということが報道されたり、国会で議論された直後に、国会図書館が所蔵している検察官向けの刑事裁判権放棄に関するマニュアルを法務省が閲覧禁止にするよう国会図書館に依頼し、2008年6月、これを国会図書館が受け入れたというもの。その閲覧禁止自体が報道された後、8月にジャーナリストの斎藤貴男さんが、閲覧を申し込んだが、それを拒否されたため、2009年2月、閲覧禁止処分の取り消しを求めて訴訟を起こしていた。
私は斎藤さんの申し込みに同行し、情報公開訴訟、表現の自由に関する訴訟に詳しい先輩や仲間たちと斎藤さんの代理人として、活動してきた。
閲覧禁止とした【資料は法務省刑事局が1972年に発行。「実質的に重要であると認める事件のみ第1次裁判権を行使するのが適当」と各地検などに指示した53年の刑事局長通達も含まれている】(共同)。
閲覧禁止を要請した法務省の理由は、【(1)米軍関係者らの犯罪に関する捜査、公判の担当検事が執務の参考とするための内部資料(2)米側の信頼を損なう恐れがある―など】(共同)であった。2008年6月に閲覧が禁止された。
その後、2009年2月までの間に、一部開示されたうえ、段階的に開示範囲が広がったが、斎藤さんは全面開示を求めて提訴した。
一部は法務省と外務省の協議で同年11月から開示されたが、ジャーナリスト斎藤貴男さんが09年2月、国に全面開示を求めて東京地裁に提訴していた。
訴訟では、国側は、その後に部分的に開示しているにもかかわらず、斎藤さんに対して全面禁止にした理由について合理的な回答ができないなど厳しい立場に追い込まれた。(【国会図書館閲覧禁止事件で国打つ手なし?~次回1月19日11時要チェック】http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/792c65274e627925332639fb009d7a90)
その結果、ついに、【国会図書館内にこの資料のマイクロフィルムが所蔵され、一般にも利用可能だったことが判明。「閲覧禁止の継続は保有図書、資料の矛盾した取り扱いになる」として、個人情報部分を除き、全面解除された】(共同)わけだ。
しかし、本来、閲覧禁止にする必要があったならば、マイクロフィルム側を同様に閲覧禁止とすればよかったのであり、マイクロフィルムが閲覧されているから、本体も閲覧させるというのは、まぁ、おかしな感じはする。
訴訟もあるため、形式的には当初の判断を維持しつつも、事実上、その判断を修正したということだろう。
で、問題は、このことをいまだに報道していない社があることだ。
国会図書館が資料を合理的な理由もなく、閲覧禁止にしたうえ、政権交代後、それが解除されたのだから、本来、政権交代との関係も含めて、大きく報道されるべきだろう。表現の自由に対する過去の政権と現在の政権の違いが明確になる事実であるからだ。そして、表現の自由に対する政権の姿勢は、ただちに、報道の自由に基づいてビジネスをしている報道機関にとって、極めて関心が高いことであるはずだからだ。
本来であれば、斎藤さんに任せるのではなく、自らの記者に訴訟を提起させ、それをレポートしてもよいくらいの話だ。
しかし、そんな話になるどころか、いまだに、閲覧禁止が解除されたことを報道していないところが多いはずだ。
今後、明らかに新聞は衰退するし、テレビも現在のような制作と放送をテレビ局が一緒に行うようなシステムではなくなるだろう。
そのとき、新聞を支え、テレビニュースを支えるのは、比較的意識の高い層になることだろう。もちろん、この層ができるだけ広くなることを期待するが、現実には、惰性で購読している層は、確実に新聞の購読を中止するだろう。無駄だと感じる新聞代を支払う余裕が普通の世帯にはなくなっているからだ。
皮肉をいえば、中間層を破壊した小泉改革を支持した新聞の自業自得だが、個人的には、プロの報道機関に対する期待は捨てきれない。
近い将来、新聞(制作が分離した後のテレビニュースを含む)を支えるのは、意識的にその新聞を購読する人となるだろう。そして、それらの人は、どの新聞を選択するか迫られる。
その時、もちろん、新聞の政治的スタンスによって判断する人もいるだろう。
しかし、政治的スタンスの決まっていない多くの市民は、新聞が事実をどこまで伝えようとしているかによって判断するのではないだろうか。
たとえば、国会図書館閲覧禁止事件があったときに、どこまで真剣に国の矛盾を追及し、閲覧させる方向での紙面をつくるか?
あるいは、自らの記者が情報公開などの訴訟を提起し、それをルポとして伝えるか?
情報公開制度の拡充にどこまで真剣に取り組むか?
記者会見・クラブの開放を率先して行うか?
はたまた、抑止力があるというマジックワードに満足せず、なぜ、それが抑止力になるのかを追求し、レポートするか?
新聞が本来の権力監視機能を発揮できるかどうか、それが問われるはずだ。
まずは、国会図書館事件を報道していないところはそれを報道することから始めてみませんか、そして、読者の方は報道したかどうかを尋ね、まだだったらなぜ掲載しないのか、市民の閲覧の権利を軽視しているのか、と尋ねてみませんか?
●沖縄への連帯ツイッターキャンぺーン●
【ツイッターアカウント】@BarackObama
【メール】→http://www.whitehouse.gov/contactから
【ツイッター例文】
JAPAN IS NOT US'S COLONY! We won't support US BASE. All US BASE OUT! from our country.
Please HELP Okinawa. 75% of the American bases in JP is in the islands, only 0.6% of JP land. Relocate #Futenma base outside.
Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.
Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko
At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8
【ツイッターアカウント】yamebun
【PR】

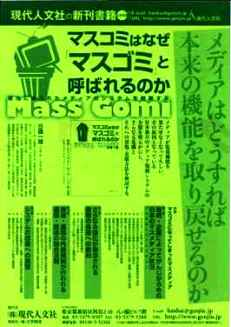
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。なお、多忙につき、試行的に、コメントの反映はしないようにします。コメント内容の名誉毀損性、プライバシー侵害性についての確認をすることが難しいためです。情報提供、提案、誤りの指摘などは、コメント欄を通じて、今後ともよろしくお願いします。転載、引用はこれまでどおり大歓迎です。