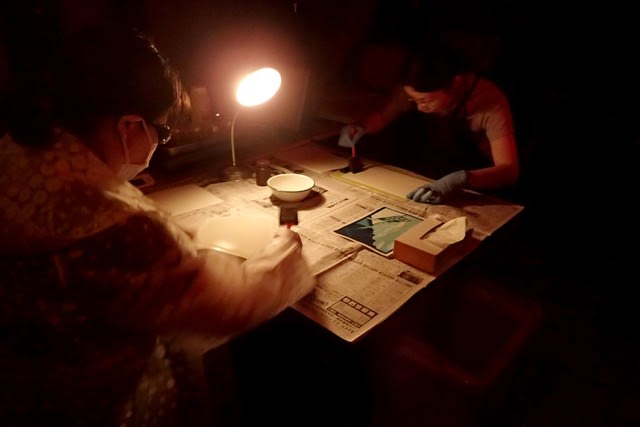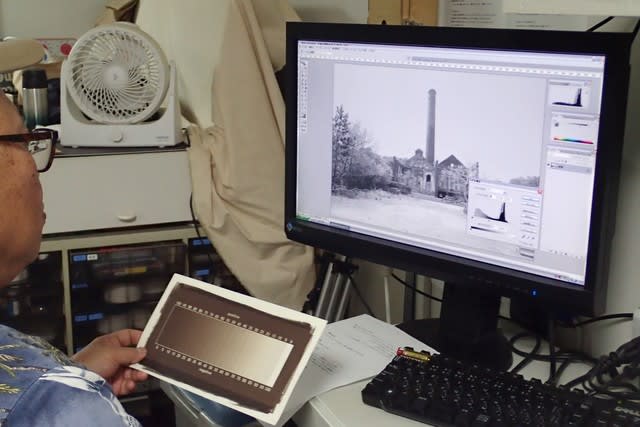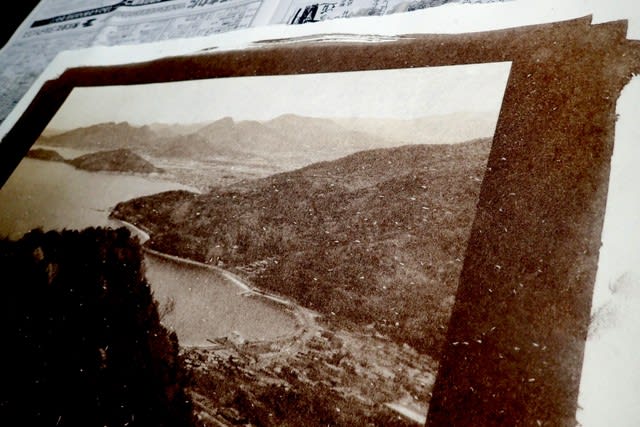この日は前回の暗室実習にて
現像を終えたフィルムからの
プリント作業に取り組みました。
まずは
コンタクトプリントの作成から。
テストプリントとして
段階露光をおこない
その結果を見て本番プリント。
その後
仕上がったコンタクトプリントを俯瞰して
引き伸ばす写真を選びます。
フィルム現像時に
うまくリール巻きができなかった部分は
コンタクトプリントで
白く画像が抜ける事となります。
(涙)
経験を重ねるなかで
このミスは失くしていきます。
受講生の方が
これまでにプリントした
モノクロ写真をご持参くださいました。
幾度となく焼き直しながら
1枚の写真が完成したことが伺えます。
本講座においても
後半は
バライタ印画紙を用いて
丁寧に暗室作業をおこない
銀塩写真制作に励みます。
*
<ご案内>
2020年度4月開始の講座は
現在、準備中です。
募集中の講座については
下記ページにて案内中。
http://tokunaga-photo.com/class/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所
大阪・鶴橋にて
写真・写真表現・シルクスクリーンetc.
表現の研究活動をおこなっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・