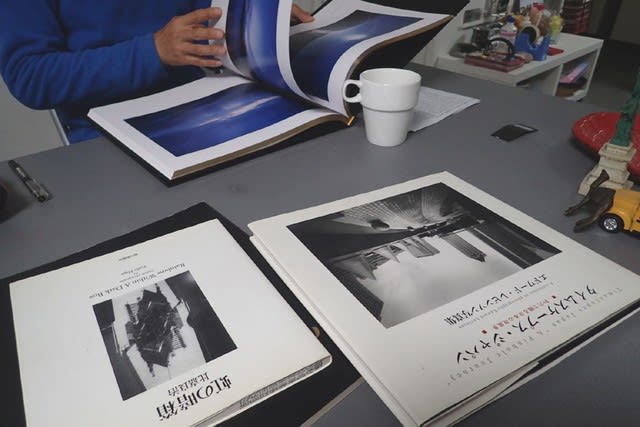2018年度より
月イチ創作実験クラブとして
月に1回のペースで活動してきました。
毎回
新たな実験をご用意していましたが
月イチでは文字通り「実験」に留まるため
2019年度は実験をもとに
次の展開も期待することにして
隔週での活動としました。
今回のレポートは
新たな体制でスタートした
クラブ活動1回目の報告です。
ホワイトボードに貼られたものは
何だと思われますか?
フクロウの目のように
見えるものもありますね。
これらがどのように描かれたのか
順を追って紹介します。
今回は
紙・墨汁・糸が
描く道具となります。
紙に墨汁を落としたり・・・
墨汁を塗った糸を置いたり・・・
本にはさんで糸を引き抜きます。
すると!
糸の動きが紙に軌跡として残り・・・
左右対称の・・・
そうでない場合もありますが・・・
絵筆を用いずに描いた絵図が
出現します。
タコ糸、毛糸、ロープなど
糸の種類を変えたり
墨汁の扱いを工夫すると
際限なく何パターンもの展開が可能です。
この技法はデカルコマニー。
糸を使う場合は
ストリングと限定的に呼ばれることもあります。
偶然の中に必然を見出せる本技法は
様々な展開ができそうです。
部員の皆さんにとって
多くの気づきがあったようでした。
このような気づきが
表現活動の引き出しを
増やすことに繋がるはず・・・。
きっと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所
大阪・鶴橋にて
写真・写真表現・シルクスクリーンetc.
表現の研究活動をおこなっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・