御師(おし・おんし)とは、特定の寺社に所属して、
その社寺へ参詣者を案内し、参拝・宿泊などの世話をする人のことです。
特に伊勢神宮のものは「おんし」と読んでいました。
御師は、元々は「御祈祷師」を略したもので、
平安時代のころから神社に所属する社僧を指すようになり、
後に神社の参詣の世話をする神職も指すようになりました。
平安時代の御師には、石清水・賀茂・日吉などがありますが、
代表的なのは熊野三山の熊野御師です。
熊野詣では平安時代末期に貴族の間で流行しましたが、
その際の祈祷や宿泊の世話、山内の案内をしたのが熊野御師でした。
鎌倉時代には武士にも広まり、
室町時代には農民などの庶民まで檀那とするようになります。
江戸時代には百姓と神職の中間の身分とされ、
経済の安定により庶民の間で寺社詣が流行するようになると、
伊勢や富士を中心に、出雲など多くの神社で御師の制度が発達し、
特に伊勢や富士では全国に檀那を持つまでに至ります。
伊勢御師は全国各地に派遣され、現地の伊勢講の世話を行い、
彼らが伊勢参りに訪れた際には自己の宿坊で迎え入れて便宜を図りました。
どのような便宜を図ったのか、
最近読んで神崎宣武さんの「江戸の旅文化」に具体的に載っていましたので、
概略を書いておきます。
「江戸の旅文化」が参考にしたのが「伊勢参宮献立道中記」と言う記録で、
1848年(弘化5年)の春、讃岐国寒川郡神埼村から20人ほどの
志度ノ浦講中の記録で、誰が記録したのかは明らかになっていません。
一行が御師岡田大夫の館に滞在したのは、3月27日から29日までの3日間です。
初日は駕籠を何台か手配してもらって、
手代の案内で二見ヶ浦を見物、内宮にも回って館に着きます。
大座敷に案内され、手代が裃姿で挨拶した後、
岡田大夫が衣冠を正して登場し、祝詞を述べて挨拶をします。
夕食は二の膳付きの豪華な料理が供されます。
翌日は手代の案内で外宮に参拝し、館に戻って朝食が出されますが、
旅籠の夕食並みの豪華な朝食です。
その後、一行は髪月代を整え、清めの風呂に入って裃袴の支度をします。
裃袴の用意がない者には、有料で貸し出しが行われます。
そして神楽が始まるまでの間に昼食が出されます。
神楽は館の中に神楽殿があって、そこで行われますが、総勢60人ほどの大勢の神楽です。
神楽が終わると直会ですが、
瓶子と神酒が下され、外宮内宮の供え物の授与があります。
神楽から直会まで、概ね4時間程度との事です。
その後饗宴になりますが、これが本膳から始まって四の膳まである豪華なもので、
講中の人々の度肝を抜くような豪華さです。
最終日は、朝食の後、手代の挨拶があって、
弁当などによる送別の小宴があり、外宮まで見送られます。
ここまでの費用は、神楽の初穂料が30両で、
祝儀などその他の費用も含めて、
講中から岡田大夫に渡された金額は36両と載っているとの事です。
講中の庶民達には、夢のような待遇なのだと思います。
このような講による伊勢参りは、農閑期に行われるのが通例です。
農繫期には、今度は御師や手代達が、全国各地の講を回って、
大神宮と銘された神札を配布して歩きます。
御師達は厚遇され、多くの浄財を集めますが、
こうした地道な営業活動が、お伊勢参りを盛んにしたのでしょう。
因みに、1755年(宝暦5年)の伊勢の御師の数は573家となっているとの事です。
その社寺へ参詣者を案内し、参拝・宿泊などの世話をする人のことです。
特に伊勢神宮のものは「おんし」と読んでいました。
御師は、元々は「御祈祷師」を略したもので、
平安時代のころから神社に所属する社僧を指すようになり、
後に神社の参詣の世話をする神職も指すようになりました。
平安時代の御師には、石清水・賀茂・日吉などがありますが、
代表的なのは熊野三山の熊野御師です。
熊野詣では平安時代末期に貴族の間で流行しましたが、
その際の祈祷や宿泊の世話、山内の案内をしたのが熊野御師でした。
鎌倉時代には武士にも広まり、
室町時代には農民などの庶民まで檀那とするようになります。
江戸時代には百姓と神職の中間の身分とされ、
経済の安定により庶民の間で寺社詣が流行するようになると、
伊勢や富士を中心に、出雲など多くの神社で御師の制度が発達し、
特に伊勢や富士では全国に檀那を持つまでに至ります。
伊勢御師は全国各地に派遣され、現地の伊勢講の世話を行い、
彼らが伊勢参りに訪れた際には自己の宿坊で迎え入れて便宜を図りました。
どのような便宜を図ったのか、
最近読んで神崎宣武さんの「江戸の旅文化」に具体的に載っていましたので、
概略を書いておきます。
「江戸の旅文化」が参考にしたのが「伊勢参宮献立道中記」と言う記録で、
1848年(弘化5年)の春、讃岐国寒川郡神埼村から20人ほどの
志度ノ浦講中の記録で、誰が記録したのかは明らかになっていません。
一行が御師岡田大夫の館に滞在したのは、3月27日から29日までの3日間です。
初日は駕籠を何台か手配してもらって、
手代の案内で二見ヶ浦を見物、内宮にも回って館に着きます。
大座敷に案内され、手代が裃姿で挨拶した後、
岡田大夫が衣冠を正して登場し、祝詞を述べて挨拶をします。
夕食は二の膳付きの豪華な料理が供されます。
翌日は手代の案内で外宮に参拝し、館に戻って朝食が出されますが、
旅籠の夕食並みの豪華な朝食です。
その後、一行は髪月代を整え、清めの風呂に入って裃袴の支度をします。
裃袴の用意がない者には、有料で貸し出しが行われます。
そして神楽が始まるまでの間に昼食が出されます。
神楽は館の中に神楽殿があって、そこで行われますが、総勢60人ほどの大勢の神楽です。
神楽が終わると直会ですが、
瓶子と神酒が下され、外宮内宮の供え物の授与があります。
神楽から直会まで、概ね4時間程度との事です。
その後饗宴になりますが、これが本膳から始まって四の膳まである豪華なもので、
講中の人々の度肝を抜くような豪華さです。
最終日は、朝食の後、手代の挨拶があって、
弁当などによる送別の小宴があり、外宮まで見送られます。
ここまでの費用は、神楽の初穂料が30両で、
祝儀などその他の費用も含めて、
講中から岡田大夫に渡された金額は36両と載っているとの事です。
講中の庶民達には、夢のような待遇なのだと思います。
このような講による伊勢参りは、農閑期に行われるのが通例です。
農繫期には、今度は御師や手代達が、全国各地の講を回って、
大神宮と銘された神札を配布して歩きます。
御師達は厚遇され、多くの浄財を集めますが、
こうした地道な営業活動が、お伊勢参りを盛んにしたのでしょう。
因みに、1755年(宝暦5年)の伊勢の御師の数は573家となっているとの事です。














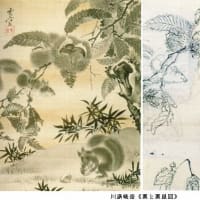







そうですね。
江戸時代には、旅行が大きなブームになったようです。
「江戸の旅文化」は、とても詳しくその辺を述べていて、面白かったです。
御師は、正に旅行業者ですね。
色々な便宜を図り、来た人に満足を与え、シーズン外には、地元に出掛けてPRしていますので、今の業者と同じだと思います。
僕も出掛けますが、余り会社を使わないので大人の休日俱楽部の冊子を見る程度です。