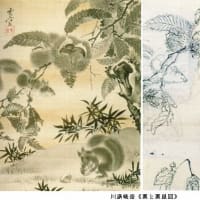大塩平八郎はご承知の通り、江戸時代後期の儒学者、大坂町奉行組与力で、
大塩平八郎の乱を起こした事で有名です。
天保の飢饉のために疲弊した市民を救うため、
天保8年2月19日(1837年3月25日)に門人、民衆と共に蜂起しますが、
同心の門人数人の密告によって蜂起当日に鎮圧されました。
大塩は戦場から離れた後、河内国を経て大和国に逃亡しますが、
数日後、再び大坂に舞い戻って
下船場の靱油掛町の商家美吉屋五郎兵衛宅の裏庭の隠居宅に潜伏していました。
しかし、これが発覚し、1837年5月1日(天保8年3月27日)、役人に囲まれる中、
養子の格之助と共に短刀と火薬を用いて自決しました。享年45歳でした。
大塩平八郎には生存伝説がある事を以前書きました。
https://blog.goo.ne.jp/tennnennkozi/s/%E5%A4%A7%E5%A1%A9
大塩平八郎の潜伏が発覚したのは、
この店に奉公していた17歳の女が帰省した際、
その家では毎朝飯を入れた飯櫃に茶碗を添えて棚下に置く習慣があり、
翌朝も空になったお櫃に飯を入れて出していると話した事が発端です。
この情報を元に、大塩平八郎の捕縛に向かったのが、
当時大阪城代だった土井利位の家老鷹見泉石です。
この時の状況が、鷹見泉石の書いた日記に下記のように詳しく書かれています。
3月26日、この通報を受けた泉石は、迅速に情報の裏付けを行い、
捕方への指示を行うと共に、
懇意にしていた大坂町奉行所与力内山彦次郎への根回しを行い、
翌日の捕縛を決定しました。
商家の路地口が開き、大塩が顔を出すと、
室内での捕方を想定し長さを半分に仕立てていた樫の召し捕り棒で打ち合います。
捕方の包囲を見て大塩平八郎は室内に引っ込み雨戸を締め切りにしました。
「中斎先生ともいわれるもの、卑怯千万、出て勝負せい」との呼びかけに、
大塩は「鉄砲、鉄砲」と答えますが、「鉄砲之なき事はとく知れて有る」とし、
続いて、「大塩平八郎といわれ候もの、尋常に出てこい」との言葉に、
「今出る、今出る」と応答します。
養子格之助を突き殺した上、火薬を取り出し火をかけようとする気配があったので、
雨戸を打ち破って突入したところ、
大塩は、喉へ三度ばかり突き立てた脇差しを投げつけ火薬に着火したとの事です。
先日行った、古河市の歴史博物館には、
この捕縛の様子が詳しく展示され、上記の樫の召し捕り棒が展示されていました。
大塩平八郎の乱を起こした事で有名です。
天保の飢饉のために疲弊した市民を救うため、
天保8年2月19日(1837年3月25日)に門人、民衆と共に蜂起しますが、
同心の門人数人の密告によって蜂起当日に鎮圧されました。
大塩は戦場から離れた後、河内国を経て大和国に逃亡しますが、
数日後、再び大坂に舞い戻って
下船場の靱油掛町の商家美吉屋五郎兵衛宅の裏庭の隠居宅に潜伏していました。
しかし、これが発覚し、1837年5月1日(天保8年3月27日)、役人に囲まれる中、
養子の格之助と共に短刀と火薬を用いて自決しました。享年45歳でした。
大塩平八郎には生存伝説がある事を以前書きました。
https://blog.goo.ne.jp/tennnennkozi/s/%E5%A4%A7%E5%A1%A9
大塩平八郎の潜伏が発覚したのは、
この店に奉公していた17歳の女が帰省した際、
その家では毎朝飯を入れた飯櫃に茶碗を添えて棚下に置く習慣があり、
翌朝も空になったお櫃に飯を入れて出していると話した事が発端です。
この情報を元に、大塩平八郎の捕縛に向かったのが、
当時大阪城代だった土井利位の家老鷹見泉石です。
この時の状況が、鷹見泉石の書いた日記に下記のように詳しく書かれています。
3月26日、この通報を受けた泉石は、迅速に情報の裏付けを行い、
捕方への指示を行うと共に、
懇意にしていた大坂町奉行所与力内山彦次郎への根回しを行い、
翌日の捕縛を決定しました。
商家の路地口が開き、大塩が顔を出すと、
室内での捕方を想定し長さを半分に仕立てていた樫の召し捕り棒で打ち合います。
捕方の包囲を見て大塩平八郎は室内に引っ込み雨戸を締め切りにしました。
「中斎先生ともいわれるもの、卑怯千万、出て勝負せい」との呼びかけに、
大塩は「鉄砲、鉄砲」と答えますが、「鉄砲之なき事はとく知れて有る」とし、
続いて、「大塩平八郎といわれ候もの、尋常に出てこい」との言葉に、
「今出る、今出る」と応答します。
養子格之助を突き殺した上、火薬を取り出し火をかけようとする気配があったので、
雨戸を打ち破って突入したところ、
大塩は、喉へ三度ばかり突き立てた脇差しを投げつけ火薬に着火したとの事です。
先日行った、古河市の歴史博物館には、
この捕縛の様子が詳しく展示され、上記の樫の召し捕り棒が展示されていました。