昨日に続き地震のことを調べてみた。
<ダムが、引き起こす地震>って嘘っぽい題名に驚かれる方も多いと感じる。
成美堂出版から発売されている、「地震のすべてがわかる本」に掲載されていた記事のタイトルである。
読んでいくと、今回の岩手・宮城内陸地震との意外な類似点を感じたので記事にしようと思う。
コイナダムはインド西部のデカン高原に位置し、1963年に完成した高さ103mのコンクリート重力式ダム。
貯水池誘発地震との関連で有名なダムで1967年9月13日にはM6.5の地震が発生している。
コイナダム周辺の地質は、6500万年前頃の溶岩で厚く覆われており、ダム建設以前は地震のほとんどない場所であった。
しかし、貯水が始まる1962年頃には、周辺で繰り返し地震が起きるようになり、5年後の大地震で180人以上の人が亡くなっている。
地震の引き金になったのは、ダムの貯水による水圧であり、その水圧は地下深部の断層を刺激し、岩盤と溶岩層が水圧の重力で限界に達した時に滑り落ちた考えられているようだ。
荒砥沢ダム(中央遮水壁型ロックフィルダム)、は、1998年11月に完成。
今回の荒砥沢ダム上流の山地の大崩落について専門家は、
「地震の揺れで火山性のもろい地盤が地中で液状化し、一気に横滑りしたのではないか。」と指摘している点にも注目。
岩盤の上に堆積した脆い火山灰性の地盤と、コイナダム地震との関連はあるのか?
個人的な素人の見解だが、M7,2もの大地震が、ダムの貯水池による水圧とは考えにくい。
また、そうした可能性があれば専門化の方々の意見としてWeb上に何らかの記載があると考えられるが見つけることはできなかった。
ただ、気になる記載(火山活動)を見つけたので掲載したい。
今回の、岩手・宮城内陸地震に位置を地図で調べてみると、焼石岳の南に石淵ダム、栗駒山の直ぐ南に荒砥沢ダム、栗駒ダム、花山ダムと直線上に北から南に向かってダムが次々と建設されているのが分かる。
また、この山間部を襲った内陸型地震は、ダムからダムに向かうように断層の破壊が起きたことは周知の通りであろう。
ダム周辺の地質を調べようと、焼石岳と栗駒山について調べてみると、焼石岳については死火山として認識されているようだが、栗駒山については昭和60年以降、火山活動に起因するものと思われる地震が多発しているとの記述もあり、さらに最新のニュースでは、宮城県の災害対策本部の発表として、6月16日、栗駒山、山頂南西約7キロで火山性ガスの可能性がある水蒸気の噴出を確認したと報道もある。
しかし、東北大学地震・噴火予知研究観測センターの話として、
「地震で山の地盤が動き地下にたまっていた火山性ガスが噴出したり、温泉のもとになる地下水脈の流れが変わって水蒸気が出たりした可能性がある。」とし、
「現場は栗駒山の山頂付近から相当離れており、火山活動の活発化を意味するものではない。」
との見解を示している。
地元の研究者の方が火山活動を否定するのだから事実だと信じるが、
「火山活動」と、
「地質」と、
「ダムの水圧」の、
3要素が今回の地震にどのような係わりを持っているのか知りたいと感じた。
また、地震が起きた当初の報道では、荒砥沢ダムの崩落は、通常起きる山地の上部からの崩落でなく、下部からの崩落の可能性を示唆する報道があったと記憶するが、このことはダムを作らなかった自然の状態の場合は崩落は起きなかった可能性を意味し、ダム施工に問題点はなかったかの解答も知りたい。
さらに、地震との関連性とは別に、仮に栗駒山で火山活動が起きた場合のダム機能への影響を調査すべきだと感じる。
過去の富士山の火山活動と、東海地方の大地震との事例を調べてみると、今後栗駒山で絶対に火山活動が起きないと断言はできないように思う。
300億円もの費用を要する荒砥沢ダムの大改修工事の必要性は、今後の温暖化多雨を想定して必須条件と考えるが、火山活動が起きた場合に再び埋まる可能性のある場所ではないのか?
そうした調査も必要なのではないかと考える。
・・・ などと、素人が余計なお世話?
失礼しました。
余談だが、断層上地震によるダムの破壊は、1999年9月29日に起きた台湾中部(集集=チチ)大地震(M7,7)において、台中の北西にあった石岡(シーカン)ダムで実際に起きているが、この時にはコンクリートブロックの流失はなく、貯水は割れ目からの噴出で留まっている。
<今回の参考資料>
 |
地震のすべてがわかる本―発生のメカニズムから最先端の予測まで 成美堂出版 このアイテムの詳細を見る |










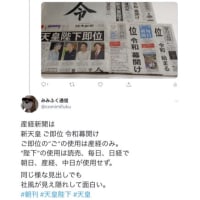

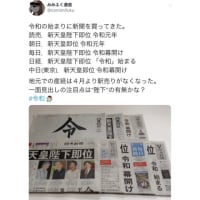

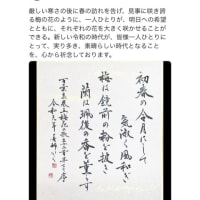
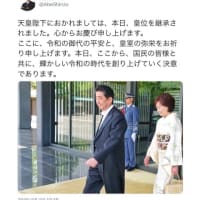



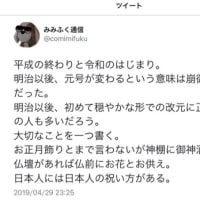





地震と火山活動の連動生は、かなり前から指摘され、東北地方では、火山活動と関連しない地震を探す方が大変なくらいでした。
イタリアのバイヨントダムも、ダムの水を吸った脆い岩盤の崩落で、大災害をもたらしたのですが、三度目の崩落で、ダム堤を越える津波が起き、2000名以上が死亡しました.
ちょっと、調べてみました。
下記、6月29日の読売新聞web記事です。
岩手・宮城内陸地震で起きた荒砥沢ダム上流部の大規模な地滑りで、土砂の一部がダム湖に流入し、高さ約3メートルの津波を発生させていたことがわかった。
イタリア北部のバイヨントダムでは1963年、豪雨による大規模な地滑りで津波が発生。
ダムを越えた津波は濁流となって下流域を襲い、約2600人が死亡した。
京大防災研究所の釜井俊孝教授も「土砂の流入量が数倍大きいか、流入した場所の水深が深ければ、津波がダムを越えた可能性が高い」と話している。
6月29日3時12分配信:読売新聞の記事。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080628-00000064-yom-sci
でも、自然が起こす災害を推測するのは極めて困難で、過去の経験(歴史資料)を丹念に調べながら現代の事情に当てはめることが必要なようです。
ブログ内の関連記事「荒砥沢ダムの大崩落」と「島原大変肥後迷惑」/ダムの限界。
も読んでいただければ幸いです。
http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/80b1b31791c27c2b5c540ca073617889
また、気付いたことがあれば教えてくださいね。
コメントありがとうございます。
ダムを造った事によって地震が誘発されるか否か?
地下水位の上昇と地下深部の歪み。
海洋地震やその他のダム地域と地震の関連性を考慮し、
ダムに貯めた水が地下に浸透し地震を起こすかどうか?
例えば黒部ダムや御母衣ダム等の大型ダムのの完成後に、
地域圏内で顕著な地震活動があったかどうだったか?
中筋さんが指摘される牧尾ダムの完成から15年後に起きた、
1976年~84年の地域の地表変動との関連性とタイム・ラグ。
さらに牧尾ダム周辺の地質はダム建設に適していたのか?
ダムの完成と群発地震の関連性を断定するには、
もう少し論点を詰めてみる必要もありそうです。
趣旨に沿った興味深いお話をありがとうございます。
またコメントをいただければ幸いです。