あいちトリエンナーレの「表現の不自由展・その後」を再開したことで、国民の怒りの矛先は大村秀章愛知県知事と津田大介に向けられている。マスコミが加勢してくれるからと、二人は国民を甘く見ていたのだろうが、そうは問屋がおろさないのである▼マスコミは表現の自由の問題に矮小化しようとしているが、それがかえって最悪の事態を引き起こおこしかねないのである。事実をきちんと伝えずに、一方的な報道を続ければ、危機感を募らせて、実力行動に訴える人も出てくるだろう。マスコミが両方の意見を伝えないことで、かえってそうしたムードが醸成される危険性が高まっている▼昭和天皇の写真を焼き、靴で踏み潰すというのは、明らかに常軌を逸している。だからこそ、それが国民に知れ渡れば、とんでもないことになるのを、マスコミは恐れているのである。マスコミが伝えなくても、ネットがその事実を拡散し、国民の怒りは爆発寸前のマグマである。さらに、原発事故を喜ぶような展示物があるとの指摘もあり、二人は日を追うごとに孤立し、追い詰められている▼大村と津田は被害者面をしていれば、英雄になられると思っていたに違いない。しかし、ネットの反応をみても、二人に味方する国民はほんのわずかである。聖書にも書かれているように「蒔いた種は自ら刈り取る」しかないのである。
応援のクリックをお願いいたします













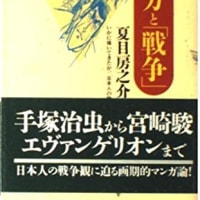


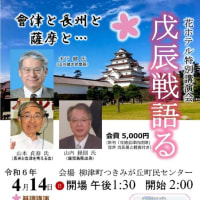

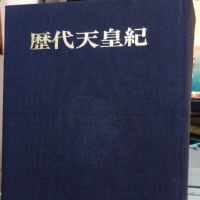
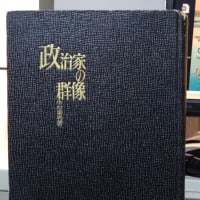
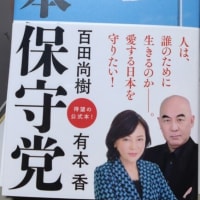
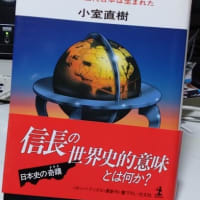
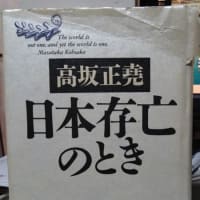






李氏朝鮮の真実は、隠そうとしても隠しきれるものではない。「隠すより現る」である。
『検定版 高等学校韓国史』は、救いようのないものを無理矢理庇おうとして詭弁を弄することになる。
「高宗の俄館播遷により日本の干渉からある程度抜け出したものの、ロシアをはじめとする列強の利権侵奪はいっそう激しくなった。政府は国家の自主的地位と国王の権威を取り戻すために努力した。」(178ページ)というのであるが、高宗と取り巻きはロシア公使館に1年近くとどまり続けて執政しているのだから、これは詭弁でしかない。
「ロシアは軍事教官と財政顧問を派遣して朝鮮の内政に干渉」というが、そもそも高宗と政府がロシアに軍事教官と財政顧問の派遣を要請したのである。
また、「5. 近代主権国家をうちたてようとする」という項目にあわせて、「民衆を呼び覚まして国民国家をつくろう」とする「独立協会」の澎湃(ホウハイ)たる運動があったかのように記述を装うのだが、実際は大衆的な広がりがなく、線香花火のように終息させられたのである。
「政府批判を続けた独立協会は1898年、弾圧によって壊滅するのであるが、その批判の一つとは国王と政府がロシア公使館にあったとき、鉱山や鉄道といった国家利権を密かに欧米列強に売り飛ばしていたことに対してであった。」(「朝鮮史」)
つまり、韓国の教科書の著者・官製民族主義者が「外勢の侵奪だ。利権強奪だ」と金切り声をあげることの多くは、実は、私腹を肥やすために高宗とその取り巻きたちが国内利権を外国に切り売りした結果なのである(今でもアフリカの独裁国ではありがちな事)。
高宗は、およそ1年後にロシア公使館から王宮に戻った。
「中国では、古来から皇帝が天壇で祭天の儀式を行っていた。しかし、朝鮮では、祭天を行う事ができるのは中国の皇帝だけであり、中国の皇帝から冊封されている朝鮮国王は、祭天を行えないとされていた。ところが、日清戦争で日本が清に勝った結果、下関条約で朝鮮は中国からの独立が認められ、1897年に朝鮮国王は大韓帝国皇帝に昇格した。そのため、独自に祭天を行うこととなり、中国の天壇のまねをして圜丘壇を作った。」(Wiki)
「10月12日に祭天の儀式を行い、翌13日に詔を出して皇帝に即位した。その後、清の冊封の象徴であった迎恩門、『恥辱碑』といわれる大清皇帝功徳碑を倒して独立門を立て独立を記念した。」(同)