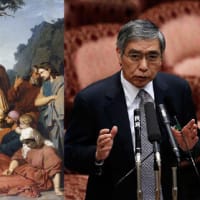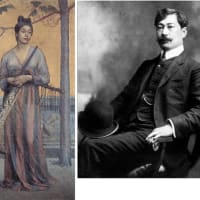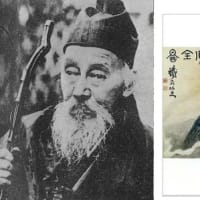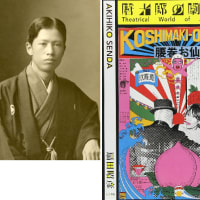A.自己決定という虚構
デモクラシーの基本は、個々の人間が主権者であり、それぞれが主体的な意思と決定権をもち、さまざまな課題について言葉で討議し、一致点を求めてやりあうが合意に至らない場合は、武力暴力ではなく公平な投票による多数決によって決定する、という方法を最善とするということだろう。だとすると、まずは個々の人間が、さまざまな問題について十分な情報と冷静な判断力をもっている、ということが必要だ。そのためには必要な情報に接することのできるメディア環境と判断力を養う教育が、成人有権者になるまでに誰もがしっかり身につけている社会でなければならない。しかし、現実にはそれはかなり難しいことであって、日本では政治にも選挙にも関心が薄い人が半数近くいるのが現実であるし、逆に情報統制で独裁体制下の国々で90%以上の投票率があったりするのも矛盾している。
そもそも誰もが理性的合理的な情報と判断力をもっている、というのは虚構であって、マス・メディアと教育制度が整っている先進国でも、ポピュリズムやカルト宗教が大きな勢力をもっていたりする現状からすれば、デモクラシーが最善の決定システムかどうか、疑われてもしかたがない。しかし、自己決定と自己責任という論理の危うさは、エイドスに対するコナトゥスとして世界を見るスピノザ哲学からすれば、どうなるのだろう?人は自分のことを自分で決定できると考えること自体、自己の主体というものを無条件に前提にした虚構ではないのか。
「私はスピノザと違って、絵も描かないし、釣りもしないのですが、もしそれをやるようになったら、世界は違って見えるでしょう。これまで受け取ったことのなかった刺戟を世界から受け取ることになるからです。
スピノザが「人間身体を多くの仕方で刺激されうるような状態にさせるもの」と言っているのは、このようにして受け取れる刺激の幅を広げてくれるもののことです。たとえば精神的な余裕はこれに当たるでしょう。また学ぶという行為もそれに当たります。それをスピノザは「有益」と言っているのです。
考えてみればこれはごく当たり前のことです。そして、当たり前のことですが、大切なことです。こういうとても常識的なことをしっかり書き記しているところも『エチカ』の面白いところです。
次の「賢者」の話も、私の好きな箇所です。
もろもろの物を利用してそれをできる限り楽しむ〔……〕ことは賢者にふさわしい。たしかに、ほどよくとられた味のよい食物および飲料によって、さらにまた芳香、緑なす植物の快い美、装飾、音楽、運動競技、演劇、そのほか他人を害することなしに各人の利用しうるこの種の事柄によって、自らを爽快にし元気づけることは、賢者にふさわしいのである。(第四部定理45備考)
これはまさしく「多くの仕方で刺激されうるような状態」にある人のことです。「嘲弄」ではない笑いやユーモアは「純然たる喜び」であり、そうした喜びに満ちた生活こそ「最上の生活法」だとも述べられています。そういう生活法を知っている人こそが賢者なのです。
賢者とは難しい顔をして山にこもっている人のことではありません。賢者とは楽しみを知る人、いろいろな物事を楽しめる人のことです。なんとすばらしい賢者観でしょうか。
前章では、スピノザのエチカは実験することを求めるという話をしました。それに関連するスピノザの有名な言葉があります。私たちは「身体が何をなしうるか」を知らないというものです(第三部定理2備考)。
これは身体一般が何をなしうるかを我々は知らないという意味でもありますし、私の身体が何をなしうるかを私は知らないという意味でもあります。
さらには、身体だけではありません。私の精神が何をなしうるのかも私にはよくわかっていません。それを知ることは、私の精神や身体がより多くの仕方で刺激されるようになることにつながります。
それは教育の役割でもあるでしょう。
おそらく優れた教育者や指導者というのは、生徒や選手のエイドスに基づいて内容を押しつけるのではなくて、生徒や選手自身に自分のコナトゥスのあり方を理解させるような教育や指導ができる人なのだと思います。
そう考えると、古典芸能などで言う「型」というのは、その型を経ることで自分の力の性質を知ることができる、そのようなものなのかもしれません。
さて、スピノザのコナトゥスの考え方を聞いてこんな反論を思いつく方もいるかもしれません。どんな存在にも自分の存在を維持しようとする力が働いているとすれば、自殺はなぜ起こるのかという反論です。
実はスピノザはこの問いについても答えを用意しています。
あえて言うが、何びとも自己の本性の必然性によって食を拒否したり自殺したりするものでなく、そうするのは外部の原因に強制されてするのである。(第四部定理20備考)
つまり自殺の場合、本人には意識されないかもしれないが、何らかの外部の原因がそれを強制しているということです。
コナトゥスはもちろん働くけれども、その原因が圧倒的であり、いわばキャパシティオーバーになってしまう。たとえば、幼い頃、激しい虐待を受けていて、その記憶に耐えきれず、生きるのがつらい。あるいは何かの責任に追い詰められて、その状況の苦しさに耐えることができない。
ポイントは自殺と呼ばれているものであっても、自分が原因になっているのではなくて、外部に原因が、しかも圧倒的な原因があるということです。
驚くべきことにスピノザはここで「食の拒否」という拒食症に近いことまで考えています。
実際にここで想定されているのが拒食症に近いものであるのか、十七世紀に拒食症のような症状が知られていたのか、私には分かりません。いずれにせよ、それは自分のコナトゥスが外部の圧倒的な原因によって踏みにじられた状態において起こるとスピノザは考えているわけです。
これは活動能力を低めるどころか、力そのものが踏みにじられる状態です。外部の力によって自分が完全に支配されてしまい、うまく自分のコナトゥスに従って生きることができない。スピノザは自殺夜食の拒否のことまで考えてコナトゥスという概念を提示しているのです。
では、死についてはどう考えればいいのでしょうか。本質を力としてとらえるスピノザ哲学からはどのような死の概念が導き出せるのか。
スピノザは次のように述べています。
人間身体は死骸に変化する場合に限って死んだのだと認めなければならぬいかなる理由も存しない〔……〕。(第四部定理39備考)
いわゆる死、私が死骸になる死というのは、私の本質を支えていた諸々の部分の関係が変化し、別物になってしまうということです。ですが、そのような変化は死骸になるときにだけ起こることではないとスピノザは言っているわけです。
この箇所では「あるスペインの詩人」のエピソードが紹介されています。その詩人は病気にかかり、ここから回復はしたものの、自分の過去を忘れてしまって、自分がかつて作った物語や悲劇を自分の作品だと信じなかったというのです。
スピノザはこの詩人は一度死んだも同然であると考えます。個体の中の諸部分の組み合わせ、この場合にはこの詩人の精神の中の諸部分の組み合わせかもしれませんが、それが本格的に変更され、ある閾値を超えた時、本質は全く違うものに生まれ変わることがありうる。それはある種の「死」であるというわけです。
スピノザは子供の成長の例も挙げています。大人は、自分がかつて子どもであったことを信じることができないほどに、今の自分の本質と子どもの時の本質が異なることを知ります。ここでも人は一度生まれ変わっている、つまりある意味で一度死んでいると考えられるというわけです。
ここで『エチカ』の専門用語を少し解説しておきたいと思います。
スピノザは「おのおのの物は自己の及ぶ限り自己の有に固執するように努める」(第三部定理6)という定理でコナトゥスの概念を提示した際、その「証明」の中で次のように書いています。
なぜなら、個物は神の属性をある一定の仕方で表現する様態である〔……〕、言いかえればそれは〔……〕神が存在し・活動する神の能力をある一定の仕方で表現する物である。(第三部定理6証明)
スピノザの用語を理解していなければとても読み解けない一節です。ですが、スピノザ哲学の根幹を説明した一節でもあります。頑張って解説していきましょう。
ここに出てくる「変状」という概念についてはすでに触れました。物が何らかの形態や性質を帯びることを変状と言います。ここにはそれに加えて、「属性」と「様態」という専門用語が使われています。この一節はスピノザにおける個物の地位、より詳しく言うと、神と個物の関係を説明したものです。
前章で、神は無限であり外部がない。したがって、私たちも含めた万物がその中にいるのだという話をしました。だからこそ神は自然と同一視されるのであり、その自然は宇宙と呼んでもよいと言いました。
実は、私たちは神の中にいるだけではありません。私たちは神の一部でもあります。万物は神なのです。
このことを説明するためには、神のもう一つの定義を紹介しなければなりません。神は自然であるだけでなく、「実体substantia」とも呼ばれます。
実体というのは哲学で古くから使われてきた言葉ですが、その意味するところは決して難しくはありません。実体とは実際に存在しているもののことです。神が実体であるとは、神が唯一の実体であり、神だけが実際に存在しているということを意味しています。
実際に存在しているのが神だけだとすると、私たちはどうなってしまうのでしょうか。
私たちは神という実体の変状であるというのがスピノザの答えです。つまり、神の一部が、一定の形態と性質を帯びて発生するのが個物であるわけです。
個物はそうやって生じる変状ですから、条件が変われば消えていきます。しかし個物は消えても、実体は消えません。
スピノザは水を例にしてこんなふうに述べています。
水は水としては生じかつ滅する。しかし実体としては生ずることも滅することもない。(第一部定理15備考)
水は科学的に分解してしまうこともあるでしょうし、個体や液体にもなります。しかし、水へと変状していた実体が消え去るわけではありません。これは気質保存の法則にも似た科学的な考え方だと思います。
神を無限に広がる一枚のシーツのようなものにたとえれば分かりやすいかもしれません。シーツに皺が寄ると、さまざまな形や模様ができますが、それが変状としての個物です。シーツを引っ張ると皺は消え、また元の広がりに戻りますが、シーツは消えません。」國分功一郎『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』講談社現代新書、2020.pp.71-80.
西欧近代は、神による創造というキリスト教の原理を徐々に希薄化させ、教会と結びついた「神」という観念を疑って来たから、デカルトやスピノザが言う「神」という言葉にも今はあまり関心は向けない。日本人はもともとユダヤ=キリスト教的一神教をもたなかったから、「神」という概念も、なんでもありのあやふやなものでしかない。でも、神による世界の創造、という観念は、近代を導いたデカルトやスピノザの哲学には、神の否定ではなく神の証明こそが基軸にあったということを、確認しておく必要がある。

B.地方議会の悲惨な現状
4月の統一地方選挙が終わって、新たな首長のもと地方議会が開かれたが、どうも地方自治の活性化には程遠く、投票率と市民の関心は低いままだ。とくに人口減少の著しい地方の議会は、議員になり手が乏しいという。選挙に立つ人がいないのでは、無投票で世襲的議員が決まり、旧態依然の議会で何が議論されているのかもど~でもいいと思う人が多くなる。もと知事で大臣も経験している片山善博氏の意見が新聞にあった。
「地方議会 関心上げるには 片山善博 声生かし、まず予算案修正
四月の統一地方選の結果を見て、地方自治に対する住民の関心がますます低くなっているとの印象を深くした。関心の低さを象徴するのが低投票率と議員のなり手不足である。後者は特に地方部で目立っている。立候補者が議員定数を超えず、選挙自体が執行されなくなった例が少なくない。
そもそも地方自治とは、地域のことは地域の住民が責任をもって決める仕組みである。その決める場が、住民の代表で構成される議会にほかならない。そうであるなら住民の関心が議会にもっと向けられていい。
「学校の教師の多忙化を解消できないか」「子どもたちの通学路に安全な歩道を整備すべきだ」「保育所の運営を改善してほしい」など、自治体の施策やその裏付けとなる予算に対して不満や要望がないはずがないと思う。
しかし、議会に対する住民の関心は低いままだ。理由の一つとして、自治体の施策を決めるのは議会ではなく、首長(知事、市町村長)だと認識する人が多いことが挙げられる。それは全くの誤解なのだが、議会と首長との関係の現状をみる限り、そう勘違いされてもやむを得ない面はある。
例えば、自治体の施策を決める予算は、首長が予算案を作って議会に提案し、それを議会が審議した上で決定する。これが地方自治法上のルールである。審議の過程では、必要に応じて修正などがなされることも、当然想定されている。
ところが、全国のほとんどの自治体では、首長の予算案がそのまま予算そのものとなる。議会での審議を経ても無傷、無修正のままである。いや、審議とは名ばかりで、実質的にはほとんどしていないに等しい。首長が予算案を議会に提出する段階で、すでに議会の多数派が、無傷で可決することを事実上約束しているからである。
もちろん形式的な審議は行われる。そこでは多数派に属さない一部の議員が予算案に異論を唱えたり、修正を提案したりするが、数の論理のもとでは多勢に無勢で、しょせんはごまめの歯ぎしりでしかない。
当の議会の多数派の人たちから、住民が議会を信頼してくれないし、関心も寄せてくれないと愚痴を聞かされることもしばしばである。ただ、予算の扱い一つとってもこんなありさまであれば、住民は議会の審議に関心のもちようがないし、まして信頼などとは縁遠いと知るべきである。
議会の将来を真剣に考えている人に、次のようにアドバイスしている。まず、予算審議に本気で取り組むことから始めてはどうか、と。それだけでも、議会に対する住民の関心度が飛躍的に高まる第一歩となる。
それには、審議が行われる前から結論を決めてしまう悪弊を断ち切らなければならない。議会という公開の場で、予算案の項目を一つ一つ吟味する。歳出に無駄があるなら削減する、必要な経費が不十分なら、削減によって生じた財源を充てて増額すればよい。
多数派の人々は「自分たちは予算案を作る過程で、内々に協議や調整をやっているので、いまさら議場で議論する必要はない」と言う。しかし、闇の談合めいたことの結果では、住民の納得は得られない。かえって議会に対する不信感が募るだけである。
予算案を修正すれば、首長の顔をつぶすことになると反論する人もいるが、そんな心配は無用である。議会は首長の親衛隊などではなく、住民や地域のことを第一義に考えるべき存在だからだ。
公開の場でちゃんと予算を審議する議会であれば、住民は必ず関心を寄せるようになる。もし、審議の過程で住民の切実な声が議会で取り上げられ、それが予算の修正に反映されるようなことにでもなれば、住民は確実に議会を信頼する。
議会に対する住民の関心が低いことは、地方自治の空洞化につながる。それを避けるべく、議会には思い切った自己改革をしてほしい。ちなみに、筆者が鳥取県で知事を務めていた
なず時、予算案が議会で修正されることは珍しくなかった。
もとより、それで知事の顔がつぶれることなどなかったし、修正内容も「なるほど」とうけるものばかりだった。首長と議会がこんな間柄である自治体が増えることを切に願っている。 (かたやま・よしひろ=大正大教授・地域構想研究所長)」東京新聞2023年6月1日夕刊3面。
ぼくも地方議員だった配偶者のおかげで、自治体行政の仕組みと地方議会の実体、とくに地方議員のやっていること、考えていることを多少は見聞きしている。片山氏が書いているように、議会が正常に機能しない状況にあるところが多く、投票率の低下と立候補者の固定化減少は、国会の自民党一党支配が強まったこの10年で末期的症状を呈していると思う。与党議員は少数野党議員の意見は初めから無視して、さまざまな決定が議会以前に一部ボスによってほぼ決まっているような実態を強めたことで、議会が無意味化してしまった。有権者もそれを知って、選挙も議会もどうせ変わらないとばかばかしく思うようになった。それは人口減少で衰弱を強める地域社会を、さらに悪化させるしかない。