 1980年代
1980年代
雛祭りの3月3日が過ぎた。女の子の健やかな成長を願う行事の事。雛壇に飾る3枚重ねの餅菓子。赤白草餅にはそれぞれ解毒作用のあるクチナシ、血圧を下げる菱の実、厄除けの力があるヨモギが使われる。
さらに、白酒は蒸した餅米に、麹とみりんを加えて熟成させた酒。飲むと邪気を払うという。雛あられは焼き米の一種で、もみ殻が付いたままの餅米をゆっくり煎って作る。よくはぜると吉といい、作る時その年の吉凶を占った。ハマグリのお吸い物は、貝殻がほかの貝とは決して合わないことから一夫一婦の願いが込められている。
私の家の雛飾りは長女が初節句を迎える時に、家内の実家から贈られた。40年を超えて前のこと。雛飾りのお陰もあって、現在娘は元気に育ち、結婚して2児の母親になっている。写真は飾り段の前の娘、なんだか嬉しそうだ。
その後長い間雛壇は本人の祖父母の家に置かれていた。そのため雛祭りの日には、娘はもちろんだが、祖父母も「どうしたものか」と飾ることに困惑。大きく重いものであり、「本人がいない」ためだ。「たいへんだったよ」とお知らせとも愚痴ともとれる母のことばを聞いたこともある。現在はすでに役割を終えているが、雛人形だけはこの時期、明るい場所に並んで湿気対策されている。私はその姿を見て、この40年余りを振り返り、父母や義父母を思い出している。感謝である。
















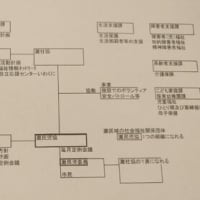



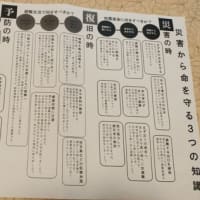





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます