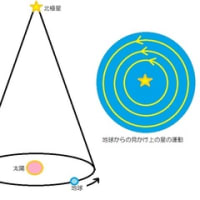1 問題の発端
文章は言葉の連鎖からなります。けれども、「言葉」を使いこなすのは難しいものです。
言葉の意味と活用法を理解しなければならないからです。用語の意味は、辞典や辞書に書いてあるものだけで理解できるとは限りません。
前回、私は、哲学の用語Dialektikを「弁証法」ではなく、「対論法」と訳した方がよいと述べました。現代人にとっては、弁証法という難しい漢語よりも、対論方の方がずっとわかりやすいと判断したからです。
「弁」という漢字には、「反論する」「論駁する」という意味がありますが、「弁証」という語に「敵対的・対立的な言説・論証」という意味があることを知るためには、かなりの調査や検索を必要とします。
それに、この訳のわからない用語には、呪物的な神秘性、理性的な考証や分析を拒否してきた、哲学アカデミズムの悪弊が絡みついています。
●「弁証法」に関するエピソード●
そのむかし、京都にあったさる帝国大学の超がつくほど高名かつ「偉大な」(と哲学界では信じられていた)大教授が、「弁証法」の観念論的解釈を展開した。その論のなかで、「絶対的矛盾の自己同一」という呪文のようなテーゼ(いや大向こうを狙ったキャッチコピーというべきか)を提示した。
矛盾というのは、2つ(以上)の事象のあいだの関係性(つまりは相対的なもの)をいう用語なのに、「絶対的」と形容した。あるいは、相手を完全に排斥するほどの敵対性をもつ事象をいうのか。そのうえ、その絶対的矛盾をして、「自己同一性」のうちにあるもの、と規定した。
いや、この「絶対的」というのは、この矛盾関係にある2つの存在(属性)が、そのほかのあらゆる事象から切り離されて独立し、1個の揺るぎない全体を形づくっているということなのか。だとすれば、外観上は自立自存するかに見える事象を体系性や総体性のなかに位置づけて認識する、「弁証法」の方法論とは相容れないものとなる。
わたしは、この大先生の所論がちっとも理解できない。
ヘーゲルについては理解できたが、この大教授の理論はさっぱりわからない。
で、私のホンネは、「おうおう、ご大層なキャッチフレイズでご苦労さん。でも、アホか!」だった。この大先生は、思考回路が一般人と別の次元、キレた次元にあって、常人に理解できるような文章が書けないのだ。と判断した。
ところが、アカデミズムの反応と評価はというと、きわめて高く、「ヘーゲルを超えた弁証法」と絶賛された――主として頑迷な右派から。ほかは、権威に飲まれて「沈黙の大絶賛」を贈ったらしい。
この「学派」は、こうして、カントやヘーゲル、フィヒテなどの哲学史の流れを一気に超越して、神棚に祭り上げられてしまった。
「弁証法」という訳語は、その意味では神秘化され、超絶的な呪物崇拝に絡みつかれてしまった。論理的な説明に代わって、宗教的・政治的スローガンのように独り歩きしてしまった。
このことも、この訳語についての、私の違和感の根底にあるかもしれない。
●本筋に話を戻す●
さて、同じようなことは、明治以降、日本の「近代化」のために西欧から輸入・導入して翻訳し、模倣してきた、数多くの「専門用語」にも当てはまります。学術や政治経済、行政、文学などについて。
これらの翻訳語=訳語は、西欧やアメリカの先端的な文明技術や文化、制度を日本でも採用し、模倣し、独特の変容や改良を加えて導入・定着させようとする目的で生み出されたものです。
この輸入=翻訳は、日本のエリートシステムの形成と結びついていました。
こうした西洋の文明や文化、技術・制度について最初に接触し、日本への導入を考えた人たちは、言葉の訳出によって、アカデミズムや官界などで、新進気鋭のエリートとして認められる仕組みができ上がっていったのです。
すると、今度は、学術、行政、経済経営などのエリートは、「輸入学問」や「輸入制度」の紹介・研究の導入の旗振り役を自任するような傾向が、アカデミズムや官界の仕組みにおいて支配的になりました。「欧米コンプレクス」ともいえます。
もちろん、訳出の作業は、頭抜けた知性と大変な努力を必要とするものでした。
ヨーロッパの歴史や思想史に深い造詣をもつだけでなく、訳出のために漢籍・漢学についても該博な知識がなければならなかったのです。
当時、あらゆる世界に通暁した飛び抜けた秀才・碩学たちが、用語の意味や成り立ちなどを考えて、輸入したこの用語にしかるべき漢語熟語の訳を当てはめたのです。それは、大変な労苦だったでしょう。
ところが、こうした訳語がアカデミズムや官界、政界、経済界などで定着普及していき、ゆえにまた権威を得ていくと、あとからこれらの世界のエリートにのし上がってきた人びとは、訳語をすでに与えられた当たり前のもの(所与の用語)として、深い省察もなしに(無批判に)使用することになりました。
訳出時の労苦や苦難、用語の来歴(成り立ちの歴史的文脈)を深く考えることもなく、駆使することになりました。こうして、訳出用語が独り歩きしていくことになりました。
さて、ヨーロッパで成立した専門用語が、漢籍の古典などを参考に翻訳されたため、それらの訳語は、おおむねかなり難解な漢語熟語となりました。訳出作業者の努力の結果でしたが、漢語熟語は難解なものとなりました。そのことで、これらの用語は、一般の人びとのアプローチや評価を遠ざけることになりました。それゆえまた、これらの用語の活用は、特別の訓練=高等教育を受けたエリート=インテリだけに限定されることにもなりました。
それでも、論壇(マスメディア)に頻繁に登場することで、やがて社会に徐々に広がっていきました。
さて、第2次世界戦争後、マスメディアの発達、大学=「高等教育」の大衆化によって、ヨーロッパ生まれの専門用語の日本語訳語は広く社会に浸透し、人口に膾炙するようになります。訳語から始まった専門用語は、ごく少数のエリートの術語(terminology)から、(社会現象を現す)より一般的な言葉になりました。
それとともに、ヨーロッパでのそれらの用語の歴史的な成立の文脈や本来の意味などは、いよいよ、まったく顧みられなくなりました。
そこで、《用語の難解さ》とその《使用の大衆化》とは、まさに「矛盾する」ことになりました。しかし、訳語はすでに確固とした地位と権威を獲得して、いまさら取り換えができそうもない状況です。
ところが、今日、「IT化」が進展する状況のなかで、これまでとはまた一段と違う意味で、文章を正確かつ論理的につくり、思考や認識を組み立てるために、日本の明治以降の「訳語文化」を再検討・再吟味する必要が生じている、と私は見ています。
しかし、再検討や吟味を試みる人びとは、超少数派にとどまるでしょう。
とすれば、この問題を自覚した人たちが、自分が文章を記述するにあたって、こうした用語を吟味し、再規定(定義の仕直し)を試みていくしかなさそうです。
以下では、このような問題を含むと私が考える言葉を列挙し、用語の成り立ちや来歴、訳語の来歴や背景を、わかる範囲で、私見を交えながら、説明します。
( )のなかは、訳語に対応するヨーロッパの原語です。
●国家(state, Staat, d'etat)●
厳密には、これは近代の「国民国家」「主権国家」「中央集権的国家」を意味します。この政治体の属性としては、
・「中央政府」の政治的・行政的・軍事的権力の独占が法的に正統化されていること
・その権力の行使によって維持される「国境システム」の存在(軍事的防衛線の固定化)
・その地理的範囲の内部の住民(の全体または一部)を市民権を保持する「国民(nation)」として組織すること
などが、制度上の条件となります。
私が知る限り、「国家」という漢語は、中国の古典『易経』からの出典です。
『易経』では、国家とは、君主の権力・家産(領地)とその統治組織、その統治権威がおよぶ範囲を意味したようです。ただし、この範囲とは、現在のように「国境で囲まれたひとまとまりの地理的範囲(の住民集団)」を意味するわけではありません。むしろ、王権に臣従する家臣や豪族(部族の長)との臣従=恩顧関係を意味したと考えられます。
このように、中国古典の漢語熟語を、その本来の意味や文脈からまったく切り離して、ヨーロッパ近代の歴史が生み出した用語の訳語に当てはめました。
とはいえ、ヨーロッパでも《state》とか《Staat》という用語は、はじめから「集権的な主権国家」を意味するものではありませんでした。本来は、身分とか地位、身分集団の結集状態(君侯や領主の諮問機関としての身分制評議会)、あるいは君侯や領主の家産=所領・支配地の権限関係を意味しました。その意味では、中国の古典と似た文脈で出現しました。
それが、局地的な領域国家から、周囲の君侯・領主を統合して「絶対王政」の統治レジームを形成し、やがて国民国家へと変遷していくのにともない、言葉の意味内容が転換していきました。
この近代的な現象に当てはめた用語である限り、「国家」は古代の「帝国」や中世の「王権」「領主権」などに当てはめることはできません。
ところが、一般の人びとどころか、専門の「学者たち」のあいだでも、意味と用語法はすっかり混乱しています。
「国家」や「政府」、いわゆる「お国」をめぐる用語は、論理的な明確性を要求される法学・法律学の世界にこそ一番ひどい混乱が見られます。
憲法解釈や行政をめぐる訴訟や裁判では、「国」「国の責任」とかが問題になります。行政府に対して申し立てをおこなう市民の側も「国を訴える」と言い、判決文でも「国は…」などと表記されます。
ところで、ごく曖昧に表記される、この「国」とはいったい何でしょうか。
「国家」ということでしょうか。それとも、内閣を頂点とする「行政府」のことでしょうか。あるいは、「立法府」や「司法府」なども合わせた「中央の国家機構」全体を意味するのでしょうか。または、国家から市民権を付与された住民の集合体としての「国民」でしょうか。
明治以降、敗戦まで、日本では国家権威主義が強すぎたせいしょうか、戦後は、とくに法律家(裁判官も含む)のあいだでは「国家」という用語を使用は敬遠されてきました。それに代わって「国」という曖昧な用語がまかり通ることになりました。
しかし、判決文のなかで権利や義務、責任の主体として「国」というような曖昧な用語を使っているのは、世界のなかで日本くらいではないでしょうか。
曖昧な用語法は、意味内容の曖昧さに導き、立法や政治意思の決定、さらに政治現象の認識や分析において、不明確さや曖昧さを誘導するように見えます。
もとより、欧米にもcountryのような、日本の「お国」に当たるような曖昧かつ情緒的な言葉があります。アメリカの政治家も、選挙戦とか議会の論戦などでは、やたらにcountryというような情緒的な言い方を好むようです。
しかし、法案とか判決や政治学の論文にはまずそんな用語は登場しないでしょう。「国家」や「合州国」「連邦政府」「連合王国」「政府」などと、明確さをともなった(そのように装われた)用語を使うのが通常です。
したがって、欧米の文献の日本語訳で、「国」と表記されているのが「国家」なのか「国民」なのか、「郷土」や「祖国」というような情緒的ないし文化的な存在なのかを、よく吟味しなければ、著者の論旨や意図がきちんと伝わりません。
●国民(はじめはnation, Volk, gens, natioだったが、やがてpeople)●
現在では、現行憲法やマスメディアで、「国民」とは日本の市民一般、住民一般を意味するようになりました。
ところが、本来は、近代国家によって、あるいは国家という形態で、組織された、一定の地理的範囲の住民集合を意味する言葉として訳出されました。
もっと旧い時代、中世後期のヨーロッパでは、gensとかnatioという言葉で、領主貴族や有力聖職者などの身分、あるいは自治権を持つ都市の参事会に結集する富裕市民層身分を意味しました。これらの身分は、有力君侯領主に税や賦課金を納めるのと引き換えに、身分制評議会に身分代表を送り込んで、君侯領主の統治に(事後的な諮問ではあっても)関与できる階層でした。
その意味では、家系や家門とか生まれ育ち、つまり、もって生まれた資産や身分、権威を保有する特権的な人びとを意味しました。生まれとか生得のという語源からつくられた用語で、nativeとかnatureと共通の語源からつくられました。
ところが、王権による集権化と国家形成、絶対王政や市民革命を経て、近代国民国家ができあがっていくのにともない、政治的権利や市民権が「より下層の」住民にも拡大されていきました。
はじめは、ごく少数の特権身分や特権階層を意味していた「国民」は、やがて市民権を認められた一般庶民を含む、国境の内部の住民集団全体を意味する言葉になりました。通常、国民とは、国家をつうじて組織され統合された複数の民族からなる住民集合です。
それにしても、国家という形態で組織された(市民権を付与された)住民集団というのが、国民です。市民1人ひとりとか、市民としての民衆、人民というような意味はありません。集合概念です。
合州国の「国家安全保障会議NSC」は、正確には「国民安全保障会議」ですし、「国際連合the United Nations」も正確には「諸国民の連合体」または「連合した諸国民(連合諸国民)」です。
前者の場合には、国民とは、国民国家であって、国家によって組織された集団、つまりは独立の軍事的単位をなしている集合=組織体です。
後者は、第2次世界戦争中には、日本語訳では「連合国」とされていて、日本を含む「枢軸国」と軍事的に敵対する諸国家の同盟でした。それが、戦勝側の国際組織として戦争後、アメリカの主導下で、世界秩序の調整システムとなりました。同じ組織が、日本語では、軍事的に敵対する「連合国」から「国際連合」にすり替えられてしまいました。
国連の過去の法規で、日本が「敵対国民」となっているのは、そのためです。
日本のマスコミでよく報道される、「国民の議論」は、discussion of the peopleであって、本来は「市民・人びとによる議論」と表記すべきものです。
国民ということになれば、国家のなかで国籍=市民権を付与された人びとの集合ということになります。
現行憲法でも、日本語では「国民の権利・義務」と表記されていますが、英語での原案や憲法の英語版では、peopleとなっています。「国民」と表記すると、そこに「論理のすりかえ」や「誤魔化し」が入り込んできます。
どういうことかというと、
peopleは、法理論上は、論理的には、国家の法制度・手続きによって「日本国籍」やそれにともなう市民権が付与される以前の「人びと」=人民=民衆を意味するのです。したがって、外国からやってきた人びとも含め、国家や行政制度というものを通過する前の「自然人」にも、市民権や人権そして義務を認めるという含意があります。ただのpoepleの権利を、原則上、日本国家(政府と国民)は、日本の領土内では認めないといけないのです。
ところが、実際の制度と憲法解釈(国籍法など)では、そうなっていません。行政府や裁判所は、できるだけ法的・市民権的保護を与える対象を狭く解釈しようとしています。大きな財政支出がともなうからでしょう。
護憲派も改憲派も、ともに、こういう法や人権の基本問題にはまったく目配りしていません。ヨーロッパで生まれて発展してきた法理とその用語法を理解していないからです。法律家のほとんども、そうです。
やはり、言葉の正確な理解、用語法は、きわめて重要な課題です。
●経済(economy, oeco-nomos, Wirtschaft)●
現在では、世界中で「経済」という用語は、物質的・精神的な財物を生産し、流通させ、分配し、消費または生産投入する社会の動きの総体を意味します。
日本では明治期に、ヨーロッパの「エコノミー」「オエコノモス」「ヴィルトシャフト」などの言葉の訳語として、「経済」という語を当てました。
知っている人も多いと思いますが、もともとは、古代中国の古典で「経世済民」ないし「経国済民」という熟語で使用されていました。「経世・経国」とは、君侯(王)や貴族の「領地と家産」=支配圏域を統治・管理することです。「済民」とは、社会の平穏な秩序を保持して、生産活動や文化活動を運営させ、人びとの生活を成り立たせることです。
要するに、権力者が統治をおこなうことです。
ヨーロッパでも、古代から、ほぼ同じ意味で使われていました。
ラテン語の「オエコノモス」は、ギリシャ語の「オイコス」と「ノモス」の合成語です。
オイコスとは、権力者(王や貴族)の家系とか家産や所領、支配地のことであり、彼らの権力や権威がおよぶ区域に生活する人びとや施設、財物などの総体を管理統制することです。ノモスとは、統治の規則とか、法規範や規律、秩序の仕組みとか、運動法則などを意味します。
こうして、オエコノモスないしオエコノミーとは、権力者がその支配圏域を統治管理するという意味になります。
ドイツ語の「ヴィルトシャフト」も、支配者の家産・所領を意味する「ヴィルト」と、規範体系や組織・秩序を意味する「シャフト」との合成語です(ただし、この用語の成立は、17世紀以降と見られる)。
洋の東西で、同じような言葉が古くから成立し、使用されてきたのです。
これが、ヨーロッパでは近代初頭から、しだいに意味が変化していきます。
中世晩期から、有力君侯が、自分の所領や支配地を中心に周囲の領主たちや諸都市の支配圏を統合し、ことに16世紀以降には、君侯たちは集権化を進めて領域国家をつくり、やがてそのなかから、将来の国民国家につながる強力な王権国家が出現していきます。
その時代には、支配集団や専門家のあいだでは、「エコノミー」が単独で使われるよりも、「ポリティカル・エコノミー」つまり、「政治的経済(学)」として使われる場合が多かったのです。領土の内部の社会全体(経済も政治もひっくるめて)の統治、政治的支配、行政管理、財政運営――そして、それを研究する学術――を意味する場合が多かったようです。
そのうち、この用語は、王権国家によって「上から」統治されている《「市民社会」の秩序や運営》を主として意味するようになっていきます。その当時、社会の経済活動、商業や製造業は、法制度上は、税や賦課金の支払いと引き換えに、王権政府から付与された身分または団体の特権として許可され運営されていました。
それが、18世紀半ばから、とりわけイングランドでは、世界貿易や金融などの分野を除いて、しだいに(納税の義務は相変わらず負うのですが)王権の規制や介入から切り離され、自由かつ自立的に運営されるようになっていきます。
ただし、世界貿易や金融の分野は、政府との強い癒着や連携をともなう身分的=団体的特権による障壁で取り囲まれていました。
しかし、そこに、あたかも王権国家の介入から自立的に運営されるべき「市民社会」の固有の秩序や運営法則があるかのように想定し、それらを理想化し、観念する用語になる素地が生まれました。純然たるエコノミーのカテゴライズです。
19世紀には、「政治的」という形容詞から切り離されて、市民社会の生産活動や流通・分配・消費活動の体系やその組織形態、運動法則などを意味する語となっていったようです。
そして、いつのまにやら、「政治」と「経済」は理論上、分離される社会現象となってしまいました。
しかし、双方とも権力闘争、力の強弱、支配者による影響力の組織化などがともなう現象です。
ともかく、日本に輸入される頃には、ほぼ現在の意味用法になっていました。
これに、社会科学の方法論として政治と経済との分離・形態区分を際立たせるようになったのが、やはり「輸入された」マルクシズムです。「経済的土台(下部構造)」と「政治的・イデオロギー的上部構造」という区分、そして「経済による政治の究極的な規定性」という方法論が、単純化されて普及してしまいました。
左右の政派を問わず、単純化された「経済決定論」がまかり通るようになりました。
そして、最近では「市場原理主義」とか「マニーゲイム優越論」が幅を利かせています。これも、俗物化した「経済決定論」の亜流かもしれません。
●形而上学(metaphysic, Metaphysik)●
哲学を学んだことがある人は、一度は、この難解で一見意味不明な用語に出会ったことがあるでしょう。
メタフィジークとは、古代ギリシャの古典哲学を集約したアリストテレスの方法論と体系化による学術分野(諸科学)の区分にもとづいています。
アリストテレスは、ひとまず具体的な形態(形状)を備えた、自然界の諸現象(人体、生物、天体、地球、水や岩石など)を理論的に説明したのちに、こうした自然現象=具体的な形態の背後にある根源的なあるいは高次の原理や法則性を説明する章を設けました。
つまり、自然学(フィジーク)の「あとに(メタ)」説かれた学という意味で、「メタフィジーク」と名づけられました。これは、古代ローマに引き継がれ、やがてローマ帝国の宗教となったキリスト教の神学や哲学的研究の方法の原理になりました。
つまりは、具体的な形状=形態性をもつ、それゆえ経験的に知覚できる事象の背後、根底にある、より高次の原理や法則性、あるいは「理念(イメイジ、価値や価値観)」「理想=観念」を扱う学問が、メタフィジークです。
五感や経験によって知覚・認識できない存在ですから、「直観(直接的観照)」とか「純粋理性」による抽象的な思考(思弁)によってはじめて把握されるしかないものとされました。
これが、明治期の日本では「形而上学」と訳出されました。
この時代の碩学たちが参考にしたのは、これまた古代中国の古典中の古典、「周易」とこれを孔子が(陰陽二元論を基礎に)体系化した「易経」でした。
易経では、やはり具体的な形状・外形をともなわない存在とか理念・価値観などを、「形而上」のものと認識しました。つまり、形から見るとそれを超えた次元=上にあるもの、というほどの意味でしょう。これに対して、具体的形状をともなう存在を「形而下」なるものと定義づけました。
ここでも、ヨーロッパの古代と中国の古代の思考方法というか認識論が照応するのです。やはり、人間の認識は、同じような展開経過、構造をもつのでしょうか。
しかし、メタフィジークが形而上学では、何やら意味深遠すぎて、私たちには理解できそうもない用語になってしまいました。
文章は言葉の連鎖からなります。けれども、「言葉」を使いこなすのは難しいものです。
言葉の意味と活用法を理解しなければならないからです。用語の意味は、辞典や辞書に書いてあるものだけで理解できるとは限りません。
前回、私は、哲学の用語Dialektikを「弁証法」ではなく、「対論法」と訳した方がよいと述べました。現代人にとっては、弁証法という難しい漢語よりも、対論方の方がずっとわかりやすいと判断したからです。
「弁」という漢字には、「反論する」「論駁する」という意味がありますが、「弁証」という語に「敵対的・対立的な言説・論証」という意味があることを知るためには、かなりの調査や検索を必要とします。
それに、この訳のわからない用語には、呪物的な神秘性、理性的な考証や分析を拒否してきた、哲学アカデミズムの悪弊が絡みついています。
●「弁証法」に関するエピソード●
そのむかし、京都にあったさる帝国大学の超がつくほど高名かつ「偉大な」(と哲学界では信じられていた)大教授が、「弁証法」の観念論的解釈を展開した。その論のなかで、「絶対的矛盾の自己同一」という呪文のようなテーゼ(いや大向こうを狙ったキャッチコピーというべきか)を提示した。
矛盾というのは、2つ(以上)の事象のあいだの関係性(つまりは相対的なもの)をいう用語なのに、「絶対的」と形容した。あるいは、相手を完全に排斥するほどの敵対性をもつ事象をいうのか。そのうえ、その絶対的矛盾をして、「自己同一性」のうちにあるもの、と規定した。
いや、この「絶対的」というのは、この矛盾関係にある2つの存在(属性)が、そのほかのあらゆる事象から切り離されて独立し、1個の揺るぎない全体を形づくっているということなのか。だとすれば、外観上は自立自存するかに見える事象を体系性や総体性のなかに位置づけて認識する、「弁証法」の方法論とは相容れないものとなる。
わたしは、この大先生の所論がちっとも理解できない。
ヘーゲルについては理解できたが、この大教授の理論はさっぱりわからない。
で、私のホンネは、「おうおう、ご大層なキャッチフレイズでご苦労さん。でも、アホか!」だった。この大先生は、思考回路が一般人と別の次元、キレた次元にあって、常人に理解できるような文章が書けないのだ。と判断した。
ところが、アカデミズムの反応と評価はというと、きわめて高く、「ヘーゲルを超えた弁証法」と絶賛された――主として頑迷な右派から。ほかは、権威に飲まれて「沈黙の大絶賛」を贈ったらしい。
この「学派」は、こうして、カントやヘーゲル、フィヒテなどの哲学史の流れを一気に超越して、神棚に祭り上げられてしまった。
「弁証法」という訳語は、その意味では神秘化され、超絶的な呪物崇拝に絡みつかれてしまった。論理的な説明に代わって、宗教的・政治的スローガンのように独り歩きしてしまった。
このことも、この訳語についての、私の違和感の根底にあるかもしれない。
●本筋に話を戻す●
さて、同じようなことは、明治以降、日本の「近代化」のために西欧から輸入・導入して翻訳し、模倣してきた、数多くの「専門用語」にも当てはまります。学術や政治経済、行政、文学などについて。
これらの翻訳語=訳語は、西欧やアメリカの先端的な文明技術や文化、制度を日本でも採用し、模倣し、独特の変容や改良を加えて導入・定着させようとする目的で生み出されたものです。
この輸入=翻訳は、日本のエリートシステムの形成と結びついていました。
こうした西洋の文明や文化、技術・制度について最初に接触し、日本への導入を考えた人たちは、言葉の訳出によって、アカデミズムや官界などで、新進気鋭のエリートとして認められる仕組みができ上がっていったのです。
すると、今度は、学術、行政、経済経営などのエリートは、「輸入学問」や「輸入制度」の紹介・研究の導入の旗振り役を自任するような傾向が、アカデミズムや官界の仕組みにおいて支配的になりました。「欧米コンプレクス」ともいえます。
もちろん、訳出の作業は、頭抜けた知性と大変な努力を必要とするものでした。
ヨーロッパの歴史や思想史に深い造詣をもつだけでなく、訳出のために漢籍・漢学についても該博な知識がなければならなかったのです。
当時、あらゆる世界に通暁した飛び抜けた秀才・碩学たちが、用語の意味や成り立ちなどを考えて、輸入したこの用語にしかるべき漢語熟語の訳を当てはめたのです。それは、大変な労苦だったでしょう。
ところが、こうした訳語がアカデミズムや官界、政界、経済界などで定着普及していき、ゆえにまた権威を得ていくと、あとからこれらの世界のエリートにのし上がってきた人びとは、訳語をすでに与えられた当たり前のもの(所与の用語)として、深い省察もなしに(無批判に)使用することになりました。
訳出時の労苦や苦難、用語の来歴(成り立ちの歴史的文脈)を深く考えることもなく、駆使することになりました。こうして、訳出用語が独り歩きしていくことになりました。
さて、ヨーロッパで成立した専門用語が、漢籍の古典などを参考に翻訳されたため、それらの訳語は、おおむねかなり難解な漢語熟語となりました。訳出作業者の努力の結果でしたが、漢語熟語は難解なものとなりました。そのことで、これらの用語は、一般の人びとのアプローチや評価を遠ざけることになりました。それゆえまた、これらの用語の活用は、特別の訓練=高等教育を受けたエリート=インテリだけに限定されることにもなりました。
それでも、論壇(マスメディア)に頻繁に登場することで、やがて社会に徐々に広がっていきました。
さて、第2次世界戦争後、マスメディアの発達、大学=「高等教育」の大衆化によって、ヨーロッパ生まれの専門用語の日本語訳語は広く社会に浸透し、人口に膾炙するようになります。訳語から始まった専門用語は、ごく少数のエリートの術語(terminology)から、(社会現象を現す)より一般的な言葉になりました。
それとともに、ヨーロッパでのそれらの用語の歴史的な成立の文脈や本来の意味などは、いよいよ、まったく顧みられなくなりました。
そこで、《用語の難解さ》とその《使用の大衆化》とは、まさに「矛盾する」ことになりました。しかし、訳語はすでに確固とした地位と権威を獲得して、いまさら取り換えができそうもない状況です。
ところが、今日、「IT化」が進展する状況のなかで、これまでとはまた一段と違う意味で、文章を正確かつ論理的につくり、思考や認識を組み立てるために、日本の明治以降の「訳語文化」を再検討・再吟味する必要が生じている、と私は見ています。
しかし、再検討や吟味を試みる人びとは、超少数派にとどまるでしょう。
とすれば、この問題を自覚した人たちが、自分が文章を記述するにあたって、こうした用語を吟味し、再規定(定義の仕直し)を試みていくしかなさそうです。
以下では、このような問題を含むと私が考える言葉を列挙し、用語の成り立ちや来歴、訳語の来歴や背景を、わかる範囲で、私見を交えながら、説明します。
( )のなかは、訳語に対応するヨーロッパの原語です。
●国家(state, Staat, d'etat)●
厳密には、これは近代の「国民国家」「主権国家」「中央集権的国家」を意味します。この政治体の属性としては、
・「中央政府」の政治的・行政的・軍事的権力の独占が法的に正統化されていること
・その権力の行使によって維持される「国境システム」の存在(軍事的防衛線の固定化)
・その地理的範囲の内部の住民(の全体または一部)を市民権を保持する「国民(nation)」として組織すること
などが、制度上の条件となります。
私が知る限り、「国家」という漢語は、中国の古典『易経』からの出典です。
『易経』では、国家とは、君主の権力・家産(領地)とその統治組織、その統治権威がおよぶ範囲を意味したようです。ただし、この範囲とは、現在のように「国境で囲まれたひとまとまりの地理的範囲(の住民集団)」を意味するわけではありません。むしろ、王権に臣従する家臣や豪族(部族の長)との臣従=恩顧関係を意味したと考えられます。
このように、中国古典の漢語熟語を、その本来の意味や文脈からまったく切り離して、ヨーロッパ近代の歴史が生み出した用語の訳語に当てはめました。
とはいえ、ヨーロッパでも《state》とか《Staat》という用語は、はじめから「集権的な主権国家」を意味するものではありませんでした。本来は、身分とか地位、身分集団の結集状態(君侯や領主の諮問機関としての身分制評議会)、あるいは君侯や領主の家産=所領・支配地の権限関係を意味しました。その意味では、中国の古典と似た文脈で出現しました。
それが、局地的な領域国家から、周囲の君侯・領主を統合して「絶対王政」の統治レジームを形成し、やがて国民国家へと変遷していくのにともない、言葉の意味内容が転換していきました。
この近代的な現象に当てはめた用語である限り、「国家」は古代の「帝国」や中世の「王権」「領主権」などに当てはめることはできません。
ところが、一般の人びとどころか、専門の「学者たち」のあいだでも、意味と用語法はすっかり混乱しています。
「国家」や「政府」、いわゆる「お国」をめぐる用語は、論理的な明確性を要求される法学・法律学の世界にこそ一番ひどい混乱が見られます。
憲法解釈や行政をめぐる訴訟や裁判では、「国」「国の責任」とかが問題になります。行政府に対して申し立てをおこなう市民の側も「国を訴える」と言い、判決文でも「国は…」などと表記されます。
ところで、ごく曖昧に表記される、この「国」とはいったい何でしょうか。
「国家」ということでしょうか。それとも、内閣を頂点とする「行政府」のことでしょうか。あるいは、「立法府」や「司法府」なども合わせた「中央の国家機構」全体を意味するのでしょうか。または、国家から市民権を付与された住民の集合体としての「国民」でしょうか。
明治以降、敗戦まで、日本では国家権威主義が強すぎたせいしょうか、戦後は、とくに法律家(裁判官も含む)のあいだでは「国家」という用語を使用は敬遠されてきました。それに代わって「国」という曖昧な用語がまかり通ることになりました。
しかし、判決文のなかで権利や義務、責任の主体として「国」というような曖昧な用語を使っているのは、世界のなかで日本くらいではないでしょうか。
曖昧な用語法は、意味内容の曖昧さに導き、立法や政治意思の決定、さらに政治現象の認識や分析において、不明確さや曖昧さを誘導するように見えます。
もとより、欧米にもcountryのような、日本の「お国」に当たるような曖昧かつ情緒的な言葉があります。アメリカの政治家も、選挙戦とか議会の論戦などでは、やたらにcountryというような情緒的な言い方を好むようです。
しかし、法案とか判決や政治学の論文にはまずそんな用語は登場しないでしょう。「国家」や「合州国」「連邦政府」「連合王国」「政府」などと、明確さをともなった(そのように装われた)用語を使うのが通常です。
したがって、欧米の文献の日本語訳で、「国」と表記されているのが「国家」なのか「国民」なのか、「郷土」や「祖国」というような情緒的ないし文化的な存在なのかを、よく吟味しなければ、著者の論旨や意図がきちんと伝わりません。
●国民(はじめはnation, Volk, gens, natioだったが、やがてpeople)●
現在では、現行憲法やマスメディアで、「国民」とは日本の市民一般、住民一般を意味するようになりました。
ところが、本来は、近代国家によって、あるいは国家という形態で、組織された、一定の地理的範囲の住民集合を意味する言葉として訳出されました。
もっと旧い時代、中世後期のヨーロッパでは、gensとかnatioという言葉で、領主貴族や有力聖職者などの身分、あるいは自治権を持つ都市の参事会に結集する富裕市民層身分を意味しました。これらの身分は、有力君侯領主に税や賦課金を納めるのと引き換えに、身分制評議会に身分代表を送り込んで、君侯領主の統治に(事後的な諮問ではあっても)関与できる階層でした。
その意味では、家系や家門とか生まれ育ち、つまり、もって生まれた資産や身分、権威を保有する特権的な人びとを意味しました。生まれとか生得のという語源からつくられた用語で、nativeとかnatureと共通の語源からつくられました。
ところが、王権による集権化と国家形成、絶対王政や市民革命を経て、近代国民国家ができあがっていくのにともない、政治的権利や市民権が「より下層の」住民にも拡大されていきました。
はじめは、ごく少数の特権身分や特権階層を意味していた「国民」は、やがて市民権を認められた一般庶民を含む、国境の内部の住民集団全体を意味する言葉になりました。通常、国民とは、国家をつうじて組織され統合された複数の民族からなる住民集合です。
それにしても、国家という形態で組織された(市民権を付与された)住民集団というのが、国民です。市民1人ひとりとか、市民としての民衆、人民というような意味はありません。集合概念です。
合州国の「国家安全保障会議NSC」は、正確には「国民安全保障会議」ですし、「国際連合the United Nations」も正確には「諸国民の連合体」または「連合した諸国民(連合諸国民)」です。
前者の場合には、国民とは、国民国家であって、国家によって組織された集団、つまりは独立の軍事的単位をなしている集合=組織体です。
後者は、第2次世界戦争中には、日本語訳では「連合国」とされていて、日本を含む「枢軸国」と軍事的に敵対する諸国家の同盟でした。それが、戦勝側の国際組織として戦争後、アメリカの主導下で、世界秩序の調整システムとなりました。同じ組織が、日本語では、軍事的に敵対する「連合国」から「国際連合」にすり替えられてしまいました。
国連の過去の法規で、日本が「敵対国民」となっているのは、そのためです。
日本のマスコミでよく報道される、「国民の議論」は、discussion of the peopleであって、本来は「市民・人びとによる議論」と表記すべきものです。
国民ということになれば、国家のなかで国籍=市民権を付与された人びとの集合ということになります。
現行憲法でも、日本語では「国民の権利・義務」と表記されていますが、英語での原案や憲法の英語版では、peopleとなっています。「国民」と表記すると、そこに「論理のすりかえ」や「誤魔化し」が入り込んできます。
どういうことかというと、
peopleは、法理論上は、論理的には、国家の法制度・手続きによって「日本国籍」やそれにともなう市民権が付与される以前の「人びと」=人民=民衆を意味するのです。したがって、外国からやってきた人びとも含め、国家や行政制度というものを通過する前の「自然人」にも、市民権や人権そして義務を認めるという含意があります。ただのpoepleの権利を、原則上、日本国家(政府と国民)は、日本の領土内では認めないといけないのです。
ところが、実際の制度と憲法解釈(国籍法など)では、そうなっていません。行政府や裁判所は、できるだけ法的・市民権的保護を与える対象を狭く解釈しようとしています。大きな財政支出がともなうからでしょう。
護憲派も改憲派も、ともに、こういう法や人権の基本問題にはまったく目配りしていません。ヨーロッパで生まれて発展してきた法理とその用語法を理解していないからです。法律家のほとんども、そうです。
やはり、言葉の正確な理解、用語法は、きわめて重要な課題です。
●経済(economy, oeco-nomos, Wirtschaft)●
現在では、世界中で「経済」という用語は、物質的・精神的な財物を生産し、流通させ、分配し、消費または生産投入する社会の動きの総体を意味します。
日本では明治期に、ヨーロッパの「エコノミー」「オエコノモス」「ヴィルトシャフト」などの言葉の訳語として、「経済」という語を当てました。
知っている人も多いと思いますが、もともとは、古代中国の古典で「経世済民」ないし「経国済民」という熟語で使用されていました。「経世・経国」とは、君侯(王)や貴族の「領地と家産」=支配圏域を統治・管理することです。「済民」とは、社会の平穏な秩序を保持して、生産活動や文化活動を運営させ、人びとの生活を成り立たせることです。
要するに、権力者が統治をおこなうことです。
ヨーロッパでも、古代から、ほぼ同じ意味で使われていました。
ラテン語の「オエコノモス」は、ギリシャ語の「オイコス」と「ノモス」の合成語です。
オイコスとは、権力者(王や貴族)の家系とか家産や所領、支配地のことであり、彼らの権力や権威がおよぶ区域に生活する人びとや施設、財物などの総体を管理統制することです。ノモスとは、統治の規則とか、法規範や規律、秩序の仕組みとか、運動法則などを意味します。
こうして、オエコノモスないしオエコノミーとは、権力者がその支配圏域を統治管理するという意味になります。
ドイツ語の「ヴィルトシャフト」も、支配者の家産・所領を意味する「ヴィルト」と、規範体系や組織・秩序を意味する「シャフト」との合成語です(ただし、この用語の成立は、17世紀以降と見られる)。
洋の東西で、同じような言葉が古くから成立し、使用されてきたのです。
これが、ヨーロッパでは近代初頭から、しだいに意味が変化していきます。
中世晩期から、有力君侯が、自分の所領や支配地を中心に周囲の領主たちや諸都市の支配圏を統合し、ことに16世紀以降には、君侯たちは集権化を進めて領域国家をつくり、やがてそのなかから、将来の国民国家につながる強力な王権国家が出現していきます。
その時代には、支配集団や専門家のあいだでは、「エコノミー」が単独で使われるよりも、「ポリティカル・エコノミー」つまり、「政治的経済(学)」として使われる場合が多かったのです。領土の内部の社会全体(経済も政治もひっくるめて)の統治、政治的支配、行政管理、財政運営――そして、それを研究する学術――を意味する場合が多かったようです。
そのうち、この用語は、王権国家によって「上から」統治されている《「市民社会」の秩序や運営》を主として意味するようになっていきます。その当時、社会の経済活動、商業や製造業は、法制度上は、税や賦課金の支払いと引き換えに、王権政府から付与された身分または団体の特権として許可され運営されていました。
それが、18世紀半ばから、とりわけイングランドでは、世界貿易や金融などの分野を除いて、しだいに(納税の義務は相変わらず負うのですが)王権の規制や介入から切り離され、自由かつ自立的に運営されるようになっていきます。
ただし、世界貿易や金融の分野は、政府との強い癒着や連携をともなう身分的=団体的特権による障壁で取り囲まれていました。
しかし、そこに、あたかも王権国家の介入から自立的に運営されるべき「市民社会」の固有の秩序や運営法則があるかのように想定し、それらを理想化し、観念する用語になる素地が生まれました。純然たるエコノミーのカテゴライズです。
19世紀には、「政治的」という形容詞から切り離されて、市民社会の生産活動や流通・分配・消費活動の体系やその組織形態、運動法則などを意味する語となっていったようです。
そして、いつのまにやら、「政治」と「経済」は理論上、分離される社会現象となってしまいました。
しかし、双方とも権力闘争、力の強弱、支配者による影響力の組織化などがともなう現象です。
ともかく、日本に輸入される頃には、ほぼ現在の意味用法になっていました。
これに、社会科学の方法論として政治と経済との分離・形態区分を際立たせるようになったのが、やはり「輸入された」マルクシズムです。「経済的土台(下部構造)」と「政治的・イデオロギー的上部構造」という区分、そして「経済による政治の究極的な規定性」という方法論が、単純化されて普及してしまいました。
左右の政派を問わず、単純化された「経済決定論」がまかり通るようになりました。
そして、最近では「市場原理主義」とか「マニーゲイム優越論」が幅を利かせています。これも、俗物化した「経済決定論」の亜流かもしれません。
●形而上学(metaphysic, Metaphysik)●
哲学を学んだことがある人は、一度は、この難解で一見意味不明な用語に出会ったことがあるでしょう。
メタフィジークとは、古代ギリシャの古典哲学を集約したアリストテレスの方法論と体系化による学術分野(諸科学)の区分にもとづいています。
アリストテレスは、ひとまず具体的な形態(形状)を備えた、自然界の諸現象(人体、生物、天体、地球、水や岩石など)を理論的に説明したのちに、こうした自然現象=具体的な形態の背後にある根源的なあるいは高次の原理や法則性を説明する章を設けました。
つまり、自然学(フィジーク)の「あとに(メタ)」説かれた学という意味で、「メタフィジーク」と名づけられました。これは、古代ローマに引き継がれ、やがてローマ帝国の宗教となったキリスト教の神学や哲学的研究の方法の原理になりました。
つまりは、具体的な形状=形態性をもつ、それゆえ経験的に知覚できる事象の背後、根底にある、より高次の原理や法則性、あるいは「理念(イメイジ、価値や価値観)」「理想=観念」を扱う学問が、メタフィジークです。
五感や経験によって知覚・認識できない存在ですから、「直観(直接的観照)」とか「純粋理性」による抽象的な思考(思弁)によってはじめて把握されるしかないものとされました。
これが、明治期の日本では「形而上学」と訳出されました。
この時代の碩学たちが参考にしたのは、これまた古代中国の古典中の古典、「周易」とこれを孔子が(陰陽二元論を基礎に)体系化した「易経」でした。
易経では、やはり具体的な形状・外形をともなわない存在とか理念・価値観などを、「形而上」のものと認識しました。つまり、形から見るとそれを超えた次元=上にあるもの、というほどの意味でしょう。これに対して、具体的形状をともなう存在を「形而下」なるものと定義づけました。
ここでも、ヨーロッパの古代と中国の古代の思考方法というか認識論が照応するのです。やはり、人間の認識は、同じような展開経過、構造をもつのでしょうか。
しかし、メタフィジークが形而上学では、何やら意味深遠すぎて、私たちには理解できそうもない用語になってしまいました。