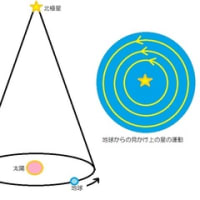7 レーオポルト大公の破滅
クーデタ計画の日の朝、ヴァルターは大公の指示にしたがって大公の城館を訪れた。だが、クーデタに参加するためではなかった。皇帝の追い落とし策謀をやめて、権力の世界から引退するよう勧告するためだった。そして、ゾーフィー殺害事件の逃れようのない容疑がかけられていることも知らせるつもりだった。
ヴァルターを見たレーオポルトは、出発の準備をしろと命じた。だが、ヴァルターは拒否して、クーデタの策謀はすでに皇帝の手許に報告が届いていて、今や大公逮捕をめざす憲兵隊がそこに向かっていることを告げた。
すると、大公は「愚か者め、現皇帝の放漫財政と気まぐれな統治政策によって帝国は崩壊の淵にあるんだぞ。それを、あの幻影師の術策にはまって私の容疑をかけ、しかもクーデタの計画を漏らすとは」と叫んで、銃を自分の頭部に向けて発射し自殺した。
殺人事件とクーデタ未遂事件は決着した。
ヴァルターの気がかりは、アイゼンハイムの幻影術の仕かけ=カラクリを解明することだった。
幻影術の仕組みを考えながら街を歩いていたヴァルターのもとに1人の少年がやってきて、封書を渡した。
封筒を開けると、なかにはアイゼンハイムの幻影術の仕かけの設計図・構想図案を収録した小冊子が入っていた。レモンの種を植えると、またたくまに発芽し、数分のうちに葉と茎が成長して樹木になり、花が咲き、果実が実るという、あのイリュージョンのカラクリの説明も書かれていた。
しばし、アイゼンハイムの幻影術のカラクリがわかって喜んだヴァルターだったが、ふとわれに返った。
少年は「あなたにこの封筒を手渡すようにある紳士から頼まれた」と言い置いて、走り去っていった。ということは、アイゼンハイムがヴァルターの居場所を知っていて、しかも「幻影術のカラクリを知りたい」と思っていることを知り抜いているということだ。
「私の心は、アイゼンハイムによってすっかり読まれている」
ヴァルターははっと気づいた。
「私はアイゼンハイムによってすっかり操られていたのだ。
レーオポルト大公に殺人容疑をかけ、クーデタの企てを皇帝に報告して大公を破滅に追い込むことも、彼によって仕組まれたことに違いない」
すると、ヴァルターの脳裏に、アイゼンハイムと出会ってからのできごとがフラッシュバックして記憶によみがえった。そして、1つの文脈に結びつけられた。
彼は幻影術を使って、ゾーフィーを仮死状態にしておいて、あたかも剣でのどを切られて殺されたかのように見せかけ、その容疑を大公に向けるように仕組んだのだ。
脳裏で目まぐるしく推理しながら、ヴァルターは駅に向かって走っていた。
「私を操っておいて、アイゼンハイムは鉄道に乗って逃げ去ろうとしている」
何とか捕まえようとしたのかもしれない。だが、間に合わなかった。というよりも、おそらく変装しているアイゼンハイムを見分けることはできなかっただろう。
ふたたび映像はカット=フラッシュバックとなる。
ヴィーンから逃げ去ったアイゼンハイムが、じつは生存しているゾーフィーが待っているオーストリアの山岳のなかにあるログハウスに到着し、ゾーフィーを抱擁する場面。これは、消え去ったアイゼンハイムとゾーフィーのその後の姿であり、また、ヴァルターの想像でもある。
しかし、ヴァルターは、利用されてレーオポルトを死に追いやったことを後悔しなかった。それどころか、「おいアイゼンハイム、みごとにやってのけたな!」と祝福したい気分だった。警視の顔には、微苦笑が広がった。
■共同主観というイリュージョンの上に成り立つ権力■
この映像物語では、有力な皇太子の1人であるレーオポルトの地位が、幻影(によって操られた警視の行動)によって脆くも崩壊してしまうという文脈が事件の中心にある。また、アイゼンハイムの幻影術は、ヴィーンの多数の民衆(大衆)の思考や感情、意識に大きく影響して、場合によっては政治的に扇動する影響力すら持ちうるということを暗示している。
少なくとも、ヴィーン市井人=庶民に対してならば、皇帝や皇太子の権威よりも、見世物にすぎないアイゼンハイムの幻影の方が、はるかに影響力が強いという状況があるということだ。
ヴィジョン(幻影という意味を持つ)や幻想が、社会のレジームを組み換え、世界戦争すら引き起こしてきた歴史(たとえばフランス革命、ナチズムの席巻とかロシア革命などの歴史的事件を見よ)を、私たちは身にしみて知っている。
日本でも「大東亜共栄圏」の幻影が破滅的な戦争への道をイデオロギー的に用意した。
また、このブログのほかの記事で見たとおり、諸国家の正史(正当な歴史記述)が、統治者のそのときどきの政治的利害や目論見によって制約されながら形成され、構成されてきた歴史観=イデオロギーであって、多分に一面的で偏見に満ちているものであることも、当たり前のことだ。
ということは、レジームや権力構造というものは、いやそういうものの正当性=正統性というのは、イリュージョンの上に成り立っていることを意味するとも言える。
要するに、権力や支配とは関係性の独特の構造(形態)のことであって、
・権力者=支配者側の意識や発想には、人民が自らに従うものが当然だ、従うべきだという主観がインプリントされ、構造化されている
・人民・民衆の側では、支配者にはなびいておくのが当然、従うべきだという主観が構造化されている
という関係性が成り立っている状態にすぎない。
したがって、社会状況が変化すれば、この「べきだ」「当然だ」という意識=価値観(価値選択とか行動スタイル)がすっかり変わってしまう。
たとえば、先頃の一連の「アラブの春」のできごとを見よ。
権力者=支配者の側では、あまり変化はないのだが、民衆の側では権力者が打撃を与えて破壊すべき敵対者と位置づけられることさえ起きるのだ。
だが、旧来のレジームを打倒したのちに、どういう新たなレジームを構築すべきかについてまでは、革命運動の最中には、なかなか目が向かない。
してみれば、レジームそのものもイリュージョンの上に成り立っているのだが、それを打倒する革命思想もまたイリュージョンから成り立っていることにもなる。
■イリュージョンとしての歴史観■
私たちの歴史に関する視点や方法もまた、ある意味でイリュージョン(ヴィジョン:幻影)だ。どれほど科学性、客観性を標榜しようとも。
というのも、どのような方法・立場であれ、私たちの歴史認識は現実の歴史過程の膨大な事実や要素のなかから、特定の少数の事実や要素を抽出してきて、それらのあいだの結びつき(因果関係や「必然性」「蓋然性」)を分析するしかないからだ。
その意味では、はじめに事柄=事実があるのではなく、むしろ、生まれてから社会のなかで育ってきた過程(譬えば公教育制度)で身につけた視座や価値観に沿って、私たちは歴史を眺めることになるからだ。私たちの精神・意識は、社会的=イデオロギー的な存在拘束を受けていて、社会を自分なりに理解しようとする年頃には、すでに既成観念や固定観念、先入観などからでき上がったフィルターを通してしか、歴史や外界を眺められないからだ。
その傾向は、とりわけ社会科学系、歴史学系のアカデミズムに著しい。というよりも、マルクスが言うように、社会科学や歴史学はそれぞれの立場によるイデオロギーのあいだの闘争なのだ。そうなることの理由=原因が、マルクスが説明するようなものではないにしても、論理化された思想・観念のあいだの争いであることは間違いない。
なかでも、明治以降にヨーロッパやアメリカから学問を輸入して近代化を推進した日本のアカデミズムには、欧米の学説や方法を「額面通りに」受け取ってしまう、それゆえ、阿呆のような「欧米崇拝」の(というよりも権威づけの基準を欧米の学説におきたがる)傾向が強かったようだ。
私の経験で一番ひどいと思ったのは、「市民革命」とか「市民社会」に関する理論史だ。もっとも、この頃では最近の実証史的研究による批判を受けてかなり治ってきているが。
市民革命が中世ないし「封建制」から近代ないし「資本主義」への転換期(転換点)であるという幻想が、左右の陣営を問わず、40年ほど前には支配的立場として堂々とまかり通っていた。
私がこのブログのいくつかの記事で説明したように、資本主義的生産様式への転換は、1000年前から始まっていたし、革命期に権力の争奪戦を繰り広げたのは、本質的に同じ諸階級(貴族と商業資本)のなかの2つのグループだった。したがって、革命の前後で統治構造=レジームは変わったが、社会の基本構造は変わらずに持続し、徐々に変容が進んでいった。
ところが、革命後に権力を掌握したフラクション(分派)は、自らが支配するようになった新たな段階(秩序)こそ、これまでの人類史のなかで最高に発展した社会状況であると宣言し、過去の歴史をそこに必然的にいたるべき諸段階として位置づけた=価値づけたのだった。
日本では、明治期の文明開化を正統化したいあまりに、江戸期以前をことさら貶める歴史評価が、左右両陣営によってまことしやかに撒き散らされた。日本は「低位後発」の劣った社会だと、単に卑下する卑屈な歴史観がまかり通っていた。
明治政府側=右翼は、江戸期をことさらに「遅れた社会」(その反照として、明治期の進歩は素晴らしい!)として描こうとした、その思想は公教育の歴史に強引に持ち込まれた。
で、他方で左翼は、日本はブリテンやフランスのような「市民革命」を経ていないから、まともな「産業資本主義」は形成されなかった、と主張した。
いずれにしろ、イリュージョンがアカデミズムに蔓延してきた。
革命のユートピア(理想論:イデアリズム)は、革命後には秩序を正統化し神聖化する虚偽意識としてのイデオロギーになったというのは、カール・マンハイムが指摘したとおりだ。
その同じ方法論=発展段階論を、マルクスたちはそっくりそのまま継承して、未来の理想社会(コミュニズム)を描いたのだ。
そして、マルクスたちが想定した文脈とはおよそすっかりかけ離れた状況で発生したロシア革命後に、ソヴィエト権力は、マルクスの方法を利用して、革命を社会構造(生産様式)の構造転換の過程とする「方法論の鋳型」をつくり出した。過去の歴史をその鋳型のなかに強引に流し込んでいった。
その陣営が「正統派マルクシズム」を標榜したことから、その後恐るべき混乱と紛糾が出来した。「社会科学」の論争が、正統派と異端派との宗派争い、宗祖の片言隻句を呪物崇拝する非歴史主義・アナクロニズムへと変貌したのだ。
レジームを批判して変革を求める側が、そのような虚偽意識にまみれた理論を基礎にしたのだから、まともな変革の展望を描けるはずもなかった。私は、そのような「失われた世代」に属する。
今だって、「市場幻想」の崇拝者とか「自由化幻想」の崇拝者たちが、市場の暴力に圧迫されて呻吟する人びとの苦難を無視して、偉そうに高説を垂れているではないか。
いずれも、幻想と幻滅の博物館に陳列されることになるのかもしれないが。
しょせん、(歴史観というのはきわめて重要なものだが)現実の歴史というとらえようのない厖大な事象の、一部分を、多かれ少なかれ屈折したフィルター・レンズを通して写し出した、ごく大雑把なシミュレイションでしかないのだ。
クーデタ計画の日の朝、ヴァルターは大公の指示にしたがって大公の城館を訪れた。だが、クーデタに参加するためではなかった。皇帝の追い落とし策謀をやめて、権力の世界から引退するよう勧告するためだった。そして、ゾーフィー殺害事件の逃れようのない容疑がかけられていることも知らせるつもりだった。
ヴァルターを見たレーオポルトは、出発の準備をしろと命じた。だが、ヴァルターは拒否して、クーデタの策謀はすでに皇帝の手許に報告が届いていて、今や大公逮捕をめざす憲兵隊がそこに向かっていることを告げた。
すると、大公は「愚か者め、現皇帝の放漫財政と気まぐれな統治政策によって帝国は崩壊の淵にあるんだぞ。それを、あの幻影師の術策にはまって私の容疑をかけ、しかもクーデタの計画を漏らすとは」と叫んで、銃を自分の頭部に向けて発射し自殺した。
殺人事件とクーデタ未遂事件は決着した。
ヴァルターの気がかりは、アイゼンハイムの幻影術の仕かけ=カラクリを解明することだった。
幻影術の仕組みを考えながら街を歩いていたヴァルターのもとに1人の少年がやってきて、封書を渡した。
封筒を開けると、なかにはアイゼンハイムの幻影術の仕かけの設計図・構想図案を収録した小冊子が入っていた。レモンの種を植えると、またたくまに発芽し、数分のうちに葉と茎が成長して樹木になり、花が咲き、果実が実るという、あのイリュージョンのカラクリの説明も書かれていた。
しばし、アイゼンハイムの幻影術のカラクリがわかって喜んだヴァルターだったが、ふとわれに返った。
少年は「あなたにこの封筒を手渡すようにある紳士から頼まれた」と言い置いて、走り去っていった。ということは、アイゼンハイムがヴァルターの居場所を知っていて、しかも「幻影術のカラクリを知りたい」と思っていることを知り抜いているということだ。
「私の心は、アイゼンハイムによってすっかり読まれている」
ヴァルターははっと気づいた。
「私はアイゼンハイムによってすっかり操られていたのだ。
レーオポルト大公に殺人容疑をかけ、クーデタの企てを皇帝に報告して大公を破滅に追い込むことも、彼によって仕組まれたことに違いない」
すると、ヴァルターの脳裏に、アイゼンハイムと出会ってからのできごとがフラッシュバックして記憶によみがえった。そして、1つの文脈に結びつけられた。
彼は幻影術を使って、ゾーフィーを仮死状態にしておいて、あたかも剣でのどを切られて殺されたかのように見せかけ、その容疑を大公に向けるように仕組んだのだ。
脳裏で目まぐるしく推理しながら、ヴァルターは駅に向かって走っていた。
「私を操っておいて、アイゼンハイムは鉄道に乗って逃げ去ろうとしている」
何とか捕まえようとしたのかもしれない。だが、間に合わなかった。というよりも、おそらく変装しているアイゼンハイムを見分けることはできなかっただろう。
ふたたび映像はカット=フラッシュバックとなる。
ヴィーンから逃げ去ったアイゼンハイムが、じつは生存しているゾーフィーが待っているオーストリアの山岳のなかにあるログハウスに到着し、ゾーフィーを抱擁する場面。これは、消え去ったアイゼンハイムとゾーフィーのその後の姿であり、また、ヴァルターの想像でもある。
しかし、ヴァルターは、利用されてレーオポルトを死に追いやったことを後悔しなかった。それどころか、「おいアイゼンハイム、みごとにやってのけたな!」と祝福したい気分だった。警視の顔には、微苦笑が広がった。
■共同主観というイリュージョンの上に成り立つ権力■
この映像物語では、有力な皇太子の1人であるレーオポルトの地位が、幻影(によって操られた警視の行動)によって脆くも崩壊してしまうという文脈が事件の中心にある。また、アイゼンハイムの幻影術は、ヴィーンの多数の民衆(大衆)の思考や感情、意識に大きく影響して、場合によっては政治的に扇動する影響力すら持ちうるということを暗示している。
少なくとも、ヴィーン市井人=庶民に対してならば、皇帝や皇太子の権威よりも、見世物にすぎないアイゼンハイムの幻影の方が、はるかに影響力が強いという状況があるということだ。
ヴィジョン(幻影という意味を持つ)や幻想が、社会のレジームを組み換え、世界戦争すら引き起こしてきた歴史(たとえばフランス革命、ナチズムの席巻とかロシア革命などの歴史的事件を見よ)を、私たちは身にしみて知っている。
日本でも「大東亜共栄圏」の幻影が破滅的な戦争への道をイデオロギー的に用意した。
また、このブログのほかの記事で見たとおり、諸国家の正史(正当な歴史記述)が、統治者のそのときどきの政治的利害や目論見によって制約されながら形成され、構成されてきた歴史観=イデオロギーであって、多分に一面的で偏見に満ちているものであることも、当たり前のことだ。
ということは、レジームや権力構造というものは、いやそういうものの正当性=正統性というのは、イリュージョンの上に成り立っていることを意味するとも言える。
要するに、権力や支配とは関係性の独特の構造(形態)のことであって、
・権力者=支配者側の意識や発想には、人民が自らに従うものが当然だ、従うべきだという主観がインプリントされ、構造化されている
・人民・民衆の側では、支配者にはなびいておくのが当然、従うべきだという主観が構造化されている
という関係性が成り立っている状態にすぎない。
したがって、社会状況が変化すれば、この「べきだ」「当然だ」という意識=価値観(価値選択とか行動スタイル)がすっかり変わってしまう。
たとえば、先頃の一連の「アラブの春」のできごとを見よ。
権力者=支配者の側では、あまり変化はないのだが、民衆の側では権力者が打撃を与えて破壊すべき敵対者と位置づけられることさえ起きるのだ。
だが、旧来のレジームを打倒したのちに、どういう新たなレジームを構築すべきかについてまでは、革命運動の最中には、なかなか目が向かない。
してみれば、レジームそのものもイリュージョンの上に成り立っているのだが、それを打倒する革命思想もまたイリュージョンから成り立っていることにもなる。
■イリュージョンとしての歴史観■
私たちの歴史に関する視点や方法もまた、ある意味でイリュージョン(ヴィジョン:幻影)だ。どれほど科学性、客観性を標榜しようとも。
というのも、どのような方法・立場であれ、私たちの歴史認識は現実の歴史過程の膨大な事実や要素のなかから、特定の少数の事実や要素を抽出してきて、それらのあいだの結びつき(因果関係や「必然性」「蓋然性」)を分析するしかないからだ。
その意味では、はじめに事柄=事実があるのではなく、むしろ、生まれてから社会のなかで育ってきた過程(譬えば公教育制度)で身につけた視座や価値観に沿って、私たちは歴史を眺めることになるからだ。私たちの精神・意識は、社会的=イデオロギー的な存在拘束を受けていて、社会を自分なりに理解しようとする年頃には、すでに既成観念や固定観念、先入観などからでき上がったフィルターを通してしか、歴史や外界を眺められないからだ。
その傾向は、とりわけ社会科学系、歴史学系のアカデミズムに著しい。というよりも、マルクスが言うように、社会科学や歴史学はそれぞれの立場によるイデオロギーのあいだの闘争なのだ。そうなることの理由=原因が、マルクスが説明するようなものではないにしても、論理化された思想・観念のあいだの争いであることは間違いない。
なかでも、明治以降にヨーロッパやアメリカから学問を輸入して近代化を推進した日本のアカデミズムには、欧米の学説や方法を「額面通りに」受け取ってしまう、それゆえ、阿呆のような「欧米崇拝」の(というよりも権威づけの基準を欧米の学説におきたがる)傾向が強かったようだ。
私の経験で一番ひどいと思ったのは、「市民革命」とか「市民社会」に関する理論史だ。もっとも、この頃では最近の実証史的研究による批判を受けてかなり治ってきているが。
市民革命が中世ないし「封建制」から近代ないし「資本主義」への転換期(転換点)であるという幻想が、左右の陣営を問わず、40年ほど前には支配的立場として堂々とまかり通っていた。
私がこのブログのいくつかの記事で説明したように、資本主義的生産様式への転換は、1000年前から始まっていたし、革命期に権力の争奪戦を繰り広げたのは、本質的に同じ諸階級(貴族と商業資本)のなかの2つのグループだった。したがって、革命の前後で統治構造=レジームは変わったが、社会の基本構造は変わらずに持続し、徐々に変容が進んでいった。
ところが、革命後に権力を掌握したフラクション(分派)は、自らが支配するようになった新たな段階(秩序)こそ、これまでの人類史のなかで最高に発展した社会状況であると宣言し、過去の歴史をそこに必然的にいたるべき諸段階として位置づけた=価値づけたのだった。
日本では、明治期の文明開化を正統化したいあまりに、江戸期以前をことさら貶める歴史評価が、左右両陣営によってまことしやかに撒き散らされた。日本は「低位後発」の劣った社会だと、単に卑下する卑屈な歴史観がまかり通っていた。
明治政府側=右翼は、江戸期をことさらに「遅れた社会」(その反照として、明治期の進歩は素晴らしい!)として描こうとした、その思想は公教育の歴史に強引に持ち込まれた。
で、他方で左翼は、日本はブリテンやフランスのような「市民革命」を経ていないから、まともな「産業資本主義」は形成されなかった、と主張した。
いずれにしろ、イリュージョンがアカデミズムに蔓延してきた。
革命のユートピア(理想論:イデアリズム)は、革命後には秩序を正統化し神聖化する虚偽意識としてのイデオロギーになったというのは、カール・マンハイムが指摘したとおりだ。
その同じ方法論=発展段階論を、マルクスたちはそっくりそのまま継承して、未来の理想社会(コミュニズム)を描いたのだ。
そして、マルクスたちが想定した文脈とはおよそすっかりかけ離れた状況で発生したロシア革命後に、ソヴィエト権力は、マルクスの方法を利用して、革命を社会構造(生産様式)の構造転換の過程とする「方法論の鋳型」をつくり出した。過去の歴史をその鋳型のなかに強引に流し込んでいった。
その陣営が「正統派マルクシズム」を標榜したことから、その後恐るべき混乱と紛糾が出来した。「社会科学」の論争が、正統派と異端派との宗派争い、宗祖の片言隻句を呪物崇拝する非歴史主義・アナクロニズムへと変貌したのだ。
レジームを批判して変革を求める側が、そのような虚偽意識にまみれた理論を基礎にしたのだから、まともな変革の展望を描けるはずもなかった。私は、そのような「失われた世代」に属する。
今だって、「市場幻想」の崇拝者とか「自由化幻想」の崇拝者たちが、市場の暴力に圧迫されて呻吟する人びとの苦難を無視して、偉そうに高説を垂れているではないか。
いずれも、幻想と幻滅の博物館に陳列されることになるのかもしれないが。
しょせん、(歴史観というのはきわめて重要なものだが)現実の歴史というとらえようのない厖大な事象の、一部分を、多かれ少なかれ屈折したフィルター・レンズを通して写し出した、ごく大雑把なシミュレイションでしかないのだ。