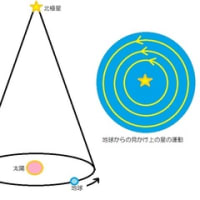第120回 ガンディー(1982年)
原題 Gandehi
見どころ
映画《ガンディ》の素晴らしい点は、単なる偉人伝ではなく、インド独立の指導者、ガンディたちがインドをブリテン植民地帝国から独立させ、おそろしく多様で分裂した諸地方・諸民族を1つの国民(Nation)へと政治的に統合=形成していくうえでの苦難や困難を率直に描き出したところにある。
そして、独立運動過程で直面した困難や苦悩の多くは、経済発展が目覚ましいインドがいまだに抱え込んでいる深刻な問題なのだ。
そんなことをあらためて考えさせてくれる作品である。
1 インド …そこには世界のあらゆる問題がつめ込まれている
日本人のほとんどは、国家や国民について、世界のほかにないほどに単純で安易なイメイジを持っている。それでも、生活ができるような幸運に、この数百年間めぐまれてきたのだ。だが、これからはそうはいかないだろう。
島国で、例外的に早期に「1つの天下」「1つのくに」という観念ができあがったからだろう。だが、その分、深刻な闘争や紛争をつうじて、苦難に満ちた国民形成、国家形成を体験した諸地域と比べて、国民や国家についての歴史的ないし社会史的、論理的に省察する機会を持つことはなかった。
「ボーダーレス」という用語が飛び交う現在の世界で、ボーダー(国境や国家・国籍・国民性)の壁の役割について問い直しが迫られている。私たち日本人は、この「置き忘れた問題」を深刻に見つめなければならないのかもしれない。
■500以上の言語と3000の民族(部族)■
現代インドでは、映画作品やテレヴィ作品で使用される言語が500以上もあるという。そして、民族や部族(ethnic group)は3000近くもあるという。しかも、カースト制による民衆内部の断裂が縦横に走っている。ヒンドゥー(その分派としての仏教)、イスラム、シーク、ジーナ、そのほか多数の宗教の慣習や戒律、組織が住民をこれまた分断している。
多様性というか分断要因に満ちている大陸国家なのだ。
独立ののち60年間以上も国家統合や国民形成が進展しても、なお断裂した社会構造になっているのだ。独立以前は、いったいどれほどの分断・断裂があったのか、見当もつかない。
さて、私たちは「インド独立」という言い方をする。
あたかも、1つの文明的ないしは文化的まとまりとしてのインドが昔からあって、17、18世紀からヨーロッパ列強による侵略や収奪にさらされ、やがてブリテン王国の植民地になった。そして、20世紀半ばに政治的・軍事的に独立し、国家を形成したというようなストーリーを思い描くかもしれない。
まったくの間違いだ。インドという「まとまり」は、ブリテンの植民地支配の帰結なのである。
アジアやアフリカにおいて植民地から独立した諸国民の多くは、ヨーロッパの植民地争奪戦と植民地支配が生み出した軍事的・政治的単位(境界線)を所与の前提として、政治的独立と国家形成を「達成」したのだ。
したがって、多くの場合、内発的な統合要因(まとまり)は本来存在せず、むしろ分裂・分断要因を抱え込んだまま国家形成・国民形成が進められた(いや停滞した)のだ。
ブリテンの植民地支配の以前には、まとまった社会としてのインドは存在したことはなかった。
だが、ムガール帝国があったではないか、と反論する人もいるかもしれない。
しかし、ムガール皇帝は、今日のインド領土の北部を「外から=上から」支配しただけであって、皇帝の権力がインドにおよぶのは、ヨーロッパ人のインド洋進出にわずか半世紀ほど先立つにすぎなかった。
現代の地理でいえば、アフガニスタンとパキスタンがムガール帝国の中心だった。だが、高度な文明と豊かな富の集積に惹きつけられて、皇帝の統治組織の本拠が北インドの一部に置かれたにすぎない。そして、イスラムの文明装置と宗教権力も目立つほどの規模で浸透し始めた。
ムガール皇帝が、その半世紀ほどあとでヨーロッパ人たちが、インド亜大陸にやって来た頃、インドははるか古代から続く多数の局地的政治体、たとえば領主圏(太守国)、公国、王国、民族、部族集団に分かれていた。皇帝の支配は、北部の一定地域に表層的な政治的・軍事的統合をもたらしたが、インドの太守や王たちの主権そのものを奪うことはできなかった。
というのも、皇帝は自前の行政・徴税装置を持たなかった(持とうとも考えなかった)。各地方の太守や領主の権力(それもさらに地方的な政治組織に頼っていた)に完全に依存して、皇帝の権威は成り立っていた。
太守や王たちの権力の独立を認めるのと引き換えに、皇帝への軍役奉仕(巨額の報酬を代償とした)とか納税・貢納の義務を課しただけだった。皇帝は、そういう皇帝権力の相対的優位を確保するために、太守や王たちの同意をなとか取り付けて、彼らの局地的紛争を抑えるために遠征をおこなった。だが、膨大な軍事的出費をともない、皇帝の財政的基盤を掘り崩していった。
■ブリテンの植民地支配■
やがて、ポルトゥガルがアジアの特産物(香辛料や陶器、財宝)を求めてインド洋に進出してきた。あとを追って東アジア、東南アジアに進出してきたのがネーデルラントだった。ネーデルラントの連合東インド会社(VOC)は、東南アジアに貿易と海洋軍事力の拠点を築いて、インド洋に入り込み、やがてポルトゥガルを圧倒した。
そのネーデルラントを18世紀に圧迫し駆逐したのが、イングランド(ブリテン)の東インド会社だ。
ブリテン東インド会社は王室から貿易独占の特許状を与えられた企業で、貿易独占の特権には、艦隊や地上軍の保有と運用、植民地建設と支配、固有の立法権と裁判権などが含まれていた。
要するに、世界的規模で海外で活動する国家装置でもあり、経済的・財政的・金融的装置でもあった。とはいえ、ロンドンの中央政府の統制は、この会社にはほとんどおよばなかった。というよりも、統制をおよぼすという発想や行動スタイル自体が、その当時はなかった。
会社ははじめのうちムガール皇帝や地方の太守、王侯たちに巨額の税=運上金を差し出して、域内での商業特権を買い取っていった。やがて、近代的軍事力による威嚇をちらつかせて、商業特権を入手するようになっていった。
ブリテンによるインドの植民地化と支配のレジームは、東インド会社によって創出され確立されたのだ。
東インド会社の貿易品目は多品目におよんだ。なかでも巨額の利潤をもたらしたのは、インドでの収奪から得た貨幣で中国から買い入れた茶の貿易だった。
だが、茶の購入価格は高くて、対中国貿易は赤字を累積していった。その解決策が、アヘン(麻薬)貿易だった。麻薬貿易は密貿易ではなく、王室御用達の会社の公然たる事業として営まれた。麻薬⇒茶の世界貿易という巨額の資金循環が組織された。
ところで、東インド会社がインドに拠点を固めた頃から、ムガール皇帝の権力は衰退し始めた。インド各地で太守や王侯たちのあいだでの紛争が頻発した。ブリテン人は、会社の活動のために各地での紛争に介入していった。紛争を鎮圧することもあれば、貿易特権や土地支配権の引き渡しを拒否する太守や王侯を追い詰め破滅させるために戦争を仕かけるようになった。
会社の活動に都合のいい太守や君侯を傀儡として押し立てることもあった。
18世紀末には、ムガール皇帝は東インド会社の傀儡となった。
19世紀前半までに、インド洋=南アジアにおけるブリテンの植民地支配は、今日のパキスタン、インド、バングラディシュ、ミャンマーのそれぞれ全域を含む広がりにおよんだ。
会社は、インドでの政治的・軍事的再優位を維持するために、民族や部族、宗教組織やカーストのあいだの対立や反目、格差をとことん利用する巧妙な「分断統治」の仕組みをつくり上げた。インドの民衆をインドで徴募組織した軍隊によって抑圧する仕組みも。
ところが、東インド会社は、独立の事業権を持つ社員=商人たちが、自己の利益のために好き勝手に活動し、紛争や反乱の原因をつくっていた。その結果、会社の正規軍が出動したり、それでも収まらない場合には、ブリテン本国から軍を派遣したり、本国の財政支出が必要になったりした。もちろん、会社の内部統制や内部牽制はそもそもどこにもなく、財政や会計は乱脈を極め、現地社員の私的利権の巣窟となっていた。
こうして、「植民地支配と貿易による利潤は会社(社員と株主)に、尻拭いは本国政府に」という悪循環ができ上がった。
とうとう本国政府が調査と統制に乗り出し、19世紀半ばには会社は解散させられ、ブリテン政府による直接植民地支配となった。
だが、支配と収奪の性格はまったく同じか、さらにひどくなった。
ことに、ブリテン人不在地主による土地所有=土地支配が著しく拡大した。
その頃から、インド民衆や民族・部族による蜂起や反乱が頻発するようになった。
ブリテンは、インド支配のための行財政装置や正規軍(拠点)を組織し、鉄道連絡網を建設していった。それはまた、多数のインド人を政府組織の周囲に集結・組織化し、各地に人びとのコミュニケイション手段を形成する条件を生み出すことでもあった。統治=行財政の実務に堪能な多数のインド人が生まれ始めた。
1877年には、インドをブリテン帝国に組み込み、ヴィクトリア女王がインド皇帝として戴冠した。それはまた、インドの特権階級・富裕階級への市民権を付与する道でもあった。本国で市民権保護のために利用される法制度や慣習が、インドでもインド人のために利用されることにもつながった。
とはいえ、ブリテン人によるインドの経済的支配は深化していった。
1885年には、第1回インド国民評議会が開催された。
2年後に、インド国民評議会は独立運動の中心組織、統一戦線組織となった。とはいえ、いまだ富裕な特権的エリートの運動であって、インド植民地全体の人口からすればごく少数の運動にすぎなかった。
やがて、大学などの高等教育機関も創出され、インド人特権・富裕階級のなかからインテリゲンチャや準エリートが生み出されていく。そのなかから、インドの独立、国民形成を課題として意識するグループが登場する。
1906年には汎インドイスラム教徒(ムスリム)連盟が結成された。
その年、連盟の有力な若手指導者、ムハマード・アリ・ジンナは国民評議会に加盟した。
■「インド洋亜世界システム」■
ところで、ヨーロッパ人たちが近代的軍事力をもってインド洋に進出する以前は、東南アジアからインドシナ沿岸部、インド、スリランカ、マダガスカル、セイシェルなどの群島、ペルシア、東アフリカ、アラビア半島沿岸部にいたる広大な地域は、海洋交易をつうじてゆるやかに結びついた「亜世界貿易圏」を形成していた。
東南アジアの香辛料やインドの綿織物やペルシアの陶器や宝石などが活発に取引され、豊かな経済圏の集合をなしていた。
インド人たちは古くから、ペルシアや東アフリカに移住して、貿易省や工芸職人として現地社会に溶け込んできた。
その豊かさが、軍事力と癒合しながら拡大するヨーロッパの資本主義を引き寄せてしまった。そして、インド洋沿岸の大半の地域がヨーロッパの植民地支配によって蹂躙されることになってしまった。
2 南アフリカとブリティッシュ・コモンウェルス
映像は、1948年、ガンディの暗殺の場面から始まる。そして、半世紀以上も時代をさかのぼり、1893年のブリテン帝国のコモンウェルス、南アフリカに移る。
24歳のモハンダス・カラムチャンド・ガンディが長距離列車の一等客室(コンパートメント)で旅をしている場面だ。
それから5年前、ガンディはロンドンの法学院に留学して帝国全域で認められる法廷弁護士の資格を取っていた。ロンドンでは、知識人・準エリートしての処遇を得ていた。もっとも、周囲の人びとは洗練されたエリートや専門職層だったから、あからさまな差別を受けるはずもなかった。
■アパルトヘイト■
ところが、列車で切符改札に回ってきた車掌は、有色人種のガンディが一等席車両に乗っているを見て驚きを示した。車掌は引き返し、まもなく官憲を連れてきた。
「有色人種は一等客室には乗れない、三等席車両に移れ」と命じた。
憤慨したガンディは抗議したが、力づくで車両から追い立てられ、次の駅で列車から放り出された。
アパルトヘイトの実態を身にしみて体験したわけだ。
当時、南アフリカ「共和国」もまたブリティッシュ・コモンウェルスに属している限り、抽象的な法理論では、ブリテン帝国の憲法的規範が妥当すべきであった。だが、ヨーロッパ系住民が圧倒的多数派を占める地域以外では、そんな法理は、原住民による独立運動が活発化するまでは、ほとんどまったく顧みられなかった。
南アフリカはことさらにひどかった。
しかも、南アフリカ政権は、原住民やインド人(アジア系有色人種)の反乱・抵抗運動には過酷な暴力による弾圧をもって臨んできた。闘争的な運動は、組織化する前に残酷な抑圧によって粉砕されてしまった。
■高品格の異議申し立て■
そこで、ガンディが考案した戦術は「非暴力」の「不服従」だった。だが、非暴力=不服従は、それまでのような民衆の自然発生的で粗暴な結集とか組織だった集結や集団的示威運動とかに結びつくものではなかった。
むしろ、個々人の倫理観と心性にきわめて強く依拠する運動形態だった。
官憲の捕縛や規制に対しては力づくの抵抗をしないが、しかし畏怖し服従するわけではない。結局、なされるがままに拘束され投獄される。だが、監獄もすぐに満員になる。短期の投獄期間で釈放される。これでは、当局の手間がかかるだけである。
スタイルからいって、個人の行動スタイルの選択であって、そういう行動スタイルがモード化することで、非暴力=不服従は「社会的広がり」をもった運動に発展するものだった。
したがって、表立った組織化や抵抗運動にはならないから、当局は群衆を弾圧するようには抑圧・封じ込めはできなかった。こういうモードの代表者を拘束・投獄することはできても、彼らは組織をつうじて運動=モードを指導しているわけではないから、封じ込めや壊滅はできない。
むしろ、統治の停滞や機能不全がいたるところで生じるだけだった。
そして、ブリティッシュ・コモンウェルスやヨーロッパでのアパルトヘイトへの道義的・倫理的批判を拡大するだけだった。
南アフリカ政府は、そのためにこの運動に譲歩して、インド人に対しては一定の制限の範囲内で市民権を認めざるをえなくなった。アパルトヘイトに入った小さな小さな亀裂だったが、ガンディ派の決定的な勝利だった。亀裂は100年近くかかって、ゆるやかにアパルトヘイトをヒビだらけにして解体させるための一歩になった。
南アフリカにおいて、ガンディはこの非暴力=不服従運動を1897年に始めて、1914年まで続けた。翌年、彼はインドに帰国することになった。
■植民地帝国の解体への兆し■
1914年といえば、ヨーロッパを主戦場とする第1次世界戦争が勃発した年だ。言い換えれば、ヨーロッパにおいて圧倒的だったブリテンの覇権、すなわち大がかりな戦争を抑止するはずのブリテンの力に陰りが見え、いたるところに力の空隙が生じてきていたということだ。
世界戦争となったから、ブリテンの敵対勢力は、世界各地で、ことにブリテンの植民地支配に蹂躙された諸地域でブリテンの支配の不当性を訴え、反乱や抵抗を(そのための援助をもって)教唆した。そうなると、世界的規模でのブリテンの帝国的な植民地支配の仕組みが動揺することになった。
そのうえ、ヨーロッパ大陸でのドイツ帝国の戦争能力はすこぶる大きかった。そのため、ブリテンは戦争に動員する資源の確保とか、兵員補充、後方支援(兵站管理:ロジスティクス)のために、植民地側の支援を求めることになった。
その植民地側では、それゆえ原住民たちの発言力が強まることになった。
したがって、ブリテン本国はあれこれの側面で大幅な譲歩を示すことになる。とりわけ、巨大な資源・資産の源泉だったインド植民地の態度は、戦況の行方を左右しかねないほど大きかった。
しかも、インドでは国民評議会派とムスリム同盟との協力・同盟関係が強化されてきていた。
従属的な植民地統治ではなく、主要な統治実務をインド人たちに担わせようというブリテン政府の妥協策も提起されるようになった。
ブリテンの支配層=エリートのあいだには、インド植民地の将来構想をめぐって対立があったわけだ。開明派と守旧派との鬩ぎ合いが繰り広げられていた。
3 インドへの帰還
ガンディがインドに帰ったのは、そういう状況下だった。
すでに、南アフリカでの運動によって制限つきながらインド人の市民権確保への道を開いたことで、彼はインド独立をめざす諸勢力からは「英雄」としてあつかわれていた。つまりは、インド独立運動に新たな指導者を迎えようという気運があった。
とはいえ、インドにはすでに独立運動の固有の指導層(いくつかの勢力=政派とその指導部、そして指導部のあいだの同盟)が形成されていた。という意味では、すでに運動には独特のヴェクトルがはたらいていて、ガンディというカリスマ的個人が加わったからといって、その方向がただちに変わるというものではなかった。
そのときの独立運動の担い手、国民評議会派は、多数派のヒンドゥ教徒とムスリム連盟が主要勢力だったが、シーク教徒やジーナ教徒も加わっていた。ヒンドゥの指導者は、若いネルだった。
ムスリム連盟の指導者はムハマード・アリ・ジンナ。映画では、当初必ずしもジンナは、ガンディの非暴力=不服従の思想=行動スタイルには賛成ではなかったかに描かれている。というのも彼は、合法的な運動だけでなく、自然発生的でときに粗暴な抵抗運動や反乱・蜂起をも必要な闘争形態と見なしていたからだった。粗暴な抵抗はは、多くの場合、植民地政府の抑圧によって強いられた反応だからだった。
やがてジンナは、ガンディの方法論を受け入れたが、それでもやはり一歩距離を置いていたように見える。
ネルもジンナも、貴公子然とした端正な容姿をしていた。
■非暴力=不服従とサティヤガラ■
ガンディの行動スタイルあるいはめざした運動形態は「サティヤガラ」と呼ばれる。
サティヤガラとは、ヒンドゥの古語(サンスクリット語)で、「真実の追求」「求道」「理想を真摯に求め続けること」という意味だという。
ここでは、真実=理想をインドの独立と多様な民衆の統合だと解釈すると、サティヤガラの目標はインドでの独立した国民形成ということになろうか。非暴力=不服従という運動形態(多分に運動の担い手の精神的態度、行動スタイルに依存するということ)は、サティヤガラの内容からして必然的なものという論理になりそうだ。
実力による抵抗を極力避けるという運動形態は、担い手の高い知性や精神性を求めることになる。それゆえ、非暴力=不服従は、消極的・受動的な異議申し立てではない。粗暴な抵抗や反乱を回避して、内部統制のとれた平穏な運動形態を意識的に組織する能力が求められることになる。
その意味では、高い知性や精神的訓練を経たエリート向きの運動形態ともいえる。インドのインテリ層の知的水準がすこぶる高かったという事情をは反映しているのかもしれない。
貧困な、それゆえ教育水準がきわめて低い多数の民衆を抱えるインドでは、きわめてむずかしい運動形態だっただろう。その後の事態を見るとき、インドの民衆のどれほどがサティヤガラを理解していたかは、疑わしい。
あるいは、インド民衆はとびきり高い知能をもっているのか?
さて、サティヤガラ運動で画期的な事件は、1930年(3月から4月)の「ソルト・サティヤガラ」だ。
ガンディらが始めた、製塩の自由を求めて、多数の民衆が内陸部から海岸までの長い旅をする運動だ。海水から塩をつくるために人びとが海岸まで歩き、浜辺で昔ながらの方法で塩をつくるという運動なのだが、この運動はブリテンの植民地支配への不服従=抵抗という点では、決定的に重要な意味を持っていた。
■ブリテンの植民地支配とソルト・サティヤガラ■
というのは、東インド会社の時代から、インドで製塩と食塩の販売はブリテン商業資本の独占だったからだ。製造と販売の独占(専売)によって、生存に不可欠な食塩の製造・流通・販売の全過程からまんべんなく税金を取り立て、巨額の剰余価値を集積して、当初は東インド会社の、続いて植民地政府(本国政府)の収入としていたのだ。
この制度は、とりわけて貧しい階級の民衆の生活を圧迫していた。
そのために、ブリテン当局は、海浜での住民の活動や商業活動に対して、きわめて厳格な監視と統制をおこなっていた。違反には厳しい処罰で対処した。
その意味では、食塩専売制度は、ブリテンの植民地支配の過酷さの象徴だった。
政治がシンボルをめぐる闘争ないしは駆け引きだとすれば、サルト・サティヤガラは、まさに植民地的従属への痛烈な異議申し立てにほかならない。
とはいえ、この運動は、直接的には食塩専売に直接的に反対するものではなかった。海浜まで歩くだけの運動だった。平穏に道を歩き続けるだけの行事だった。すっかり合法的な運動だった。
しかし、はじめはガンディが逼塞する内陸のコミューン農園から歩き始めたときには、わずか数十名にすぎなかった集団は、数々の村々を過ぎ、町を過ぎていくにしたがって、参加者は膨れ上がり、海浜に到達する頃には数万におよんでいた。
ムンバイ(ボンベイ)からおよそ400キロメートル北にあるアーメダバードからグジャラート西部の海岸まで、400キロメートルの道のりを歩く大行進だった。
この運動は、インド人を搾取・収奪するブリテンの植民地支配の仕組みの不当性(不正義)を訴え、インド人自らがそういう軛からの独立・解放を意識し希求するということを表明するものだった。このできごとは民衆の話題となり、町から町へ、村から村へと伝えられ広がり、支配され抑圧されている人びととしての連帯を拡大していった。
一般民衆が参加するという点では、それまでの高度に精神的・知的なエリートの運動から大衆的な運動形態への試みだったといえるかもしれない。
続く