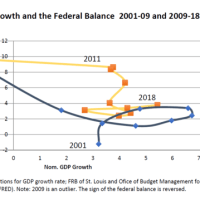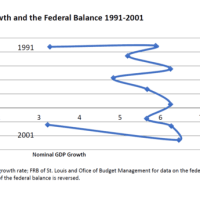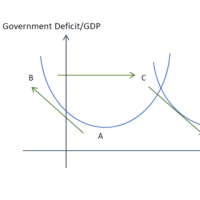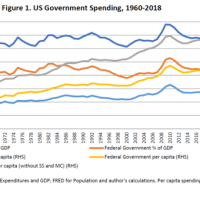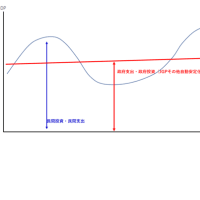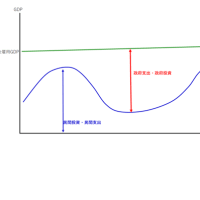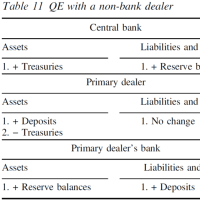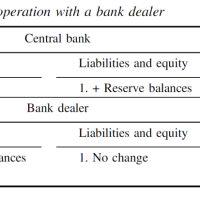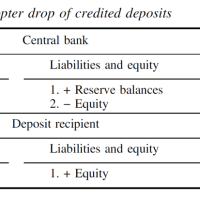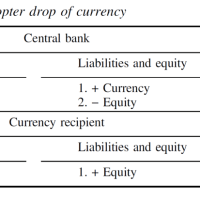L. Randy Wray
Endogenous Money: Structuralist and Horizontalisを
簡単に訳してみた。
内生的貨幣供給論という言葉については
おいらは特に強調する意図はない。
「内生的貨幣供給論」といったって
単に中央銀行が経済情勢に合わせて
一定のルールに従い(あるいは
結果的にルールに従っているように見えているだけなのかも
しれないがいずれにせよ)
ベースマネーの供給量を調節している
というだけの話なら、
別段関心はない。
個人的に言えば
貨幣供給が内生的か外生的かということ自体より
貨幣には
明確に発行者が存在して、
利用者にとっては決済手段であり
貯蓄手段である者が
発行者にとっては
決済されることを必要とする負債に過ぎない、
という点
(そしてその決済のためには
その発行者が「利用者」となる
もう一つ別の「貨幣」が存在していなければならない、と
いうシステム)が重要なんで、
その点についての認識なしに
単に月末の、あるいは毎日の民間金融機関営業終了時点での
何かの変数の値が
何かに連動していて
それはどうやら中央銀行が何かの
「ルール」に従ってオペレーションしているからだ、
だからマネーストックだかマネタリーベースだかは
何かの従属変数なのです、だから
内生的貨幣供給理論、
というのは、まあ、何でもいいや、
みたいな気がしている。
本稿は2007年に発表されたものだから
ちょっと古いところがある。
合衆国の準備に金利が付かないとか、
バーゼルIIIじゃなくてバーゼルIIだったり。
あと、
これは何とかしてほしかったが
まだ使い慣れていないワープロを使っていたようで
入力補助というのか自動変換(こりゃ日本語用にしか
無いのか?)というのか、
どうも明らかに"us"とあるべきところが
"U.S."とかになっていたりで、
なんちゅうか、こう、
ワーキングペーパーって校正とかって
ないんだっけ?みたいな。。。。
レイは、どっちかというと
ミンスキーの直弟子ということもあって
ストラクチャリストという印象が強いんだけれど、
で、現に、現時点で主著とでもいうべき
The Rise and Fall of MMC 何かを
読んでいると
明らかにストラクチャリスト的印象が強いんだけれど、
このペーパーでは
どちらかというとホリゼンタリスト側に与するような
印象を与える。
結論はどっちつかずというか、曖昧というか
お茶を濁したというか、世渡り上手というか
まああれなんだが、
というか、
もともとストラクチャリストとして出発した
レイがどのような形で
どちらかというとホリゼンタリストあるいはサーキュレーショニストとの
親近性を強く感じさせるMMTの
主唱者になったのか、
その辺の一貫性というものを
理解するうえでは面白いペーパーだと思う。
https://drive.google.com/file/d/0Bz2V1zKzg0azalo1bllSS1NDV0U/view?usp=sharing
Endogenous Money: Structuralist and Horizontalisを
簡単に訳してみた。
内生的貨幣供給論という言葉については
おいらは特に強調する意図はない。
「内生的貨幣供給論」といったって
単に中央銀行が経済情勢に合わせて
一定のルールに従い(あるいは
結果的にルールに従っているように見えているだけなのかも
しれないがいずれにせよ)
ベースマネーの供給量を調節している
というだけの話なら、
別段関心はない。
個人的に言えば
貨幣供給が内生的か外生的かということ自体より
貨幣には
明確に発行者が存在して、
利用者にとっては決済手段であり
貯蓄手段である者が
発行者にとっては
決済されることを必要とする負債に過ぎない、
という点
(そしてその決済のためには
その発行者が「利用者」となる
もう一つ別の「貨幣」が存在していなければならない、と
いうシステム)が重要なんで、
その点についての認識なしに
単に月末の、あるいは毎日の民間金融機関営業終了時点での
何かの変数の値が
何かに連動していて
それはどうやら中央銀行が何かの
「ルール」に従ってオペレーションしているからだ、
だからマネーストックだかマネタリーベースだかは
何かの従属変数なのです、だから
内生的貨幣供給理論、
というのは、まあ、何でもいいや、
みたいな気がしている。
本稿は2007年に発表されたものだから
ちょっと古いところがある。
合衆国の準備に金利が付かないとか、
バーゼルIIIじゃなくてバーゼルIIだったり。
あと、
これは何とかしてほしかったが
まだ使い慣れていないワープロを使っていたようで
入力補助というのか自動変換(こりゃ日本語用にしか
無いのか?)というのか、
どうも明らかに"us"とあるべきところが
"U.S."とかになっていたりで、
なんちゅうか、こう、
ワーキングペーパーって校正とかって
ないんだっけ?みたいな。。。。
レイは、どっちかというと
ミンスキーの直弟子ということもあって
ストラクチャリストという印象が強いんだけれど、
で、現に、現時点で主著とでもいうべき
The Rise and Fall of MMC 何かを
読んでいると
明らかにストラクチャリスト的印象が強いんだけれど、
このペーパーでは
どちらかというとホリゼンタリスト側に与するような
印象を与える。
結論はどっちつかずというか、曖昧というか
お茶を濁したというか、世渡り上手というか
まああれなんだが、
というか、
もともとストラクチャリストとして出発した
レイがどのような形で
どちらかというとホリゼンタリストあるいはサーキュレーショニストとの
親近性を強く感じさせるMMTの
主唱者になったのか、
その辺の一貫性というものを
理解するうえでは面白いペーパーだと思う。
https://drive.google.com/file/d/0Bz2V1zKzg0azalo1bllSS1NDV0U/view?usp=sharing