
■フランシス・ベーコン
東京国立近代美術館で「フランシス・ベーコン展」を5/26までやっている。
意外に人がすいていた。早朝に行ったからかもしれない。
展覧会はとてもよかった。
フランシス・ベーコンは、相当に昔から好きな画家。同名の哲学者もいるが別人。
1909年-1992年。アイルランド生まれ。
画集は何冊か持っている。若い時期はよく眺めていた。
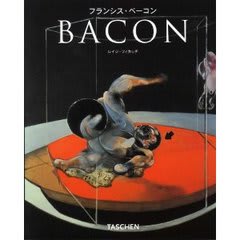
この人の作品はあまりに人気があって散在しているので、なかなか展覧会自体が行われない。
日本では1983年に回顧展があって、今回は30年ぶりらしい。
基本的に、ベーコンの絵には大量の毒が含まれている、と思う。
毒は、知らないうちに体に回ることもあるし、摂取したことを意識できないこともある。
ただ、毒は必ずしも悪を意味しない。そこに善悪は介在していない。
毒は生命エネルギーとのバランスで語られうるものだ。飲み込むことができるかどうかだ。
一つの物差しとして、毒は存在している。
毒を持って毒を制する、という言葉もある。
これはホメオパシーの原理に近い。
ホメオパシー自体が近代医学で否定されてしまった。近代医学や科学という名のものとに、多くのものが切り捨てられたが、そこに偏見や理性の落とし穴がある。
偏見はよくない。それは子供の存在が証明している。
ただ、弱い毒を摂取して自分の免疫反応を高めるという点では、ワクチンは似た考えに乗っ取っている。
ワクチンのように広く受け入れられるとその存在を疑いもしないことは多い。
それは「毒」も同じものだ。
岡本太郎の名著「自分の中に毒を持て」青春出版社 (1993/08) もそのことを示唆している。この本は高校生の時に20回くらい読んだ。思い出深い本だ。

■
ベーコンの絵は危険だ。毒がある。
毒には、この「現実」の見方を変える力がある。
もちろん、この「現実」は一層構造でない。
人間の「成長」の度合いに従って、この自然や宇宙は「現実」を薄皮一枚をはがすように、徐々に深い地層を人間に見せてくれる。
何事にも時期がある。物事には順番があり、階梯がある。
生のRealityにも層構造はある。
生は、生命活動の一面に過ぎない。
生命活動には「生」だけではなく「死」も含まれる。現代はなぜかここが抜け落ちていることが多い。
生も死も含まれた上で、生命活動は一巡し一周する。
死は悲しむべきものではない。生命活動の一つだ。
死において悲しむべきことは、自分がその相手に対して愛を表現できなかったこと、そういう自分の行為そのものが悲しむべき対象だ。
愛や思いを尽くせば、死と悲しみは必ずしもリンクしない。
エジプトの死者の書では、死んだときに最初に聞かれることは
「あなたの人生は喜びだったか?そして、人生の中で人に喜びを与えたか?」ということらしいと聞いた。このことは生と死の真理をついているように思う。


■
ベーコンの絵は、人間存在の深層構造をほのかに暗示している。
見える身体(皮膚や内臓も含め)だけではなく、見えない身体のことを暗示している。
「オーラ」という言葉で暗示される身体。身体のはみだし。そういう部分を扱っている。
ベーコンはもともとインテリアデザイナーだっただけに、色彩に関してもかなりのこだわりがあったことが見受けられる。
色彩の本質。
そのあたりが分かると、ベーコンの絵はさらに深く分かる。
■■■■■■■■■
■オーラ、エネルギー
aura(オーラ)という日常使う言葉は、深い。
通常の絵描は、絵画の対象にオーラは含まれている。
オーラは色として感知される。
色には力がある。
色を見るだけで心地よくもなり、不快にもなり、高揚もし、鬱々ともする。
色そのものの中に感情を動かすエネルギーが内在している。
1983年、英国でヴィッキー・ウォールによって「オーラソーマ」は生み出された。
オーラは「光」、ソーマは「身体」。
光(色)と身体の関係性を追求し、そのことを医療(ヒーリング)に応用したもの。

カラーセラピー自体は、古代エジプトや古代中国の文献にもある。
当時は医療への偏見は小さく、ありとあらゆる角度から医療やケアは探求されたのだろう。
現代では固定観念の元に、医療や芸術や・・・いろんな狭い分野に押し込められて分離されている。
ただ、基本的には人間の営みのプロセスの中に、色も治療も芸術も・・・すべてがあった。
オーラとは、エネルギーフィールド(気の場)のこととされる。
人体には、物質的な身体のほかにエネルギーとしての身体があり、重なっている。
これは人間を見ていくうえで非常に重要な観点だと思う。
量子力学で原子を物質と波動の重ね合わせ、として見る観点に近い。
エネルギー的な身体は、身体の外側に広がっているとされる。
エネルギーの層は物質的な身体の状態や感情、思考を映し出していて、そのことをオーラ(エネルギー的な身体)と呼んでいるようだ。
このことは誰もが直感的に感じているだろう。
「元気」だとか、「病気」だとか・・・、「気」が付く言葉に多い。誰かを見て直感的に感じる印象は、このエネルギー的な身体の共鳴だと思う。
このエネルギー的な身体のおかげで、物質的な身体を健康に保つことができる。
エネルギー的な身体には色々な名前がある。サトルボディ(微細な体)と言うこともある。
ちなみに、心理学者のユングも晩年はサトルボディを研究していた。

ちなみに、ヨガで鍛錬する「チャクラ」は、エネルギーの通り道であり、変電所、ターミナルのような場所。そこは伝統的に経験的に知られていたものだ。
チャクラは、サンスクリットで「車輪・円」を意味する。漢訳は「輪」(りん)、チベット語では「コルロ」(khorlo)という。
回転し、振動させ、循環させる。
チャクラ(車輪)とオーラには関係がある。
生体エネルギーはチャクラ(車輪)から取り込まれ、チャクラ(車輪)の回転による振動でエネルギーが循環する。それがオーラ(気の場)となり現れるとされる。
チャクラは色とも関係がある。虹の七色。
だから、ヨガという身体技法ではチャクラを整える。
それはエネルギーの流れをよくする。エネルギーで表現される第2の身体(サトルボディ)が健康であれば、いくら物理的な身体の故障が起きていても、健康で元気に生きていくことができる。
もちろん、理想的には物理的な身体もエネルギー的な身体も両方が健康なことだ。
若い時は意識しなくても両方保たれるが、年をとるとどちらもその人の意志や意識で保持していかないといけないものだ。



■色
「色」「色彩」に関して。
色の研究には二つの流れがある。
それはニュートンとゲーテの流れ。
ニュートンは、プリズム実験を通して、色の物理学的側面を探求。
それに対して、ゲーテは、色彩体験の主観的体験の現象学としての色彩論を探求。
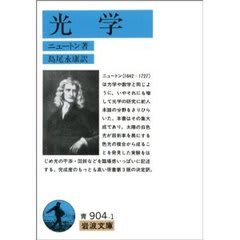

ニュートンは、光(光子)が目に入り、電気的な神経インパルスに変換され、大脳に伝わって起こる感覚を「色」とした。
ただ、その解釈だけで青空の美しさや朝焼けや夕焼けの美しさ、絵画の美しさは語れない、と自分は思う。
ゲーテは、「色」を一つの世界とした。
色はニュートンのように抽象化されるものではなく、体験するもの、と考えた。
シュタイナーは「色彩の本質」でそのことを的確に指摘している。
シュタイナーは、元々は著明なゲーテ研究家でもある。
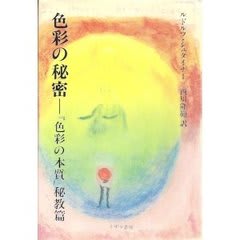
=============
シュタイナー「色彩の本質」(イザラ書房)
『理解しがたいことかもしれませんが、一度、色彩の真の意味を把握しようとしてみてください。
たとえば赤というのは、なにか攻撃的な色です。
赤の前を走り去ろうとすると、赤は人を突き返します。
青紫にむかって走ると、青紫はわたしたちから逃げ去り、ますます遠くなっていきます。
色彩のなかになにかが生きているのです。
色彩は一個の世界です。
心を込めて色彩を体験すると、 感動せずにはいられません。
そのように魂は、色彩世界のなかで自己を感じるのです。』
=============
『さまざまな自然界、死の世界と生命の世界と魂の世界と霊の世界とをとりあげるとき、
ちょうど私が死から生へ、生から魂へ、魂から霊へと昇るように、
黒から緑へ、桃色へ、白へと昇っていきます。
私が死から生を通って、魂と霊の世界へ昇っていけるように、
私が私を取りまく周囲の世界の中で、黒から緑へ、 桃色へ、白へと昇るとき、
私は私を取りまく周囲の世界を像として見いだすのです。
私はいろいろな現実世界の中でその現実世界を辿っていけます。
そして自然は私にこれらの現実世界の像をも与えてくれます。
自然はこれらの現実世界を像に変えます。
色彩の世界は現実の世界ではありません。
色彩の世界は自然そのものの中でさえも像なのです。
死の像は黒です。生の像は緑です。魂の像は桃色です。そして霊の像は白です。
このことによって私たちは色彩の客観的世界の中に導かれます。
色彩の本性、色彩の本質の中に入っていけるには、このことを前提にしなければなりません。
色彩が主観的な印象に過ぎない、と述べるだけでは何の役にも立たないのです。』
=============
『黄は外へ輝き、青は内へ輝き(輝きが内へ集まり)、
そして赤は両者を中和して、一様に輝きます。
この一様に輝くものを、運動する白と黒の中へ輝かせると桃色が生じます。
静止した白の方へ、一方では黄と他方では青とを照射させますと、緑が生じます。』
=============
『黄色は私たちを快活にします。
快活であるというのは、魂を大きな生命力で充たすことです。
ですから黄色によって、私たちは私たちの自我によりふさわしくなるのです。
別な言葉でいえば、私たちはより霊化されるのです。
黄色の根源的本性は外へ向かって拡がり、薄れていきます。
その輝きが今、皆さんの内部へ向けて輝くのです。
それが皆さんの内部で霊として輝くとき、
「黄色は霊の輝きの色である」、と皆さんは言うでしょう。
青色は内的に集中し、鬱積し、内的に持続します。それは魂の輝きです。
赤色は空間を一様に満たし、中心を保持します。それは生命の輝きです。』
=============
『わたしたちは色彩のなかに生き、感情によって色彩を理解します。
このようにして、色彩の世界の輝きと形象のなかに生きると、内的に、魂から画家になります。
色彩とともに生きることを学ぶからです。
個々の色がわたしたちに、なにを語ろうとしているかを感じとれるようになります。』
=============
赤は近づき、青は遠ざかる。
朝焼けや夕焼けのように、闇を通して光を見ると、赤く見える。
闇を通して見た光は、赤い。
一方、光を通して見た闇は、青い。
■
ベーコンの絵は、おそらくこういうことも示唆している、と自分は感じる。
絵を通して、人間の身体そのものを考える。エネルギーフィールドとしての身体を考える。
そこで色を感じ、色の独立した一つの世界を見る。
絵画を通して、結局それは鏡となり、自分のことを見ることになる。
ベーコンの絵に「箱」がよく出てくる。「箱」は、人間の「自我(ego)」の世界のように見える。
「自我(ego)」という狭い箱で苦しむ人間。それをベーコンは冷静に観察し、そういう人間の状況を描き出しているように見えた。
人間が顔面筋を収縮させて笑顔を演じていても、そこに悲しみや絶望が奥に見て取れるときには、そういうエネルギーとして発する悲しみの身体の方を描いていた、と思う。


晩年の絵画。
あの世に行くのが次のステージに進むかのように、隣の部屋へまたぐように移動する絵を描いて、実際のベーコンは死んだ。
肉体を人間のシンボルのように書きながら、そのことで肉体だけではない人間の存在を逆説的に表現していたのだろう。
ベーコンの死んだ肉体はあくまでも物質的な身体。ベーコンのエネルギー的な身体がどうなったかは、鑑賞者へゆだねられている。
・・・・・・・
展覧会の感想としてかけ離れたものになっているけれど、絵を見ながらこういうことをふと思った。

東京国立近代美術館で「フランシス・ベーコン展」を5/26までやっている。
意外に人がすいていた。早朝に行ったからかもしれない。
展覧会はとてもよかった。
フランシス・ベーコンは、相当に昔から好きな画家。同名の哲学者もいるが別人。
1909年-1992年。アイルランド生まれ。
画集は何冊か持っている。若い時期はよく眺めていた。
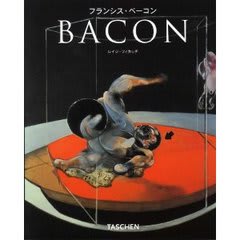
この人の作品はあまりに人気があって散在しているので、なかなか展覧会自体が行われない。
日本では1983年に回顧展があって、今回は30年ぶりらしい。
基本的に、ベーコンの絵には大量の毒が含まれている、と思う。
毒は、知らないうちに体に回ることもあるし、摂取したことを意識できないこともある。
ただ、毒は必ずしも悪を意味しない。そこに善悪は介在していない。
毒は生命エネルギーとのバランスで語られうるものだ。飲み込むことができるかどうかだ。
一つの物差しとして、毒は存在している。
毒を持って毒を制する、という言葉もある。
これはホメオパシーの原理に近い。
ホメオパシー自体が近代医学で否定されてしまった。近代医学や科学という名のものとに、多くのものが切り捨てられたが、そこに偏見や理性の落とし穴がある。
偏見はよくない。それは子供の存在が証明している。
ただ、弱い毒を摂取して自分の免疫反応を高めるという点では、ワクチンは似た考えに乗っ取っている。
ワクチンのように広く受け入れられるとその存在を疑いもしないことは多い。
それは「毒」も同じものだ。
岡本太郎の名著「自分の中に毒を持て」青春出版社 (1993/08) もそのことを示唆している。この本は高校生の時に20回くらい読んだ。思い出深い本だ。

■
ベーコンの絵は危険だ。毒がある。
毒には、この「現実」の見方を変える力がある。
もちろん、この「現実」は一層構造でない。
人間の「成長」の度合いに従って、この自然や宇宙は「現実」を薄皮一枚をはがすように、徐々に深い地層を人間に見せてくれる。
何事にも時期がある。物事には順番があり、階梯がある。
生のRealityにも層構造はある。
生は、生命活動の一面に過ぎない。
生命活動には「生」だけではなく「死」も含まれる。現代はなぜかここが抜け落ちていることが多い。
生も死も含まれた上で、生命活動は一巡し一周する。
死は悲しむべきものではない。生命活動の一つだ。
死において悲しむべきことは、自分がその相手に対して愛を表現できなかったこと、そういう自分の行為そのものが悲しむべき対象だ。
愛や思いを尽くせば、死と悲しみは必ずしもリンクしない。
エジプトの死者の書では、死んだときに最初に聞かれることは
「あなたの人生は喜びだったか?そして、人生の中で人に喜びを与えたか?」ということらしいと聞いた。このことは生と死の真理をついているように思う。


■
ベーコンの絵は、人間存在の深層構造をほのかに暗示している。
見える身体(皮膚や内臓も含め)だけではなく、見えない身体のことを暗示している。
「オーラ」という言葉で暗示される身体。身体のはみだし。そういう部分を扱っている。
ベーコンはもともとインテリアデザイナーだっただけに、色彩に関してもかなりのこだわりがあったことが見受けられる。
色彩の本質。
そのあたりが分かると、ベーコンの絵はさらに深く分かる。
■■■■■■■■■
■オーラ、エネルギー
aura(オーラ)という日常使う言葉は、深い。
通常の絵描は、絵画の対象にオーラは含まれている。
オーラは色として感知される。
色には力がある。
色を見るだけで心地よくもなり、不快にもなり、高揚もし、鬱々ともする。
色そのものの中に感情を動かすエネルギーが内在している。
1983年、英国でヴィッキー・ウォールによって「オーラソーマ」は生み出された。
オーラは「光」、ソーマは「身体」。
光(色)と身体の関係性を追求し、そのことを医療(ヒーリング)に応用したもの。

カラーセラピー自体は、古代エジプトや古代中国の文献にもある。
当時は医療への偏見は小さく、ありとあらゆる角度から医療やケアは探求されたのだろう。
現代では固定観念の元に、医療や芸術や・・・いろんな狭い分野に押し込められて分離されている。
ただ、基本的には人間の営みのプロセスの中に、色も治療も芸術も・・・すべてがあった。
オーラとは、エネルギーフィールド(気の場)のこととされる。
人体には、物質的な身体のほかにエネルギーとしての身体があり、重なっている。
これは人間を見ていくうえで非常に重要な観点だと思う。
量子力学で原子を物質と波動の重ね合わせ、として見る観点に近い。
エネルギー的な身体は、身体の外側に広がっているとされる。
エネルギーの層は物質的な身体の状態や感情、思考を映し出していて、そのことをオーラ(エネルギー的な身体)と呼んでいるようだ。
このことは誰もが直感的に感じているだろう。
「元気」だとか、「病気」だとか・・・、「気」が付く言葉に多い。誰かを見て直感的に感じる印象は、このエネルギー的な身体の共鳴だと思う。
このエネルギー的な身体のおかげで、物質的な身体を健康に保つことができる。
エネルギー的な身体には色々な名前がある。サトルボディ(微細な体)と言うこともある。
ちなみに、心理学者のユングも晩年はサトルボディを研究していた。

ちなみに、ヨガで鍛錬する「チャクラ」は、エネルギーの通り道であり、変電所、ターミナルのような場所。そこは伝統的に経験的に知られていたものだ。
チャクラは、サンスクリットで「車輪・円」を意味する。漢訳は「輪」(りん)、チベット語では「コルロ」(khorlo)という。
回転し、振動させ、循環させる。
チャクラ(車輪)とオーラには関係がある。
生体エネルギーはチャクラ(車輪)から取り込まれ、チャクラ(車輪)の回転による振動でエネルギーが循環する。それがオーラ(気の場)となり現れるとされる。
チャクラは色とも関係がある。虹の七色。
だから、ヨガという身体技法ではチャクラを整える。
それはエネルギーの流れをよくする。エネルギーで表現される第2の身体(サトルボディ)が健康であれば、いくら物理的な身体の故障が起きていても、健康で元気に生きていくことができる。
もちろん、理想的には物理的な身体もエネルギー的な身体も両方が健康なことだ。
若い時は意識しなくても両方保たれるが、年をとるとどちらもその人の意志や意識で保持していかないといけないものだ。



■色
「色」「色彩」に関して。
色の研究には二つの流れがある。
それはニュートンとゲーテの流れ。
ニュートンは、プリズム実験を通して、色の物理学的側面を探求。
それに対して、ゲーテは、色彩体験の主観的体験の現象学としての色彩論を探求。
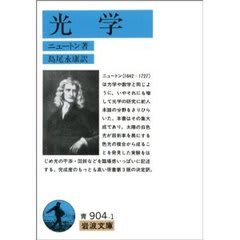

ニュートンは、光(光子)が目に入り、電気的な神経インパルスに変換され、大脳に伝わって起こる感覚を「色」とした。
ただ、その解釈だけで青空の美しさや朝焼けや夕焼けの美しさ、絵画の美しさは語れない、と自分は思う。
ゲーテは、「色」を一つの世界とした。
色はニュートンのように抽象化されるものではなく、体験するもの、と考えた。
シュタイナーは「色彩の本質」でそのことを的確に指摘している。
シュタイナーは、元々は著明なゲーテ研究家でもある。
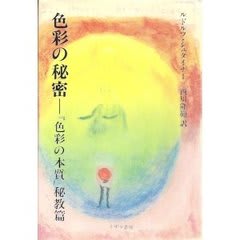
=============
シュタイナー「色彩の本質」(イザラ書房)
『理解しがたいことかもしれませんが、一度、色彩の真の意味を把握しようとしてみてください。
たとえば赤というのは、なにか攻撃的な色です。
赤の前を走り去ろうとすると、赤は人を突き返します。
青紫にむかって走ると、青紫はわたしたちから逃げ去り、ますます遠くなっていきます。
色彩のなかになにかが生きているのです。
色彩は一個の世界です。
心を込めて色彩を体験すると、 感動せずにはいられません。
そのように魂は、色彩世界のなかで自己を感じるのです。』
=============
『さまざまな自然界、死の世界と生命の世界と魂の世界と霊の世界とをとりあげるとき、
ちょうど私が死から生へ、生から魂へ、魂から霊へと昇るように、
黒から緑へ、桃色へ、白へと昇っていきます。
私が死から生を通って、魂と霊の世界へ昇っていけるように、
私が私を取りまく周囲の世界の中で、黒から緑へ、 桃色へ、白へと昇るとき、
私は私を取りまく周囲の世界を像として見いだすのです。
私はいろいろな現実世界の中でその現実世界を辿っていけます。
そして自然は私にこれらの現実世界の像をも与えてくれます。
自然はこれらの現実世界を像に変えます。
色彩の世界は現実の世界ではありません。
色彩の世界は自然そのものの中でさえも像なのです。
死の像は黒です。生の像は緑です。魂の像は桃色です。そして霊の像は白です。
このことによって私たちは色彩の客観的世界の中に導かれます。
色彩の本性、色彩の本質の中に入っていけるには、このことを前提にしなければなりません。
色彩が主観的な印象に過ぎない、と述べるだけでは何の役にも立たないのです。』
=============
『黄は外へ輝き、青は内へ輝き(輝きが内へ集まり)、
そして赤は両者を中和して、一様に輝きます。
この一様に輝くものを、運動する白と黒の中へ輝かせると桃色が生じます。
静止した白の方へ、一方では黄と他方では青とを照射させますと、緑が生じます。』
=============
『黄色は私たちを快活にします。
快活であるというのは、魂を大きな生命力で充たすことです。
ですから黄色によって、私たちは私たちの自我によりふさわしくなるのです。
別な言葉でいえば、私たちはより霊化されるのです。
黄色の根源的本性は外へ向かって拡がり、薄れていきます。
その輝きが今、皆さんの内部へ向けて輝くのです。
それが皆さんの内部で霊として輝くとき、
「黄色は霊の輝きの色である」、と皆さんは言うでしょう。
青色は内的に集中し、鬱積し、内的に持続します。それは魂の輝きです。
赤色は空間を一様に満たし、中心を保持します。それは生命の輝きです。』
=============
『わたしたちは色彩のなかに生き、感情によって色彩を理解します。
このようにして、色彩の世界の輝きと形象のなかに生きると、内的に、魂から画家になります。
色彩とともに生きることを学ぶからです。
個々の色がわたしたちに、なにを語ろうとしているかを感じとれるようになります。』
=============
赤は近づき、青は遠ざかる。
朝焼けや夕焼けのように、闇を通して光を見ると、赤く見える。
闇を通して見た光は、赤い。
一方、光を通して見た闇は、青い。
■
ベーコンの絵は、おそらくこういうことも示唆している、と自分は感じる。
絵を通して、人間の身体そのものを考える。エネルギーフィールドとしての身体を考える。
そこで色を感じ、色の独立した一つの世界を見る。
絵画を通して、結局それは鏡となり、自分のことを見ることになる。
ベーコンの絵に「箱」がよく出てくる。「箱」は、人間の「自我(ego)」の世界のように見える。
「自我(ego)」という狭い箱で苦しむ人間。それをベーコンは冷静に観察し、そういう人間の状況を描き出しているように見えた。
人間が顔面筋を収縮させて笑顔を演じていても、そこに悲しみや絶望が奥に見て取れるときには、そういうエネルギーとして発する悲しみの身体の方を描いていた、と思う。


晩年の絵画。
あの世に行くのが次のステージに進むかのように、隣の部屋へまたぐように移動する絵を描いて、実際のベーコンは死んだ。
肉体を人間のシンボルのように書きながら、そのことで肉体だけではない人間の存在を逆説的に表現していたのだろう。
ベーコンの死んだ肉体はあくまでも物質的な身体。ベーコンのエネルギー的な身体がどうなったかは、鑑賞者へゆだねられている。
・・・・・・・
展覧会の感想としてかけ離れたものになっているけれど、絵を見ながらこういうことをふと思った。










