
(今回のブログも途方もなく長いです・・)
佐々木閑さんの「犀の角たち」大蔵出版 (2006/07) を読みました。
仏教関係の本のはずだけれど、数学や科学の歴史の本としてもめちゃくちゃ勉強になった。
メモをしまくりで、どこまでブログで紹介したもんか、と思うほど、眼から鱗がポロポロと落ちまくりました。
→この本は、後に「科学するブッダ 犀の角たち」(角川ソフィア文庫:2013/10/25)として文庫化されました。
=================
<内容(「BOOK」データベースより)>
科学とはなにか?仏教とはなにか?まったく無関係にみえるこの問いの根底にある驚くべき共通点を、徹底した論理性だけを用いて解き明かす、知的冒険の書。
<著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)>
佐々木/閑
1956年、福井県生まれ。
福井県立藤島高校卒業。京都大学工学部工業化学科および文学部哲学科仏教学専攻卒業。
京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学後、米国カリフォルニア大学バークレー校に留学。
花園大学文学部講師、助教授を経て、教授。文学博士。
1992年、日本印度学仏教学会賞、2003年、鈴木学術財団特別賞受賞
=================
目次
序文
第一章 物理学
第二章 進化論
第三章 数学
付論 ペンローズ説の考察
第四章 釈尊、仏教
第五章 そして大乗
あとがき 未来の犀の角たちへ
=================
佐々木閑さんは、NHK「100分de名著」シリーズで『ブッダ 真理のことば』を担当されていた時に初めてご本人をお見かけしました。ブッダの言葉をとても分かりやすく説明されている姿に感銘。とてもいい番組でした。
その後、自宅にあった
〇「犀の角たち」大蔵出版 (2006/07)
〇「日々是修行 現代人のための仏教100話」ちくま新書(2009/5/9)
が同じ佐々木さんの著作だということを知り、一気に全部読んだのでした。
特に、この「犀の角たち」は山の中に持ち込んで人里離れた山中で読んだのでとても印象深く(⇒『2012年涸沢』(2012-07-18))。赤線や青線を引きまくりました。
この本では、ブッダの話の前に、まずは物理学(物の理コトワリを学ぶ)の歴史から幕をあけます。
■第一章 物理学
---------------------
デカルトは世界を精神と物質に二分し、物質世界の法則性だけを探求する科学という分野が誕生した。
感覚的経験よりも数学的確実性を重視して、探究のための言語として数学を用いた。
デカルトは座標平面を発明した。空間概念を数字でデジタル表記。
人類は、ものごとの「変化」を図形的な「あらわれ」として扱う事が可能になった。
---------------------
コペルニクスは、地動説の原型を示したがそれでパラダイムが一挙に変わったわけではない。
なぜ地動説で地球が動くか、という理由が不明確だった。
---------------------
その理論を出したのはイギリスの医師ギルバート。
1600年に『磁石論』を書き、ケプラー、ニュートンへと続く、天体運動論の基本概念を提示した。
ギルバートは、磁力と電気力を区別して考えた。
磁力を、神の知性による本源的霊力であると考えた。
地球そのものが一つの巨大な磁石で、その磁力が地球の活力と考えた。
---------------------
ギルバートのいう天体の磁力を、ケプラーは太陽や惑星が互いに引き合う力、重力だと解釈した。
くっつこうとする磁力と、つき動かそうとする不思議な力がバランスをとって楕円軌道が現れる。
そのつき動かす力は、太陽から出る運動霊とも呼ぶべきものが、遠い空間を瞬時に伝わるとした。
---------------------
ケプラーの法則で、その動きの美しさや法則の数学的端正さこそが、神の存在証明と考えた。
---------------------
その次に出たガリレイとデカルトは、ケプラーが導入した天体間の磁力(重力)も不思議な力も認めず、すべては機械論的に動いていると考えた。
---------------------
イギリスでは、ギルバート・ケプラーの遠隔力肯定説と、ガリレイ・デカルトの機械論的宇宙節とが微妙に並列していた。
そして、「遠隔力を要素に組み込んだ機械論的力学」という独自の力学体系がフック、ニュートンで完成していく。
---------------------
ニュートンは、重力の源を「神」と考えた。
ニュートン力学は偏在する神の力の数学的な表出だった。
この時代には、何らかの形で「神」が存在していた。
法則性の解明が、そのまま神の存在証明になりえた。
---------------------
→池内了さんの「物理学と神」集英社新書(2002/12/17)というものすごく面白い新書がありますが(ものすごくおすすめ! ちなみに、松岡正剛さんが詳細な書評を書かれています・・・)、当時の物理学者にとっては「神」という存在と物理学とはきっても切れない深い関係だったのです。
確かに、そもそも重力はどこから来たの?宇宙はどこからできたの?を考えていくと、「すべてをつくった何か(創造主)」を想定したくなるもので、「神」という抽象的なイメージとそこが重なるのだと思います。
・ギルバートは『磁力=神の知性による本源的霊力』であると考えていたし
・ケプラーは『天体をつき動かそうとする力=瞬時に伝わる太陽から出る運動霊』と考えていたし、
・ニュートンは『重力の源=神』と考えていました。
霊や神のような超越的な存在を前提として考える、その前提自体はあまりとやかく言われなかった時代だったんですよね。それだけ近い存在だったのでしょう。今はなんだか遠い存在になりました・・・。
そういえば、はじめてデカルト「方法序説」を読んだとき、あの本が最終的に神の存在証明をしようとしているのだ、と知って驚いたものでした。(そんなことは実際に読むまで知らなかった。)
ただ、デカルトが行う<神の存在証明>自体が
・・・・・
哲学の第一原理「ワレ惟(おも)ウ、故ニワレ在リ(Je pense, donc je suis.)」
まず、方法的懐疑を基本指針にしましょう。
そもそも、何かを疑う「わたし」は、疑っている時点ですでに不完全ですよね。
完全なもの(=神)は、不完全なもの(=わたし)から生じるわけがない。
<不完全なもの>は<完全なもの>から与えられたはずだろう。
だから<完全なもの>はある。
ということは、<神>は存在している。
・・・・・
みたいな証明が展開されていて、岩波文庫を読んだ時でも今でも、いまいち納得できなかったのを覚えています・・・(^^;
*****************
デカルト「方法序説」岩波文庫
「神と魂の観念を把握するのに想像力を用いようとする人たちは、
音を聞き匂いを嗅ぐために眼を用いようとする人と、まるで同じことをしていると思える」
*****************
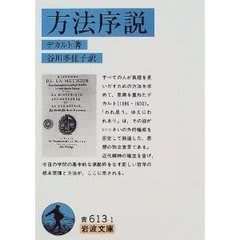
---------------------
パラダイムシフトとは、頭の中の直覚と、現実から得られる情報のせめぎ合いにおいて、直覚が負けて情報が勝つ、という現象だと考えることができる。
脳の生み出す理想世界が、現実を監査することで得られる外部情報で修正を迫られ、「いやだけど仕方がない」と軍門に下る事だ。
---------------------
→これは確かになるほどなぁ、と思いました。
僕らは「地動説」を知識としては知ってますが、太陽が東から登って西に沈むとき、「ああ、太陽は止まっているのに、自分たちが立っているこの地球は動いているなぁ」とは感じませんし、量子力学が言う「粒子と波の重なり合わせ」という概念も、実感として理解しにくいものです(映像での表現も困難)。
別の言い方をすれば、ヒトというシステムは「思い込み(偏見、先入観、固定観念・・)」で物事を見る性質が前提にある、ということでしょう。
それは差別や分離意識のはじまりにもなりえます。そこに意識的であった方が軌道修正しやすくていいです。
---------------------
ニュートンは、天体の磁力や太陽の運動霊と言った磁力の作用は否定し、重力と言う1種類の遠隔力で物体の運動を規定した。
磁力が科学的探索対象とされるのは18世紀のマイアーやクーロンの時代になってから。
---------------------
当時は「光」の扱いにも難渋していた。
ホイヘンスやフックは光を「波」と考え、波を伝える媒体として「エーテル」(最初の発案はデカルト!)が想定された。
ニュートンの時代、すでに光は特定の速度で伝わる物質的現象であることが承認されていた。
ニュートンは1704年『光学』を出して、「粒子説」を提唱した。
1800年にはヤングの「波動説」(2重スリットによる干渉現象の観察)が優勢となり、やがてアインシュタインらによって「波動と粒子の二重説」へと移る。
---------------------
1837年、マクスウェルは光と電磁波は実は同じものであるとし、光の数学的記述を完成させた。
---------------------
19世紀後半、マッハのフランス啓蒙思想により、科学は神の視点を離れて、人間認識を中心に現象を見るようになった。
---------------------
1905年、特殊相対性理論はアインシュタインが証明したが、ローレンツやポアンカレもギリギリのとこに来ていた。
アインシュタインが頭一つ出た理由は、エーテル(宇宙空間に充満していると考えられた物質)という概念を捨てたこと。
エーテルの概念を捨て去ったことで、絶対的な視点(神の視点)が消えて、すべては「相対的なもの」となった。
---------------------
1915年、一般相対性理論では、重力と言う遠隔力が、実は「時空間のねじれ」で引き起こされる一種の「場」であると示された。
---------------------
→こうして眺めると、科学の発展と共に「物の考え方」そのものが変わっていくのがとてもよくわかります。
より広く自由に捉えることができる歴史です。
すべての学門も「歴史」の視点で見ると、当時の人たちがどういう風に切実に乗り越えようとしたのか、その人類の流れがよく分かります。
特に「時間」と「空間」をどうとらえるか、というのが根本問題のようです。
ただ、夢や眠りの世界では「時間」や「空間」といった尺度がそもそも存在しません。死んだ後の世界でもそういう観念は存在しないらしいです。
科学が次に求めるのは、この辺りの世界(夢、眠り、死後・・・)をどう受け入れていくか、という段階なのかもしれませんね。(もちろん、インチキにもなりやすい。)
---------------------
アインシュタインの相対性理論は、ニュートン力学がいう<神の視点>を、<人間の視点>へと移し替えるきっかけになった。
人間それぞれが自分を中心にして時間と空間の基点を定めており、それは光という特定の媒介を用いた認識で決定される、とした。
ただ、「転変する外的世界を不変不動の意識世界が見る」という、「私が世界を見る」という構図は、実はニュートン力学でも相対性理論でも同じ。
---------------------
1900年にプランクが、量子化されたエネルギーというアイディアを世に出した。
エネルギーは連続ではなく、飛び飛びでしか移らない。
1905年、アインシュタインは電磁波(光)がとびとびのエネルギーでしか伝わらないという説を提示した。
1910年代、ボーアが原子の構造の体型を確立。
1925年、ハイゼンベルグは行列を内に含む量子数学を提唱。
前後の状況が分かっていても、観測していない時の状況については一切説明できない、というもの。
可能性の重なり合った状態として物が存在している、とされる。
観測の状況に応じて粒子だったり波だったりするが、観測していない時にどういう状態でいるかは分からない。
ヤングの二重スリットの実験では、観測行為に応じて世界のあり様が変わる、ということが分かった。
つまり、世界は本質的に不確定で、どう見えるかは観測者側の在り方が決める。
世の物事は常に確率的な存在である。
当時、そんな確率的な世界を指示するコペンハーゲン学派(ボーア、ハイゼンベルグ、パウリ・・)と、そのことを認めないアインシュタインは対立した。
---------------------
しかし、コペンハーゲン学派も「波の収縮」(波動がどうやって粒子に変わるのか、その変換の原理)に関しては解答できなかった。
---------------------
1957年、エベレットは「多世界解釈」を提唱した。(パラレルワールド)
つまり、不確定なのは観測の対象だけではなく、観測者自身も不確定であると考える。
量子論は、観測者の自己同一性も成り立たないと語るものだった。
---------------------
→つまりは「わたし」が世界を見る、という構図で前提となる、「わたし」自体も確率的に実態が解体されていく、ということでしょう。それは、まさに仏教の「縁起」、「空」、「無我」・・のようなものですね。
「わたし」が見た時点で、すでに世界は変わっているし、「わたし」そのものも変わっているので、ありのままの絶対的な世界を認識することはそもそも不可能である、というわけで・・・。
量子力学では、全てのものごとを確率として捉えます。
ただ、波と粒子が二重に同時存在しているとしたら、波の要素が消えて粒子としてだけこの世界が観測されるのか(=波の収縮)ということは解決できなかったんです。
その矛盾を解決する思考は「多世界解釈」(パラレルワールド)というもの。
全ての物事が確率的に存在しているのならば、わたしもあなたもこの世界もすべて確率的なものであって、確率的に瞬間瞬間に枝分かれしている(パラレルワールド)、、という途方もないアイディアです。
無限にある存在可能性の中で、一瞬一瞬が枝分かれする。自分が望む世界を常に選択し続けて枝分かれしている。
この辺りの考えは、精神世界での考えにも、一部が抽出されて取り上げられています。
村上春樹愛好家の自分は、すぐに村上春樹さんを思い出してしまうわけですが、「1Q84」でも青豆や天吾が迷い込む「1Q84」「猫の街」というパラレルワールド(多次元世界?)を思い出させる世界が出てきます。
*********************
村上春樹「1Q84 book3」
『深い孤独が昼を支配し、大きな猫たちが夜を支配する町のことだよ。
美しい河が流れ、古い石の橋がかかっている。
でもそこは僕らの留まるべき場所ではないよ。』
*********************
『暗い入口をこれ以上のぞき込まない方がいい。
そういうのは猫たちにまかせておけばいい。
そんなことをしたってあなたはどこにも行けない。
それよりも先のことを考えた方がいい』
*********************
『彼は自分が失われてしまっていることを知った。
ここは猫の町なんかじゃないんだ、と彼はようやく悟った。ここは彼が失われるべき場所だった。
それは彼自身のために用意された、この世ではない場所だった。
そして列車が、彼をもとの世界に連れ戻すために、その駅に停車することはもう永遠にないのだ』
*********************
村上春樹「1Q84」
『It’s Only A Paper Moon
Without your love
It's a honky-tonk parade
Without your love
It's a melody played in a penny arcade
It's a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me
君の愛がなければ
それはただの安物芝居に過ぎない
ここは見世物の世界
何から何までつくりもの
でも私を信じてくれたなら
全てが本物になる』
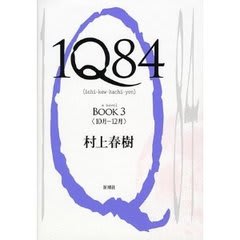
*********************
ショウペンハウエル
『蠅を叩たたきつぶしたところで、
蠅の「物そのもの」は死にはしない。
単に蠅の現象をつぶしたばかりだ。
*********************
萩原朔太郎「猫町」
『私は悪夢の中で夢を意識し、目ざめようとして努力しながら、必死にもがいている人のように、おそろしい予感の中で焦燥した。
空は透明に青く澄んで、充電した空気の密度は、いよいよ刻々に嵩まって来た。
建物は不安に歪んで、病気のように瘠せ細って来た。
所々に塔のような物が見え出して来た。
屋根も異様に細長く、瘠せた鶏の脚みたいに、へんに骨ばって畸形に見えた。
「今だ!」
と恐怖に胸を動悸しながら、思わず私が叫んだ時、或る小さな、黒い、鼠のような動物が、街の真中を走って行った。
私の眼には、それが実によくはっきりと映像された。
何かしら、そこには或る異常な、唐突な、全体の調和を破るような印象が感じられた。
瞬間。万象が急に静止し、底の知れない沈黙が横たわった。何事かわからなかった。
だが次の瞬間には、何人にも想像されない、世にも奇怪な、恐ろしい異変事が現象した。
見れば町の街路に充満して、猫の大集団がうようよと歩いているのだ。
猫、猫、猫、猫、猫、猫、猫。どこを見ても猫ばかりだ。
そして家々の窓口からは、髭ひげの生はえた猫の顔が、額縁の中の絵のようにして、大きく浮き出して現れていた。
戦慄から、私は殆んど息が止まり、正に昏倒するところであった。
これは人間の住む世界でなくて、猫ばかり住んでる町ではないのか。
一体どうしたと言うのだろう。こんな現象が信じられるものか。
たしかに今、私の頭脳はどうかしている。自分は幻影を見ているのだ。さもなければ狂気したのだ。
私自身の宇宙が、意識のバランスを失って崩壊したのだ。
*********************
■第二章 進化論
物理の歴史の次は、生命の歴史としての進化論が取り上げられます。
---------------------
史上初めて体系的に進化論を提唱したのはダーウィンではなく、ラマルク。
ダーウィンが「種の起源」を書く50年前に、ラマルクは神の意志とそれに応える生物側の思いがひとつになって進化が起こるとした。
同時代人のキュヴィエは生命の歴史に関しては天変地異説に立っていた(ノアの方舟伝説を科学的に解釈したようなもの)。
---------------------
1859年、ダーウィン「種の起源」出版。
ダーウィンは、若い時はビーグル号で5年間世界の海をまわり、その後に健康を害して田舎で45年間の静養生活をしながら書きあげた。
ダーウィンは<変異>と<自然淘汰>という2本柱。
1882年に亡くなり、その後1900年に遺伝に関するメンデルの法則が知られた。
---------------------
木村資生の進化の中立説。進化を厳密な数学で証明しようとした。
「良い変異」というものを考えず、遺伝子は変わりたい放題変わっていくが、生存に都合の悪いものだけが排除され、有害でも無害でもない中立のものが蓄積されるとした。
---------------------
ダーウィンは、自然淘汰で生き残った生物を最良品と見ていて、木村は進化の基本構造が中立であると捉えていた。
---------------------
→自分も木村資生さんの「進化の中立説」の方が性に合います。

ダーウィンは、「進化に有利なもの」が遺伝子として残り、そのことが進化としました。
そこに前提として「有利・不利」という概念が入りこんでいますが、そもそも「有利・不利」は「善・悪」と同じように人間の都合に合わせた考え方ですよね。それは結果論であり、見方の違いだと思うのです。
人間が「有利」とか「善」だとか解釈しただけ。
だからこそ、ダーウィンの考えは優生思想のように、反転されて悪用される可能性があるわけです。(優れた人類こそがこの地球に残っていく、それ以外は必要ない、というような選民思想や優生思想につながるわけです。)
物事はすべて中立でニュートラルなのだと思います。
それをイイとかワルイとか判断するのは人の都合であり、自然や宇宙そのものにはそもそも善も悪もなく、ただ無限に変化し続ける中立的な現象そのものがある、と思うわけです。そのことを明晰な意識状態でジャッジせずに観察し続ける行為が瞑想なのだと思いますし、『柳緑花紅真面目』(蘇東坡)のような禅の境地に近くなると思います。
***************
蘇東坡
「柳は緑、花は紅、真面目(しんめんもく)」
***************
一休
「見るほどに
みなそのままの姿かな
柳は緑 花は紅」
***************
■第三章 数学
物理、進化(生命)と続き、次は数学の思考方法に関してです。
---------------------
数学の画期的な変革点。
円周率π、無理数、ゼロ、複素数、非ユークリッド幾何学、実無限・・・などの概念。
---------------------
数学では直覚と論理思考という二つの力のせめぎあいで人間化が進んでいく。
---------------------
数学に証明を初めて持ちこんだのがピタゴラス派。
---------------------
16世紀のイタリア、方程式合戦の中で、虚数(二乗するとマイナスになる)が導入された。
虚数発見の主役は3人。
独学の万能エンジニアであるタルターニャ、
医者で数学者で文学者で先生術者でいかさまギャンブル研究家のカルダーノ、
カルダーノの弟子であるフェラーリ。
デカルトが虚数という名前を付け、ベルヌーイ、オイラーが発展させ、ガウスが複素平面を導入した。
複素数は四元数へと発展して量子力学とも関係してくる。
虚数は3次方程式を解く論理手続きで生まれ、300年かかって承認された。
---------------------
カントールは超限数を導入した。
無限を基調として、有限の壁を超えたところにある数のこと。
この世には色々な無限があり、あたかも「もの」であるかのように扱われるそれぞれの無限を「超限数」と呼ぶ。
無限はある手順をいつまでも繰り返す、ということを意味していたが、
無限を実体視して「もの」(実在する無限、実無限)があると考えたのはカントールが初めて。
数と数の関係から出発した数学が、実無限を扱う段階になって集合と集合の関係を扱う新たな段階に入った。
---------------------
数学の場合、物質世界からの情報で従来の概念が変更されることはなく、
精神内部の論理思考が次第に先鋭化して、それまでの体系でおさまりがつかなくなると、大きな概念の拡張が起こる。
---------------------
→数学は精神世界(精神の営み)の探求での究極の姿の気がします。意味化する以前の世界の探求。
ロマンがあって、かっこいいです。
---------------------
ヒルベルトは、特定の公理と論理作業を真理として仮定すれば、あとはその組み合わせですべての問題が機械的に解決される体系を求めた。
しかし、ゲーデルの不完全性定理が現れて、ヒルベルトの計画は絶対に完成しないことが証明されてしまった。
「その数学体系に矛盾がない場合、つまり完全である場合は、その体系を使って正しいということが証明できないような真理が必ず存在する。
矛盾がない数学体系では、その体系に矛盾がないという事を証明することはできない。」
このゲーデルの証明は、数年後にチューリングが別の形で証明した。
(チューリング機械の原理は、現在のコンピュータの大元になった原理)
---------------------
ポアンカレの科学論の基盤には、
「科学は人間が生み出したものだ。科学的真理は人間だけに適用されるものだ」
という思想が根本にある。
科学の中には、人間特有の認識方法、思考方法、総合方法が必ず含まれてしまう、ということ。
近代科学の歴史は、科学的真理が人間の視点から見たひとつの見解に過ぎない、ということを実証していく歴史だ、と考えていた。
---------------------
科学が生まれる過程。
単に外界を認識している段階
→何かしらの基本概念が身につく段階(例えば空間概念や時間概念など)
→最終的には全宇宙空間という概念が産み出され、それを外から眺める視点が生まれる(神の視点の第一歩)
→この世界にはたまたま固体が多い。空間内を自己の形状を変えず移動する<物体>という概念が生まれ、力学や幾何学の元になる。
→こういう事柄が積み重なると、空間や時間の概念が成立していく。
---------------------
論理思考の本質は数学的帰納法(k=1のときにある規則が成立し、k=Nのときにこの規則が成立するなら、必ずk=N+1においても成立する。そのことで、この規則はすべての整数で成立する。)である。
これは自然勝手に身につく思考法ではなく、習って初めて使えるようになる人工的な思考方法である。
説明すれば納得するが、納得できても感得はできない。
そのことで、有限の世界と無限の世界に橋をかけることができるようになった。
このことで、数学は単なる数の置き換えである算術の段階から、
真理を証明という武器で探り当てる冒険者の世界へと変貌した。
---------------------
こうして、世界の様相をできるだけ単純な規則に集約しようという科学一般の基本スタンスが生まれ、
原初的世界像しかもっていなかった人類に帰納法という特殊な論理思考が登場。
しかもそれが「不思議だけど本当だ」と皆に承認されたことで、人類は科学という独自の領域を獲得した。
---------------------
ポアンカレは、科学がそもそも人間存在に根差した形で、その体系内に矛盾がない形で創作された世界であるのに、たいていの人たちはそれに気付いておらず、あたかもそれが天与の真理であるかのように信じ込んでいるという点を認識していた。
---------------------
そのため、ポアンカレはカントールの集合論を、いづれは自己陳述の段階(自分自身をどうあらわすのか)で矛盾を引き起こす、と考えていた。
---------------------
トポロジーの生みの親であるポアンカレは、人間の肉体機能が持つ特殊性から幾何学が生まれてくる過程を説明した。
---------------------
→この辺りの論考はとてもスリリングで明快で面白すぎます!
科学が、人間の思考の枠内で考えられる限り、かならず枠内の限界に達する、ということ。
ポアンカレが指摘していることは、科学畑にいる自分も全く同様に思っています。いい面も悪い面もはっきり見えるものです。

科学で何か失敗したときも、納得できる言い訳も作れてしまう(そして聞き手もなぜか納得する)点も含め、それが雪だるま式に続くと、壮大な自己欺瞞(捏造、自作自演)の世界を作り出す危険性をはらんでいます。
その辺り(ホントがウソへとねじれていく分岐点)には常に慎重でありたいものです。前提は常に疑わないと気付けない。
この世界は人間だけのものではありません。色んな生命との共生です。
地球の人間視点で考える時代から、人類という生命の集合意識として未来を構想する時代の入り口にいます。
人間が宇宙に飛び出したのも、宇宙的な視点を得るためだったはずなのですが・・・。
手塚治虫が、横尾忠則さんとの対談!で指摘しています。
***************
横尾忠則「今、生きる秘訣―横尾忠則対話集」(2012-08-14)
横尾忠則+手塚治虫(宇宙文明の夜明け)
手塚『人間が本来持っている原初の本質的なものに戻るということもあるわけです。
一つには宇宙主義みたいな哲学的な思想だと思うんですよ。
僕は月が征服されたりしたときに少しずつ目覚めてくるかと思ったら、軍備競争ばかりにこだわってできなくなってしまった。
つまり、宇宙開発技術そのものも一種の軍備というものに置き換えられてしまった。
僕は、宇宙に飛び出して地球を一つの個として考える時点になったら、全然今までとは違った思想を持った若者が増えていくと思うんです。
それは、民族、国家、イデオロギーを超越した大きなものですね。』
***************
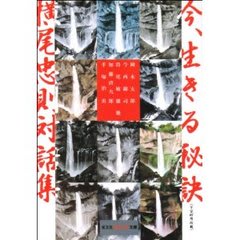
---------------------
<付論 ペンローズ説の考察>
数学的論理思考が現実世界と出会って軋轢を生じる場所。
物理学ではそういう場所がただ一か所ある。
それは、量子論における「波の収縮」である(ペンローズはこれを「量子飛躍」と言い、Rという記号で表示する)。
数学的思考では「可能性の重ね合わせ」としか表せないものが、現実の確定した事物として現れ来るのか、それは量子論では説明できない。
この「波の収縮」こそが計算不可能性の現れであり、物理理論のほころびとなっている。
意識を産み出す脳が計算不可能性を処理できる場所ならば、そこの未知の科学理論を解明する必要がある。
それは、脳ニューロン内部の微小管と呼ばれる部分を研究することで、新たな物理論が見つかるかもしれない。
---------------------
ペンローズは自分をプラトン主義だと言っているが、それは「神の視点を含んで世界が実在する」ことを信じているという意味。
---------------------
ただ、「波の収縮」を認める必要がないという「多世界解釈」が存在するので、この説とペンローズは真っ向から対立する。
---------------------

■第四章 釈尊、仏教
ついにブッダの話へ移ります。
---------------------
神の視点が次第に放棄されると、人間固有の世界観の中でしか生きられなくなる。
その先には絶対者のいない法則性だけの世界で、自己のアイデンティティーをどうやって確立していくか、という話になる。
仏教は常に分化分裂を繰り返し、きわめて多様な形態を含みこんだ複合的宗教になった。
そのことで、華厳経にフラクタルを見て、法華経に量子論を見て、宇宙論に曼荼羅を見るような、科学論を探せば何でも相似なものが見つかってしまう仏教の懐の広さがある。
ただ、仏教を何でも受け入れる寛容な宗教だと考える先に、他者を害する邪悪な行為でさえも必要悪と言う名目のもとに受け入れてしまう危険性が存在することには注意すべきである。
---------------------
『ヴェーダ』はインドに伝わる神の賛歌集だが、そこでは神々の力を借りて悪人どもを征服する正しき者たちのことをアーリア人と呼んでいる。
そこで、このインド・ヨーロッパ語族を使う人たちは便宜的にアーリア人と呼ばれることになった。
アーリア人がインド方面に持ち込んだ独自の文化が、インドで仏教が誕生する直接のきっかけになった。
アーリア人の侵入は現地人との間に摩擦を起こし、複雑な身分制度を作る。
支配者と被支配者の二重構造を基盤として成立するのがヴァルナという差別制度で、これがカースト制度の元になる。
神々との交信システムがバラモン教となり、ヒンドゥー教はその末裔。
そのヴァルナ制度を否定しようとして生まれてきたのが、仏教の創始者としてのブッダである。
---------------------
反バラモンの立場に立ち、生まれではなく努力にこそ人の価値があるとした人たちは、主張内容から「努力する人」と呼ばれ、インド語でシュラマナ。中国では「沙門」となった。
日本での「沙門」はお坊さんをさすが、元々はバラモン教に反対して、自分の努力で最高の幸福を手に入れようと考える修行者全てが「沙門」である。釈尊も沙門のひとり。
古代インドで起こった沙門宗教の中で、日本には仏教だけが入ってきた。(他にインドで残っているのはジャイナ教などがある。)
その努力の方法として苦行をするものもいたが、釈尊は苦行を伴わない純粋な瞑想、座禅という努力法を確立した。
仏教は、ひとりの指導者で全体が統制される中央集権機構を放棄し、律(お坊さんの法律)だけを行動規範とする極めて民主的な組織に変貌した。
---------------------
→仏教も当時では新しい思想として現れてきたもの。時代のあだ花のように。極めて前衛的だったと思います。
その原動力は、「カースト制度のように生まれつき差別されるのはおかしいだろう」という常識的で倫理的で良心的な声だったのだろうと思います。
その誰も超えようとしなかった高い壁を、努力や理性で超えていこうとしたのです。
---------------------
最初期の仏教の特性は、
1.超越者の存在を認めず、現象世界を法則性で説明する。
2.努力の領域を肉体ではなく、精神に限定する。
3.修行のシステムとして、出家者による集団生活体制をとり、一般社会の余り物をもらうことで生計を立てる。
---------------------
1.釈尊は、自分で道を切り開いた後に、みんながいるところにもう一度戻り、非力な他人を励ましながら連れていくようなリーダーの姿。
「自分は確かな安らぎへの道を見つけた。もし私を信頼するならばあとについてきなさい。途中でいくらでも手助けはするが、実際に歩くのは君たちだから、精一杯がんばりなさい」と励ます。
2.仏教は精神の解明された法則性に基づき、自己の精神における苦の消滅を目指す。
世界を理解した上でその理解に立脚して自己改造を目指す。日々に反復練習をするための具体的方法として瞑想をあげた。
仏教は神秘性が少ないが、自己の精神内部のみに神秘性を認めている。精神のレベルアップと言う現象として。
3.もし立派な人間として行動しないならば、たちまち皆の尊敬をなくし、布施の道は断たれる。
---------------------
釈尊時代の仏教は自己鍛錬の宗教である。
99%の合理精神と、自己の精神内部における1%の神秘から成り立っていて、その1%が仏教を宗教として成り立たせている。
悟りのプロセスにおける精神のレベルアップに関しては理論的説明がないため、それを最初から信じてかからなければいけない点が、仏教が宗教として存在している。
---------------------
釈尊が目指したのは、他の人たちに自分の体験を伝え、同じ方法で精神の向上を成功させることだった。
---------------------
→釈尊の教えは極めて論理的で明晰です。
そこでは偏見や固定観念を捨て去るため、知性をフル回転することが求められます。
日本での仏教があれだけの多様性を生んだのも、釈尊そのものの教えが精神の自由を求めた極めて重要性の高いものだったからだと思います。
<99%の合理精神と、自己の精神内部における1%の神秘>、1%の神秘性こそが仏教が科学ではなく宗教となっている、というのは素晴らしい表現。
■第五章 そして大乗
---------------------
新たに起こった大乗仏教では、我々自身が釈尊と同じ立場のリーダーになって、悟りへと導かねばならない、という思いが前面に出てくる。
---------------------
大乗では瞑想一本やりではなく、日常生活を基盤としてできた修行法の六波羅蜜行を推奨する。
その中でとくに重要視されたのが智慧の完成。つまり、般若波羅蜜。
六波羅蜜行:
①布施波羅蜜(檀那、ダーナ):分け与えること
②持戒波羅蜜(シーラ):戒律を守ること
③忍辱波羅蜜(クシャーンティ):耐え忍ぶこと。怒りを捨てること(慈悲)
④精進波羅蜜(ヴィーリヤ):努力すること
⑤禅定波羅蜜(ディヤーナ):特定の対象に心を集中して散乱する心を安定させること。
⑥智慧波羅蜜( 般若、プラジュニャー):物事(主に四念処)をありのままに観察する「観」によって、思考に依らない、本源的な智慧を発現させること。
---------------------
大乗仏教を形作る基本的枠組みでは並行世界のアイディアが最も重要。
この考えで、この世には釈尊以外にも無数の仏陀がいるはずだと考えられるようになり、数多くの仏陀や修行中の菩薩が作られていった。
---------------------
→
壮大な内容の本でしたが、物理、進化、生物学、数学、仏教と続き、最後に<大乗の教え>で終わります。
誰もが<釈尊と同じ立場のリーダーになろう>という提案として。
智慧の完成というものは科学も人類も求めていたものでしょう。その歴史が積み重なり、学問となり科学となったはずです。
・・・・・
ドライアイになりそうなほどこのブログに大量の情報量を詰め込みすぎましたが、これもひとえには自分の中で「智慧」を発展させていくプロセスの一環だとして許して下さい。
■あとがき 未来の犀の角たちへ
---------------------
ブッダ「スッタニパータ 六十八」
『究極の真理へと到達するために努力策励し、
心、ひるむことなく、行い、怠ることなく、
足取り堅固に、体力、知力を身につけて、
犀の角の如くただ独り歩め』
---------------------
→この言葉こそが、「犀の角たち」というタイトルに込められています。
学門も仕事もそうですが、真実や真理(ほんとのこと)を追求しようとすると色んな抵抗があります。
そのときには孤独な思いもするでしょう。
ただ、そんなときも「ほんとうのほんとう(by.宮沢賢治)を追求して、孤立を恐れるのではなく、孤独が孤高へ次元転換するよう自分を高め、『犀の角の如くただ独り歩む』勇気が必要な時もあるのだと思います。
そういう勇気ある人にこそ、ブッダは優しい眼差しを向けて暖かく見守ってくれるように思います。それこそが大乗への道の第一歩として。
この本は超名著です!!!
科学の畑にいる方は特に是非ご一読ください!
●補足:中村元訳『ブッダのことば』(岩波文庫)より

=====================
〈犀の角〉『スッタニパータ』
三五 あらゆる生きものに対して暴力を加えることなく、あらゆる生きもののいずれをも悩ますことなく、また子を欲するなかれ。況んや朋友をや。犀の角のようにただ独り歩め。
三六 交わりをしたならば愛情が生ずる。愛情にしたがってこの苦しみが起る。愛情から禍いの生ずることを観察して、犀の角のようにただ独り歩め。
三九 林の中で、縛られていない鹿が食物を求めて欲するところに赴くように、聡明な人は独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
四二 四方のどこにでも赴き、害心あることなく、何でも得たもので満足し、諸々の苦難に堪えて、恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
四五 もしも汝が、〈賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者〉を得たならば、あらゆる危難にうち勝ち、こころ喜び、気をおちつかせて、かれとともに歩め。
四六 しかしもしも汝が、〈賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者〉を得ないならぱ、譬えば王が征服した国を捨て去るようにして、犀の角のようにただ独り歩め。
四七 われらは実に朋友を得る幸を讃め称える。自分よりも勝れあるいは等しい朋友には、親しみ近づくべきである。このような朋友を得ることができなければ、罪過(つみとが)のない生活を楽しんで、犀の角のようにただ独り歩め。
四八 金の細工人がみごとに仕上げた二つの輝く黄金の腕輪を、一つの腕にはめれば、ぶつかり合う。それを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
四九 このように二人でいるならば、われに饒舌といさかいとが起るであろう。未来にこの恐れのあることを察して、犀の角のようにただ独り歩め。
五〇 実に欲望は色とりどりで甘美であり、心に楽しく、種々のかたちで、心を攪乱する。欲望の対象にはこの患いのあることを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
五一 これはわたくしにとって災害であり、腫物であり、禍であり、病であり、矢であり、恐怖である。諸々の欲望の対象にはこの恐ろしさのあることを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
五五 相争う哲学的見解を超え、(さとりに至る)決定に達し、道を得ている人は、「われは智慧が生じた。もはや他の人に指導される要がない」と知って、犀の角のようにただ独り歩め。
五六 貪ることなく、詐ることなく、渇望することなく、(見せかけで)覆うことなく、濁りと迷妄とを除き去り、全世界において妄執のないものとなって、犀の角のようにただ独り歩め。
五七 義ならざるものを見て邪曲にとらわれている悪い朋友を避けよ。貪りに耽り怠っている人に、みずから親しむな。犀の角のようにただ独り歩め。
五八 学識ゆたかで真理をわきまえ、高邁・明敏な友と交われ。いろいろと為になることがらを知り、疑惑を除き去って、犀の角のようにただ独り歩め。
六一 「これは執着である。ここには楽しみは少く、快い味わいも少くて、苦しみが多い。これは魚を釣る針である」と知って、賢者は、犀の角のようにただ独り歩め。
六八 最高の目的を達成するために努力策励し、こころが怯むことなく、行いに怠ることなく、堅固な活動をなし、体力と智力とを具え、犀の角のようにただ独り歩め。
七三 慈しみと平静とあわれみと解脱と喜びとを時に応じて修め、世間すべてに背くことなく、犀の角のようにただ独り歩め。
七四 貪欲と嫌悪と迷妄とを捨て、結び目を破り、命を失うのを恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
七五 今のひとびとは自分の利益のために交わりを結び、また他人に奉仕する。今日、利益をめざさない友は、得がたい。自分の利益のみを知る人間は、きたならしい。犀の角のようにただ独り歩め。
=====================
佐々木閑さんの「犀の角たち」大蔵出版 (2006/07) を読みました。
仏教関係の本のはずだけれど、数学や科学の歴史の本としてもめちゃくちゃ勉強になった。
メモをしまくりで、どこまでブログで紹介したもんか、と思うほど、眼から鱗がポロポロと落ちまくりました。
→この本は、後に「科学するブッダ 犀の角たち」(角川ソフィア文庫:2013/10/25)として文庫化されました。
=================
<内容(「BOOK」データベースより)>
科学とはなにか?仏教とはなにか?まったく無関係にみえるこの問いの根底にある驚くべき共通点を、徹底した論理性だけを用いて解き明かす、知的冒険の書。
<著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)>
佐々木/閑
1956年、福井県生まれ。
福井県立藤島高校卒業。京都大学工学部工業化学科および文学部哲学科仏教学専攻卒業。
京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学後、米国カリフォルニア大学バークレー校に留学。
花園大学文学部講師、助教授を経て、教授。文学博士。
1992年、日本印度学仏教学会賞、2003年、鈴木学術財団特別賞受賞
=================
目次
序文
第一章 物理学
第二章 進化論
第三章 数学
付論 ペンローズ説の考察
第四章 釈尊、仏教
第五章 そして大乗
あとがき 未来の犀の角たちへ
=================
佐々木閑さんは、NHK「100分de名著」シリーズで『ブッダ 真理のことば』を担当されていた時に初めてご本人をお見かけしました。ブッダの言葉をとても分かりやすく説明されている姿に感銘。とてもいい番組でした。
その後、自宅にあった
〇「犀の角たち」大蔵出版 (2006/07)
〇「日々是修行 現代人のための仏教100話」ちくま新書(2009/5/9)
が同じ佐々木さんの著作だということを知り、一気に全部読んだのでした。
特に、この「犀の角たち」は山の中に持ち込んで人里離れた山中で読んだのでとても印象深く(⇒『2012年涸沢』(2012-07-18))。赤線や青線を引きまくりました。
この本では、ブッダの話の前に、まずは物理学(物の理コトワリを学ぶ)の歴史から幕をあけます。
■第一章 物理学
---------------------
デカルトは世界を精神と物質に二分し、物質世界の法則性だけを探求する科学という分野が誕生した。
感覚的経験よりも数学的確実性を重視して、探究のための言語として数学を用いた。
デカルトは座標平面を発明した。空間概念を数字でデジタル表記。
人類は、ものごとの「変化」を図形的な「あらわれ」として扱う事が可能になった。
---------------------
コペルニクスは、地動説の原型を示したがそれでパラダイムが一挙に変わったわけではない。
なぜ地動説で地球が動くか、という理由が不明確だった。
---------------------
その理論を出したのはイギリスの医師ギルバート。
1600年に『磁石論』を書き、ケプラー、ニュートンへと続く、天体運動論の基本概念を提示した。
ギルバートは、磁力と電気力を区別して考えた。
磁力を、神の知性による本源的霊力であると考えた。
地球そのものが一つの巨大な磁石で、その磁力が地球の活力と考えた。
---------------------
ギルバートのいう天体の磁力を、ケプラーは太陽や惑星が互いに引き合う力、重力だと解釈した。
くっつこうとする磁力と、つき動かそうとする不思議な力がバランスをとって楕円軌道が現れる。
そのつき動かす力は、太陽から出る運動霊とも呼ぶべきものが、遠い空間を瞬時に伝わるとした。
---------------------
ケプラーの法則で、その動きの美しさや法則の数学的端正さこそが、神の存在証明と考えた。
---------------------
その次に出たガリレイとデカルトは、ケプラーが導入した天体間の磁力(重力)も不思議な力も認めず、すべては機械論的に動いていると考えた。
---------------------
イギリスでは、ギルバート・ケプラーの遠隔力肯定説と、ガリレイ・デカルトの機械論的宇宙節とが微妙に並列していた。
そして、「遠隔力を要素に組み込んだ機械論的力学」という独自の力学体系がフック、ニュートンで完成していく。
---------------------
ニュートンは、重力の源を「神」と考えた。
ニュートン力学は偏在する神の力の数学的な表出だった。
この時代には、何らかの形で「神」が存在していた。
法則性の解明が、そのまま神の存在証明になりえた。
---------------------
→池内了さんの「物理学と神」集英社新書(2002/12/17)というものすごく面白い新書がありますが(ものすごくおすすめ! ちなみに、松岡正剛さんが詳細な書評を書かれています・・・)、当時の物理学者にとっては「神」という存在と物理学とはきっても切れない深い関係だったのです。
確かに、そもそも重力はどこから来たの?宇宙はどこからできたの?を考えていくと、「すべてをつくった何か(創造主)」を想定したくなるもので、「神」という抽象的なイメージとそこが重なるのだと思います。
・ギルバートは『磁力=神の知性による本源的霊力』であると考えていたし
・ケプラーは『天体をつき動かそうとする力=瞬時に伝わる太陽から出る運動霊』と考えていたし、
・ニュートンは『重力の源=神』と考えていました。
霊や神のような超越的な存在を前提として考える、その前提自体はあまりとやかく言われなかった時代だったんですよね。それだけ近い存在だったのでしょう。今はなんだか遠い存在になりました・・・。
そういえば、はじめてデカルト「方法序説」を読んだとき、あの本が最終的に神の存在証明をしようとしているのだ、と知って驚いたものでした。(そんなことは実際に読むまで知らなかった。)
ただ、デカルトが行う<神の存在証明>自体が
・・・・・
哲学の第一原理「ワレ惟(おも)ウ、故ニワレ在リ(Je pense, donc je suis.)」
まず、方法的懐疑を基本指針にしましょう。
そもそも、何かを疑う「わたし」は、疑っている時点ですでに不完全ですよね。
完全なもの(=神)は、不完全なもの(=わたし)から生じるわけがない。
<不完全なもの>は<完全なもの>から与えられたはずだろう。
だから<完全なもの>はある。
ということは、<神>は存在している。
・・・・・
みたいな証明が展開されていて、岩波文庫を読んだ時でも今でも、いまいち納得できなかったのを覚えています・・・(^^;
*****************
デカルト「方法序説」岩波文庫
「神と魂の観念を把握するのに想像力を用いようとする人たちは、
音を聞き匂いを嗅ぐために眼を用いようとする人と、まるで同じことをしていると思える」
*****************
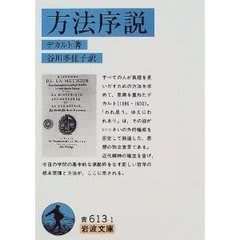
---------------------
パラダイムシフトとは、頭の中の直覚と、現実から得られる情報のせめぎ合いにおいて、直覚が負けて情報が勝つ、という現象だと考えることができる。
脳の生み出す理想世界が、現実を監査することで得られる外部情報で修正を迫られ、「いやだけど仕方がない」と軍門に下る事だ。
---------------------
→これは確かになるほどなぁ、と思いました。
僕らは「地動説」を知識としては知ってますが、太陽が東から登って西に沈むとき、「ああ、太陽は止まっているのに、自分たちが立っているこの地球は動いているなぁ」とは感じませんし、量子力学が言う「粒子と波の重なり合わせ」という概念も、実感として理解しにくいものです(映像での表現も困難)。
別の言い方をすれば、ヒトというシステムは「思い込み(偏見、先入観、固定観念・・)」で物事を見る性質が前提にある、ということでしょう。
それは差別や分離意識のはじまりにもなりえます。そこに意識的であった方が軌道修正しやすくていいです。
---------------------
ニュートンは、天体の磁力や太陽の運動霊と言った磁力の作用は否定し、重力と言う1種類の遠隔力で物体の運動を規定した。
磁力が科学的探索対象とされるのは18世紀のマイアーやクーロンの時代になってから。
---------------------
当時は「光」の扱いにも難渋していた。
ホイヘンスやフックは光を「波」と考え、波を伝える媒体として「エーテル」(最初の発案はデカルト!)が想定された。
ニュートンの時代、すでに光は特定の速度で伝わる物質的現象であることが承認されていた。
ニュートンは1704年『光学』を出して、「粒子説」を提唱した。
1800年にはヤングの「波動説」(2重スリットによる干渉現象の観察)が優勢となり、やがてアインシュタインらによって「波動と粒子の二重説」へと移る。
---------------------
1837年、マクスウェルは光と電磁波は実は同じものであるとし、光の数学的記述を完成させた。
---------------------
19世紀後半、マッハのフランス啓蒙思想により、科学は神の視点を離れて、人間認識を中心に現象を見るようになった。
---------------------
1905年、特殊相対性理論はアインシュタインが証明したが、ローレンツやポアンカレもギリギリのとこに来ていた。
アインシュタインが頭一つ出た理由は、エーテル(宇宙空間に充満していると考えられた物質)という概念を捨てたこと。
エーテルの概念を捨て去ったことで、絶対的な視点(神の視点)が消えて、すべては「相対的なもの」となった。
---------------------
1915年、一般相対性理論では、重力と言う遠隔力が、実は「時空間のねじれ」で引き起こされる一種の「場」であると示された。
---------------------
→こうして眺めると、科学の発展と共に「物の考え方」そのものが変わっていくのがとてもよくわかります。
より広く自由に捉えることができる歴史です。
すべての学門も「歴史」の視点で見ると、当時の人たちがどういう風に切実に乗り越えようとしたのか、その人類の流れがよく分かります。
特に「時間」と「空間」をどうとらえるか、というのが根本問題のようです。
ただ、夢や眠りの世界では「時間」や「空間」といった尺度がそもそも存在しません。死んだ後の世界でもそういう観念は存在しないらしいです。
科学が次に求めるのは、この辺りの世界(夢、眠り、死後・・・)をどう受け入れていくか、という段階なのかもしれませんね。(もちろん、インチキにもなりやすい。)
---------------------
アインシュタインの相対性理論は、ニュートン力学がいう<神の視点>を、<人間の視点>へと移し替えるきっかけになった。
人間それぞれが自分を中心にして時間と空間の基点を定めており、それは光という特定の媒介を用いた認識で決定される、とした。
ただ、「転変する外的世界を不変不動の意識世界が見る」という、「私が世界を見る」という構図は、実はニュートン力学でも相対性理論でも同じ。
---------------------
1900年にプランクが、量子化されたエネルギーというアイディアを世に出した。
エネルギーは連続ではなく、飛び飛びでしか移らない。
1905年、アインシュタインは電磁波(光)がとびとびのエネルギーでしか伝わらないという説を提示した。
1910年代、ボーアが原子の構造の体型を確立。
1925年、ハイゼンベルグは行列を内に含む量子数学を提唱。
前後の状況が分かっていても、観測していない時の状況については一切説明できない、というもの。
可能性の重なり合った状態として物が存在している、とされる。
観測の状況に応じて粒子だったり波だったりするが、観測していない時にどういう状態でいるかは分からない。
ヤングの二重スリットの実験では、観測行為に応じて世界のあり様が変わる、ということが分かった。
つまり、世界は本質的に不確定で、どう見えるかは観測者側の在り方が決める。
世の物事は常に確率的な存在である。
当時、そんな確率的な世界を指示するコペンハーゲン学派(ボーア、ハイゼンベルグ、パウリ・・)と、そのことを認めないアインシュタインは対立した。
---------------------
しかし、コペンハーゲン学派も「波の収縮」(波動がどうやって粒子に変わるのか、その変換の原理)に関しては解答できなかった。
---------------------
1957年、エベレットは「多世界解釈」を提唱した。(パラレルワールド)
つまり、不確定なのは観測の対象だけではなく、観測者自身も不確定であると考える。
量子論は、観測者の自己同一性も成り立たないと語るものだった。
---------------------
→つまりは「わたし」が世界を見る、という構図で前提となる、「わたし」自体も確率的に実態が解体されていく、ということでしょう。それは、まさに仏教の「縁起」、「空」、「無我」・・のようなものですね。
「わたし」が見た時点で、すでに世界は変わっているし、「わたし」そのものも変わっているので、ありのままの絶対的な世界を認識することはそもそも不可能である、というわけで・・・。
量子力学では、全てのものごとを確率として捉えます。
ただ、波と粒子が二重に同時存在しているとしたら、波の要素が消えて粒子としてだけこの世界が観測されるのか(=波の収縮)ということは解決できなかったんです。
その矛盾を解決する思考は「多世界解釈」(パラレルワールド)というもの。
全ての物事が確率的に存在しているのならば、わたしもあなたもこの世界もすべて確率的なものであって、確率的に瞬間瞬間に枝分かれしている(パラレルワールド)、、という途方もないアイディアです。
無限にある存在可能性の中で、一瞬一瞬が枝分かれする。自分が望む世界を常に選択し続けて枝分かれしている。
この辺りの考えは、精神世界での考えにも、一部が抽出されて取り上げられています。
村上春樹愛好家の自分は、すぐに村上春樹さんを思い出してしまうわけですが、「1Q84」でも青豆や天吾が迷い込む「1Q84」「猫の街」というパラレルワールド(多次元世界?)を思い出させる世界が出てきます。
*********************
村上春樹「1Q84 book3」
『深い孤独が昼を支配し、大きな猫たちが夜を支配する町のことだよ。
美しい河が流れ、古い石の橋がかかっている。
でもそこは僕らの留まるべき場所ではないよ。』
*********************
『暗い入口をこれ以上のぞき込まない方がいい。
そういうのは猫たちにまかせておけばいい。
そんなことをしたってあなたはどこにも行けない。
それよりも先のことを考えた方がいい』
*********************
『彼は自分が失われてしまっていることを知った。
ここは猫の町なんかじゃないんだ、と彼はようやく悟った。ここは彼が失われるべき場所だった。
それは彼自身のために用意された、この世ではない場所だった。
そして列車が、彼をもとの世界に連れ戻すために、その駅に停車することはもう永遠にないのだ』
*********************
村上春樹「1Q84」
『It’s Only A Paper Moon
Without your love
It's a honky-tonk parade
Without your love
It's a melody played in a penny arcade
It's a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me
君の愛がなければ
それはただの安物芝居に過ぎない
ここは見世物の世界
何から何までつくりもの
でも私を信じてくれたなら
全てが本物になる』
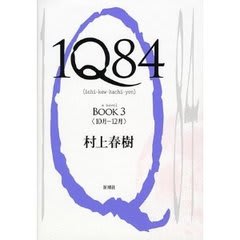
*********************
ショウペンハウエル
『蠅を叩たたきつぶしたところで、
蠅の「物そのもの」は死にはしない。
単に蠅の現象をつぶしたばかりだ。
*********************
萩原朔太郎「猫町」
『私は悪夢の中で夢を意識し、目ざめようとして努力しながら、必死にもがいている人のように、おそろしい予感の中で焦燥した。
空は透明に青く澄んで、充電した空気の密度は、いよいよ刻々に嵩まって来た。
建物は不安に歪んで、病気のように瘠せ細って来た。
所々に塔のような物が見え出して来た。
屋根も異様に細長く、瘠せた鶏の脚みたいに、へんに骨ばって畸形に見えた。
「今だ!」
と恐怖に胸を動悸しながら、思わず私が叫んだ時、或る小さな、黒い、鼠のような動物が、街の真中を走って行った。
私の眼には、それが実によくはっきりと映像された。
何かしら、そこには或る異常な、唐突な、全体の調和を破るような印象が感じられた。
瞬間。万象が急に静止し、底の知れない沈黙が横たわった。何事かわからなかった。
だが次の瞬間には、何人にも想像されない、世にも奇怪な、恐ろしい異変事が現象した。
見れば町の街路に充満して、猫の大集団がうようよと歩いているのだ。
猫、猫、猫、猫、猫、猫、猫。どこを見ても猫ばかりだ。
そして家々の窓口からは、髭ひげの生はえた猫の顔が、額縁の中の絵のようにして、大きく浮き出して現れていた。
戦慄から、私は殆んど息が止まり、正に昏倒するところであった。
これは人間の住む世界でなくて、猫ばかり住んでる町ではないのか。
一体どうしたと言うのだろう。こんな現象が信じられるものか。
たしかに今、私の頭脳はどうかしている。自分は幻影を見ているのだ。さもなければ狂気したのだ。
私自身の宇宙が、意識のバランスを失って崩壊したのだ。
*********************
■第二章 進化論
物理の歴史の次は、生命の歴史としての進化論が取り上げられます。
---------------------
史上初めて体系的に進化論を提唱したのはダーウィンではなく、ラマルク。
ダーウィンが「種の起源」を書く50年前に、ラマルクは神の意志とそれに応える生物側の思いがひとつになって進化が起こるとした。
同時代人のキュヴィエは生命の歴史に関しては天変地異説に立っていた(ノアの方舟伝説を科学的に解釈したようなもの)。
---------------------
1859年、ダーウィン「種の起源」出版。
ダーウィンは、若い時はビーグル号で5年間世界の海をまわり、その後に健康を害して田舎で45年間の静養生活をしながら書きあげた。
ダーウィンは<変異>と<自然淘汰>という2本柱。
1882年に亡くなり、その後1900年に遺伝に関するメンデルの法則が知られた。
---------------------
木村資生の進化の中立説。進化を厳密な数学で証明しようとした。
「良い変異」というものを考えず、遺伝子は変わりたい放題変わっていくが、生存に都合の悪いものだけが排除され、有害でも無害でもない中立のものが蓄積されるとした。
---------------------
ダーウィンは、自然淘汰で生き残った生物を最良品と見ていて、木村は進化の基本構造が中立であると捉えていた。
---------------------
→自分も木村資生さんの「進化の中立説」の方が性に合います。

ダーウィンは、「進化に有利なもの」が遺伝子として残り、そのことが進化としました。
そこに前提として「有利・不利」という概念が入りこんでいますが、そもそも「有利・不利」は「善・悪」と同じように人間の都合に合わせた考え方ですよね。それは結果論であり、見方の違いだと思うのです。
人間が「有利」とか「善」だとか解釈しただけ。
だからこそ、ダーウィンの考えは優生思想のように、反転されて悪用される可能性があるわけです。(優れた人類こそがこの地球に残っていく、それ以外は必要ない、というような選民思想や優生思想につながるわけです。)
物事はすべて中立でニュートラルなのだと思います。
それをイイとかワルイとか判断するのは人の都合であり、自然や宇宙そのものにはそもそも善も悪もなく、ただ無限に変化し続ける中立的な現象そのものがある、と思うわけです。そのことを明晰な意識状態でジャッジせずに観察し続ける行為が瞑想なのだと思いますし、『柳緑花紅真面目』(蘇東坡)のような禅の境地に近くなると思います。
***************
蘇東坡
「柳は緑、花は紅、真面目(しんめんもく)」
***************
一休
「見るほどに
みなそのままの姿かな
柳は緑 花は紅」
***************
■第三章 数学
物理、進化(生命)と続き、次は数学の思考方法に関してです。
---------------------
数学の画期的な変革点。
円周率π、無理数、ゼロ、複素数、非ユークリッド幾何学、実無限・・・などの概念。
---------------------
数学では直覚と論理思考という二つの力のせめぎあいで人間化が進んでいく。
---------------------
数学に証明を初めて持ちこんだのがピタゴラス派。
---------------------
16世紀のイタリア、方程式合戦の中で、虚数(二乗するとマイナスになる)が導入された。
虚数発見の主役は3人。
独学の万能エンジニアであるタルターニャ、
医者で数学者で文学者で先生術者でいかさまギャンブル研究家のカルダーノ、
カルダーノの弟子であるフェラーリ。
デカルトが虚数という名前を付け、ベルヌーイ、オイラーが発展させ、ガウスが複素平面を導入した。
複素数は四元数へと発展して量子力学とも関係してくる。
虚数は3次方程式を解く論理手続きで生まれ、300年かかって承認された。
---------------------
カントールは超限数を導入した。
無限を基調として、有限の壁を超えたところにある数のこと。
この世には色々な無限があり、あたかも「もの」であるかのように扱われるそれぞれの無限を「超限数」と呼ぶ。
無限はある手順をいつまでも繰り返す、ということを意味していたが、
無限を実体視して「もの」(実在する無限、実無限)があると考えたのはカントールが初めて。
数と数の関係から出発した数学が、実無限を扱う段階になって集合と集合の関係を扱う新たな段階に入った。
---------------------
数学の場合、物質世界からの情報で従来の概念が変更されることはなく、
精神内部の論理思考が次第に先鋭化して、それまでの体系でおさまりがつかなくなると、大きな概念の拡張が起こる。
---------------------
→数学は精神世界(精神の営み)の探求での究極の姿の気がします。意味化する以前の世界の探求。
ロマンがあって、かっこいいです。
---------------------
ヒルベルトは、特定の公理と論理作業を真理として仮定すれば、あとはその組み合わせですべての問題が機械的に解決される体系を求めた。
しかし、ゲーデルの不完全性定理が現れて、ヒルベルトの計画は絶対に完成しないことが証明されてしまった。
「その数学体系に矛盾がない場合、つまり完全である場合は、その体系を使って正しいということが証明できないような真理が必ず存在する。
矛盾がない数学体系では、その体系に矛盾がないという事を証明することはできない。」
このゲーデルの証明は、数年後にチューリングが別の形で証明した。
(チューリング機械の原理は、現在のコンピュータの大元になった原理)
---------------------
ポアンカレの科学論の基盤には、
「科学は人間が生み出したものだ。科学的真理は人間だけに適用されるものだ」
という思想が根本にある。
科学の中には、人間特有の認識方法、思考方法、総合方法が必ず含まれてしまう、ということ。
近代科学の歴史は、科学的真理が人間の視点から見たひとつの見解に過ぎない、ということを実証していく歴史だ、と考えていた。
---------------------
科学が生まれる過程。
単に外界を認識している段階
→何かしらの基本概念が身につく段階(例えば空間概念や時間概念など)
→最終的には全宇宙空間という概念が産み出され、それを外から眺める視点が生まれる(神の視点の第一歩)
→この世界にはたまたま固体が多い。空間内を自己の形状を変えず移動する<物体>という概念が生まれ、力学や幾何学の元になる。
→こういう事柄が積み重なると、空間や時間の概念が成立していく。
---------------------
論理思考の本質は数学的帰納法(k=1のときにある規則が成立し、k=Nのときにこの規則が成立するなら、必ずk=N+1においても成立する。そのことで、この規則はすべての整数で成立する。)である。
これは自然勝手に身につく思考法ではなく、習って初めて使えるようになる人工的な思考方法である。
説明すれば納得するが、納得できても感得はできない。
そのことで、有限の世界と無限の世界に橋をかけることができるようになった。
このことで、数学は単なる数の置き換えである算術の段階から、
真理を証明という武器で探り当てる冒険者の世界へと変貌した。
---------------------
こうして、世界の様相をできるだけ単純な規則に集約しようという科学一般の基本スタンスが生まれ、
原初的世界像しかもっていなかった人類に帰納法という特殊な論理思考が登場。
しかもそれが「不思議だけど本当だ」と皆に承認されたことで、人類は科学という独自の領域を獲得した。
---------------------
ポアンカレは、科学がそもそも人間存在に根差した形で、その体系内に矛盾がない形で創作された世界であるのに、たいていの人たちはそれに気付いておらず、あたかもそれが天与の真理であるかのように信じ込んでいるという点を認識していた。
---------------------
そのため、ポアンカレはカントールの集合論を、いづれは自己陳述の段階(自分自身をどうあらわすのか)で矛盾を引き起こす、と考えていた。
---------------------
トポロジーの生みの親であるポアンカレは、人間の肉体機能が持つ特殊性から幾何学が生まれてくる過程を説明した。
---------------------
→この辺りの論考はとてもスリリングで明快で面白すぎます!
科学が、人間の思考の枠内で考えられる限り、かならず枠内の限界に達する、ということ。
ポアンカレが指摘していることは、科学畑にいる自分も全く同様に思っています。いい面も悪い面もはっきり見えるものです。

科学で何か失敗したときも、納得できる言い訳も作れてしまう(そして聞き手もなぜか納得する)点も含め、それが雪だるま式に続くと、壮大な自己欺瞞(捏造、自作自演)の世界を作り出す危険性をはらんでいます。
その辺り(ホントがウソへとねじれていく分岐点)には常に慎重でありたいものです。前提は常に疑わないと気付けない。
この世界は人間だけのものではありません。色んな生命との共生です。
地球の人間視点で考える時代から、人類という生命の集合意識として未来を構想する時代の入り口にいます。
人間が宇宙に飛び出したのも、宇宙的な視点を得るためだったはずなのですが・・・。
手塚治虫が、横尾忠則さんとの対談!で指摘しています。
***************
横尾忠則「今、生きる秘訣―横尾忠則対話集」(2012-08-14)
横尾忠則+手塚治虫(宇宙文明の夜明け)
手塚『人間が本来持っている原初の本質的なものに戻るということもあるわけです。
一つには宇宙主義みたいな哲学的な思想だと思うんですよ。
僕は月が征服されたりしたときに少しずつ目覚めてくるかと思ったら、軍備競争ばかりにこだわってできなくなってしまった。
つまり、宇宙開発技術そのものも一種の軍備というものに置き換えられてしまった。
僕は、宇宙に飛び出して地球を一つの個として考える時点になったら、全然今までとは違った思想を持った若者が増えていくと思うんです。
それは、民族、国家、イデオロギーを超越した大きなものですね。』
***************
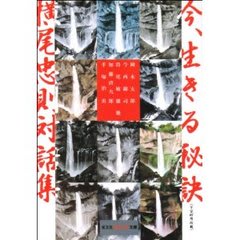
---------------------
<付論 ペンローズ説の考察>
数学的論理思考が現実世界と出会って軋轢を生じる場所。
物理学ではそういう場所がただ一か所ある。
それは、量子論における「波の収縮」である(ペンローズはこれを「量子飛躍」と言い、Rという記号で表示する)。
数学的思考では「可能性の重ね合わせ」としか表せないものが、現実の確定した事物として現れ来るのか、それは量子論では説明できない。
この「波の収縮」こそが計算不可能性の現れであり、物理理論のほころびとなっている。
意識を産み出す脳が計算不可能性を処理できる場所ならば、そこの未知の科学理論を解明する必要がある。
それは、脳ニューロン内部の微小管と呼ばれる部分を研究することで、新たな物理論が見つかるかもしれない。
---------------------
ペンローズは自分をプラトン主義だと言っているが、それは「神の視点を含んで世界が実在する」ことを信じているという意味。
---------------------
ただ、「波の収縮」を認める必要がないという「多世界解釈」が存在するので、この説とペンローズは真っ向から対立する。
---------------------

■第四章 釈尊、仏教
ついにブッダの話へ移ります。
---------------------
神の視点が次第に放棄されると、人間固有の世界観の中でしか生きられなくなる。
その先には絶対者のいない法則性だけの世界で、自己のアイデンティティーをどうやって確立していくか、という話になる。
仏教は常に分化分裂を繰り返し、きわめて多様な形態を含みこんだ複合的宗教になった。
そのことで、華厳経にフラクタルを見て、法華経に量子論を見て、宇宙論に曼荼羅を見るような、科学論を探せば何でも相似なものが見つかってしまう仏教の懐の広さがある。
ただ、仏教を何でも受け入れる寛容な宗教だと考える先に、他者を害する邪悪な行為でさえも必要悪と言う名目のもとに受け入れてしまう危険性が存在することには注意すべきである。
---------------------
『ヴェーダ』はインドに伝わる神の賛歌集だが、そこでは神々の力を借りて悪人どもを征服する正しき者たちのことをアーリア人と呼んでいる。
そこで、このインド・ヨーロッパ語族を使う人たちは便宜的にアーリア人と呼ばれることになった。
アーリア人がインド方面に持ち込んだ独自の文化が、インドで仏教が誕生する直接のきっかけになった。
アーリア人の侵入は現地人との間に摩擦を起こし、複雑な身分制度を作る。
支配者と被支配者の二重構造を基盤として成立するのがヴァルナという差別制度で、これがカースト制度の元になる。
神々との交信システムがバラモン教となり、ヒンドゥー教はその末裔。
そのヴァルナ制度を否定しようとして生まれてきたのが、仏教の創始者としてのブッダである。
---------------------
反バラモンの立場に立ち、生まれではなく努力にこそ人の価値があるとした人たちは、主張内容から「努力する人」と呼ばれ、インド語でシュラマナ。中国では「沙門」となった。
日本での「沙門」はお坊さんをさすが、元々はバラモン教に反対して、自分の努力で最高の幸福を手に入れようと考える修行者全てが「沙門」である。釈尊も沙門のひとり。
古代インドで起こった沙門宗教の中で、日本には仏教だけが入ってきた。(他にインドで残っているのはジャイナ教などがある。)
その努力の方法として苦行をするものもいたが、釈尊は苦行を伴わない純粋な瞑想、座禅という努力法を確立した。
仏教は、ひとりの指導者で全体が統制される中央集権機構を放棄し、律(お坊さんの法律)だけを行動規範とする極めて民主的な組織に変貌した。
---------------------
→仏教も当時では新しい思想として現れてきたもの。時代のあだ花のように。極めて前衛的だったと思います。
その原動力は、「カースト制度のように生まれつき差別されるのはおかしいだろう」という常識的で倫理的で良心的な声だったのだろうと思います。
その誰も超えようとしなかった高い壁を、努力や理性で超えていこうとしたのです。
---------------------
最初期の仏教の特性は、
1.超越者の存在を認めず、現象世界を法則性で説明する。
2.努力の領域を肉体ではなく、精神に限定する。
3.修行のシステムとして、出家者による集団生活体制をとり、一般社会の余り物をもらうことで生計を立てる。
---------------------
1.釈尊は、自分で道を切り開いた後に、みんながいるところにもう一度戻り、非力な他人を励ましながら連れていくようなリーダーの姿。
「自分は確かな安らぎへの道を見つけた。もし私を信頼するならばあとについてきなさい。途中でいくらでも手助けはするが、実際に歩くのは君たちだから、精一杯がんばりなさい」と励ます。
2.仏教は精神の解明された法則性に基づき、自己の精神における苦の消滅を目指す。
世界を理解した上でその理解に立脚して自己改造を目指す。日々に反復練習をするための具体的方法として瞑想をあげた。
仏教は神秘性が少ないが、自己の精神内部のみに神秘性を認めている。精神のレベルアップと言う現象として。
3.もし立派な人間として行動しないならば、たちまち皆の尊敬をなくし、布施の道は断たれる。
---------------------
釈尊時代の仏教は自己鍛錬の宗教である。
99%の合理精神と、自己の精神内部における1%の神秘から成り立っていて、その1%が仏教を宗教として成り立たせている。
悟りのプロセスにおける精神のレベルアップに関しては理論的説明がないため、それを最初から信じてかからなければいけない点が、仏教が宗教として存在している。
---------------------
釈尊が目指したのは、他の人たちに自分の体験を伝え、同じ方法で精神の向上を成功させることだった。
---------------------
→釈尊の教えは極めて論理的で明晰です。
そこでは偏見や固定観念を捨て去るため、知性をフル回転することが求められます。
日本での仏教があれだけの多様性を生んだのも、釈尊そのものの教えが精神の自由を求めた極めて重要性の高いものだったからだと思います。
<99%の合理精神と、自己の精神内部における1%の神秘>、1%の神秘性こそが仏教が科学ではなく宗教となっている、というのは素晴らしい表現。
■第五章 そして大乗
---------------------
新たに起こった大乗仏教では、我々自身が釈尊と同じ立場のリーダーになって、悟りへと導かねばならない、という思いが前面に出てくる。
---------------------
大乗では瞑想一本やりではなく、日常生活を基盤としてできた修行法の六波羅蜜行を推奨する。
その中でとくに重要視されたのが智慧の完成。つまり、般若波羅蜜。
六波羅蜜行:
①布施波羅蜜(檀那、ダーナ):分け与えること
②持戒波羅蜜(シーラ):戒律を守ること
③忍辱波羅蜜(クシャーンティ):耐え忍ぶこと。怒りを捨てること(慈悲)
④精進波羅蜜(ヴィーリヤ):努力すること
⑤禅定波羅蜜(ディヤーナ):特定の対象に心を集中して散乱する心を安定させること。
⑥智慧波羅蜜( 般若、プラジュニャー):物事(主に四念処)をありのままに観察する「観」によって、思考に依らない、本源的な智慧を発現させること。
---------------------
大乗仏教を形作る基本的枠組みでは並行世界のアイディアが最も重要。
この考えで、この世には釈尊以外にも無数の仏陀がいるはずだと考えられるようになり、数多くの仏陀や修行中の菩薩が作られていった。
---------------------
→
壮大な内容の本でしたが、物理、進化、生物学、数学、仏教と続き、最後に<大乗の教え>で終わります。
誰もが<釈尊と同じ立場のリーダーになろう>という提案として。
智慧の完成というものは科学も人類も求めていたものでしょう。その歴史が積み重なり、学問となり科学となったはずです。
・・・・・
ドライアイになりそうなほどこのブログに大量の情報量を詰め込みすぎましたが、これもひとえには自分の中で「智慧」を発展させていくプロセスの一環だとして許して下さい。
■あとがき 未来の犀の角たちへ
---------------------
ブッダ「スッタニパータ 六十八」
『究極の真理へと到達するために努力策励し、
心、ひるむことなく、行い、怠ることなく、
足取り堅固に、体力、知力を身につけて、
犀の角の如くただ独り歩め』
---------------------
→この言葉こそが、「犀の角たち」というタイトルに込められています。
学門も仕事もそうですが、真実や真理(ほんとのこと)を追求しようとすると色んな抵抗があります。
そのときには孤独な思いもするでしょう。
ただ、そんなときも「ほんとうのほんとう(by.宮沢賢治)を追求して、孤立を恐れるのではなく、孤独が孤高へ次元転換するよう自分を高め、『犀の角の如くただ独り歩む』勇気が必要な時もあるのだと思います。
そういう勇気ある人にこそ、ブッダは優しい眼差しを向けて暖かく見守ってくれるように思います。それこそが大乗への道の第一歩として。
この本は超名著です!!!
科学の畑にいる方は特に是非ご一読ください!
●補足:中村元訳『ブッダのことば』(岩波文庫)より

=====================
〈犀の角〉『スッタニパータ』
三五 あらゆる生きものに対して暴力を加えることなく、あらゆる生きもののいずれをも悩ますことなく、また子を欲するなかれ。況んや朋友をや。犀の角のようにただ独り歩め。
三六 交わりをしたならば愛情が生ずる。愛情にしたがってこの苦しみが起る。愛情から禍いの生ずることを観察して、犀の角のようにただ独り歩め。
三九 林の中で、縛られていない鹿が食物を求めて欲するところに赴くように、聡明な人は独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
四二 四方のどこにでも赴き、害心あることなく、何でも得たもので満足し、諸々の苦難に堪えて、恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
四五 もしも汝が、〈賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者〉を得たならば、あらゆる危難にうち勝ち、こころ喜び、気をおちつかせて、かれとともに歩め。
四六 しかしもしも汝が、〈賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者〉を得ないならぱ、譬えば王が征服した国を捨て去るようにして、犀の角のようにただ独り歩め。
四七 われらは実に朋友を得る幸を讃め称える。自分よりも勝れあるいは等しい朋友には、親しみ近づくべきである。このような朋友を得ることができなければ、罪過(つみとが)のない生活を楽しんで、犀の角のようにただ独り歩め。
四八 金の細工人がみごとに仕上げた二つの輝く黄金の腕輪を、一つの腕にはめれば、ぶつかり合う。それを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
四九 このように二人でいるならば、われに饒舌といさかいとが起るであろう。未来にこの恐れのあることを察して、犀の角のようにただ独り歩め。
五〇 実に欲望は色とりどりで甘美であり、心に楽しく、種々のかたちで、心を攪乱する。欲望の対象にはこの患いのあることを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
五一 これはわたくしにとって災害であり、腫物であり、禍であり、病であり、矢であり、恐怖である。諸々の欲望の対象にはこの恐ろしさのあることを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
五五 相争う哲学的見解を超え、(さとりに至る)決定に達し、道を得ている人は、「われは智慧が生じた。もはや他の人に指導される要がない」と知って、犀の角のようにただ独り歩め。
五六 貪ることなく、詐ることなく、渇望することなく、(見せかけで)覆うことなく、濁りと迷妄とを除き去り、全世界において妄執のないものとなって、犀の角のようにただ独り歩め。
五七 義ならざるものを見て邪曲にとらわれている悪い朋友を避けよ。貪りに耽り怠っている人に、みずから親しむな。犀の角のようにただ独り歩め。
五八 学識ゆたかで真理をわきまえ、高邁・明敏な友と交われ。いろいろと為になることがらを知り、疑惑を除き去って、犀の角のようにただ独り歩め。
六一 「これは執着である。ここには楽しみは少く、快い味わいも少くて、苦しみが多い。これは魚を釣る針である」と知って、賢者は、犀の角のようにただ独り歩め。
六八 最高の目的を達成するために努力策励し、こころが怯むことなく、行いに怠ることなく、堅固な活動をなし、体力と智力とを具え、犀の角のようにただ独り歩め。
七三 慈しみと平静とあわれみと解脱と喜びとを時に応じて修め、世間すべてに背くことなく、犀の角のようにただ独り歩め。
七四 貪欲と嫌悪と迷妄とを捨て、結び目を破り、命を失うのを恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
七五 今のひとびとは自分の利益のために交わりを結び、また他人に奉仕する。今日、利益をめざさない友は、得がたい。自分の利益のみを知る人間は、きたならしい。犀の角のようにただ独り歩め。
=====================









