<「清少納言」最終章>
いつまでも清少納言につき合っていたいが、この章をもって終
章とする。最初に何も説明しなかったが、難しい解説や評論は
専門家の先生にお任せするとして、私は自分が印象に残ること
について述べてきた。
最後に、清少納言の短い宮廷生活の中で、初めて長い里居をさ
せられた出来事と、彼女の「女」としての人生を採り上げて
「清少納言」を締めくくることとしたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<清少納言、長期間の里居下がり>
たった7~8年の短い宮廷出仕生活にも拘わらず、清少納言は
半年前後の長期にわたる期間、痛恨の、里居下がりを余儀なく
される。頃は996年(長徳二年)の夏から秋にかけて、丁度
中宮定子の兄伊周と弟隆家兄弟の左遷という重大事件があり
中宮定子は落飾、という、亡くなった関白道隆家の凋落が決定
的となった時期に重なるものと推測される。
(内通の疑念)
道長派の腹心である、藤原斉信と行成との親密な関係、さらに
道長に対しても親近感を持つ清少納言。この濃密な関係から、
伊周、隆家兄弟失脚に関連した情報を内通したのではないかと
定子の女房達を含む道隆家周辺から疑惑を持たれたのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このとき定子は、天皇の子を身ごもっていながら、伊周たちの
失脚により、落飾という思わぬ状況に追い込まれ、住いも宮中
から出て、最初母方の伯父高階明順邸へ、後に、小二条殿に
移り住むなど、不便な生活を強いられていた。
尊敬する定子がそういう状況にも係わらず、清少納言が定子の
傍から離れざるを得なくなるほど、清少納言に対する疑心暗鬼
の視線と、のけ者扱いによるいじめがひどくなり、長期間の里
居下がりを経験することとなった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その辺の経緯と苦渋については、いくつかの段に詳しく書いて
ある。しかし、周囲の視線に対する不愉快さや困惑している様
子は分かるが、その原因が、行成たちと親しかったが故の
「とばっちり」なのか、あるいは、策略と知らずに、無意識の
うちに、伊周たちの日常の行動や、関白就任に対する執着心な
どについて洩らしていたのか、それが敵方への「内通」と写っ
たものなのか、いずれにせよ、真相は分からない。
ただ、変わらないことは、定子の清少納言に対する心遣いであ
り、信頼であり、慈愛の心である。ついに、美しい光景が展開
され、清少納言もやっと定子のもとに出仕する。それを取り上
げて、この章は終わることとする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(定子からの便り)
定子から届いた手紙を、胸を躍らせながら、急いで開いてみた
ら、目に飛び込んできたのは、一枚の山吹の花びら、そこには
「言はで思ふぞ」とだけ書かれている。
[詠み人知らず]
「心には 下行く水のわきかへり
言はで思ふぞ 言ふにまされる」
胸のうちには伏流する水のように思いがわきかえり、それは言
葉にできない思いだが、その思いは言葉にするよりも、もっと
強いものなのだ、という意味である。
(山吹の花の色は、くちなしの実を染料としてできる色と同色
のため、山吹は「くちなし(口無し)」に通じる常套句)
********************************************
<恋の行方>
>>>夫、橘則光<<<
最初の結婚相手である橘則光とは、どういう出会いで結婚した
のか不明であるが、結婚生活は981年(天元四年)ごろから
991年(正暦二年)頃まで、つまり宮廷に出仕する前後までの
10年間ぐらい続いたのではないかと考えられるが、恋とか愛と
かいうものではなかったのではないかと思われる。
橘則光は、他の記録で武勇の人と伝わっているが、枕草子では
歌が苦手ということになっており、一方清少納言は、宮仕え論で
の考え方のように、当時としては先進的な考え方であったから、
結婚生活としては相容れない間柄となったものの、枕草子の中
では気心知れた元、夫として、親しく接している様子が描かれ
ている。こんな風景は、最近の芸能界でよくある、離婚後もよく
分かり合える友達宣言、の関係とよく似ている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>藤原斉信(ただのぶ)<<<
藤原三代目摂政、忠平の二男師輔の子息である太政大臣為光
の子。為光の兄弟は為光を除き、伊尹(これまさ)、兼通、兼家
の三人が摂政になっている。兼家の子、道隆、道兼、道長とは
従兄弟関係。
当時最高の知識人であった、藤原斉信(ただのぶ)は、頭中将
参議、後ち大納言で、朗詠の達人。藤原行成、藤原公任、源
俊賢とともに、「一条朝の四納言」といわれ、和歌、漢詩にも
長じていた。
*****
枕草子では貴公子として、常に作者(清少納言)の憧憬の的で
あり、再三にわたり、和歌や漢詩のやり取りをする間柄である。
お互いに才能を認め合った仲であるが、男女のきわどいやり取
りもあり、もしかしたら、作者にとって、内心恋の対照だったのか
どうか。しかし、表面上、作者は最後まで斉信を憧憬の貴公子
として扱い、それ以上の関係については一線を画す返歌をおく
っている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
斉信については、第八十二段「頭の中将のすずろなるそら言を
聞きて(当時、斉信は蔵人頭)」と第百六十一段「故殿の御服
のころ(関白道隆が亡くなった後の6・7月頃)」で、作者は斉信
を主人公として遇しており、清少納言における斉信の位置づけ
は変わっていない。
斉信が、職務上接点のある蔵人頭から参議に昇進し、藤原道長
の側近として活躍するようになってからは、自然に接触の機会
が遠のいた。
父、祖父が早く亡くなったために後ろ盾を失い、結局、従兄弟
道長の腹心として活躍したが、兄伊周を左遷した政敵でもある
道長と斉信の関係、斉信と清少納言との親しい関係が後に清少
納言を中傷の渦に巻き込むことになったものと思われる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>藤原実方(さねかた)<<<
歌人として名高かった。藤原三代目摂政、忠平の三男師尹(もろ
まさ)の流れで、斉信、道隆、道兼、道長とは従兄弟関係。
995年(長徳元年)、陸奥守として赴任。長徳4年、任地にて
死去。
(歌から見る親しい関係)
実方とは親しい関係にあったのではないかと思われる。陸奥守
として任地へ赴任した実方が相手ではないかと思われる歌があ
る。もっとも、清少納言集などに載っている歌は本人の作かどう
か不明である。
実方とはもっとも親しかったのではないかと推測するが、相手が
実方と思われる歌をここに載せる。
「とこも淵、ふちも瀬ならぬ涙川、そでのわたりはあらじとぞ思ふ」
(私の寝床も淵になり、その淵も浅瀬になることなく流れ続ける
涙川、もはや、陸奥の国(=そでのわたり)の渡りも渡れない
だろうと思う)
「これを見よ、うへはつれなき夏草も、下はかくこそ思ひみだるれ」
いとさわがしきときの水無月に、萩の下葉に書きつけて人のもと
へつかわしける、とあることから年代考証を類推して実方とみる。
これを見てください。上の葉は何ともない夏草も、下葉はこんなに
色が変わるほど、思い乱れているのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>藤原行成(ゆきなり)<<<
斉信(ただのぶ)の父為光の兄弟である摂政伊尹(これまさ)の
四男義孝の子だが、祖父、父ともに早く亡くしたため母方の元で
育つ。蔵人頭、大納言。斉信のところで述べたが、行成は、斉信
公任、俊賢らとともに「一条朝の四納言」と称された。蔵人頭は
斉信と同時期、斉信が参議に昇進した後、中宮定子(清少納言た
ちが仲介)との接触は行成が行ったのではないかと推測される。
彼もまた、斉信と同様、早くして後ろ盾を失ったために道長に忠
誠を尽くすことなる。
(清少納言の父とのつながり)
祖父摂政伊尹(これまさ)、父義孝ともに、歌詠みとして名高く
祖父伊尹は撰和歌所別当(長官)として後撰和歌集の編纂に携
わった清少納言の父清原元輔と交流があった。
この関係から、後に、行成と清少納言は馴染みの仲となったが、
行成は書家としては名高いが、血筋にもかかわらず、本人は和歌
が得意ではなかった模様である。
なお、行成との関係は、斉信との関係と同様、後に清少納言が
中傷される原因となったものと推測される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(女房達の評判、「けすざまじ」)
枕草子を読むと、女房たちにとって、行成はあまり高い評価を
得ていない。彼の生真面目さ、実直さを貶し、歌に興じないこ
とから、第四十九段「職(しき)の御曹司(みぞうし)の西面
(にしおもて)の立蔀(たてじとみ)のもとにて」では、散々
であり、「けすざまじ」(なんとなくつまらない)と云われる
始末である。
(清少納言の思いは)
しかし、清少納言は行成の違う面を見ている。一見、派手さや
風流がなく、地味だが、「さほ奥深き心ざまを見知り」と云うので
ある。
長くなるので細かい説明はしないが、上記の第四十九段でも
行成の細やかな行動とことばのやり取りを紹介している。
最後のところでは、
物陰に隠れているのが、元夫の弟則隆だろうと思って心安くして
いたら、それは行成だった。寝起き顔をすっかり見たよ、と言う
わけだが、
「それより後は、局の簾うちかづきなどし給ふめりき」
で終わらせている。それから後は、行成さまは私の部屋の簾をく
ぐってお入りになったりなさるようだった、というのだから、
親しい関係になったことを暗示している。
(行成、餅菓子を贈る)
第百三十三段「頭の辧の御もとより」には行成が贈ってきた
餅菓子の件とその後のやり取りが面白く書かれている。そこ
には十分に興趣に満ちた人物として描かれているのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下、行成との間の、恋の歌のやり取りである。
第百三十六段
「頭の辧の、職にまゐり給ひて、物語などし給ひしに、
夜いたうふけぬ。「あす、御物忌なるに籠もるべければ、
丑になりなばあしかりなん」とて、まゐり給ひぬ。」
二人が清少納言の居所で夜更けまで話しこんでいたところ、
行成は、
すっかり長居してしまった、明日は殿上に詰めていな
ければいけない日だから、
と云って、宮中に参内してしまった。そして、早朝になって
もっと話をしたかったのに、鶏の声にせきたてられた
ものだから、
という内容の手紙が行成から届く。それに対して清少納言は、
あなたを、鳴いてせかせた鳥の声は、孟嘗君(もう
しょうくん)が聞いた、という鶏の声でしょうか。
(本当は鳴きもしないのに)
孟嘗君が、鶏の鳴き声を聞いた、といって開かせたの
は函谷関(かんこくかん)だけれども、私が開きたい
のは逢坂の関です。あなたと深い仲になりたいので。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(注)孟嘗君(もうしょうくん)
中国の戦国時代、斉の国の貴族である孟嘗君が使者とし
て出向いた秦で捕虜になりそうになり、鶏の鳴き声の真
似が上手い部下の食客を使って、鶏の鳴き声を真似させ
て、函谷関の関門を開けさせて脱出した、という故事。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
そこで、清少納言は次の歌を返した。
「夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも
世に逢坂の関はゆるさじ
心かしこき関守はべり」
夜が明けないうちに 鶏の鳴き声を真似て騙まそうとし
ても、(函谷関ならばともかく)、逢坂の関は、決して
通ることを許さないでしょう。ここの番人は手ごわいで
すよ。
この歌は、「鶏の声」から孟嘗君の故事を連想する清少
納言の頭の回転の鋭さと、その故事から「逢坂の関」へ
思いを転ずる行成の直截的な思考のすばらしさを表現し
ているものと思われる。
(後世に残る歌となる)
見事なこの歌は後世に広まり、本人があまり得意ではな
さそうにしていた和歌の世界でも、代表的な歌として、
有名になった。清少納言の予期せぬところで彼女に輝き
をあたえることとなったのである。
勅撰「後拾遺和歌集」、「百人一首」に載る。現代の
高校の教科書にも載ることになる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[行成後書き]
あまり余計なことは書かないほうがいいと思うが、やは
り補足しておくことにする。
この段はこれで終りではない。この後に行成の歌が続く。
「逢坂は 人越えやすき関なれば
鳥鳴かぬにも あけて待つとか」
この歌に対して清少納言は返書しなかった。
実は、この歌にすっかりへこまされて、返歌もできず、
「いとわろし」(まったくみっともない)と書いている。
清少納言が、何故返歌しなかったのかについては、この
歌の、行成の裏の趣旨を読むと、
「あなたは、いつだって、身体を開いて
男を待っているようだね」
ということになり、「失礼な!」ということなのだ。
そしてこの段は、更に続く。行成が、
あなたのあの歌を、皆に見せてしまいましたよ
という。
清少納言は、
私のすばらしい歌を公表してくれてありが
とうございます。あなたの歌はひどい歌だ
ったので隠してあります。お互い五分五分
ですね
と云った。原文は
「・・・、御文はいみじう隠して、人につゆ
見せ侍らず。御心ざしのほどをくらぶる
に、ひとしくこそは」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二人のやり取りはもうすこしあるが、このような経緯か
ら、清少納言の歌は後世に名歌として残り、行成の失礼
な歌は、非難されることなく、二人だけの歌として隠さ
れたのだということになる。何と洒脱な!
それにしても、清少納言と行成との関係は、何であった
のだろうか。
****************************
<終章>
清少納言「枕草子」については、沢山の研究家がいろいろ
な意見、感想を述べておられるので、ここで私ごときが申
し上げるのは、おこがましい限りであるので、大先達の故
東京大学池田亀鑑教授(岩波文庫「枕草子」校訂者)の
ことばを引用させて頂いて、最後の締めくくりとしたい。
++++++++++++
・・・我々は平安中期における生活と感覚の具体相を
万華鏡を見るようにうかがい知ることができるの
であるが、それを同時に我々が文学として享受し
得るのは、ひとえに作者の卓抜なる散文家として
の稟性によるのである。また日記的章段に見る作
者の高い志操と、中宮定子との美しい魂の触れ合
いが、全体としてこの草子の文学的香気の高さの
淵源をなしていることも知らなければならない。
*****************************
京都湧泉寺境内に、清少納言の歌碑がある。
「夜をこめて、鳥のそら音ははかるとも、
世に逢坂の関はゆるさじ」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<清少納言>すべておわり。
いつまでも清少納言につき合っていたいが、この章をもって終
章とする。最初に何も説明しなかったが、難しい解説や評論は
専門家の先生にお任せするとして、私は自分が印象に残ること
について述べてきた。
最後に、清少納言の短い宮廷生活の中で、初めて長い里居をさ
せられた出来事と、彼女の「女」としての人生を採り上げて
「清少納言」を締めくくることとしたい。
 | ビギナーズ・クラシックス 枕草子角川書店このアイテムの詳細を見る |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<清少納言、長期間の里居下がり>
たった7~8年の短い宮廷出仕生活にも拘わらず、清少納言は
半年前後の長期にわたる期間、痛恨の、里居下がりを余儀なく
される。頃は996年(長徳二年)の夏から秋にかけて、丁度
中宮定子の兄伊周と弟隆家兄弟の左遷という重大事件があり
中宮定子は落飾、という、亡くなった関白道隆家の凋落が決定
的となった時期に重なるものと推測される。
(内通の疑念)
道長派の腹心である、藤原斉信と行成との親密な関係、さらに
道長に対しても親近感を持つ清少納言。この濃密な関係から、
伊周、隆家兄弟失脚に関連した情報を内通したのではないかと
定子の女房達を含む道隆家周辺から疑惑を持たれたのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このとき定子は、天皇の子を身ごもっていながら、伊周たちの
失脚により、落飾という思わぬ状況に追い込まれ、住いも宮中
から出て、最初母方の伯父高階明順邸へ、後に、小二条殿に
移り住むなど、不便な生活を強いられていた。
尊敬する定子がそういう状況にも係わらず、清少納言が定子の
傍から離れざるを得なくなるほど、清少納言に対する疑心暗鬼
の視線と、のけ者扱いによるいじめがひどくなり、長期間の里
居下がりを経験することとなった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その辺の経緯と苦渋については、いくつかの段に詳しく書いて
ある。しかし、周囲の視線に対する不愉快さや困惑している様
子は分かるが、その原因が、行成たちと親しかったが故の
「とばっちり」なのか、あるいは、策略と知らずに、無意識の
うちに、伊周たちの日常の行動や、関白就任に対する執着心な
どについて洩らしていたのか、それが敵方への「内通」と写っ
たものなのか、いずれにせよ、真相は分からない。
ただ、変わらないことは、定子の清少納言に対する心遣いであ
り、信頼であり、慈愛の心である。ついに、美しい光景が展開
され、清少納言もやっと定子のもとに出仕する。それを取り上
げて、この章は終わることとする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(定子からの便り)
定子から届いた手紙を、胸を躍らせながら、急いで開いてみた
ら、目に飛び込んできたのは、一枚の山吹の花びら、そこには
「言はで思ふぞ」とだけ書かれている。
[詠み人知らず]
「心には 下行く水のわきかへり
言はで思ふぞ 言ふにまされる」
胸のうちには伏流する水のように思いがわきかえり、それは言
葉にできない思いだが、その思いは言葉にするよりも、もっと
強いものなのだ、という意味である。
(山吹の花の色は、くちなしの実を染料としてできる色と同色
のため、山吹は「くちなし(口無し)」に通じる常套句)
 | 大庭みな子の枕草子講談社このアイテムの詳細を見る |
********************************************
<恋の行方>
>>>夫、橘則光<<<
最初の結婚相手である橘則光とは、どういう出会いで結婚した
のか不明であるが、結婚生活は981年(天元四年)ごろから
991年(正暦二年)頃まで、つまり宮廷に出仕する前後までの
10年間ぐらい続いたのではないかと考えられるが、恋とか愛と
かいうものではなかったのではないかと思われる。
橘則光は、他の記録で武勇の人と伝わっているが、枕草子では
歌が苦手ということになっており、一方清少納言は、宮仕え論で
の考え方のように、当時としては先進的な考え方であったから、
結婚生活としては相容れない間柄となったものの、枕草子の中
では気心知れた元、夫として、親しく接している様子が描かれ
ている。こんな風景は、最近の芸能界でよくある、離婚後もよく
分かり合える友達宣言、の関係とよく似ている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>藤原斉信(ただのぶ)<<<
藤原三代目摂政、忠平の二男師輔の子息である太政大臣為光
の子。為光の兄弟は為光を除き、伊尹(これまさ)、兼通、兼家
の三人が摂政になっている。兼家の子、道隆、道兼、道長とは
従兄弟関係。
当時最高の知識人であった、藤原斉信(ただのぶ)は、頭中将
参議、後ち大納言で、朗詠の達人。藤原行成、藤原公任、源
俊賢とともに、「一条朝の四納言」といわれ、和歌、漢詩にも
長じていた。
*****
枕草子では貴公子として、常に作者(清少納言)の憧憬の的で
あり、再三にわたり、和歌や漢詩のやり取りをする間柄である。
お互いに才能を認め合った仲であるが、男女のきわどいやり取
りもあり、もしかしたら、作者にとって、内心恋の対照だったのか
どうか。しかし、表面上、作者は最後まで斉信を憧憬の貴公子
として扱い、それ以上の関係については一線を画す返歌をおく
っている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
斉信については、第八十二段「頭の中将のすずろなるそら言を
聞きて(当時、斉信は蔵人頭)」と第百六十一段「故殿の御服
のころ(関白道隆が亡くなった後の6・7月頃)」で、作者は斉信
を主人公として遇しており、清少納言における斉信の位置づけ
は変わっていない。
斉信が、職務上接点のある蔵人頭から参議に昇進し、藤原道長
の側近として活躍するようになってからは、自然に接触の機会
が遠のいた。
父、祖父が早く亡くなったために後ろ盾を失い、結局、従兄弟
道長の腹心として活躍したが、兄伊周を左遷した政敵でもある
道長と斉信の関係、斉信と清少納言との親しい関係が後に清少
納言を中傷の渦に巻き込むことになったものと思われる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>藤原実方(さねかた)<<<
歌人として名高かった。藤原三代目摂政、忠平の三男師尹(もろ
まさ)の流れで、斉信、道隆、道兼、道長とは従兄弟関係。
995年(長徳元年)、陸奥守として赴任。長徳4年、任地にて
死去。
(歌から見る親しい関係)
実方とは親しい関係にあったのではないかと思われる。陸奥守
として任地へ赴任した実方が相手ではないかと思われる歌があ
る。もっとも、清少納言集などに載っている歌は本人の作かどう
か不明である。
実方とはもっとも親しかったのではないかと推測するが、相手が
実方と思われる歌をここに載せる。
「とこも淵、ふちも瀬ならぬ涙川、そでのわたりはあらじとぞ思ふ」
(私の寝床も淵になり、その淵も浅瀬になることなく流れ続ける
涙川、もはや、陸奥の国(=そでのわたり)の渡りも渡れない
だろうと思う)
「これを見よ、うへはつれなき夏草も、下はかくこそ思ひみだるれ」
いとさわがしきときの水無月に、萩の下葉に書きつけて人のもと
へつかわしける、とあることから年代考証を類推して実方とみる。
これを見てください。上の葉は何ともない夏草も、下葉はこんなに
色が変わるほど、思い乱れているのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>藤原行成(ゆきなり)<<<
斉信(ただのぶ)の父為光の兄弟である摂政伊尹(これまさ)の
四男義孝の子だが、祖父、父ともに早く亡くしたため母方の元で
育つ。蔵人頭、大納言。斉信のところで述べたが、行成は、斉信
公任、俊賢らとともに「一条朝の四納言」と称された。蔵人頭は
斉信と同時期、斉信が参議に昇進した後、中宮定子(清少納言た
ちが仲介)との接触は行成が行ったのではないかと推測される。
彼もまた、斉信と同様、早くして後ろ盾を失ったために道長に忠
誠を尽くすことなる。
(清少納言の父とのつながり)
祖父摂政伊尹(これまさ)、父義孝ともに、歌詠みとして名高く
祖父伊尹は撰和歌所別当(長官)として後撰和歌集の編纂に携
わった清少納言の父清原元輔と交流があった。
この関係から、後に、行成と清少納言は馴染みの仲となったが、
行成は書家としては名高いが、血筋にもかかわらず、本人は和歌
が得意ではなかった模様である。
なお、行成との関係は、斉信との関係と同様、後に清少納言が
中傷される原因となったものと推測される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(女房達の評判、「けすざまじ」)
枕草子を読むと、女房たちにとって、行成はあまり高い評価を
得ていない。彼の生真面目さ、実直さを貶し、歌に興じないこ
とから、第四十九段「職(しき)の御曹司(みぞうし)の西面
(にしおもて)の立蔀(たてじとみ)のもとにて」では、散々
であり、「けすざまじ」(なんとなくつまらない)と云われる
始末である。
(清少納言の思いは)
しかし、清少納言は行成の違う面を見ている。一見、派手さや
風流がなく、地味だが、「さほ奥深き心ざまを見知り」と云うので
ある。
長くなるので細かい説明はしないが、上記の第四十九段でも
行成の細やかな行動とことばのやり取りを紹介している。
最後のところでは、
物陰に隠れているのが、元夫の弟則隆だろうと思って心安くして
いたら、それは行成だった。寝起き顔をすっかり見たよ、と言う
わけだが、
「それより後は、局の簾うちかづきなどし給ふめりき」
で終わらせている。それから後は、行成さまは私の部屋の簾をく
ぐってお入りになったりなさるようだった、というのだから、
親しい関係になったことを暗示している。
(行成、餅菓子を贈る)
第百三十三段「頭の辧の御もとより」には行成が贈ってきた
餅菓子の件とその後のやり取りが面白く書かれている。そこ
には十分に興趣に満ちた人物として描かれているのである。
 | 清少納言―感性のきらめき新典社このアイテムの詳細を見る |
以下、行成との間の、恋の歌のやり取りである。
第百三十六段
「頭の辧の、職にまゐり給ひて、物語などし給ひしに、
夜いたうふけぬ。「あす、御物忌なるに籠もるべければ、
丑になりなばあしかりなん」とて、まゐり給ひぬ。」
二人が清少納言の居所で夜更けまで話しこんでいたところ、
行成は、
すっかり長居してしまった、明日は殿上に詰めていな
ければいけない日だから、
と云って、宮中に参内してしまった。そして、早朝になって
もっと話をしたかったのに、鶏の声にせきたてられた
ものだから、
という内容の手紙が行成から届く。それに対して清少納言は、
あなたを、鳴いてせかせた鳥の声は、孟嘗君(もう
しょうくん)が聞いた、という鶏の声でしょうか。
(本当は鳴きもしないのに)
孟嘗君が、鶏の鳴き声を聞いた、といって開かせたの
は函谷関(かんこくかん)だけれども、私が開きたい
のは逢坂の関です。あなたと深い仲になりたいので。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(注)孟嘗君(もうしょうくん)
中国の戦国時代、斉の国の貴族である孟嘗君が使者とし
て出向いた秦で捕虜になりそうになり、鶏の鳴き声の真
似が上手い部下の食客を使って、鶏の鳴き声を真似させ
て、函谷関の関門を開けさせて脱出した、という故事。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
そこで、清少納言は次の歌を返した。
「夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも
世に逢坂の関はゆるさじ
心かしこき関守はべり」
夜が明けないうちに 鶏の鳴き声を真似て騙まそうとし
ても、(函谷関ならばともかく)、逢坂の関は、決して
通ることを許さないでしょう。ここの番人は手ごわいで
すよ。
この歌は、「鶏の声」から孟嘗君の故事を連想する清少
納言の頭の回転の鋭さと、その故事から「逢坂の関」へ
思いを転ずる行成の直截的な思考のすばらしさを表現し
ているものと思われる。
(後世に残る歌となる)
見事なこの歌は後世に広まり、本人があまり得意ではな
さそうにしていた和歌の世界でも、代表的な歌として、
有名になった。清少納言の予期せぬところで彼女に輝き
をあたえることとなったのである。
勅撰「後拾遺和歌集」、「百人一首」に載る。現代の
高校の教科書にも載ることになる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[行成後書き]
あまり余計なことは書かないほうがいいと思うが、やは
り補足しておくことにする。
この段はこれで終りではない。この後に行成の歌が続く。
「逢坂は 人越えやすき関なれば
鳥鳴かぬにも あけて待つとか」
この歌に対して清少納言は返書しなかった。
実は、この歌にすっかりへこまされて、返歌もできず、
「いとわろし」(まったくみっともない)と書いている。
清少納言が、何故返歌しなかったのかについては、この
歌の、行成の裏の趣旨を読むと、
「あなたは、いつだって、身体を開いて
男を待っているようだね」
ということになり、「失礼な!」ということなのだ。
そしてこの段は、更に続く。行成が、
あなたのあの歌を、皆に見せてしまいましたよ
という。
清少納言は、
私のすばらしい歌を公表してくれてありが
とうございます。あなたの歌はひどい歌だ
ったので隠してあります。お互い五分五分
ですね
と云った。原文は
「・・・、御文はいみじう隠して、人につゆ
見せ侍らず。御心ざしのほどをくらぶる
に、ひとしくこそは」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二人のやり取りはもうすこしあるが、このような経緯か
ら、清少納言の歌は後世に名歌として残り、行成の失礼
な歌は、非難されることなく、二人だけの歌として隠さ
れたのだということになる。何と洒脱な!
それにしても、清少納言と行成との関係は、何であった
のだろうか。
****************************
<終章>
清少納言「枕草子」については、沢山の研究家がいろいろ
な意見、感想を述べておられるので、ここで私ごときが申
し上げるのは、おこがましい限りであるので、大先達の故
東京大学池田亀鑑教授(岩波文庫「枕草子」校訂者)の
ことばを引用させて頂いて、最後の締めくくりとしたい。
++++++++++++
・・・我々は平安中期における生活と感覚の具体相を
万華鏡を見るようにうかがい知ることができるの
であるが、それを同時に我々が文学として享受し
得るのは、ひとえに作者の卓抜なる散文家として
の稟性によるのである。また日記的章段に見る作
者の高い志操と、中宮定子との美しい魂の触れ合
いが、全体としてこの草子の文学的香気の高さの
淵源をなしていることも知らなければならない。
*****************************
京都湧泉寺境内に、清少納言の歌碑がある。
「夜をこめて、鳥のそら音ははかるとも、
世に逢坂の関はゆるさじ」
 | 「枕草子」を旅しよう―古典を歩く〈3〉講談社このアイテムの詳細を見る |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<清少納言>すべておわり。



















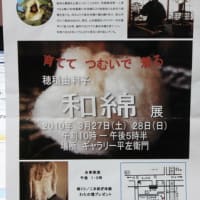
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます