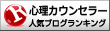講師は1級キャリア・コンサルティング技能士です。
さてセミナーの内容は表題のとおり 人事・労務管理と企業における
組織の問題、それに改正点を中心にした労働法を取り上げたもので
知識の再チェックには体変有効でした。その中で私自身が 今後の講演
等で引用させてもらおうと思ったものを1点だけあげておきます。
*日本における人事・労務管理の特徴
①三種の神器
終身雇用、年功制、企業別労働組合
②新規学卒一括採用と内部労働市場の重視
④柔軟な分業システム
⑤現場レベルへの権限移譲
⑥競争の延期と平等主義的な報酬配分
1916年度の全国安全週間が7月1日~7日に行われました。そこで顧問先の従業員教育において使用した1文を引用します。安全とは日々意識し守るべきものですが、少なくとも年1回はこの原点に思いを馳せたいと思います。
1906年世界一の製鉄会社であったUSスチール社のシカゴ製鉄所では毎年1万人の従業員のうち1,200人が事故で死亡又は重症を負っていました。
敬虔なクリスチャンであったゲイリー社長はこれに痛く心を悩ませ会社業績悪化を覚悟の上で従来の方針を転換しました。すなわち「生産第一」「品質第二」「安全第三」を「安全第一」「品質第二」「生産第三」に変更したのです。
当時の常識に反したこの決断は 社内でも反対が多く社外からは嘲笑をあびたと言われています。
ところが労働災害が激減し作業環境が整備されることにより 従業員の士気が高まり定着率も向上、品質事故が激減し生産効率も大幅にアップしたのです。これにより「安全第一」は製鉄業界、他産業にそして世界各国にも広がって我が国でも現在では常識となっています。安全衛生のテキストには必ず取り上げられている逸話ですが 110年後の現代に於いて我々は何を読み取るべきなのでしょうか?
小保方さんの「あの日」をようやく入手して、一気に読み上げました。
一連のSTAP細胞報道で私が抱いていた素朴な疑問が2つありました。
その1つは、小保方さんが一連のねつ造事件の主犯だとするならば、その動機です。彼女は父が会社役員、
母が大学教授と恵まれた家庭環境で育ち、早稲田大学、東京女子医科大学、ハーバード大学の大学院に学び
博士号を取得と、まさに絵にかいたようなエリート街道を歩んできました。そして当時、理化学研究所で最年少の
ユニットリーダーとして抜擢されたばかりで、作業環境整備にじっくり時間をかけるべき時であり、それがまた
許される時だったのです。それなのにわざわざあたふたと、世間の耳目をひきつけ、いずれは露見するような、
自爆テロともいうべきねつ造事件を起こしたのか・・・・?という動機への疑問です。
もう1つは、今回の事件の難しさは「再現実験成功はIPS細胞で3年半、クーロン細胞では5年以上かかっており、
歴史的には10年以上かかった案件もあるなど、再現不能との結論を出すまでには相当な年月を要する」ということが
言われておりました。ということで、途中経過として「再現実験は現時点では成功しておりません」との報告となるものと
予期しておりました。従ってネイチャー誌掲載から2年強の時点での、明確な実験打ち切り宣言には???でした。
小保方さんの記述が100%正しいかどうかは、断言できませんがたとえ50%の精度であっても、納得できる内容です。
今回の事件に際し私は魔女裁判的な異様なバッシングを嫌悪し、長野サリン事件を想起する様なマスコミのミスリードを
予感しました。但し講談社さんに対しては、この手記の刊行により、マスコミの中での数少ない良識派であると認識しました。
2014年4月19日付けの拙ブログ「STAP細胞騒動に思う<天才の生かし方>」を以下に再掲します。
STAP細胞関連の報道がいまだに沈静化しませんが この問題を人事労務管理の視点から
述べてみたいと思います。
まず理研への提案ですが、もし小保方さんの主導で確認作業を再開するのならば
研究者としては凡庸でもよいので、業界の文章作法に長けた速記記録者と、進行していく研究課程の
200場面を絶対にとり洩らさない(美的センスは問わない)カメラマンと もし可能ならば渉外・雑用を
務める常識ある管理職を各1名サポート要員に加えるべきです。問題が起きても責任を回避する様な
共同執筆者は百害あって一利ないので当然外して下さい。
そして業界への提案です。学生がレポートをコピペで作成するのはもちろんとんでもないことです。
(学ぶこと自体にに意味があるので)しかしながら従来の確立した理論や、論文に学びそれを基礎・土台
として新しい仮説やオリジナリティの高い理論を発表する論文には出所を明らかにすれば無制限の引用
(形式はコピペとなる場合もある)を許可してもらいたいと思います。論文を作成した方ならご経験
だと思いますが本丸ともいうべきオリジナルな仮説・理論に行き着くまでに 論拠となる著作や、
理論の要約・紹介に大変な労力を消費します。国語を得意科目とした私にしてそうなのですから
天才的な理系脳をもった異才、鬼才の研究者にとってはいかばかりかと推察致します。
私が現役時代在籍したD社においても 基礎研究で天才的と評される研究者達はいずれも自身の研究
には寝食をを忘れて没頭し全知全霊を傾けるものの 社内規則や手続・記録・報告書には無頓着で面倒
くさがり嫌悪感すら公然と発言する方が多かったです(記録は詳細にこの頭の中にある、つまらん
手続きは時間の無駄等と主張して)。徹夜で研究に没頭し、遅刻や会議のすっぽかし、書類提出忘れの
常習犯の中にD社の業績を左右する様な画期的な新技術を開発した研究者が数多くおりました。その
ような方々を擁護(降格申請を昇格申請に切り替える等の実績もしくは実績期待主義により)研究を
側面からバックアップできたことを人事労務管理の立場にいた者として誇りに思います。
いくつかの批判点に筆者のコメントを加えます。
*論拠する論文のコピペ →現状ではマナー違反(すでに謝罪済み)
*写真の取り換え・流用 →ピンボケの写真を使う意味がない 同様な実験で撮影出来た鮮明な画像を
使う方が分かりやすく親切 (同一実験におけるすべてが鮮明な200枚の画像はいつになった用意
できるか分からない :研究者はカメラマンではない)
*論文が不備なため実証されていない →(差し替え前の)写真はピンボケではあるが複数の共同
研究者が現場で実際に目視で確認している
*研究を記録したノートが少なすぎる →詳細な記録は頭の中にある
*未だ追試に成功していない →これだけ画期的な研究では数年を要するのが常識
*論文の撤回 →絶対すべきではない、追試により完全に否定されてからでよい
浴槽でアイデアを発見し、興奮のあまり全裸でそれを知人に報告しようと、通りに飛び出した
アルキメデスを「公然わいせつ罪」で追及し公職から追放し、「アルキメデスの原理」を
抹殺していたなら現代の科学の歩みはもう少し遅れていたのではないでしょうか?
共同研究者であり、一貫して論文撤回不要を唱える、ハーバード大学の教授は、プライバシーを
あれこれ興味本位に週刊誌により暴かれてはおりますが、そのぶれない姿勢はアメリカのプラグマ
ティズム(現実・実利主義)の体現者として高く評価出来ます。
STAP細胞関連の報道がいまだに沈静化しませんが この問題を人事労務管理の視点から
述べてみたいと思います。
まず理研への提案ですが、もし小保方さんの主導で確認作業を再開するのならば
研究者としては凡庸でもよいので、業界の文章作法に長けた速記記録者と、進行していく研究課程の
200場面を絶対にとり洩らさない(美的センスは問わない)カメラマンと もし可能ならば渉外・雑用を
務める常識ある管理職を各1名サポート要員に加えるべきです。問題が起きても責任を回避する様な共同
執筆者は百害あって一利ないので当然外して下さい。
そして業界への提案です。学生がレポートをコピペで作成するのはもちろんとんでもないことです。
(学ぶこと自体にに意味があるので)しかしながら従来の確立した理論や、論文に学びそれを基礎・土台
として新しい仮説やオリジナリティの高い理論を発表する論文には出所を明らかにすれば無制限の引用
(形式はコピペとなる場合もある)を許可してもらいたいと思います。論文を作成した方ならご経験
だと思いますが本丸ともいうべきオリジナルな仮説・理論に行き着くまでに 論拠となる著作や、
理論の要約・紹介に大変な労力を消費します。国語を得意科目とした私にしてそうなのですから
天才的な理系脳をもった異才、鬼才の研究者にとってはいかばかりかと推察致します・
私が現役時代在籍したD社においても 基礎研究で天才的と評される研究者達はいずれも自身の研究
には寝食をを忘れて没頭し全知全霊を傾けるものの 社内規則や手続・記録・報告書には無頓着で面倒
くさがり嫌悪感すら公然と発言する方が多かったです(記録は詳細にこの頭の中にある、つまらん
手続きは時間の無駄等と主張して)。徹夜で研究に没頭し、遅刻や会議のすっぽかし、書類提出忘れの
常習犯の中にD社の業績を左右する様な画期的な新技術を開発した研究者が数多くおりました。その
ような方々を擁護(降格申請を昇格申請に切り替える等の実績もしくは実績期待主義により)研究を
側面からバックアップできたことを人事労務管理の立場にいた者として誇りに思います。
STAP細胞存在の有無については 門外漢の私は述べるつもりはありません。ただし人事労務屋の
勘で申しますと錯誤や誤謬の線は排除できないものの 意図的なねつ造は考えにくいと考えます。
定年間近の追い詰められた研究者ならともかく 30歳の若き研究者がこれからの人生を棒に振る様な
ばくちを打つ意味があるのでしょうか?
いくつかの批判点に筆者のコメントを加えます。
*論拠する論文のコピペ →現状ではマナー違反(すでに謝罪済み)
*写真の取り換え・流用 →ピンボケの写真を使う意味がない 同様な実験で撮影出来た鮮明な画像を
使う方が分かりやすく親切 (同一実験におけるすべてが鮮明な200枚の画像はいつになった用意
できるか分からない :研究者はカメラマンではない)
*論文が不備なため実証されていない →(差し替え前の)写真はピンボケではあるが複数の共同
研究者が現場で実際に目視で確認している
*研究を記録したノートが少なすぎる →詳細な記録は頭の中にある
*未だ追試に成功していない →これだけ画期的な研究では数年を要するのが常識
*論文の撤回 →絶対すべきではない、追試により完全に否定されてからでよい
ノーベル賞を受賞した京大の山中教授のように 常識もありバランスのとれた天才もごく稀には
いらっしゃるようです。しかし私個人としてはそのような人材にお目にかかったことがありません。
あるレベル以上の秀逸な・超斬新なアイデアの創案者は100%変人・奇人・常識外れでした。
基本的には天才的人材にはそのオリジナリティの高い発想のみを期待して、実務面では分業体制で
それをサポートして成果に結びつけていくのが賢い施策ではないでしょうか?左右の人と歩調を
合わせて苗を植える・・・そんな人材は99%必要であっても、歩調を乱して他者に迷惑をかけ
ながらも農業の機械化を考える1%の人材の価値を認めそれを活かす仕組みがなければ、その
社会は進歩しないと思います。
浴槽でアイデアを発見し、興奮のあまり全裸でそれを知人に報告しようと、通りに飛び出した
アルキメデスを「公然わいせつ罪」で追及し公職から追放し、「アルキメデスの原理」を
抹殺していたなら現代の科学の歩みはもう少し遅れていたのではないでしょうか?
共同研究者であり、一貫して論文撤回不要を唱える、ハーバード大学の教授は、プライバシーを
あれこれ興味本位に週刊誌により暴かれてはおりますが、そのぶれない姿勢はアメリカのプラグマ
ティズム(現実・実利主義)の体現者として高く評価出来ます。
久々に300人を超える学生を前にすると 流石にテンションが上がります。
担当教授に講義の最後に「これから社会に出ていく皆さんへのアドバイス」を
依頼されました。そしてそのテーマが表題の「人間万事塞翁が馬」です。
新聞情報によれば 神戸大学医学部に進学し、ラグビーでの骨折などの治療を
受けた経験から整形外科医に憧れたそうです。そして卒業して研修医になったが
あまりの不器用さから簡単な手術でも同僚の何倍もかかり、「ジャマナカ」の
あだ名をつけられ「手術はうまくない」と悟り失意のうちに基礎研究の道に
転じる決意をした・・・・とのことです。
もし山中教授の不器用さ”がもう少しましであったなら 彼は3流の整形
外科医の道を歩み 今回のノーベル賞受賞という最高の業績・栄誉とは無関係
の存在であったと推察されます。
私が 時の権力者から閑職に追いやられた時にもこのこの故事を(僭越ながら
山中教授と同じように)座右の銘として耐えしのいだというささやかな体験も
含め学生諸君にお話ししました。とくに「不遇の状況にあってもやけを起こさず
それをを受け入れてその中でベストを尽くして 運命の潮目が変わるのを待つ」
ということの大切さを含め 「将来人生の危機に直面した時にこの故事を思い
出して貰いたい」という言葉で今回の講義を締めくくりました。
学校の事務局からは何時にも増して学生の授業への評価が高かったとの連絡
がありました。
山中先生、私と、学生たちと、そして全ての国民に素晴らしいプレゼントを
本当に有難うございました!
その方法は「こまめな体重測定」です。
NHKの「ためしてガッテン」にとりあげられるなど
結構有名なダイエット法ですが 私が実行するのは初めてで
その成果になるほどとガッテン致しました。
最初は体重をきめ細かく測るだけで ダイエット出来るなんて?そんなバカな!
という感想を持ちましたが これを観点を変えて 人事労務管理の視点から見直してみると
目標を与え それを評価し こまめにフィードバックするという「業務遂行管理」の原則に
見事に合致しています。
すなわち私の場合に置き換えてみるならば 3kg減量という目標に対して 体重を測定するたびに評価が具体的にフィードバックされます。減れば達成感が湧きそれがさらなる減量へのモチベーションとなり 増えれば改善行動(歩く距離を増やす、間食をやめる等)への促進力となり結果として目標達成に繋がったわけです。
地球から3億km彼方の小惑星「イトカワ」に着陸し、サンプルを採取して地球に帰還するというミッションは、あのアメリカのNASA(航空宇宙局)も手を出さないようなハイリスクのものでした。ですから今回の快挙はまずこのミッションを設定するところから始まったといえましょう。
米国は、日本以上に納税者へのアカウンタビリティが徹底しているので、NASAに代表されるような大宇宙機関であればあるほどハイリスクな計画には手を出さない傾向があります。実力ある者が手堅い、しかしアピールする計画を実行し、高い成功率を維持する・・・NASAはそういう方針で取り組み、すこしずつ成果を積み上げています。宇宙開発の基本姿勢としてはそれは正しい・・・ただし、それ一辺倒になると、イノベーションの種とリスクを同時に抱えたプロジェクトは出てこなくなってしまいます。「未来への投資」。これを怠ってはなりません。
ハイリスク・ハイリターンな事業は、加点法で評価すべきです。そうしないと、100点満点からの減点法で評価されても大丈夫な事業、つまりはローリスク・ローリターンの計画ばかりになってしまう可能性があります。
幸い「はやぶさ」プロジェクトに対して、政府系の委員会も川口先生の加点法の評価方式を認め、ハイリスク・ハイリターンという認識でゴーサインを出したのです。
この加点法の具体的な内容を見てみましょう。
それは「はやぶさミッション達成度」として
・電気推進エンジン稼働開始(3台同時運転は世界初)・・・・・・・・・50点
・電気推進エンジンある期間(1000時間)稼働・・・・・・・・・・100点
・地球スイングバイ成功(電気推進によるスイングバイは世界初)・・・150点
・(自律航法に成功して)イトカワとランデブー成功・・・・・・・・・200点
・イトカワの科学的観測成功・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250点
・イトカワにタッチダウンしてサンプル採取・・・・・・・・・・・・・275点
・カプセルが地球に帰還、大気圏に再突入して回収・・・・・・・・・・400点
・イトカワのサンプル入手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500点
どうですか・・・、目から鱗というか、これだけ見てもなんかワクワクしますね!
選手の活躍もさることながら私はザッケローニ監督のマネジメント能力の高さに感服しました。
極めて短い期間に
①選手一人ひとりの個性を把握し
(観察、データ、話し合い)
②その能力にあったポジション・活躍の場・役割を練習時点から徹底してシンプルに理解させたからこそ
③いざ火急の実戦の場において途中から投入された選手達も結果を出せたのです
それに加えるに
④日頃のコミュニケーションを通しての選手達との信頼感の構築
⑤招集選手25名中追加招集の1名と第3GKを除く23名を起用することでほぼチーム全員にチャンスを与え、岡田ジャパン以来培われた チームの結束力をさらに高め、それを評価することによって選手達との連帯感をさらに強固なものとし
⑥レッドカードの川島、1回目に結果を出せなかった岩政、李にリベンジのチャンスを与え、見事に結果を出すことによって今回の快挙を
たぐりよせたのです
これからのザックジャパンの活躍がますます楽しみとなりました。
故障続きで、地球帰還が絶望視された 「はやぶさ」の7年間60億キロに及ぶ前人未踏の旅は 最高の成果をもたらしたのです。
宇宙航空研究開発機構(JAXA) 川口プロジェクトマネジャーの強力なリーダーシップと、それを最後まで支えた全メンバーのフォロワーシップに 最大の賛辞を贈ります。
そして、長きにわたる苦難に耐え、粘り強く、あきらめずに、精進・努力を傾けられたその姿勢に 学びたいと思います。
当該保安官の処分についてはネットにおいても一部の厳罰派を除き擁護派が圧倒的に多い様ですが、私見での結論を言えばこれで良かったのではないかと思います。これはあくまで
状況から判断しての推定になりますが、映像の一般かつ全面公開の阻止は両国間で、おそらく暗黙の密約にちかいものがあったのでは?と思われます。
今回の一連の対応により、管内閣は結果的に大きく支持率を下げました。外交の舞台裏では厳しい政敵の攻勢と、国民のナショナリズムの台頭に苦慮する現在の親日政権への支援は
不可欠だったのでしょう。現政権が直接関与することなく、結果的に日本国民が求める情報が開示されたことで、外交上のメンツを保ちつつガス抜きが出来た訳です。
さて労務管理の面から今回の事件を振り返ってみますと、投稿者の上司である船長による面談と説得による事実の把握、スピーディーな報告等、組織管理者としての対処方が見事です。平常のコミュニケーションの密さ、部下への観察眼、信頼感の醸成等も容易に推定されます。