
【高田梅開く】
何年か前に、中野孝次の『「生き方の美学』を読んで、幕末の会津人、秋月悌次郎の人間性に触れた。これは拙ブログ「北越潜行の詩」2006-02-13にも書いた。
先日、月に一度の検診日に本棚から持参した本だ。待ち時間に、斜め読みしてもろもろ思いを巡らした。
秋月悌次郎は、幕末の京都で守護職を務めながら時代に翻弄され、逆賊の汚名を一身に集めてしまった会津藩主・松平容保公のそばにあって、公用方を務めた一人だ。この幕末史のなかでの一文官の生き方は感動である。
生き方の美学の『第19話 徳・・・ハーンと秋月悌次郎』には、熊本五高で同僚だったラフカディオ・ハーンが、悌次郎を「神様のような」人と呼んで尊敬したこと、熱意ある教育者として、学生に慕われたとが書かれている。そして、中野孝次は「百年たった今、この明治日本を担う新興青年が何が何でも古い日本の価値を否定して、西洋の実学を取り入れるしかないと言い張る、こうした-徳よりも実利の学を-、という国家を導いてきた結果、現代日本はまさに世界でも珍しく「徳」というものがない国になってしまったのではないか」という。また、ハーンは、「旧体制の下で育った日本人は礼儀しく、利己的でなく、善良でみなのびやかであった。それはいくら褒めても褒めたりぬ美徳である。」と書いている。
病院の帰りに短大図書館に寄り、松本健一著『秋月悌次郎 老日本の面影』(1987年 作品社)を借りてきて一気に読んだ。「生き方の美学」に紹介されていた本だ。
ハーンに与えた印象を手掛かりに、幕末から明治に生きた秋月という人物の持っている意味、歴史における革新と伝統の関係、そして秋月に係わった人物たちの像が書かれていた。秋月の人格的な温和さ、それを支える思想的中庸のエトスは、維新史の動乱をかいくぐって手に入れた「常民の心」だと述べられていた。
五高での秋月翁の古希のお祝いで諸氏が語る秋月の人間像に、人として尊いものを再確認した。それは、「教育は結局教える人の生き方の問題に凝縮される」という言葉にあるように、地位とか名誉ではなくその人の人間性だと思った。尊敬されるものはその人となりである。
数年前に読んだ、中村彰彦著『落花は枝に還らずとも 会津藩士・秋月悌次郎』でも同じような感動を得た。 著書名「落花は枝に還らずとも」は、文中にあった。
「一度枝を離れた落花は、その枝に還って咲くことは二度とできない。しかし、来年咲く花の種になることはできる。
会津滅藩に立ち会い、亡国の遺臣と化した悌次郎は、自身を落花になぞらえることにより、逆風の時代になおかつ堪えて生きる覚悟を初めてあきらかにしたのである。」
また、いずれの本にも、二人の詩人の素晴らしい漢詩が紹介され、あらためて二人の感懐がよくわかった。
特に、長州藩・奥平謙輔との往復書簡にはこみ上げるものがあった。秋月は、会津藩落城後に藩の寛容な処分を訴えに旧知の長州藩士奥平謙輔のもとへ、猪苗代から新潟へ秘かな雪中行の折り、の胸を打つ「北越潜行の詩」を残した。
有故潜行北越帰途所得 会津 秋月胤永
--------------------------------
行無輿兮帰無家 行くに輿無く 帰るに家無し
國破孤城乱雀鴉 國破れて 孤城雀鴉乱る
治不奏功戦無略 治は功を奏せず 戦は略無し
微臣有罪復何嗟 微臣罪あり 復た何をか嗟かん
聞説天皇元聖明 聞くならく 天皇元より聖明
我公貫日発至誠 我公貫日至誠に発す
恩賜赦書応非遠 恩賜の赦書は 応に遠きに非ざるべし
幾度額手望京城 幾度か手を額にして京城を望む
思之思之夕達晨 之を思い之を思うて 夕晨に達す
憂満胸臆涙沾巾 憂は胸臆に満ちて 涙は巾を沾す
風淅瀝兮雲惨澹 風は淅瀝として 雲は惨澹たり
何地置君又置親 何れの地に君を置き又親を置かん
--------------------------------
戊辰戦争において会津藩降伏を取り仕切った秋月悌次郎は、維新後は死者の影を背負い、≪自己を主張することを価値とした近代日本のなかでは永遠に失われてゆかざるをえないような、伝統を守って生きる人間の生き方の正道を踏もうとした懐かしい人≫であった。
以下は松本健一著『秋月悌次郎 老日本の面影』(勁草書房)のネットの内容説明である。
≪ラフカディオ・ハーンをして「神様のような人」といわしめた会津藩士秋月悌次郎。その生涯を描いた本書は、「司馬遼太郎さんとわたしの人生」が「交叉」した地点となった。
戊辰戦争において会津藩降伏を取り仕切った秋月悌次郎は、維新後は死者の影を背負い、≪自己を主張することを価値とした近代日本のなかでは永遠に失われてゆかざるをえないような、伝統を守って生きる人間の生き方の正道を踏もうとした懐かしい人≫であった。──「懐かしい」は司馬遼太郎さんが使う最大の褒め言葉である。(あとがき)≫

何年か前に、中野孝次の『「生き方の美学』を読んで、幕末の会津人、秋月悌次郎の人間性に触れた。これは拙ブログ「北越潜行の詩」2006-02-13にも書いた。
先日、月に一度の検診日に本棚から持参した本だ。待ち時間に、斜め読みしてもろもろ思いを巡らした。
秋月悌次郎は、幕末の京都で守護職を務めながら時代に翻弄され、逆賊の汚名を一身に集めてしまった会津藩主・松平容保公のそばにあって、公用方を務めた一人だ。この幕末史のなかでの一文官の生き方は感動である。
生き方の美学の『第19話 徳・・・ハーンと秋月悌次郎』には、熊本五高で同僚だったラフカディオ・ハーンが、悌次郎を「神様のような」人と呼んで尊敬したこと、熱意ある教育者として、学生に慕われたとが書かれている。そして、中野孝次は「百年たった今、この明治日本を担う新興青年が何が何でも古い日本の価値を否定して、西洋の実学を取り入れるしかないと言い張る、こうした-徳よりも実利の学を-、という国家を導いてきた結果、現代日本はまさに世界でも珍しく「徳」というものがない国になってしまったのではないか」という。また、ハーンは、「旧体制の下で育った日本人は礼儀しく、利己的でなく、善良でみなのびやかであった。それはいくら褒めても褒めたりぬ美徳である。」と書いている。
病院の帰りに短大図書館に寄り、松本健一著『秋月悌次郎 老日本の面影』(1987年 作品社)を借りてきて一気に読んだ。「生き方の美学」に紹介されていた本だ。
ハーンに与えた印象を手掛かりに、幕末から明治に生きた秋月という人物の持っている意味、歴史における革新と伝統の関係、そして秋月に係わった人物たちの像が書かれていた。秋月の人格的な温和さ、それを支える思想的中庸のエトスは、維新史の動乱をかいくぐって手に入れた「常民の心」だと述べられていた。
五高での秋月翁の古希のお祝いで諸氏が語る秋月の人間像に、人として尊いものを再確認した。それは、「教育は結局教える人の生き方の問題に凝縮される」という言葉にあるように、地位とか名誉ではなくその人の人間性だと思った。尊敬されるものはその人となりである。
数年前に読んだ、中村彰彦著『落花は枝に還らずとも 会津藩士・秋月悌次郎』でも同じような感動を得た。 著書名「落花は枝に還らずとも」は、文中にあった。
「一度枝を離れた落花は、その枝に還って咲くことは二度とできない。しかし、来年咲く花の種になることはできる。
会津滅藩に立ち会い、亡国の遺臣と化した悌次郎は、自身を落花になぞらえることにより、逆風の時代になおかつ堪えて生きる覚悟を初めてあきらかにしたのである。」
また、いずれの本にも、二人の詩人の素晴らしい漢詩が紹介され、あらためて二人の感懐がよくわかった。
特に、長州藩・奥平謙輔との往復書簡にはこみ上げるものがあった。秋月は、会津藩落城後に藩の寛容な処分を訴えに旧知の長州藩士奥平謙輔のもとへ、猪苗代から新潟へ秘かな雪中行の折り、の胸を打つ「北越潜行の詩」を残した。
有故潜行北越帰途所得 会津 秋月胤永
--------------------------------
行無輿兮帰無家 行くに輿無く 帰るに家無し
國破孤城乱雀鴉 國破れて 孤城雀鴉乱る
治不奏功戦無略 治は功を奏せず 戦は略無し
微臣有罪復何嗟 微臣罪あり 復た何をか嗟かん
聞説天皇元聖明 聞くならく 天皇元より聖明
我公貫日発至誠 我公貫日至誠に発す
恩賜赦書応非遠 恩賜の赦書は 応に遠きに非ざるべし
幾度額手望京城 幾度か手を額にして京城を望む
思之思之夕達晨 之を思い之を思うて 夕晨に達す
憂満胸臆涙沾巾 憂は胸臆に満ちて 涙は巾を沾す
風淅瀝兮雲惨澹 風は淅瀝として 雲は惨澹たり
何地置君又置親 何れの地に君を置き又親を置かん
--------------------------------
戊辰戦争において会津藩降伏を取り仕切った秋月悌次郎は、維新後は死者の影を背負い、≪自己を主張することを価値とした近代日本のなかでは永遠に失われてゆかざるをえないような、伝統を守って生きる人間の生き方の正道を踏もうとした懐かしい人≫であった。
以下は松本健一著『秋月悌次郎 老日本の面影』(勁草書房)のネットの内容説明である。
≪ラフカディオ・ハーンをして「神様のような人」といわしめた会津藩士秋月悌次郎。その生涯を描いた本書は、「司馬遼太郎さんとわたしの人生」が「交叉」した地点となった。
戊辰戦争において会津藩降伏を取り仕切った秋月悌次郎は、維新後は死者の影を背負い、≪自己を主張することを価値とした近代日本のなかでは永遠に失われてゆかざるをえないような、伝統を守って生きる人間の生き方の正道を踏もうとした懐かしい人≫であった。──「懐かしい」は司馬遼太郎さんが使う最大の褒め言葉である。(あとがき)≫












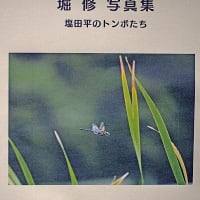








私が今ボランティアで福島県の学校に出かけている理由は子供達の心に信念を持つことの大切さがわかって欲しいが為である。辛いことから逃げる日本人に一番必要なのは武士道の精神、氣の教育である。私は東京都私立中高協会の生き方教育研究会で今月17日に講演をする。
『福島に元氣を!3.11復興支援プロジェクト』代表