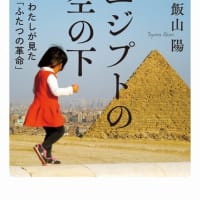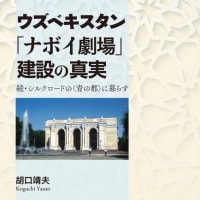ある公立高校の卒業式で、一部の教師と生徒が「君が代」斉唱を拒否したが、式の退場行進のバックには「威風堂々」(エルガー作曲)を使ったという実話を紹介したことがある。これは風聞などではなく、私自身がその現場にいて体験した事実だ。
英国の第2の国歌とされる「威風堂々」を生徒自身が選曲し平気で流すのに、「君が代」斉唱は断固拒否する…この珍妙な体験が出発点になって、私は「国歌」「愛国心」について考え始めた。
「海ゆかば」という曲がある。戦時中は「第2の国歌」ともされた曲で、祖国に殉じた兵士達の鎮魂の歌となった。
「海ゆかば みずくかばね 山ゆかば 草むすかばね 大君のへにこそ しなめ かえりみはせじ」
歌詞は、大伴家持の歌から採られ、信時潔が作曲している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E3%82%86%E3%81%8B%E3%81%B0
大戦後は、「日本軍国主義」の歌曲として永く封印され、正当な評価を受けることはなかった。「大君」(おおきみ)は天皇のことであり、「かばね」は屍のことである。天皇制を礼賛しているではないか、という理由である。事実、学徒動員で海軍に徴兵され、多くの戦友を失った、私の父は、決してこの歌を歌うことはなかった。その気持ちは十分分かっていた。だが、ことはそんな単純なのだろうかと私は疑った。大伴家持による歌詞は、少なくとも戦争を鼓舞したり、天皇を賛美するものではない。英国の準国歌「威風堂々」が、「世界中にひらめくユニオンジャック」とか歌っているのとは、むしろ正反対なのだ。
今や、若い人がこのメロディを聴くとすれば、右翼の街宣車のラウドスピーカーを通してだけかも知れない。歴史に対する無知は、さらなる悲劇をもたらしかねない。
2000年、声楽家・藍川由美が「”國民歌謡~われらのうた~國民合唱”を歌う」(DENON COCO83299)をリリースした。戦前・戦時中、NHKラジオの「國民歌謡」で採り上げられた曲を集めたCDだが、この中には「椰子の実」「春の唄」「朝」などと並んで「海ゆかば」が収められている。
藍川自身のライナーノーツによれば、「海ゆかば」はこう説明されている。
「…歌詞は万葉集所収の大伴家持の長歌からとられている。この詩にはすでに明治13年に宮内省伶人の東儀季芳が海軍の礼式歌として作曲したものがあったが、昭和18年2月に文部省と大政翼賛会が信時潔(1887-1965)作曲の歌を儀式に用いると決めたため、準国歌的な役割を果たすこととなった。」
藍川自身が歌う「海ゆかば」は、クラシックの小品のような仕上がりである。肩肘を張って勇壮に歌うわけではないので、かえって大伴家持の歌詞が浮き上がってくる。
「海ゆかば」は軍国主義、「君が代」は非民主的などと…聞いたような文句はいくらでも言えるのだが、そういう悪口を言う人間に限って、「大英帝国」を賛美する「威風堂々」を無自覚にも流したりする輩なのだ。
近代以降、ほとんどのアジア諸国は欧米列強の植民地と化した。欧米列強と唯一対抗することが出来た我が国には、植民地の苛烈な収奪からアジア人民を解放するという思想が生まれた。「アジア主義」である。「大東亜共栄圏」の構想は、「アジア主義」の具体的な結実であり、不幸にして勃発した戦争は「太平洋戦争」などではなく「大東亜戦争」であったことは疑いない。
こんなふうに書くと、まるで「右翼」の主張のようだが、そんなことはない。「海ゆかば」を聴くと、戦後日本の歪んだ精神史が浮き彫りになってくるようだ。