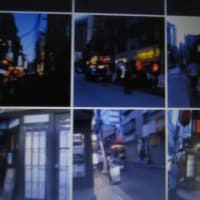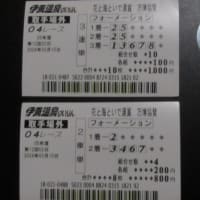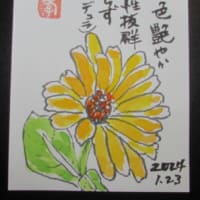太宰治の作品と生涯を解き明かした決定版
時代とともに作家のイメージや、作品の読まれ方も変化しつつも、多くの読者から支持され続ける太宰治の文学を総合的に解き明かす。激動の時代を忠実に生き、不器用さから時代錯誤を演じ続け、絶望を深めながら自身の宿命に殉じていく一人の人間像、そして日本の近代のあり方までも浮き彫りにする日本文学研究を牽引する著者による太宰治研究の決定版。東京大学出版会創立70周年記念出版。
【本書の特色】
●国語の教科書で常連の『走れメロス』『富嶽百景』やベストセラー『斜陽』『人間失格』はもちろん、習作時代のノートの落書きまであらゆる太宰作品を徹底的に分析。
●最近でも映画化やマンガ化されるなど、没後70年以上を経てなお若い愛読者も増え続ける太宰治の魅力が解き明かされる。
●同時代の作家や俳優たちとの交流、有名な肖像写真にまつわるエピソードや、実家である津島家についての新資料など太宰治の全貌が明らかになる。
【本書「序 太宰治の時空間」より】
太宰治はもはや必ずしも「無頼派」ではない。周囲の人間との距離やへだたりを言葉でいかにつくり出していくべきかという課題に、さまざまなヒントを与えてくれるのだ。
未曾有の情報化社会の中で、われわれは、人間相互の距離をどのように策定していけばよいのか、という喫緊の課題に直面している。(中略)太宰は昭和前半期の激動の時代を生き抜き、言語的実践を通して果敢にこの問題と対峙し続けた。「君にだけ教えよう」「君だけは分かってくれるにちがいない」とひそかにささやきかけてくれる〈心づくし〉の文体は、こうした状況に対し、あらたな「連帯」の可能性を提起してくれることだろう。
【主要目次】
序 太宰治の時空間
第I部 揺籃期
第1章 「百姓」と「貴族」
第2章 〈自尊心〉の二重構造
第3章 〈放蕩の血〉仮構
第4章 「哀蚊」の系譜
第5章 津軽と東京と――〈二百里〉の意味するもの
第II部 『晩年』の世界
第1章 習作から『晩年』へ
第2章 『晩年』序論
第3章 山中の怪異――「魚服記」論
第4章 回想という方法――「思ひ出」論
第5章 寓意とはなにか――「猿ケ島」「地球図」論
第6章 自殺の季節――「道化の華」論
第7章 自意識過剰と「死」の形象
第8章 「小説」の小説――「猿面冠者」論
第9章 詩と小説のあいだ――「玩具」論
第10章 散文詩の論理――「葉」論
第11章 『晩年』と“津軽"――「雀こ」ほか
第12章 転向・シェストフ・純粋小説
第13章 〈嘘〉をつく芸術家――「ロマネスク」論
第14章 現実逃避の美学――「逆行」論
第III部 中期の作品世界
第1章 “罪"の生成――『晩年』の崩壊
第2章 「太宰治」の演技空間――「ダス・ゲマイネ」を中心に
第3章 第二次“転向"の虚実――未定稿「カレツヂ・ユーモア・東京帝国大学の巻」を中心に
第4章 〈懶惰〉の論理――「悖徳の歌留多」から「懶惰の歌留多」へ
第5章 〈自己〉を語り直すということ――『愛と美について』論
第6章 「生活」と「芸術」との齟齬――「富嶽百景」論
第7章 「女生徒」の感性
第8章 女がたり
第9章 「小説」の条件――「女の決闘」論
第10章 メロスの懐疑――「走れメロス」論
第11章 太宰治と“東京"――「東京八景」を中心に
第IV部 戦中から戦後へ
第1章 戦中から戦後へ
第2章 蕩児の論理――「水仙」「花火」
第3章 「津軽」の構造
第4章 翻案とパロディと――「新釈諸国噺」論
第5章 「八月一五日」と疎開文学
第6章 〈桃源郷〉のドラマツルギー――「冬の花火」と「春の枯葉」
第7章 戦後文学と「無頼派」と
第8章 戦後の女性表象――「ヴィヨンの妻」を中心に
第9章 「斜陽」における“ホロビ"の美学
第10章 「悲劇」の不成立――「人間失格」論
第11章 関係への希求――「人間失格」の構成
第12章 「人間失格」の創作過程
第13章 最晩年の足跡
著者について
東京大学大学院人文社会系研究科教授、専門は日本近代文学。1958年生まれ、1982年東京大学文学部卒業、1987年東京大学大学院人文社会系研究科博士課程中退。