目次より
プロローグ 言葉の多面的な働き
第一章 母語としての日本語の意義
第二章 言葉の力の基礎づくり
第三章 体験から知識へ、知識から体験へ―言葉に導かれて
第四章 体験の経験化と言葉
第五章 古典的な名句・名文の暗唱を
第六章 文学作品との出会い
第七章 確かな読み取りで豊かな受け止めを
第八章 「読み」「書き」の力を三つの水準で
第九章 論理の力を育てる言語論理教育を
エピローグ 言葉の力を鍛えて賢さの実現を
あとがき
コラム
世界最小の定型詩「狂俳」
古典の学び
熟読と多読と
記述式応用問題を解く力
語彙力
「書く」ということ
実りある対話を土台とした自己内対話を
「読み・書き・計算」の反復練習を
言葉の表の意味と裏の意味を
〈識者が語る 未来を開く池田思想〉 聖ウルスラ学院理事長/教育心理学者 梶田叡一氏2024年6月11日
- 子どもの生命を開花させる
- 「創価の人間教育」を今こそ
学校法人・聖ウルスラ学院理事長の梶田叡一さんは、日本を代表する教育心理学者です。これまで兵庫教育大学など5大学で学長を歴任し、文部科学省中央教育審議会の副会長を務めたことも。敬虔なカトリックでもあります。梶田さんは教育改革が進む日本の現状を踏まえ、「創価学会初代会長・牧口常三郎先生の教育論に、時代がようやく追いついてきた」と語り、第2代会長・戸田城聖先生から第3代会長・池田大作先生へと受け継がれてきた「創価の人間教育」に大きな期待を寄せています。その理由を伺いました。(聞き手=大宮将之)
問われる私たち大人の「生き方」

本題に入る前に一つ、いいですか。
先日、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇と創価学会の原田会長が、バチカン市国で会見をされましたね(現地時間5月10日)。私は一人のカトリックとして、また約50年にわたり創価学会の運動を見続けてきた者として、とても感銘を受けたんです。
片や西洋のキリスト教最高指導者、片や東洋を代表する仏教団体のリーダー。信仰は異なれど、人類の平和と幸福を目指し、より開かれた“世界宗教”へと不断の改革を進めている点において、双方は共通しています。その意味でこの会見は、大変に象徴的な“東西の対話”でした。

フランシスコ教皇との会見を報じる本紙
ようやく時代が
〈ありがとうございます。そもそも、梶田先生が創価学会に関心を抱かれたきっかけは、牧口先生の創価教育学説との出合いだったそうですね〉
私の心理学の恩師である波多野完治先生(1905~2001、お茶の水女子大学元学長)から紹介されたんです。波多野先生は、「生涯教育」という概念を日本で初めて示された人でした。若い頃から、牧口先生の教育学に高い評価を寄せ、それに関する本も出されています(第三文明社刊『牧口常三郎全集』の編集顧問も務めた)。
私自身は後に、創価学会教育部の方々との交流を通じて、牧口先生のご著作をひもときました。その中で“わが意を得たり!”と思ったことが、特に二つあります。一つは、牧口先生の教授法のメモに記されていた“法華経に説かれる「開示悟入」と教育との関わり”について。もう一つが、富国強兵の政策と軍国主義教育が行われていた時代にあって、「教育は児童に幸福なる生活をなさしめるのを目的とする」(『創価教育学体系』)と断言された点です。

牧口先生の大著『創価教育学体系』。発刊日は1930年11月18日となっている
ひるがえって日本の教育界では近年、子どもの「学習」と「成長」に対して責任ある教育指導が、ますます求められています。また昨年6月に閣議決定された「第4期教育振興基本計画」においては、「ウェルビーイング」という概念が大きな柱として取り上げられました。
ウェルビーイングとは、「Well(良い)」と、「being(状態)」が、組み合わさった言葉です。「身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること」で、「短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含んだ概念」と定義されています。これはまさに、牧口先生の創価教育学説に説かれていたところでもあります。
こうした流れを踏まえ、私は「時代が牧口先生にようやく追いついてきた」との感を強くします。一つずつ、お話ししましょう。

開示悟入と教育
〈法華経方便品に説かれる「開示悟入」を、牧口先生は教育原理として着目し、世に示しました〉
聖教新聞の読者の多くは仏教や牧口先生について勉強されている方々だと思いますので、説明するのはそれこそ「釈迦に説法」かもしれませんが(笑)。
「開示悟入」は、「仏は何のためにこの世に出現したのか」という問いへの答えとして、出てきた言葉なんですね。それは、衆生をして仏の智慧を「①開かしめんがため」「②示さんがため」「③悟らしめんがため」「④入らしめんがため」――つまり、「一切衆生を成仏させること」が仏の目的だというんです。では、この4段階を教育に置き換えるとどうなるか。
「開く」とは、子どもたちの心を活性化させ、先入観や偏見を取り除き、学びの対象となる世界に“目を開かせる”ことと言えるでしょうか。
「示す」とは、子どもたちが学びのポイントや意義、用語の意味などが分かるように示すこと。
「悟らしめる」とは、学びの対象の良さや味わいを、自分なりに発見し、深め、納得できるようにさせることです。
「入らしめる」とは“その道に入り込ませること”。学んだことが日常生活に生かされ、実際の行動につながっていくようにすることと言えるでしょう。

「開示悟入」が明かされる法華経方便品の箇所(妙法蓮華経並開結121ページ)
「開く」ことから
〈牧口先生、そして梶田先生も、とりわけ「開く」を強調されていますね〉
心を開いた上で示さないと、効果はないからです。納得も感動も生まれないから、「悟らしめる」「入らしめる」ことにもつながりません。
実は、法華経のサンスクリット語の原典には「開」に該当する部分がなく、「示悟入」だったんですね。「妙法蓮華経」の漢訳者・鳩摩羅什が翻訳する際、独創的に「開」を付け、開示悟入としたようです。
この「開く」には、あらゆる人々の中に仏性(仏の生命)が本来、具わっているという大前提があります。具わっているのだから、開けばいい。けれど凡夫は、それをなかなか信じられない。だから仏は、種々の譬喩や物語を通して「信」を起こさせようとしたのです。
教育に話を戻すと、日本には長い間、本来具わっている無限の可能性を「開く」ための工夫や問いが欠けがちで、「示す」ばかりになっていました。「これは大事なことだから、とにかく覚えなさい」とか。
2000年代初頭からは「ゆとり教育」が本格化しましたが、実態はどうだったか。「子どもに寄り添う」「指導ではなく支援を」というかけ声ばかりが全国にこだまし、子どもを手放しで見守るだけの状態になっていなかったか。「子どもには無限の可能性がある」と口で言うだけなら“きれいごと”です。その可能性を開くために働きかけをするのが大人の責任でしょう。
2008年に、新しい学習指導要領が告示される前後から、教育界の空気は大きく変わり始めました。牧口先生の教育指導法と合致した「着実で責任ある指導を」という方向へと、向かっていったのです。
私が理事長を務める聖ウルスラ学院では約20年前から、少なからぬ教員が単元の目標分析表と目標構造図を作成する際、「開示悟入」の視点を取り入れてきました。その高い教育効果も、実証されています。

不思議ナケレド
〈「開示悟入」を、例えば小学1年の「アサガオ」を用いた学びに応用すると、どうなるでしょうか〉
あくまで一例ですが、まず「みんなはお花を育てたことはある?」といった問いから始まり、いろんな花の写真を見せたり、実際に種を触らせてみたりする。「育てる人が『きれいに咲いてね』と愛情込めて育てる場合と、そうでない場合とでは、育ち方に違いが現れるともいわれているんだよ」「自分のアサガオに名前を付けてみようか」等と呼びかけるのもいい。
大事なことは、一人一人が「これは自分が育てるアサガオなんだ」と感じられる手立てをとることです。これが「開」ですね。

子どもたちが興味・関心を持ち、「これは自分が育てるアサガオなんだ」と感じられる手立てをとる(イラスト・迎朝子)
次に「示」。具体的な世話の仕方などを教えます。世話の途中で、つるが伸びすぎて倒れそうになったり葉っぱに元気がなくなったり、さまざまな問題が起きるでしょう。その問題点を児童たちで共有し、どう解決するかを考えさせる。上級生に質問する仕組みを整えても、いいかもしれません。
こうして次第に「悟」へ進みます。この過程でアサガオの生命活動を見つめ、「生命とはどういうものか」を実感させることが大事なんです。その気持ちがあれば、教師の言葉がけも変わってくるでしょう。

具体的な世話の仕方などを教える(イラスト・迎朝子)

子どもたちがさまざまな問題と向き合いながら、「生命とはどういうものか」を自分なりに考え、深め、納得していけるようにする(イラスト・迎朝子)
北原白秋の詩に「薔薇ノ木ニ薔薇ノ花サク。ナニゴトノ不思議ナケレド」とあります。この「ナケレド」を子どもに実感させてあげられるかどうか。バラの木にバラの花が咲いても、何の不思議もない。けれど「当たり前でしょ」で片付けてしまったら、生命の実感は出てこないんです。
アサガオだって、あんな小さな種から、あんな素晴らしい花を咲かせる。自分で苦労して育ててみると、「ナケレド」に気が付くわけです。そこから自分たちが今、存在している不思議さにまで思いが広がり、生命を慈しむ日常の行動にまでつながれば、まさに「入」といえるでしょうか。

“自分だけのアサガオ”を苦労して育て、生命の不思議さを実感した子どもたちは、ほかの生命にも温かなまなざしを向けられるようになる(イラスト・迎朝子)
関わりの時間
〈アサガオを育てる意味が、人格の価値を創造するところまで高まる。まさに価値創造ですね〉
これに通じる話が、サンテグジュペリの『星の王子さま』に出てきます。遠くの小さな星から王子さまが地球にやって来て、いろんな所に行っていろんなものと出会い、いろんなものを眺めて、いろんなことを考えるという物語ですね。
ある日、その王子さまは5000本程の素晴らしいバラの花が咲く庭に着く。そこでふと、小さな星に残してきた、自分が世話をした貧弱なバラのことを思い出すんです。目の前にあるバラのほうが、ずっと美しい。けれど“大切だな”と思うのは、星に残してきたバラなんですね。
あのバラはワガママで、育てるのにはとても苦労した。けれど「関わりの時間」と「つながり」があったから、かけがえのない「自分だけの花」になった。これが生命の実感ということでしょう。










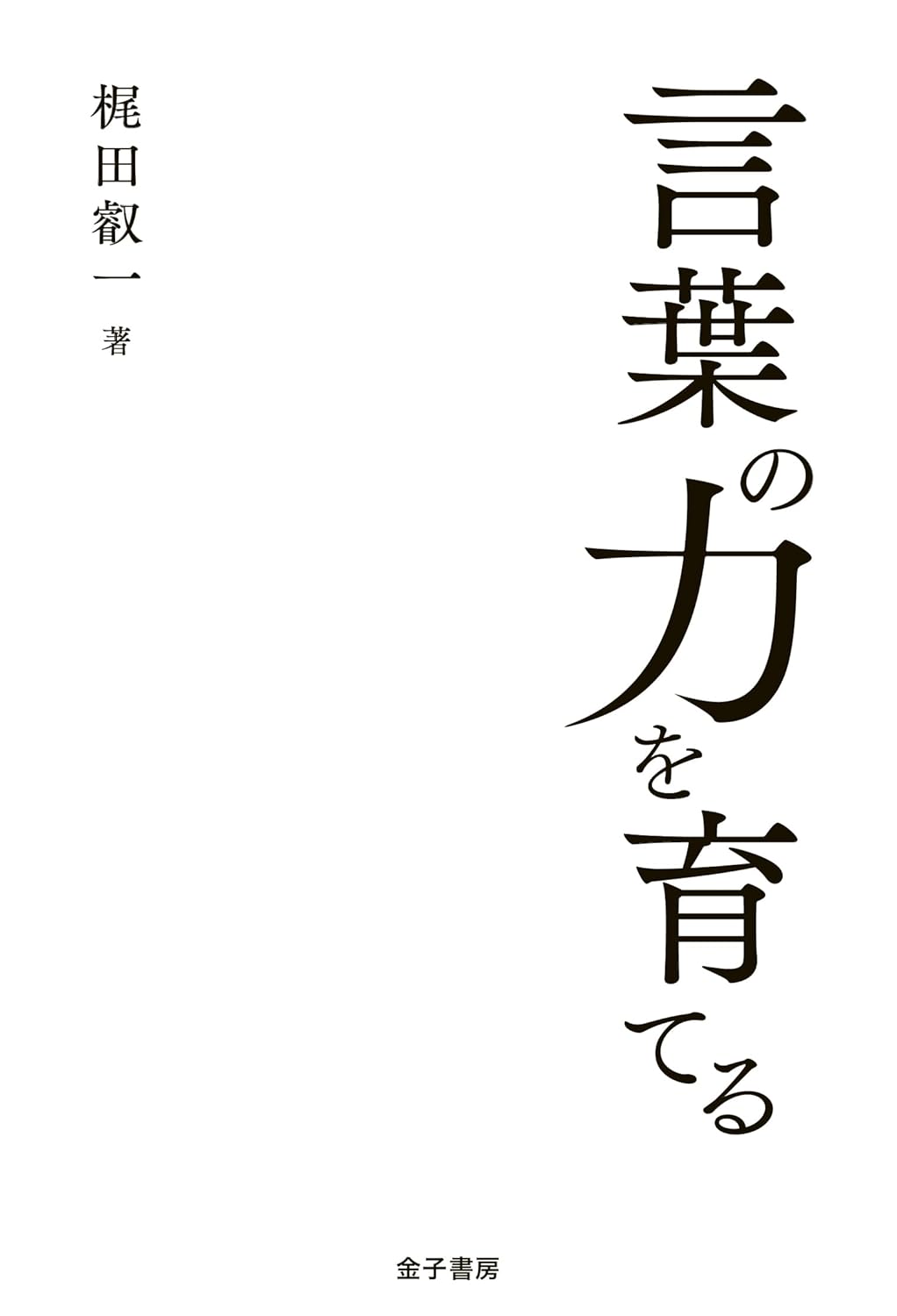









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます