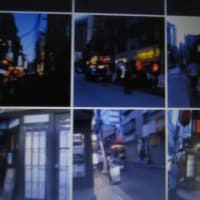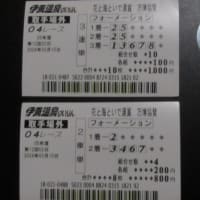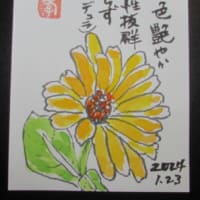日々当たり前の状態になっている、民主主義とは何かを考えた評論。
終章の結論に、
「リベラル・デモクラシーという政治・社会システムの下では、政治参加は、個人の自由や権利を守る限りにおいて価値のあるものだからです。
政治参加がもたらす実際の『効果』を強調するような、言ってしまえば『現金』な議論が横行するのも無理はありません。
そして現行秩序の下で自らの自由や権利が保障されている(と感じている)人が、政治にあまり関心を抱かないのも無理からぬことです。
だからこそ、リベラル・デモクラシーは共和主義や社会主義といった思想的要素を積極的に採り入れるべきだというのが本書の結論です。
政治参加を『義務』の問題として捉える共和主義はリベラル・デモクラシーを相対化し、また個人に対する社会の影響を強調する社会主義は、政治にできることの射程を広げます。『社会』を構成しているのは、究極的には『個人』です。
それゆえに、どれだけ微小なものでもあったとしても、個人は社会のあり方に対して責任があります。
そしてまた、社会のあり方は個人に対して影響を与えます。
私たちは同時代的な社会のあり方だけでなく、歴史的に長く続いてきた伝統によっても思考を規定されます。
しかし『伝統』というのは結局のところ人間の産物であり、その意味で私たちは過去の人間による想像の産物によって自分たとの想像力を縛られているのです。
リベラル・デモクラシーが歴史の執着地点とは限りません。
私たちのシステムには改善の余地がある。
そうした信念に基づき、政治思想はこれまでの歴史の中で、世界のあり方に何度も変更を加えてきました。
神ではないが、動物でもない人間。そのような存在だからこそ、人間社会には『政治』というものの余地が生まれてきます。
民主主義というバベルの塔は、それだけでは大変心許ないものです。だからこそ、それは自由主義、共和主義、社会主義といった『支え』を必要とします。
その意味ではバベルの塔というよりも、破壊と再生を繰り返しながら現代までしぶとく残り続けたパルテノン神殿の柱の一つにたとえたほうが的確かもしれません。
いずれにせよ、民主主義はいまの政治の世界を構成する政治思想のうちの一つにすぎません。
それは善き統治の必要条件ではあっても十分条件ではありません。
一つの原理に拘泥することなく、目的達成のためであれば状況に応じて異なる原理を利用することも厭わない。民主主義国家の主権者たる市民には、このようなマキアベッリ的君主であることが求められていると言えるでしょう」
と書いてあり、自由主義、共和主義、社会主義の定義に関しては、
自由主義
公的なものよりも私的なものを優先し、プライベートの充実を目指すヘレニズム思想
ヘレニズム思想に見られたような「私的なるものの優越」だけでなく、このような「個人の価 値」を前提とした理論
共和主義
「王の不在」「共和制」が「王政」ないし「君主政」と区別される目印
「混合政体」「直観によって得られた感覚的な知識は間違っているかもしれない」という自制的な視点
社会主義
自らの私有財産に対する愛着という自然的感情を統治や公益のために利用し、市場経済における「見えざる手」による自然調和に運命を委ねる経済自由主義(資本主義)に対抗して、政府という機関を通じて市場経済を人為的統御の下に置き、また貧困や自殺など、それまでに個人の問題として処理されてきた事象を「社会問題」として捉えることにより、国家全体で社会問題の人為的解決を図る思想
という風になっておりました。解釈が違ったらすいません。
昔の西部劇で「真昼の決闘」という傑作とされる映画で、ならず者が釈放されて、報復で捕まえた保安官のところに戻ってくるのが判り、町でその保安官を排除しようとしたり、できなかったら逃げ出したり・・・という展開で、最後は保安官が助かりますが、保安官のバッヂを捨てて町を出ていく所で終わりになる、という作品でしたが、民主主義は当たり前の様に享受しているだけではダメで、日々国民(或いは市民)で実現させないといけない、という事でしょうか。
日本の憲法の前文でも、最後に「不断の努力によって実現させなければならない」と書いてあって、努力しないと実現しない、努力目標らしいですが、私が努力しているかと聞かれて、はっきり言って何もしていなかったり・・・というしょうもない中年です。すいません。
ただ、文中に「市民の義務としての反乱」という言葉が出てきますが、人によっては、革命、暴動、クーデター、と捉える人もいらっしゃると思うので、平和に選挙で解決しようと補足しても良かったかもとも思いました(解釈を間違えていたらすいません)。
少々難解で、大学にも行っていない輩には難しい所もありますし、メモを取りながら読んだら、殆どの所をメモしないといけなくなるぐらいの情報量でしたが、民主主義の事が判ったー(つもりですが)ーので良かったです。
民主主義はただ享受しているだけでは実現しない、という評論。必読。