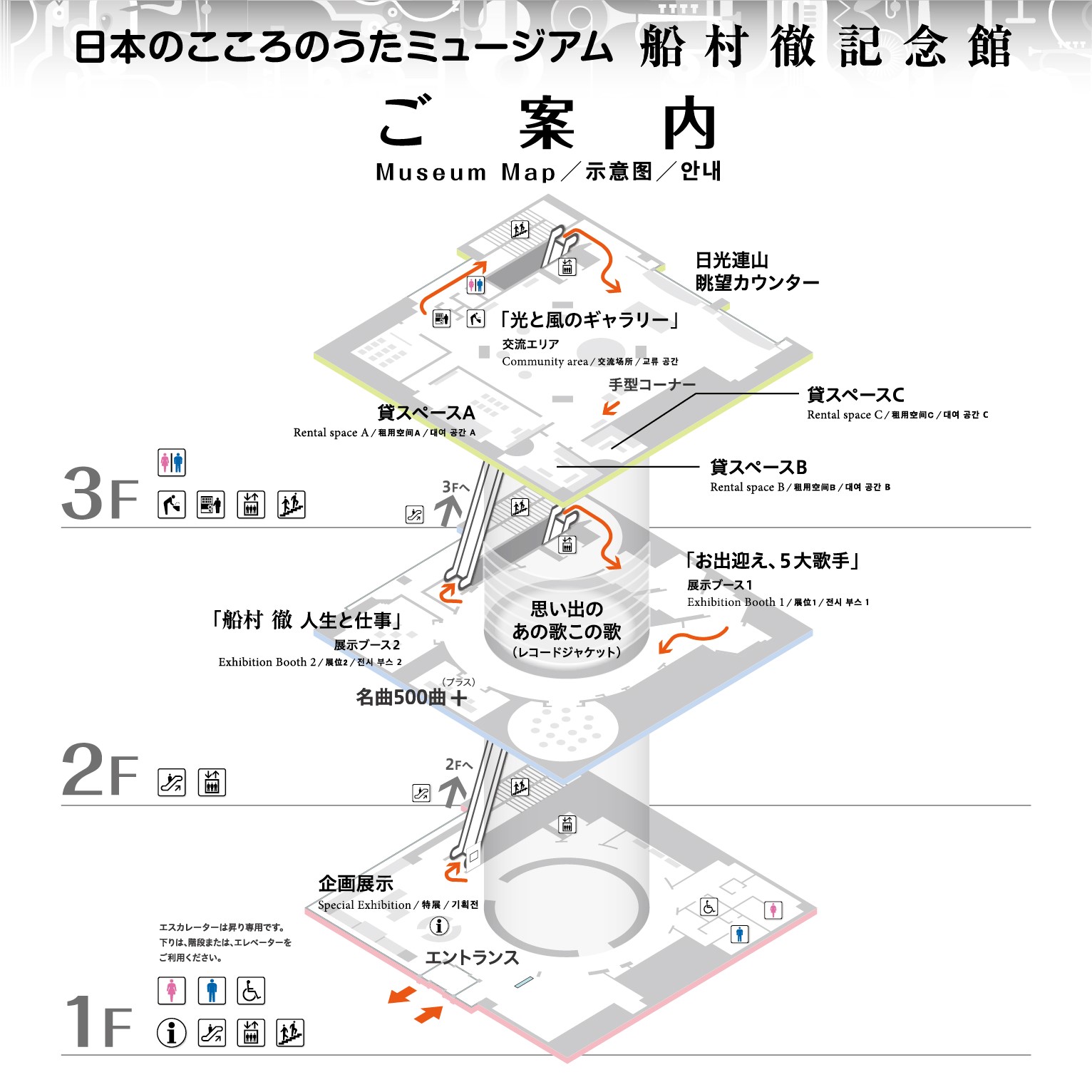私が無罪となり、再就職した共同農業新聞社は、上野駅に近い昭和道り面した雑居ビルの5階にあった。
私は記者ではなく、広告とりの営業マンとして採用されたのだった。
農業は機械化され、個人の農家まで農機具が普及していく時代である。
「君はな、頑なになっているのではないか?広告とりは、決して難しいものではない」口髭を生やした加賀太郎社長は、ヒトラーの様な容貌をいていた。
私は、初めての営業に気乗りがしなかったのだ。
そして、事務員の村岡純子は「社長は強引な広告とりをしている。ヒトラーを尊敬しているのよ。変わった人」と言うのである。
純子は、38歳で独身であった。
私は昼休みに妻が用意した弁当を食べていた。
「愛妻弁当か」純子はため息をつく、彼女は自分が作った弁当を食べていた。
3人の記者たちは外食だった。
農機具の特集のために社長は地方へ出張していた。
加賀社長は、全国共同農業協同組合連合会をバックにするような営業方針だった。
つまり、営業企画書には、全国共同農業協同組合連合会が協賛しているような表現と地方の傘下共同農業協同組合の理事長印まで押されていた。
純子はその日、「私がおごるからね」と私を上野のアメ横近くの居酒屋へ私を誘った。
その日は、私は大津典子と会う約束をしていたが、連絡の取りようもなかった。
まだ、携帯電話は普及していなかったのだ。
2軒の梯子酒になるが、純子は酒が強い女だった。
私の方が先に酔ってしまった。
「南さん、私を神楽坂まで送ってよ。いいわね」二人は中央通りからタクシーに乗った。
純子の住まいは、神楽坂の路地裏の2階建てアパートの6畳一間だった。
純子は、私が抱いた初めての太めの女である。
下北沢のアパートへ、妻が息子連れて福島の実家から戻って来てきいたのだが、私の不祥事を妻が許さねば離婚する他ない状態が続いていた。
妻は、私と寝ることを、かたくなまでに拒絶していたのだ。
私は、尚子が想像すらできないような浮気な男に成り下がっていた。