
遮る雲が無ければ、全国的に国際宇宙ステーション(ISS)/きぼうを見るチャンスです。日が沈んで暗くなった空を見上げて、国際宇宙ステーションの姿を探してみてください。
(通過時間は、多少前後する可能性がありますのでご了承ください。)

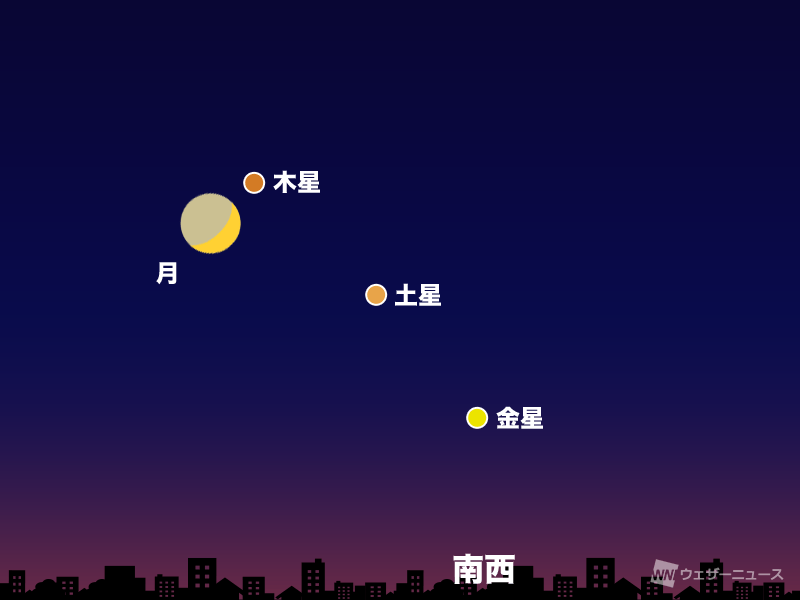

▼世界貢献の人材の育成
▼教育は<対話>によって人間の成長を促す。
▼人類の変革と発展を目指した世界規模の大学。
▼人類の未来のために平和を希求する。
▼平和な人間共和の世界を築く。
▼人間主義、人権の世界的ネットワーク、人間の尊厳を掲げる。
▼「多用性」大学においては、多様性は基本的に最も優先すべきものだ。
多様性は、包括的な社会を促進するだけでなく、世界全体に存在する深刻な不平等の問題を克服するための基本的ステップだ。
▼クオータ制(割り当て)の導入。
人種問題に対する不平等に立ち向かう必要な条件だ。
▼「持続可能性」である。
学内でプラスチックの使用を認めない。
▼エネルギー基盤の多様性を推進する。
学内に太陽光発電所を設置する。
国内でも、自然環境に対する破壊行為を続けている。
▼政治は政治家だけに任せるものではない。
社会や地球全体で抱えている深刻で緊急性の高い問題を認識することは、基本的なことだ。
▼平和のための事業を構築するのは、生活の質を高めるための具体的な条件に基づいて、良い対話と意見交換が不可欠だ。
▼政治とは「自由」である。
「自由」とは、より良く暮らし、社会の運命を決定する、共生の時代を生きるための必要不可欠な条件だ。
▼大学のモットーの一つは人間教育において、<人間を変革し、その人間が世界を変革する>ことにある。
つまり、世界に貢献する人材を育成する。
「世界平和のためのリーダー」を育成する。
▼教育のためのSDGs(持続可能な開発目標)と平和の文化を推進していく。
持続可能と平和の文化を若者の教育の必須カリキュラムとして取り入れる。
2006年08月28日 中原隆一
1.大学の社会的位置づけ
| <fontsize="-3">*「我が国の高等教育の将来像(答申)」:平成17年1月28日中央教育審議会 [大学の機能] ①世界的研究・教育拠点②高度専門職業人養成③幅広い職業人養成④総合的教養教育⑤特定の専門的分野(芸術,体育等)の教育・研究⑥地域の生涯学習機会の拠点⑦社会貢献機能(地域貢献、産学官連携、国際交流等)</fontsize="-3"> |

潮木守一著
大学が危機に直面しているのは日本だけではない。 先進国の大学は、第二次大戦後に拡張政策をとったために、それぞれ構造的な問題が生じている。 古典的な高等教育を維持しようとするイギリス、平等な公立大学の限界から脱出しようとするドイツ、大学以外の高等教育機関との調整に苦慮するフランス、そして、大学院化が一層進むアメリカ。 それぞれに事情の異なる各国の対処法から日本の大学が学ぶべきことは何か。
第1章 イギリスの大学
第2章 ドイツの大学
第3章 フランスの大学
第4章 アメリカの大学
第5章 大学拡大政策の背景
第6章 知識のディズニーランド
--------------------------------------------
日本の大学のこれから、受験戦争、大学を筆頭とする教育界全体のこれからを考える。
子どもにとっての受験、親にとってのお受験、社会人にとっての資格試験など、さまざまな人のための「必勝術」指南。
アメリカ・フランス・イギリス・シンガポールでは、エリートはどのように作られていくのか。ローズ奨学金制度とはなにか、日本のエリートはどこをめざすのかなどについて。
子どもの学力は低下しているかどうかの議論。学力低下を招いた要因の追求。大学生の学力の実態。問題の背後にある教育制度や改革について。
アメリカの経営大学院の実態を詳細に紹介。ハーバード・ビジネス・スクールの基本理念や授業内容、そして学生たちが得るものとは。社会人大学院を利用して取得可能な資格の中身とその活かし方。急増する社会人大学院の実態。
教育問題が大きな社会問題となり、教育改革の必要性が叫ばれている。その実態や方向性、問題点など。
社会性に乏しい教師がいる一方で、心の病にかかる教師も多い。クレーマーと化した無理難題を要求する親の存在が学校を脅かす。いま学校で何が起きているのか。「学校再生」に必要なものとは。
就職活動に関する疑問とその背後にある社会的要因の解明。日本の転職事情の変化とリストラ時代をチャンスに変える法。再就職支援のプロが教える自分の"売り"の作り方から面接での受け答えまで。
ソ連崩壊後、唯一の超大国として世界に君臨するアメリカ。その政治経済を牛耳るアメリカのエリートはどのように作られるのか。その実態と実像を報告。
日本の学校教育、家庭での躾、古典の素養や道徳観、宗教心など日本人の身につけている教養などから、現代の日本人像を考える。

大学教育のあるべき姿とは何か。近代大学の成立以来、学術自体の価値という面から、また国家や社会が抱えるニーズへの対応、そして「消費者」としての学生への対応など、大学教育のあり方は、大学の役割の多面性を背景に多様に論じられてきた。
現代の社会・世界の変化が大学教育に何をもたらし、大学教育に何を求めているのかを考察する。