▼人間を変革し、その人間が世界を変革する。
▼世界に貢献する人材を育成する。
▼世界平和のためのためのの人材を育成する。
▼民衆が形成する草の根運動こそ、世界を変革する鍵である。
▼不和と敵対から平和的共存へと移行する世界に変革する。
▼人権保護、人間の生命の尊厳、持続可能性の開発、平和文化の発展のための教育、核兵器の廃絶。
▼レジリエンス(困難を乗り越える力)が、社会を変える。
▼「多用性」
多様性は、包括的な社会を促進するだけではなく、存在する深刻な不平等の問題を克服するための基本的なステップだ。
▼ブラジルでは「クオータ(割り当て)制が実施されている。
クオータ制とは、格差是正のためにマイノリティに割り当て を行うポジティブ・アクションの手法の一つ。 政治分野におけ るジェンダー・クオータとは、議会における男女間格差を是正 することを目的とし、性別を基準に女性又は両性の比率を割 り当てる制度である。
▼政治は私たちの生活に絶対に必要なものだ。
「政治は政治家に任せるもので、私たちは政治を語ってはいけない」という単純なものではない。
▼私たちが社会や地球全体で抱えている深刻なで緊急性の高い問題を認識することは、基本的なことだ。
▼平和のための事業を構築するためには、生活の質を高めための具体的な条件に基づいて、良い対話と意見の交換が不可欠だ。
▼政治とは「自由」である。
「自由」とは、私たちがより良く暮らし、社会の運命を決定する、共生の時代を生きるための「必要不可欠」な条件なのだ。
2日間、友人との早朝散歩に同行しなかった。
曇空では、星も月も見えないし、新道町内会の婦人が育ている花壇の菊なども見えない。
当方は写真を撮る目的でもある散歩なので、実は午前7時以降の散歩が好ましいと思っている。
でも、散歩仲間の2人は、1年を通じて、午前5時集合なのだ、
鈴木さんは、東京まで自身が経営していたIT企業に通勤してた時代は、散歩のコースが往復2㌔で「からたいの里」までであった。

その元気さに驚くばかりだった。
利根川を行き、帰りは田圃の畦道を歩いていた。
稲が育つ時期には、カルガモ農法を観ながらの散歩だった。
利根川も12月に入り、土手の草が赤く染まってきている。
鈴木さんはそんな利根川堤防の光景を間接的に当方のスマホの映像で観ているばかりなのだ。
「利根川から観る富士山の写真いいね」と言うが自分では実際の光景を観には行かない。
生活習慣を頑なまでに変えない人だ。
![]()
取手市立かたらいの郷
「かたらいの郷」は、1階は研修室・クッキングサロン・和室などのコミュニティの場、2階はつつじの湯・大利根の湯の浴室をはじめとしたリラクゼーションの場があります。
あらゆる世代の交流を目的としたスペースで、どなたでもご利用になれます。
取手市長兵衛新田193番地2
安楽死の願望高まる
スイスの自殺ほう助団体の会員数は増え続けている
国内主要3団体の会員数は昨年末で計17万6493人となり、前年に比べ1万人以上増加した。昨年中、3団体のサービスを利用して自死した人は1503人に上った。国内最大の組織エグジットは「自殺ほう助への需要は依然として大きい」という。
2021/03/15 06:002021/03/15 06:00
swissinfo.ch/ku
他の言語(4カ国語)
エグジットによると、同団体のサービスを利用し自死した人は913人で、前年に比べ51人増加した。理由の36%は末期がん、25%が加齢に伴う多疾患罹患、9%が慢性疼痛で、前年とほぼ同じ傾向だった。82%が自宅で自死した。
安楽死はなぜOK?スイスに住む人達はこう考える
このコンテンツは 2020/09/172020/09/17 自殺ほう助はなぜ、スイスで広く容認されているのか。現地の人たちに聞いた。
会員数も毎年数千人規模で増え、2020年末時点では過去最高の13万5041人(前年比6829人増)に上った。同団体はドイツ語圏、イタリア語圏のスイス国籍保有者、在住外国人の会員にサービスを提供している。
同団体は、需要の高まりの背景に社会の高齢化があると指摘する。昨年、同団体で自殺ほう助を受けた人の平均年齢は78.7歳で、徐々に上昇している。
同団体によると、新型コロナウイルス感染症を理由としたケースはなかった。ただパンデミック(世界的大流行)により、大規模な行動制限措置が敷かれた昨年3月20日~5月20日
-------------------------------------------------
自殺ほう助はなぜ、スイスで広く容認されているのか。現地の人たちに聞いた。
このコンテンツは 2020/09/17 12:112020/09/17 12:11
宇田薫
マルチメディア・ジャーナリスト。2017年にswissinfo.ch入社。以前は日本の地方紙に10年間勤務し、記者として警察、後に政治を担当。趣味はテニスとバレーボール。
筆者の記事について | 日本語編集部
swissinfo.chのジャーナリストと読者をつなぐエンゲージメント担当マネジャーが8月3日、フェイスブックのフォロワーに「なぜ我々は(安楽死に対して)こんなにも寛大なのか?」と聞いた他のサイトへ。以下はユーザーの回答だ。
●ロマーナさん
たぶん、自分が当事者になることがほぼないからじゃない?
だって、どうやって考えたらいいの?昼も夜も痛みにさいなまれたり、たくさんの薬を飲んで頭がおかしくなったりする毎日がそんなに良い?それとも、もう死が近いんだって考えることが…?もしかしたら答えはないのかも。
生きることに疲れ 死を望む高齢者たち
このコンテンツは 2014/06/172014/06/17 スイスの二つの自殺ほう助団体エグジットとエグジットADMDが、ほう助の適用範囲を拡大しようとしている。不治の病以外の苦しみに耐えている高齢者も、ほう助の対象としたい考えだ。だが医師や倫理学者は、この拡大で自殺ほう助が乱用されるのではないかと危惧している。...
それに、死にゆく人に何週間も、下手したら何カ月も付き添える人なんている?みじめに、尊厳もまるでなく死んでいくのをただ見ていられる?その無力感に耐えられる人なんているのかな。私には分かるー 本当に大変なことなんだって。
●ニーナさん
自由には、自分の「逝く日」を決めることだって含まれてると思う。頭に浮かぶのは、何回も蘇生させられるお年寄りたちのこと。私の祖母も、薬なしではこんなに長生きしていなかったと思う。
そうなりたくない人には(自殺ほう助団体の)EXITを使える環境がこの国にはある。老人が自分の頭を撃ち抜いて自殺するような国よりはよっぽど良いと思う。
外部リンクへ移動
●ミカドさん
スイスでは(安楽死に)目くじらを立てるような宗教とは深いつながりがない。(もちろん、厳格なカトリック教徒にとってはご法度だろうけど、今でもまだそんな戒律を守って暮らしてる人なんている?)
2021年10月26日 18:38
ALS嘱託殺人事件に関する本紙報道
医学・医療分野の優れた報道活動を顕彰する「日本医学ジャーナリスト協会」は26日、第10回日本医学ジャーナリスト協会賞の大賞に、京都新聞社取材班の「筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者嘱託殺人事件を巡る一連の報道」を選んだと発表した。
取材班は、医師2人がALS患者の女性に薬物を投与して死なせたとされる嘱託殺人事件を追跡。生前の女性の苦悩や医師の言動を丹念に調べ、両者が会員制交流サイト(SNS)でつながり事件に至った経緯や背景を明らかにした。ALS患者を取り巻く支援の実情も伝え、医療・介護現場の課題を掘り下げた。
同協会は授賞理由として「難病患者の生きる権利の保障などを多角的に詳報した」と指摘。「よくある安楽死議論に終わらず、『生きたいと思える社会に』という報道姿勢で一貫している」と評価した。
優秀賞には東洋経済オンラインの「精神医療を問う」と、毎日新聞記者著書「ルポ「『命の選別』誰が弱者を切り捨てるのか?」(文藝春秋)を選んだ。表彰式は11月15日に東京都千代田区の日本記者クラブで行われる。
同賞は、医療の報道に携わる記者や学識者らでつくるNPO法人日本医学ジャーナリスト協会(東京都)が2012年に創設した。
人は死ぬと新しい生命に生まれ変わると言われており、このことを「輪廻転生」と呼びます。輪廻転生では、現世での行いが来世になんらかの影響を及ぼすと言われています。
そこで今回は、輪廻転生とはなんなのか?その言葉の意味、そして、現世でのどのような行動が来世に影響を及ぼすのかを解説していきます。
目次
輪廻転生は生前の悪行が関係する
輪廻転生とは、人が何度も生死を繰り返し、新しい生命に生まれ変わることを意味します。
輪廻は、車輪が回る様子、転生は生まれ変わることを意味しています。
また、「輪廻」、「転生」のみでも輪廻転生と同じ意味の言葉として使われます。
人の生まれ変わりには、生前の悪行が関連しており、それに応じて六道という6つある世界のいずれかに生まれ落ちます。
輪廻転生では、必ずしも人に生まれ変われるというわけではありません。生まれ変わる世界は、6つの世界に分けられています。
その世界は、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つで総称して「六道」と呼ばれています。修羅を人間として括る場合には、五趣と呼ばれるときもあります。
また、地獄、餓鬼、畜生の3つの世界を三悪道といい、特に苦しみの激しい世界だといわれています。
続いては六道の世界が、具体的にどのような世界なのか、1つずつ解説していきます。
六道のなかでも最も苦しい地獄界
六道のなかでもっとも苦しい世界で、その苦しさは言葉では言い表せない世界だといわれています。
餓鬼界は飢えによる苦しみを味わう
餓鬼界は、飢えによって苦しみを味わう世界です。
食べ物や飲み物があったとしても、それを口に運ぼうとした瞬間に青白い炎となり、食べられません。そして、なにも食べられず、最終的には、骨と皮だけになってしまいます。
犬や猫などと同じ畜生界
犬や猫など動物界のことを畜生界と呼びます。人間界からでもその様子を見るれるので、わかりやすいとは思いますが、弱肉強食の世界なので、不安に怯える日々を過ごすことになります。
争いだらけの修羅界
修羅界とは、鬼神である阿修羅が住む世界です。阿修羅は好戦的なため、修羅界では絶えず争いが起きているといわれています。
私たちが暮らす人間界
私たちが今生きている、苦しみも楽しみも感じられる世界のことです。
人間界のみが輪廻転生の枠から逃れられるための仏の教えを学べるとされています。
天上界は極楽と異なる
六道の中で、もっとも楽しみの多い世界のことを天上界と呼びます。ですが、極楽浄土とは違い、迷いのある世界です。また、悲しみも寿命もあります。
次に生まれ変わる世界を決めているのは「引業」
次に生まれる世界は、死ぬまでに行った行為「引業」によって、決まっています。引業とは、生前に行った悪行のことを意味します。なので、引業の重さによって、次に生まれ変わる世界が決まります。
また、引業以外のすべての業ことを満業と呼びます。引業では、次に生まれ変わる世界が決まりますが、満業では、生まれ変わった世界での容姿、家柄、知性などの生まれた時点での状況が決まります。
次に生まれ変わる世界が地獄になってしまう行為
地獄には5つの種類があり、生前の行為によって、生まれ変わる地獄も違います。どのような行為によって生まれ変わる地獄が変わるのかを解説していきます。
*等活地獄:生き物を殺す殺生罪の場合
*黒縄地獄:殺生罪に加えて、他人の物を盗む偸盗罪の場合
*衆合地獄:殺生・偸盗罪、淫らなことを行う邪婬の罪をもつ場合
*叫喚地獄:殺生・偸盗・邪婬・飲酒の罪をもつ場合
*大叫喚地獄:殺生・偸盗・邪婬・飲酒の罪、嘘をつく妄語の罪をもつ場合
ふたたび人間に生まれ変わるためには「五戒」を守り続ける
ふたたび人間に生まれ変わるためには、「五戒」という戒律を守り続けなければなりません。
五戒とは、不殺生・不偸盗・不邪婬・不飲酒・不妄語の5つのことを意味します。
この5つの戒律を守り続けられる人は、非常に少なく、お釈迦様は、涅槃経で「人趣に生まるるものは、爪の上の土のごとし。三途に堕つるものは、十方の土のごとし」と説いています。
この文章は、「地獄に堕ちる人は大宇宙の土のように多く、人間に生まれる人は爪の上の土のように少ない」という意味が込められています。それだけ、ふたたび人間に生まれ変わることは困難で、輪廻転生によって、苦しみ迷いの世界を繰り返していかなければなりません。
終わることのない輪廻転生の世界から離れるためには仏の教えを守る
終わることのない輪廻転生の世界から離れるためには、原因を見極める必要があります。すべての結果には、原因が存在します。なので、輪廻転生が起こる原因を見極められれば、終わることのない世界から離れられるとされています。
輪廻転生は日本では仏教の教えとして知られていますが、その解釈は諸説あるようです。生まれ変わりを思うのは、現在の自分に満足していないからでしょう。過去や未来ばかり見ずに今、生きている事の素晴らしさ、命の尊厳性を忘れずに一日、一日を大切に生きていく事も肝要ではないでしょうか。
輪廻転生に関するよくある質問
- 輪廻転生は仏教ならではの考え方ですか?
- 輪廻転生は元々古代インドに伝わる考え方から派生したものという説があります。また、仏教のみならず古代ギリシャやイスラム教のごく一部でも見られ、世界各地に似たような思想があります。
- 輪廻転生はどのくらいの人が信じているのでしょうか?
- 現代でも日本人の42・6%が「輪廻転生はあると思う」と答えたという調査があります。(NHK放送文化研究所より、2008年11月ISSP国際比較調査)
2021年8月26日 更新
【死生観】輪廻転生の意味とは。
輪廻転生(りんねてんしょう)とは、魂が生まれ変わりを繰り返すことを意味する言葉です。
仏教における輪廻転生を深く理解するには、六道と呼ばれる6つの世界を知る必要があります。
輪廻転生の意味を紐解く
仏教における輪廻転生とは
六道を詳しく知る
日々の過ごし方を考えさせてくれる輪廻転生
輪廻転生の意味を紐解く
生まれ変わりを意味するサムサラの車輪
輪廻転生(りんねてんしょう)は、魂が生まれ変わることを意味する言葉です。その言葉の基となっているのは、“輪廻”と“転生”。これら2つの言葉は意味が重複する部分も多いですが、実は細かな部分に違いがあります。まずは、輪廻と転生の意味をそれぞれ解説します。
輪廻の意味
輪廻は、人を含む生き物が亡くなったとき、動物などを含めた生類に何度も生まれ変わることを指す教えを意味します。命を持つものが生命の転生を無限に繰り返す様子を、車輪の軌跡に例えたことが輪廻の由来だそうです。
ちなみに、輪廻という言葉は、インドにおける「ヴェーダ」という思想の中や、仏教の聖典の「仏典(ぶってん)」の中に登場します。
転生の意味
転生は、「てんしょう」のほか、「てんせい」とも読みます。人の肉体が死を迎えた後、その人の魂は別の肉体に宿り、新しい人生を始めるという考え方です。つまり、転生は「生まれ変わり」そのものを指す言葉です。
輪廻と転生の違い
どちらも生命の生まれ変わりを意味する点では大きな差はありません。輪廻が繰り返すことに対し、転生は必ずしも繰り返しではないという違いがあります。「輪廻転生」は合わせて使われることが多いです。
仏教における輪廻転生とは
水面に浮かぶ蓮の花
お釈迦様は、輪廻転生の目的を説いています。仏教の知識を深めるために役立つであろう、六道輪廻という考え方と、六道の意味、仏教の目的を解説します。
六道輪廻という考え方
仏教において、輪廻転生とは「六道(ろくどう、りくどう)と呼ばれる6つの世界を、生まれ変わりながら何度も行き来するもの」と考えられています。
ここで言う六道は、地獄・餓鬼(がき)・畜生(ちくしょう)・修羅(しゅら)・人間(にんげん)・天上の6つ。つまり、魂が生まれ変わる先が6種類あるというわけです。このことから、仏教では輪廻転生ではなく六道輪廻と表現されることもあります。この六道輪廻の考え方は、仏教が成立するよりも前に存在し、古代インド思想が起源とも言われています。
六道は苦しみの世界
生まれ変わり先である六道は、どれも苦しみの世界とされています。中でも特に苦しむことが多いとされるのは「三悪道(さんあくどう、さんなくどう、あんまくどう)」と呼ばれる、地獄、餓鬼、畜生の3つです。落とされる道のことは趣とも書き換えられ、三悪趣(さんあくしゅ)とも呼ばれます。一方で、天道、人間道、修羅道の3つの世界は苦しみが少ない「三善道(さんぜんどう)」と呼ばれます。
また、三悪道に修羅を加えて「四悪趣(しあくしゅ)」、三悪道に人と天を加えて「五悪趣(ごあくしゅ)」とすることもあります。どの世界に行けるかは、生きているときの行動で決まるとされます。天道が極楽浄土ではないというのがややこしいところです。
仏教における目的
お釈迦様は、六道にいる間は誰しもが苦しみから逃れられない、としています。六道の先にある世界こそが極楽浄土という考え方であり、仏教の目標は苦しみの六道から抜け出すことなのです。
ちなみに、苦しみの六道から抜け出すには、むさぼる心を表す「貪(とん)」、怒りの心を表す「瞋(じん)」、真理を知らないおろかな心を表す「痴(ち)」の「三毒」を克服することが重要とされています。
六道を詳しく知る
開かれた本
輪廻転生の中で、魂が行き着く場所とされる六道。天上道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道、それぞれの世界について解説します。
天上道
天道、天界道と呼ばれることもある天上道。六道の中で最も楽しいことが多く、苦しむことが少ない世界です。人間よりも秀でた「天人」が住んでいると考えられています。しかし、天上道は極楽浄土ではないので、迷いや悲しみは存在する上、悟りの世界には行けません。
人間道
ここは苦しみだけでなく楽しみも感じられる、私たち人間が生きている世界です。六道の中で生まれ変わりを繰り返す、輪廻転生から逃れるために欠かせない、仏教の教えを学べる唯一の世界でもあります。
修羅道
その名の示す通り、阿修羅という鬼神の住まう世界が修羅道です。常に争いごとが起きており、怒りや苦しみに満ち溢れていると考えられています。それに加え、この世界にいる者は欲望を抑えられません。
しかし、この修羅道までが、比較的苦しみの少ない「三善道」。六道の世界がいかに苦しいものか、ひしひしと伝わってくるのではないでしょうか。
畜生道
ここからが、特に苦しみのある「三悪道」と呼ばれる世界。畜生道は犬や猫、馬や牛などの動物が住む世界です。弱肉強食ですので、ここにいる者は常に不安を抱え、自分だけが助かれば良いと考えています。人間道と違い、仏教の教えに触れられる機会もないため、救いのない世界とされます。
餓鬼道
餓鬼は苦しみと飢えによっておなかが膨らんだ鬼のこと。人を思いやる気持ちがないと餓鬼になってしまうと考えられています。餓鬼道は何も飲み食いができず、嫉妬や欲望に満ちあふれた世界です。一度餓鬼道に入ると、ここから脱出するのは難しいとされます。
地獄道
六道の中で最も苦しい世界です。この世界で受ける苦しみは、言葉では表現できないと言われるほど。また、これまでに重ねてきた罪を償わせるための世界とも言われています。
人が亡くなってから49日目におこなわれる四十九日法要は、故人の魂の行き先にも関係してくる大切な法要です。こちらでは、輪廻転生と四十九日の関係性と、四十九日法要の意味を紹介します。
審判では生前の罪が裁かれ、罪が重いほど苦しみの深い世界に行くとされます。
日々の過ごし方を考えさせてくれる輪廻転生
輪廻転生は、私たち人間を含む生き物の魂が生まれ変わることを意味する言葉です。仏教における輪廻転生・六道輪廻は、悟りを開けずに六道の中で過ごすことを意味します。
この記事の監修者
瀬戸隆史 1級葬祭ディレクター(厚生労働省認定・葬祭ディレクター技能審査制度)
2021/8/13 18:39 産経新聞
中村 昌史
樺太で初の市制施行を記念し、豊原駅、商店、銀行、劇場などが並ぶ大通りを行進する祝賀行列=昭和12年7月1日(全国樺太連盟提供)
旧ソ連が侵攻する昭和20年8月まで日本が統治していた南樺太の引き揚げ者らでつくる「全国樺太連盟」(樺連)が3月、解散した。
先の大戦に敗れた日本は南樺太を放棄。複雑な状況に置かれた故郷を思い、戦没者慰霊などに取り組んできたが、会員の高齢化や減少が著しく活動に終止符を打った。15日で終戦から76年。記憶の風化は進み、元会員らは「歴史の真実を次世代に引き継いでほしい」と切望している。
26年のサンフランシスコ講和条約で日本は南樺太と千島列島を放棄したが、ソ連が調印しなかったため、国際法上の帰属は未定だ。国内に返還運動の動きもあったが、難しい活動を余儀なくされ、引き揚げ者2、3世の加入も進まなかった。国が啓発する北方領土などに比べ、南樺太が日本領だった事実は風化し、関心は薄れていった。
侵攻で故郷を追われた引き揚げ者らによって23年に設立された樺連は、元住民の支援をはじめ、南樺太が日本領だった歴史的事実や生活、文化、産業などの実情を継承してきた。平成初期の6300人をピークに会員は939人まで減少。平均年齢は84・1歳に達し、体力や気力の限界を迎えていた。
猛暑が続く8月上旬、樺連が本部を置いた東京都港区の事務所では、元会員らが書類整理や電話対応に追われていた。解散後の清算手続きを補佐する元常務理事の辻力(つとむ)さん(75)は「作業が膨大で追いつかない」と話す。約3千点にも上る資料や物品の受け入れ先の調整も難航している。
戦災に備えた鉄兜(かぶと)や、元住民の手記をはじめとする貴重な資料もある。中でも記憶を基に手書きされた多数の住宅地図が目を引く。世帯名が記された建物、道路の位置などが細かく記され、豆腐屋、ブリキ店、パチンコ店などの表記が生活の息吹を伝える。
辻さんも平成13年から数回現地を訪れ、住宅地図で実家の場所にたどり着いた。昭和21年7月にソ連占領下で生まれた翌年、北海道へ引き揚げ、当時の記憶はないが「街並みに地図の面影があった。夏場で緑が深く、故郷に戻ったと実感した」と振り返る。祖母らの遺骨を安置していた寺はソ連の攻撃で焼失。草が茂る跡地で、線香をあげた。
樺連は、中学校の歴史教科書や大学入試センター試験で樺太をめぐる経緯の正確な記述を求め、国に意見提言もしてきた。辻さんは「『樺太』の読みを知らない若い世代も多く、風化の危機。子供たちが日本や樺太の歴史や背景を正しく知り、学ぶ機会は重要だ」と話す。
ロシアがサハリンと呼ぶ樺太には現在、多くのロシア人が生活する。
「故郷を失う悲しみは実体験として痛いほど分かる。帰属問題の解決は簡単ではない」。前置きした上で辻さんはこう力を込めた。「ロシアと平和条約交渉をするなら、歴史の事実はもちろん、領土権などでも毅然(きぜん)とした主張をすべきだ。それが、あまたの日本人を開拓で樺太に送り込んだ国の責務でもある」(中村昌史)
引き揚げ75年、大学生が奮闘
看護師集団自決描く 大学生制作の映像 「地方の時代」で入選
全国規模のドキュメンタリー映像の祭典「第41回地方の時代」で稚内北星大学の学生が樺太にあった炭鉱病院で勤務していた看護師が集団自決した事件を取り上げ制作した作品「あの日、ニレの木の下で」が市民・学生・自治体部門で入選。
日本放送協会などが主催する映像祭には、全国から4部門に300近い作品が寄せられた。今年は市民・学生・自治体部門で10作品が入選した。この中から11月中旬に関西大学で開催される映像祭でグランプリ、優秀賞などの各賞が決まる。
大学の映像制作の講義で3年生5人が制作した作品は、終戦後の1945年8月17日未明、樺太北部に位置する恵須取町(現ウグレゴルスク)の太平炭鉱病院で働いていた看護師23人がソ連軍の進攻を恐れ、太平から約8㌔ほど離れた武道沢という山中のニレの木の下で集団自決し6人が亡くなった悲劇について、当時の事に詳しい写真家の斉藤マサヨシさんや生存者の人に取材した内容など31分の映像で描いている。
入選作は現在、副港市場2階の樺太記念館で上映されており、学生から取材を受けた斉藤さんは「樺太の集団自決で9人の乙女の事件は皆さん知っていると思いますが、炭鉱病院看護師の事件を知る人は少なく、我々大人はこのような事件が二度と繰り返さぬよう後世にしっかりと教えていかなければいけない」と話していた。
「北海道映像コンテスト2021」最優秀作品の決定
一般社団法人北海道映像関連事業者協会、北海道テレコム懇談会、北海道総合通信局の主催により、「北海道映像コンテスト2021」の映像作品を募集し、審査の結果、受賞作品が決定しました。
学生部門の最優秀作品については、当会ホームページ 北海道映像コンテストにて公開しております。
学生の皆様の力作をぜひご覧ください。
北海道総合通信局長賞、学生部門(高等学校の部)最優秀賞
「熊魂(ゆうこん)」 北海道札幌西高等学校 放送局
学生部門(専門学校・短大・大学の部)最優秀賞
「あの日、ニレの木の下で」 稚内北星学園大学 樺太プロジェクト
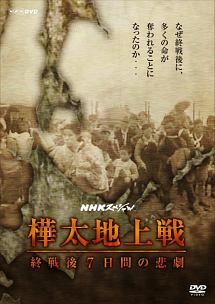
樺太地上戦―終戦後7日間の悲劇(NHKスペシャル 戦争の真実シリーズ〈2〉) の 商品概要
-
要旨(「BOOK」データベースより)
北海道の北に広がる大地、サハリン。かつて樺太と呼ばれ、約40万人の日本人が暮らしていた。 -
この地で、終戦後も7日間にわたって戦闘が続き、住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われていたことを私たちは忘れてはいけない―。最前線に立たされた住民たち―。
-
犠牲者は5000人とも6000人とも言われる住民を巻き込んだ悲惨な地上戦。知られざる戦い、悲劇の全貌に迫る。重い沈黙を破る貴重な証言。国内外の発掘資料初公開!
-
目次
はじめに
序 章「樺太地上戦」とは何だったのか
第1章 8月15日 「なぜ戦争は終わらなかったのか」問い続ける元住民たち
第2章 8月16日 終戦後の「先制攻撃」
第3章 そして「戦闘命令」は下された
第4章 樺太で現実化した「本土決戦」という悪夢
第5章 少年はゲリラ戦に身を投じた
第6章 住民たちは地獄を見た……「死の逃避行」
第7章 停戦ならず。樺太最大の地上戦「真岡の悲劇」へ
第8章 8月20日 ソビエト軍の艦砲射撃が真岡を襲う
第9章 相次ぐ集団自決。「北のひめゆりの悲劇」
第10章 8月22日 「終戦」から1週間、ようやく戦いは終わった
第11章 帰れぬ遺骨
終章 樺太地上戦は何を残したか
おわりに -
出版社からのコメント
住民を巻き込んだ悲惨な地上戦 。知られざる戦い、悲劇の全貌に迫る。 -
内容紹介
北海道の北に広がるサハリン。かつて樺太と呼ばれ、約40万人の日本人が暮らしたこの地で、
終戦後も7日間にわたって戦闘が続き、住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われていた――。
重い沈黙を破る貴重な証言、国内外の発掘資料を初公開。知られざる地上戦の実態に迫る一冊。
話題を呼んだNHKスペシャル番組、待望の書籍化。戦争の真実シリーズ第2弾の登場。
図書館選書
北海道の北に広がるサハリン。かつて樺太と呼ばれ、約40万人の日本人が暮らしたこの地で、終戦後も7日間にわたって戦闘が続き、住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われていた――知られざる地上戦の実態に迫る。 -
著者について
NHKスペシャル取材班 (エヌエイチケースペシャルシュザイハン)
報道局社会番組部
樺太地上戦―終戦後7日間の悲劇(NHKスペシャル 戦争の真実シリーズ〈2〉) の商品スペック
|
|
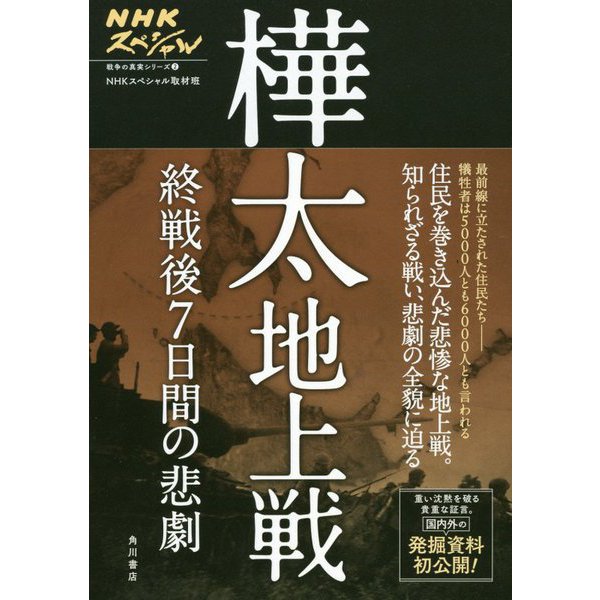 |
|
商品仕様
|
出版社名:KADOKAWA
|
|---|---|
|
著者名:NHKスペシャル取材班(著)
|
|
|
発行年月日:2019/10/25
|
|
|
ISBN-10:4041067383
|
|
|
ISBN-13:9784041067383
|
|
|
判型:A5
|
|
|
対象:一般
|
『宝の島と呼ばれた「樺太」』 森さやかの思うコト
2021.08.26 森さやか(HTBアナウンサー)
よく晴れた日に、稚内の宗谷岬に立つと、真っ青な水平線にくっきりと見える島影。
サハリン(旧樺太)です。宗谷岬から約40キロ。
肉眼でも見えるほどの距離にある「樺太の歴史」を、あなたは知っていますか?
【樺太連盟の解散】
今年3月末に、樺太からの戦後引き揚げ者らでつくる全国樺太連盟が解散するという話を聞いて、私は札幌にある樺太連盟北海道支部を訪ねました。
全国樺太連盟は、1948年の結成以降、引き揚げ者の援護や親睦のほか、樺太の暮らしや戦争など歴史を伝承するため、近年は移動展を全国各地で開くなど活動を続けてきましたが、会員の高齢化で継続が困難になったといいます。会員数はピークだった94年の6300人から激減し、今年3月時点で968人(道内は都道府県別で最多の387人)。平均年齢は84歳を超えました。
解散に伴い閉鎖することになった北海道事務所では、片付けや書類の整理に追われていました。これまで活動の中心となり尽力してこられた北海道事務所長の森川利一さん(91)も、樺太を故郷にもつ一人です。
昭和7年に樺太中部の上敷香(かみしすか)に生まれ、昭和23年に北海道に引き上げるまでの16年間を樺太で過ごした森川さん。当時の様子を伺うと、こちらが驚くほど、鮮明に記憶された樺太の風景を次々と語ってくれました。
【「樺太は宝の島だった・・・」】
樺太は、面積全体の8割が大自然林、地下には石炭・石灰石などの鉱物が眠り、近海は世界3大漁場に数えられるほどの水揚げを誇るなど、まさに陸・海ともに資源の宝庫だったといいます。
明治38年(1905年)、日露戦争後のポーツマス条約で北緯50度以南の南樺太が日本領となると、資源豊かな樺太に新天地を求め、北海道からも多くの人が移り住みました。
昭和16年12月の国勢調査では、40万6557人が暮らしていたと記録されています。
林業や漁業などで栄えた樺太。特に隆盛を極めたのが製紙業で、あちらこちらに工場が立ち並び、業界大手の王子製紙は、樺太内に9か所もの工場を持ち、社宅もズラリと並んだそうです。鉄道も整備されていきました。
大正12年(1923年)に、稚内から大泊(現コルサコフ)間に連絡船が就航すると、樺太への玄関口として、春はニシン漁の関係者、秋は林業関係者で賑わい、次第に旅行で樺太を訪れる人も増えたといいます。
詩人の宮沢賢治や北原白秋、民族学者の柳田国男、歌人の斉藤茂吉など、多くの文学者も樺太を訪れました。「樺太ガイドブック」なるものも発行されていたと知り、驚きました。
当時、樺太は避暑地としても親しまれるほど、身近な場所だったのです。
【豊かな自然と街並み】
森川さんが生まれ育った町・上敷香(かみしすか)。国境から80㎞にある、オホーツク海側の町です。
引き揚げ者らの記憶を元に作ったという、当時の街路図を見せてもらいました。
「わぁ・・・まるで、今の札幌を見ているようですね」
私は思わず、声をあげてしまいました。
町は、東西南北に整然と区画され、碁盤の目状になっていて、いくつもの南北の道と東西の道が垂直に交差しています。そして住所は、東西を条、南北を丁目で表し「東1条北6丁目」などの地名が記されていました。
川の側には神社があり、そこからまっすぐ伸びる道は「本通り」「山の手通り」「宮通り」と名付けられ、交差するメインストリートは現在の札幌と同様に「大通り」と呼ばれました。
各通りには、さまざまな商店がひしめきあっています。おやき・精肉店・鮮魚店・薬局・タバコ販売店・パン店・文具店・パチンコなどの娯楽遊戯施設もありました。ビリヤードに、カフェの文字も。
町の地図に記された小さな文字を一つひとつ追っていくと、活気あふれた、ハイカラと呼ぶにふさわしいオシャレで美しい街並みが、目に浮かぶようでした。
警察署・消防署・町役場・病院などの公共施設や、小学校・中学校・女学校・商業高校もあり、当時の人々の営みを感じ取ることができます。
「春になるとワラビ・ゼンマイ・行者ニンニク・フキなど山菜がものすごく豊富でたくさん採れて、塩漬けにして漬物のようにして食べたり、煮物にしたりしてね。秋になると、フレップという実を摘みにいきました。冬はスキーをしたり犬ぞりに乗ったり、スケートもしましたね・・。」と懐かしそうに話す森川さん。
80年ほど前の記憶とは思えないほど、はっきりと言葉を紡ぎます。
「戦前の樺太は活気にあふれていてね。自然も豊かで人情もあって。本当にいいところだった…」
何不自由なくのびのびと育ったという樺太での生活。
しかし、その日常が突然奪われました・・。
突きつけられた銃。
混沌とした日々の先に、見えた光とは?
『「樺太での体験」戦争と友情』 森さやかの思うコト HTBアナウンサー 戦争・平和を考える
『宝の島と呼ばれた「樺太」』 森さやかの思うコト HTBアナウンサー
もっと見る
森さやか(HTBアナウンサー)
済州島四・三事件は、1948年4月3日に在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある南朝鮮の済州島で起こった島民の蜂起に伴い、南朝鮮国防警備隊、韓国軍、韓国警察、朝鮮半島の李承晩支持者などが1954年9月21日までの期間に引き起こした一連の島民虐殺事件を指す[4]。
南朝鮮当局側は事件に南朝鮮労働党が関与しているとして、政府軍・警察による大粛清をおこない、島民の5人に1人にあたる6万人が虐殺された[5]。また、済州島の村々の70%が焼き尽くされた[5]。
目次
1 背景
2 済州島民の蜂起と韓国による鎮圧
3 現在の韓国政府の対応
4 題材にした作品
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
背景
事件の現場となった済州島
済州島(1948年9月以降の地図)
洞窟に横たわる犠牲者の遺体(再現)
済州四・三中文面犠牲者慰霊碑(西帰浦市)
1945年9月2日に日本が連合国に降伏すると、朝鮮半島はアメリカ軍とソ連軍によって北緯38度線で南北分割占領され、軍政が敷かれた。
この占領統治の間に、南部には親米の李承晩政権、北部には抗日パルチザンを称する金日成の北朝鮮労働党政権が、それぞれ米ソの力を背景に基盤を固めつつあった。
1945年9月10日、朝鮮建国準備委員会支部が済州島にも創設され、まもなく、済州島人民委員会と改められた[4]。
1947年3月1日、済州市内で南北統一された自主独立国家の樹立を訴えるデモを行っていた島民に対して警察が発砲し、島民6名が殺害される事件が起きた[4]。
この事件を機に3月10日、抗議の全島ゼネストが決行された。これを契機として、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁は警察官や北部・平安道から逃げてきた若者を組織した右翼青年団体「西北青年会」を済州島に送り込み、白色テロが行われるようになった。
特に上述の西北青年会は反共を掲げて島民に対する弾圧を重ね、警察組織を背景に島民の反乱組織の壊滅を図った。
島民の不満を背景に力を増していた南朝鮮労働党は、1948年4月3日、島民を中心とした武装蜂起を起こした[4]。
済州島民の蜂起と韓国による鎮圧
1948年に入ると、南朝鮮当局が南側単独選挙を行うことを決断し、島内では選挙を前に激しい左右両派の対立がはじまった。
その中で、単独選挙に反対する左派島民の武装蜂起が4月3日に起こった。警察および右派から12名、武装蜂起側からは2名の死者が出た。
済州島民の蜂起に対して、韓国本土から鎮圧軍として陸軍が派遣されるにあたり、政府の方針に反抗した部隊による反乱が生じ(麗水・順天事件)、韓国本土でも戦闘が行われた。
この混乱により済州島の住民を中心に、戦闘から逃れて日本へ渡る者が多数生じ、これが在日韓国・朝鮮人の先祖の多くを占めるともされる[6][7][8]。
済州島では韓国軍などにより蜂起したものは弾圧されたが、人民遊撃隊の残存勢力はゲリラ戦で対抗するようになったため、治安部隊は潜伏している遊撃隊員と彼らに同調する島民の処刑・粛清を行った。
これは、8月15日の大韓民国成立後も韓国軍(この時正式発足)によって継続して行われた。
韓国軍は、島民の住む村を襲うと若者達を連れ出して殺害するとともに、少女達を連れ出しては、2週間に渡って輪姦、虐待を繰り返した後に惨殺したと言われている[5]。
1948年9月に金日成は朝鮮統一国家を標榜する朝鮮民主主義人民共和国の成立を宣言した。1949年12月24日には、朝鮮半島南側で韓国軍は住民虐殺事件(聞慶虐殺事件)を引き起こし、共産主義者による犯行であると情報操作した[9]。
1950年に米軍から朝鮮半島を解放すべく朝鮮人民軍が進撃し朝鮮戦争となると「朝鮮労働党党員狩り」は熾烈さを極め、1954年9月21日までに3万人、完全に鎮圧された1957年までには8万人の島民が殺害されたとも推測される。
また、保導連盟事件が起きると本土と同様に刑務所で1200人が殺害された[10]。海上に投棄されていた遺骸は日本人によって引き上げられ、対馬の寺院に安置されている[11]。
歴史的に権力闘争に敗れた両班の流刑地・左遷地だったことなどから朝鮮半島から差別され、また貧しかった済州島民は当時の日本政府の防止策をかいくぐって日本へ密航し、定住する人々もいた。
韓国併合後、日本統治時代の初期に同じく日本政府の禁止を破って朝鮮から日本に渡った20万人ほどの大半は済州島出身であったという。日本の敗戦後、その3分の2程は帰国したが、四・三事件発生後は再び日本などへ避難し、そのまま在日朝鮮人となった人々も多い。
日本へ逃れた島民は大阪市などに済州島民コミュニティを形成したが、彼らは済州島出身者以外の韓国・朝鮮人コミュニティからは距離を置いた。済州島では事件前(1948年)に28万人[12] いた島民は、1957年には3万人弱にまで激減したとされる[13]。
木村光彦(青山学院大学)によると、済州島四・三事件及び麗水・順天事件を政府は鎮圧したが、その後共産主義者の反政府活動及び保守派の主導権争いのために政情不安定に陥る。
経済的困難の深刻化もあり、結果「たくさんの朝鮮人が海をわたり、日本にひそかに入国」し、正確な数を把握することは出来ないが1946年~1949年にかけて、検挙・強制送還された密入国者数は5万人近く。
(森田芳夫「戦後における在日朝鮮人の人口現象」『朝鮮学報』第47号)に達し、未検挙者をその3倍~4倍と計算すると、密入国者総数は20万人~25万人規模となり、済州島からは済州島四・三事件直後に2万人が「日本に脱出した」とされる[14]。
野口裕之(産経新聞政治部専門委員)は、韓国保守政権及び過去の暴露を恐れる加害者の思惑が絡み合い済州島四・三事件の真相は葬られている。
「不都合な狂気の殺戮史解明にまともに取り組めば」「事件で大量の密航難民が日本に押し寄せ、居座った正史も知るところとなろう」「膨大な数の在日韓国・朝鮮人の中で、済州島出身者が圧倒的な割合を占めるのは事件後、難民となり日本に逃れ、そのまま移住した非合法・合法の人々数千人(数万人説アリ)が原因である」と述べている[15][16]。
この事件を初めて発表した在日韓国人作家の金石範は2015年4月1日に第1回済州四・三平和賞を授賞したが、授賞に際しては右翼団体の妨害もあった。
現在の韓国政府の対応
長年「反共」を国是に掲げてきた韓国では、責任の追及が公的になされていない。また、事件を語ることがタブー視されてきたため、事件の詳細は未解明である。
2000年に金大中政権のもとで4.3真相究明特別法が制定され、4.3委員会が設置された。
21世紀になって、2003年2月25日に韓国大統領に就任した盧武鉉は、自国の歴史清算事業を進め、2003年10月に行われた事件に関する島民との懇談会で初めて謝罪し、済州四・三事件真相糾明及び犠牲者名誉回復委員会を設置した。
さらに2006年同日の犠牲者慰霊祭に大統領として初めて出席し、島民に対して正式に謝罪するとともに事件の真相解明を宣言した[17]。
事件から逃れて日本に渡った済州島出身の在日韓国人は、その恐ろしい体験から「また酷い目にあわされるのではないか」と祖国へ数十年も訪れることのない人々も多かったが、韓国政府が反省の態度を示し始めたことで、60年ぶりに祖国を訪れる決心をした人物も現れ始めた[18]。
しかし、その後の保守派の李明博政権(2008年2月25日~2013年2月24日)、朴槿恵政権(2013年2月25日~2017年3月10日)の時代には進展は見られなかった。
むしろ2010年以後は中国観光客の増加と中国人による済州島不動産買い占め懸念が問題化し、過去の事件は忘れられつつあった。
2017年5月10日に大統領に就任した文在寅は、就任後初めての4・3事件犠牲者追念日である2018年4月3日の追悼式に2006年の盧武鉉以来、大統領として12年ぶりに出席した。
文在寅大統領は追念辞で「私は今日、その(金大中政権と盧武鉉政権の取り組みの)土台の上に4.3の完全な解決を目指し揺らぎなく進むことを約束します。
これ以上4.3の真相究明と名誉回復が中断したり、後退することは無いでしょう。それと共に4.3の真実はどんな勢力も否定することのできない明らかな歴史の事実として、位置付けられたことを宣言します。
国家権力が加えた暴力の真実をきちんと明らかにし犠牲となった方たちの怒りを解き名誉を回復するようにします。
このために遺骸の発掘事業も悔いが残らないよう最後まで続けて行きます。
遺族たちと生存犠牲者たちの傷と痛みを治癒するための政府としての措置に最善を尽くす反面、賠償・補償と国家トラウマセンターの建設など立法が必要な事項は国会と積極的に協議いたします。」と事件の完全解決に意欲を示した。
文在寅はまた、「未だに4.3の真実を無視する人々がいます。未だに古い理念の屈折した目で4.3を眺める人々がいます。未だに韓国の古い理念が作り出した憎悪と敵対の言葉が溢れています。
もう私たちは痛みの歴史を直視できなければなりません。不幸な歴史を直視することは国と国のあいだでだけ必要なことではありません。私たち自らも4.3を直視できなければなりません。古い理念の枠に考えを閉じ込めることから逃れなければなりません。」
「恒久的な平和と人権に向かう4.3の熱望は決して眠ることはないでしょう。それは大統領である私に与えられた歴史的な責務でもあります。今日の追念式が4.3の英霊たちと犠牲者たちに慰安となり、わが国民たちにとっては新しい歴史の出発点になることを願います。」と強調した[19][出典無効][20]。
事件から71年目となる2019年3月4日、軍と警察が初めて公式に謝罪の意を表明した[21]。
題材にした作品
金石範『火山島』全7巻、文藝春秋、1983.6、1983.7、1983.9、1996.8、1996.11、1997.2、1997.9。ISBN 4163631704、ISBN 4163631801、ISBN 4163631909、ISBN 4163635904、ISBN 4163636005、ISBN 4163636102、ISBN 416363620X。
玄基栄、金石範訳『順伊おばさん』新幹社、2001(日本語版の刊行年、翻訳初出は1984年、原作発表は1978年)。ISBN 978-4884000158。
金吉浩『生野アリラン 』<在日>文学全集第15巻、勉誠出版2006、ISBN 4585011250
金石範『鴉の死』(1957年初稿)
高橋悠治 - あなたへ 島(李静和作詞)(事件を題材にした男声合唱曲。法政大学アリオンコールにより2005年に初演。作曲者HPにて楽譜閲覧可能)
萩原遼『北朝鮮に消えた友と私の物語』文藝春秋、1998年(幼少期に四・三事件で済州島を逃れ、日本・大阪に密航した友人の、1960年北朝鮮帰国後の足跡を探すノンフィクション作品)
梁石日『大いなる時を求めて』幻冬舎、2012年。ISBN 978-4344021402。
『チスル(英語版)』映画(2012年)監督:オ・ミヨル
『水の声を聞く』映画(2014年)監督:山本政志
『龍王宮の記憶』映画(2015年-2018年、韓国DMZ国際ドキュメンタリー映画祭2016で上映)監督:金稔万
▼思いやりのある言葉を
かけ合うことを大切にしたい。
その第一歩が「あいさつ」である。
始めは硬い表情でも、あいさつから
笑顔がうまれ、
心の通った対話が広がる。
▼どんな時代を生きようとも、
その人には、その人にしか歩めない
人生の道がある。
ありのままの心の発露がいい。
ささやかな目標でも、
そこに近づこうと努力することが、
自分にしか歩めない充実の道になる。
▼心は不思議である。心は微妙である。
こちらが悪い感情を抱いていると、相手にもそれが伝わている。
こちらが笑顔の思いで接すれば、
相手にも微笑みの心が宿る。
相手はいわば、自分にとっての鏡のような存在である。
▼心から「好きだ」という感情は、
いわば魂と魂の交響曲であり、
人間性の精髄に通じる。
そこには他の何もの
介在する余地がない。
著/遠藤 和
- 〈 書籍の内容 〉
- 1才の娘と、夫に遺した「愛」の記録
<もう、3年のうち2年半が経過した。余命は統計。私は大丈夫。>(本文の日記より)
遠藤和(のどか)さんがステージ4の大腸がんを宣告されたのは、21才のときだった。
当時交際中だった将一さんには「私、がんだった」と告げた。
将一さんは「絶対、別れない」と応じた。
22才で結婚式を挙げた。その様子は、『笑ってコラえて』(日本テレビ系)の「結婚式の旅」というコーナーで放送され、大きな反響を呼んだ。
子供がどうしても欲しかった。抗がん剤を止めなければいけない。それでも「絶対後悔する。死んでも死にきれないよ」と将一さんを説得した。
<はじめて胎動を感じた。私、ママだよ。2~3か月後には、もう会えるね>
23才で長女を出産した。
21年5月、病院で余命は数週間と宣告された。家に帰った。「それでも人生でいまが一番しあわせ」と家族3人と猫1匹の、愛しき日々を送った。
21年9月、24才の若さで亡くなった。
和さんが亡くなる10日前まで、生と死を見つめて書き続けた日記。
それは、1才の娘と、夫に遺した「愛」の記録。
-
- 〈 電子版情報 〉
- ママがもうこの世界にいなくても ~私の命の日記~
Jp-e : 093888320000d0000000
1才の娘と、夫に遺した「愛」の記録。
<もう、3年のうち2年半が経過した。余命は統計。私は大丈夫。>(本文の日記より)
遠藤和(のどか)さんがステージ4の大腸がんを宣告されたのは、21才のときだった。
当時交際中だった将一さんには「私、がんだった」と告げた。
将一さんは「絶対、別れない」と応じた。
22才で結婚式を挙げた。その様子は、『笑ってコラえて』(日本テレビ系)の「結婚式の旅」というコーナーで放送され、大きな反響を呼んだ。
子供がどうしても欲しかった。抗がん剤を止めなければいけない。それでも「絶対後悔する。死んでも死にきれないよ」と将一さんを説得した。
<はじめて胎動を感じた。私、ママだよ。2~3か月後には、もう会えるね>
23才で長女を出産した。
21年5月、病院で余命は数週間と宣告された。家に帰った。「それでも人生でいまが一番しあわせ」と家族3人と猫1匹の、愛しき日々を送った。
21年9月、24才の若さで亡くなった。
和さんが亡くなる10日前まで、生と死を見つめて書き続けた日記。
それは、1才の娘と、夫に遺した「愛」の記録。
-
ふとインスタで知った和さんの死。そこから本が出版される事を知り、読みたくなりました。即購入、一気読み。泣きました。かわいそうとか、頑張ったねとか、尊敬するとか、そういうのじゃなくて、自分や自分の周りを大事に生きていない私を、猛反省させてくれてありがとうっていう感謝の気持ちでいっぱいです。(60代 女性) 2021.12.6
こちらの著者は、以前テレビをみてファンになったというか本当に心の底から病と向き合う姿に感動を覚えてからSNSをフォローしてずっと応援していました。 同じ共通点は母親である事。だけど、遠藤さんは病を抱えながらもそれを表に出さない、弱音を吐かない、人一倍辛いのに誰かを常に心配してる人間として本当に素晴らしい女性でした。 今はこの世にはいませんが、生きること、当たり前の幸せに今一度きずかされました。女性として、母親として、人間として本当に素晴らしい人です(20代 女性) 2021.12.6
テレビやsnsを通して遠藤さんご夫婦を知り、遠くから応援させて頂いていました。 和さんのまっすぐなところや明るいところにひかれてぜひ読んでみたいと思い本を購入したいと思いました。(20代 女性) 2021.12.6
笑ってこらえてをみて20代という若さで大腸がんステージⅣで辛い毎日だと思うのに、大好きな旦那様や家族に支えられ日々の試練を乗り越えている和さん。とても素敵で番組をみて涙が止まりませんでした。(20代 女性) 2021.12.6
その人物に興味があったから。(10代 男性) 2021.12.6
ずっとインスタでのどかさんやご家族の事を拝見させて頂いてました。お亡くなりになられたと聞いた時は、やっとお辛い日々から開放されたんだなと号泣してしまいました。今はきっと大好きな遠藤さん娘ちゃん梅ちゃん、ご家族の事をそばで見守っているのではないかと思います。ご冥福をお祈りします。(40代 女性) 2021.12.6
私には当たり前に居る母がいなくなるってどういうことだろう、とタイトルだけでも考えさせられたから。24時間テレビ等でみる闘病の話に興味があるから。(10代 女性) 2021.12.6
感動して涙が止まりませんでした。 改めて自分を見つめ直すきっかけに してくれた本です。 こどもに対して、家族に対しての 接し方が変わります。(20代 女性) 2021.12.5
わたし自身、2020.10月生まれの子どもがいて同じ母親一年目として興味をもちました。子どもを残してこの世を去るという辛さ計り知れません。自分がもしガンに侵されていて息子と一緒にいられる時間が少ないことを知ったら、、子育てや周りの人との関わり方は今と違ったのか。
わたしは本書の和さんのように逞しく、最後まで自分らしく生きていくことができるのかと考えさせられました。どうか遠藤家のみなさま、周りの方が幸せに暮らせますように。(30代 女性) 2021.12.5
笑ってコラえての放送をみてからずっと気になっていました (40代 女性) 2021.12.5

10/29(金) 16:05配信
NEWSポストセブン
24才でこの世を去ってしまった和(のどか)さんが娘さんのために遺した記録
21才でステージIVの大腸がん宣告。22才で結婚。23才で出産。闘病を続けながら、娘を全力で愛した──この9月に24才でこの世を去ってしまった彼女は、未来の娘のために、日記を綴り続けていた。
【写真11枚】生前、和さんが幼い娘に離乳食を食べさせるにこやかな姿。家族3人でおそろいの赤い服を着る姿なども
9月8日14時11分、本誌・女性セブンが密着を続けてきた遠藤和(のどか)さんが、ステージIVの大腸がんとの闘病の末に、息を引き取った。24才だった。
和さんは生まれ育った青森での葬儀を望んでいたという。夫の将一さんの話。
「地元の知り合いだけでなく、インスタグラムや『女性セブン』などを通じて和のことを知ってくださった、たくさんのかたがたに弔文をいただきました。和も喜んでいたと思います。
これまでにいただいたお手紙は、全部持っていきたいと和が話していたので、大好きなひまわりと一緒に、すべて棺に入れました。ぼくたちが前に進めたのは、皆さんの応援があったからです。本当にありがとうございます」
和さんは、1997年青森県生まれ。2018年9月、21才のときに大腸がんが発覚した。和さんはそのときのことを日記にこう書き記している。
〈2018年9月5日(水)
16時頃におと(父)とまま(母)だけ呼ばれて、先生と話をした。なんかあったんだろうな。とは予想してたけど、ガンだったとは。まま号泣。おとも困ってる感じ。
まだ21才なんだけどなあ。今日は何してても涙出るわ。受け止めきれない。〉
同年10月、「ステージIIの大腸がん」と診断された。和さんはそのときに、抗がん剤治療は生殖機能に悪影響を与え、不妊になる可能性があるという説明を受けた。
妊娠を諦めたくなかった和さんは、「和の体が大事だから、治療に専念してほしい」と言う将一さんと何度も話し合い、「チャンスは1回だけ」という約束で、抗がん剤治療の開始を遅らせて卵子凍結をすることを決断する。
〈2018年10月5日(金)
私は卵だけ取るの後悔しない。それでもし再発して死ぬ事になっても死ぬ直前まで卵取ったことは絶対に後悔しないと思う。もちろん成功率は低いから、ダメかもしれないけど、やれる事は全部やったって思えるのかそうじゃないのかは全然ちがうと思う。
遠藤さんはそれでも早く治療してほしいみたいだけど、それだけ私のこと大切に思ってくれてるのは本当に嬉しいし、ありがたい。大好きだよ。〉
和と娘のどちらかが助からないかもしれない
2018年11月、手術の結果、和さんのがんは「ステージIV」であることが発覚した。
末期がんの宣告を受けても、和さんと将一さんは、前を向いていた。ふたりは2019年12月に結婚。その結婚式の様子が、翌2020年2月に『1億人の大質問!? 笑ってコラえて!』(日本テレビ系)で放送され大きな話題となった。
「『和さんの日記をまとめて本にしないか』という提案を受けたのは、この頃でした。実は去年1月に和の妊娠がわかり、そのときは出産に集中したかったので、一旦、話を保留にしました」(将一さん・以下同)
ステージIVのがんを抱えながらの妊娠生活、そして出産は、一筋縄ではいかなかった。
〈2020年5月7日(木)
両卵巣転移だった。片方(の腫瘍)は10cmごえの大物。腹水も少し増えてた。不安ね。明日から入院して抗がん剤再開するって。一応、もう18週だし、子供に影響することはなさそう。
でもこのままだとやっぱり28週くらい。うまくいっても30週くらいには産むことになりそう。辛い。ベビのためになることをしたい。あと、子供だけじゃなくて私も無事でいたい。〉
2020年7月、和さんは27週、帝王切開で娘を出産。幸い母子ともに無事だった。
「和と娘のどちらかが助からないかもしれないと言われていたので、本当に安心して泣きました。和は『か細かったけど産声が聞けてうれしかった』とすごく喜んでいました。2か月後に卵巣の摘出手術をしたのですが、腫瘍の重さが娘の980gの約3倍で……。娘3人分の腫瘍を抱えて出産したと思うと、和は本当によく頑張ったと思います」
娘という存在ができてから、和さんにとって日記をつけることの意味も少しずつ変化していった。そして日記をまとめた本の出版を考え始めたという。
「娘のために、和がどんな人間で、何を考えて出産に臨み、病気と向き合ったのかを形に残せたらいいねという話をふたりでしました。それと、和は病気になってからもずっと仕事をしたがっていたので、“本をつくるという仕事なら、体調と相談しながらできるんじゃないか”と語り合いました。
最終的に、和を中心に書き進め、ぼくが窓口役になって、娘のために本をつくろうと決めたんです」
今年2月、本格的に出版のための準備が始まった。
〈2021年2月6日(土)
20時から初Zoomで取材。いまの時代すごいね。
娘が産まれた時の気持ちをちゃんと誰かに話した事なかったから、ちょっと緊張した。いい形で娘に残せたらいいな。〉
和さんの育児や闘病を伝えた本誌・女性セブンの記事は反響を呼び、和さんの生き方に共鳴する読者から、応援の手紙やプレゼントが続々と届いた。
「和は驚くと同時に、とても喜んでいました。皆さんからのお手紙は、入院などつらいときによく読み返していたので、心の支えになっていたと思います」
今が一番しんどいけど一番幸せですごく楽しい
この4月、和さんは新たな治療の可能性を模索するため東京に移り住んだ。
しかし、東京のがん専門病院に転院するタイミングで、腸閉塞になり、青森に戻って人工肛門(ストマ)造設手術を行った。東京に戻った5月には、がんの腫瘍が尿管を圧迫したので、尿を外に出す腎ろう造設手術を行った。
満身創痍の和さんに、医師は余命宣告をした。
〈2021年5月26日(水)
退院前最後の先生との面談。予想通り永くない話された。余命は数週間単位って言われた。〉
それでも和さんは「普通の生活」を諦めなかった。
「体力的に娘を抱っこするのは難しかったけれど、あやしたり、一緒に遊んだりしていました。和は料理が大好きだったので、離乳食やぼくのご飯を作ってくれました」
〈2021年5月29日(土)
今までの人生生きてきて、今が一番しんどいけど一番幸せですごく楽しいかもしれない。些細なことがものすごく大きな幸せに感じる。
ご飯作ったり、掃除ができたり、娘を抱きしめられたり、成長を喜べたり、何気ないことが本当に全て大きな幸せ。
家族も友達もみんながすごく私のこと考えて一緒に生きようとしてくれてる。こんなに幸せなことってないなぁ……恵まれてるな。みんなのためにも生きたいな。〉
ふたりは、セカンドオピニオンを利用しながら、治すための治療ができる病院を探し続けた。6月、抗がん剤治療のできる病院が見つかり、和さんは治療に励んだ。
そして今年7月、娘が1才を迎えた。
〈2021年7月10日(土)
娘の誕生日パーティーの日。朝パッパァって呼んだ。はじめてはパパだったかぁー。
朝ご飯の時機嫌悪かったから大丈夫かなって思ってたけど、可愛いドレスに着替えたらご機嫌になってくれてよかった!
来年もお祝いしたいなぁ。
1年前の今日は初めて娘に会えた日! あまりにも小さすぎて本当に心配だったなぁ。すくすく健康に育ってくれて本当に感謝だなぁ。一生懸命生きてくれてありがとう。これからもよろしくね。〉
8月、日記をまとめて本にする作業が始まった。
「結婚した記念日の12月に本を出すと決め、和は改めて頑張ろうと思ったみたいです。
体調はよくない日の方が多かったと思います。それでも和は日記を書き続け、リモート取材や打ち合わせをこなしていました。昔の日記を読み返して、当時を懐かしんだり、娘とぼくと3人で生活できていることに感動したりしていました」
ずっと「普通になりたい」と言っていた
将一さんはいま、和さんが行っていた作業を引き継いでいる。ふたりで約束していた12月に本を出すためだ。
「日記を読んでいると、和との日々が鮮明に思い起こされます。がんだとわかってすぐに行ったドライブでは、ふたりともずっと泣きっぱなし。和は水族館が大好きで、旅行では必ず行きました」
日記には、闘病生活とともに、愛しい家族との日々が綴られている。
「“娘が初めて人見知り”“私は絶食中だけど、みんながおいしいって食べるのを見るのが好き”“目を離した隙に、娘がソファーから落ちちゃった。ごめんね”。そういった、本当の日常が書かれています。
和はずっと“普通になりたい”と言っていたから、育児をするとか家事をするとか、何気ない日常が幸せだったのではないかと感じています。
ただひたすら走り抜けた3年間でした。悲しみが消えることはないけれど、和はよく頑張りました。娘が理解できる時期になったら、『あなたには、こんなにすごくて素敵なママがいたんだよ』と伝えたいです」
※女性セブン2021年11月11日・18日号
◆遠藤和さんの著書『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』は12月上旬発売予定
【関連記事】
「がんステージIVのママ」 12月7日午前8時30分以降か、 テレビ朝日で放映された。
日記に心の軌跡を綴る。
11/19(金) 16:15配信
NEWSポストセブン
2021年9月、24歳という若さでなくなった遠藤和(のどか)さん。夫の将一さんとは2019年12月に結婚式を挙げていた
2021年9月8日14時11分。遠藤和(のどか)さんが、ステージIVの大腸がんとの闘病の末に息を引き取った。24歳だった。2018年、21歳でステージIVの大腸がんであると宣告を受けた和さん。真っ先に考えたのは「子供を産みたい」ということだった。
【写真5枚】がんステージIVのママ、命がけの出産後の家族スリーショット
抗がん剤治療を始めると、副作用で不妊になる場合があると告げられた彼女は、すぐに「卵子凍結」を考えた。しかし、卵子を採取するためには、抗がん剤治療の開始を遅らせなければならない。さらに妊娠した場合は、その最中に行えるがん治療の選択肢も狭まることになる。その間にがんが進行してしまうかもしれなかった。
〈治療が遅れて死ぬのは嫌だ。でも、そのまま抗がん剤治療する道を選んで、赤ちゃんを諦めるのも、ありえない。〉(遠藤和さんの著書『ママがもうこの世界にいなくても』=12月1日発売より。以下同)
和さんは、卵子凍結を望んだ。迷いがないわけではなかったが、強い思いで決断した。家族仲のよい環境で育った和さんにとって、結婚して母になることは幼い頃からの夢だった。どうしても、子供がほしかった。夫の遠藤将一さんが振り返る。
「結婚を考えていましたが、あのときはまだ恋人でした。和からは『遠藤さんとの子供がほしい』と言われました。でも僕は、すぐに治療を始めてほしかった。何よりも和に生きてほしかったし、生きるか死ぬかの話なのに子供とか言っている場合じゃないでしょ、とも思いました。授かるかわからない子供を待つより、治療をして、自分の身体を大事にしてほしいというのが率直な気持ちでした」(遠藤将一さん)
和さんの両親も、将一さんと同じように考えていた。和さんの母・千春さんはこう語る。
「夫は、そうでしたね。親としては目の前にいる娘が大事だから、と卵子凍結より治療を優先してほしいと考えていました。よくわかりますし、私だって全面的に賛成というわけではありませんでした。でも、ずいぶん悩んだ末に、和から『赤ちゃんを諦めたくない』と相談されたときには、一番大事なのは和の気持ちだ、と思って。あなたが希望を持てるなら、お母さんは味方になるよ、と伝えました。和の思いの強さに、夫も最後は納得して、応援すると決めました」
和さんは、将一さんと何度も話し合いを重ねた。
「最終的には、僕も卵子凍結に賛成しました。1回だけです。もし採卵できなかったり、人工授精がうまくいかなかったときには、子供を諦めて、自分の身体の治療に専念する。和とそうやって約束しました」(将一さん)
〈私は、死ぬときまで卵子凍結を決めたことを後悔しません。やれることは全部やったと思えるのと、そうじゃないのは、全然違うから。〉
──遠藤和さんは前掲著『ママがもうこの世界にいなくても』の中でこう綴っている。
卵子凍結を経て、和さんは2019年12月に将一さんと結婚式を挙げた。
2020年1月、妊娠が判明した。順調に妊娠生活を送っていた和さんだったが、5月にがんの卵巣転移が発覚した。状況は緊迫していた。
〈私も、赤ちゃんも、どちらも生きて会えますように。全然考えたくないけれど、もしものときには、娘を助けてほしい。遠藤さんにも前から伝えてある。どちらかを選ばなくちゃいけない状況になったら、赤ちゃんを優先してください。〉
2020年7月9日、和さんは命がけの出産に臨んだ。27週目、帝王切開だった。幸い母子ともに無事だった。しかし、その後の卵巣摘出手術では、産まれた娘の3倍近くの重さの腫瘍が摘出された。
和さんは、できるかぎり母親としての役割を果たしたいと願い、努力した。入院する前には期間中の離乳食や食事を作り置きし、自力で台所に立てなくなっても、ソファに臥したまま野菜をカットした。自分では食べ物を飲み込めなくなっても、家族が作った料理を口に入れて、味つけを仕上げた。娘の健診には、車イスで立ち会った。
和さんは、家族の助けを借りて厳しい闘病に立ち向かいながら、娘のために日記を書き続けていた。
〈彼女がもう少し大きくなって何かに迷ったとき、私の人生の選択が少しでも参考になったら、うれしいなと思う。〉
娘のために、自らの生きた日々を書き遺すこと──それは、和さんの心を支える作業でもあった。遠藤和さんがまとめた著書『ママがもうこの世界にいなくても』の「はじめに」で、夫・将一さんはこう記している。
〈2021年9月8日、14時11分。約3年の大腸がんとの闘病の末、妻の遠藤和は息を引き取りました。24歳でした。
彼女は心優しい両親と2人の妹に囲まれて、青森で育ちました。家族や友達、仲間、みんなから「のんちゃん」と呼ばれてかわいがられる、愛にあふれた女性でした。明るくて、押しが強くて、料理とデパコスが大好きでした。スーパーの店員さんに声もかけられないほど、めちゃくちゃ人見知りな一面もありました。
2016年10月4日、夜の本町。互いに仕事終わりだった僕たちが出会ったのも青森でした。6歳年下の彼女は初めて出会ったその日から、僕のことを好きになってくれました。いつも隣で笑っていて、僕や娘においしい手料理を食べさせたいと張り切ってキッチンに立ってくれました。和に大腸がんが発覚したのは、2018年です。そろそろ結婚の話をしよう、そう思っていた矢先のことでした。医師の先生方は口を揃えて若い女性の大腸がんは珍しいと言いました。なんで21歳の和が、と思いました。
彼女の夢はわが子を産み、母として愛情を注いで育てることでした。翌年に結婚してすぐ、僕たちは娘をさずかりました。奇跡のような出来事だと思っています。和は抗がん剤治療を一時的に休止して、お腹の赤ちゃんを守ると決めました。帝王切開のとき、1000gにも満たなかった娘はすくすく育ち、2021年7月9日に無事に1歳の誕生日を迎えました。和は食パンとヨーグルトで、赤ちゃんでも食べられるケーキを作って、お祝いをしました。
がんの発覚からほどなく、根治が難しいステージIVのがんだと宣告されたとき、和からは、普通の暮らしを続けるのが願いだと言われました。仕事を辞めて治療に専念したらどうか。そんな話をしたこともあります。でも、働きたいと言われました。和にとって仕事をすることは、料理をすることと同じぐらい、ありふれた幸せな暮らしを象徴するものだったのかもしれません。妊娠中も、食堂で働いていたほどです。
小学館の雑誌『女性セブン』から取材の申し込みがあったのは、次第にがんが進行して、アルバイトも難しくなってきた2020年の冬でした。雪の夜、記者さんが突然家を訪ねてきたので、とても驚いたことを覚えています。『笑ってコラえて!』やインスタで私たちのことを知ったということでした。人見知りの和は警戒し、最初は迷っていました。
でも、それから数か月の間、記者さんとメールや電話でやりとりをするうちに、万が一のときには娘に残せる記録になるかもしれないと思いました。和も同じように感じていたようだったので、2人で相談し、日記をもとにした定期的なインタビューを受けると決めました。結婚記念日の12月21日を目標に、娘のために本をつくることになりました。約1年、記者さん、編集者さんと一緒に、和は熱心に取り組みました。次第に症状は悪化し、長時間のインタビューに応えることが難しくなって。それでも、彼女は日記をつけて、手で書けなくなるとスマホに打ちました。和の闘病や育児の様子が雑誌に掲載されるたびに、多くの方々から励ましのメッセージや手紙をいただきました。
和は、治すための治療を続けていました。諦めずに治療を続ければ、絶対にがんは治ると、僕も和も信じていました。だから、僕はこの本を、死ぬことを目前にしたひとりの女性の、つらいばかりの闘いの記録だとは思っていません。和は、がんと闘いました。ただ生きただけでなく、ありきたりの幸せを手放さないように、一生懸命に生きました。正直な気持ちとは違うから、やり切ったねとか、立派な最期だったとか、そんなことは言いたくありません。どんなことをしても、生きてほしかった。
僕が仕事に出ている日中、点滴の管に取り囲まれる和を助けてくれたのは、青森から上京してきた2人の妹、遥ちゃんと結花ちゃんでした。この夏には、和の実家、櫛引家のご両親も東京に転居して、サポートしてくれました。僕らのもとを折々に訪ねて励ましてくれたり、コロナで会えなくても、遠くから見守ってくれた友人たちがいなければ、心の平静を保つことも難しかったと思います。
和は、9月2日まで原稿の打ち合わせを続けました。本のために必要な多くの作業を済ませましたが、すべてを終えることはできませんでした。ぎりぎりまで取り組むことができたのは、雑誌やテレビで和のことを知り、手紙やインスタで応援のメッセージを送ってくださった方々の支えがあったからです。ありがとうございます。
原稿をまとめる作業で、和の手が届かなかったところは、僕が代わりました。それから遥ちゃんと結花ちゃん、ご両親も協力してくれました。娘が将来、母である和の姿を知るための記録を残せたことに、ほっとしています。
和と僕が、欠点だらけの、どこにでもいるありふれた夫婦だと知りながらも、日々、温かい言葉をかけてくださったすべての皆さまに感謝します。
2021年11月 遠藤将一〉










