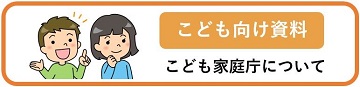smartlog.jpからの引用
怒ることで相手に対して自分を大きく見せたい
すぐ怒る人は、実はとても小心者である可能性があります。
本来はとても小心者にも関わらず、上司などの人の上に立つ立場となった場合、まずは「人から見くびられないようにしたい」という心理が働きます。
そのため、人に怒ることで自分は怖い人間であると認識させようとするでしょう。
すぐ怒る裏には、本来は小心者の自分を隠したい心理があるのです。
すぐ怒る人の心理2. 完璧主義で、自分の思い通りに物事が進まないと苛立つ
すぐ怒る人の中には、常に自分自身が正しい、自分が世の中のルールである、と考えている人もいます。
そのため、自分のやり方や考えと少しでも違った物事があれば、間違いであると判断して排除しようとするでしょう。
少しでも自分のやり方や思い通りに物事が進まないと、
自分を否定されたと思う心理があるため、すぐに怒ってしまうのです。
すぐ怒る人の心理3. プライドが高く、自分が常に正しいと思っている
すぐ怒る人はプライドが高く自分が正しいと思ってる
すぐ怒る人の中には、とにかく自分が大好きで大切と考えている人もいます。
そんな大切な自分自身が、誰かにバカにされたり、けなされたり、誰かよりも劣っていたりするのは耐えられないでしょう。
自分のことが大好きで、自分を傷つけたくないという、誰にも負けたくないプライドの高さから、自分の品位を守るために先手を打って怒っておこうとします。
プライドが高い人の原因や特徴とは。負けず嫌いを治す方法まで解説!
タップすると移動します
すぐ怒る人の心理
日頃からストレスが溜まっている
そもそも怒るという行為は、何かに対して不満やストレスを感じ、それを排除するために感情を怒りで爆発させること。
日ごろから不満やストレスを解消せずにいると、積もり積もって常に不満やストレスを抱えている状態になり、いつでもすぐに怒る状態になってしまうのです。
誰これ関係なく当たり散らすすぐ怒る人は、何らかの不満やストレスと思っていることが考えられます。
すぐ怒る人の特徴|ちょっとしたことでキレる人の共通点とは
すぐ怒る人の特徴
近所にすぐ怒る男性がいて怖い、職場の上司がすぐ怒るので周りの雰囲気が悪くなってめんどくさい、など。
すぐ怒る人の特徴1. 執着心が強く、いつまでも根に持ち続ける
すぐ怒る人の中には、物事に対する気持ちの切り替えが苦手な人もいます。
いつまでも過去の失敗や失態を引きずってしまうため、気持ちがイライラして怒ってしまうのです。
例えば、誰かのミスによって自分の評価が落ちてしまったとしたら、いつまでもそのことを根に持ち続けるのも特徴。
何かがあった時には「あの時お前のせいで自分の評価が落ちたんだ」と過去をぶり返して、いつまでもネチネチと怒るでしょう。
すぐ怒る人の特徴
理屈っぽく自分の意見を人へ押し付けやすい
すぐ怒る人の中には、自分の意見は絶対に正しいと信じて疑わない人もいます。
もしも自分の意見を曲げたり、意見を聞かなかったりする人が現れたら、自分の意見を押し付けるために全力で怒るでしょう。
職場の上司でも、今までのやり方を変えようとしたらいきなり怒鳴られた、という経験をした人も少なくありません。
上司にとっては、今までのやり方が一番正しいと信じていて、それを他人に押し付けるためにすぐに怒るのです。
すぐ怒る人の特徴3. 何事に対しても熱しやすく冷めやすい
すぐ怒る人は熱しやすく冷めやすい
感情の起伏自体がとにかく激しく、すぐ怒るけれどもすぐに忘れる、という人がいませんか。
とにかく感情的なため、その人はちょっと気に障ることがあればすぐに怒りますが、逆に嬉しいことがあればすぐに笑顔になりますし、悲しいことがあれば涙してしまうかもしれません。
子供並みに何事に対しても熱しやすく冷めやすいため、すぐに怒ってしまうのです。
熱しやすく冷めやすい男女の特徴10選|飽き性な性格を改善する3つの方法とは
感情の起伏が激しい人の特徴&原因|気分に波がある男女が喜怒哀楽をコントロールする方法
タップすると移動します
すぐ怒る人の特徴4. 神経質で細かい部分までケチをつけてしまう
「どうしてこんなところまで気が付くのだろう」と思うくらい、何事にも細かくて神経質な人。
神経質な人は、人が気にしないところまで気になってしまうため、どうしても他の人よりも気持ちがイライラしやすい気質を持っています。
例えば、書類のファイルの順番がバラバラだったとします。おおらかな人は全く気にしませんが、神経質な人は気にしてしまい、イライラしてすぐに怒りやすい状態になるのです。
神経質な人の特徴とは|細かい人にめんどくさい・うざい・疲れると思ったときどうする?神経質な人の特徴とは|細かい人にめんどくさい・うざい・疲れると思ったときどうする?
神経質な人の特徴から神経質であるメリット・デメリット、改善する方法を解説!また、周囲にいる場合の付き合い方もお届けします。
すぐ怒る人の特徴5. せっかちな性格ですぐに結論を求めようとする
身近に「早くして!」とすぐに怒る人はいませんか。せっかちな性分の人は、とにかく早く結果や結論を出して安心したい、という心理から人を急かします。
そのため、相手がもたついていたり、スムーズに物事が進まなかったりするとイライラして、怒りが爆発するのです。
例えば、職場でも大切なお客様にお茶を用意している横で「お客様に失礼があってはいけない」という心理からイライラし、「早くお茶を出して!」とすぐ怒ってしまうでしょう。
せっかちな人のあるあるな特徴とは?
仕事などでせかせかしてる人への対処法も解説せっかちな人のあるあるな特徴とは?仕事などでせかせかしてる人への対処法も解説
せっかちな人の心理やあるあるな特徴を解説すると共に、せっかちな人がやってしまう注意点を解説していきます。
すぐ怒る人の特徴6. プライドが高く、冗談を真に受ける
すぐ怒る人はプライドが高く冗談を真に受けやすい
生真面目な人は比較的すぐ怒る人も多いです。これは、物事を真正面からしか捉えられない視野の狭さと、自分がいつでも一番正しいというプライドの高さを併せ持っているからです。
飲み会の席などで冗談を言われたり、からかわれたりしたとしても、冗談と受け取れず自分が否定されたような気分になるため、すぐに怒るでしょう。
すぐ怒る人の特徴.
論理的思考が苦手で、感情に大きく左右されやすい
常に冷静沈着な人は、論理的に物事を考えているため感情で行動しようとすることはありません。
一方で感情の起伏が激しい人は、論理的に考えるのではなく逆に感情の赴くままに行動してしまうため、すぐに怒ったり泣いたりと感情的になってしまうでしょう。
仕事上で何か失敗した人がいれば、とにかく失敗をフォローするのが先決。ところが、すぐ怒る人は失敗をした人を責めることに注視してしまうでしょう。
すぐ怒る人の特徴8. コンプレックスや劣等感を抱えている
人は誰でも自分が可愛いと思いますよね。特にプライドが高い人やナルシストな人は、自分可愛さ故に人一倍傷つくことを恐れています。
さらに、可愛い自分を傷つける要素であるコンプレックスや劣等感はひた隠しにしようとします。
もしも誰かが自分のコンプレックスや劣等感に触れるようなことをすると、傷口をえぐられるようなショックを受けてしまうでしょう。
自分が傷つくのが怖いため、コンプレックスや劣等感に触れられないように先に怒って威嚇をするのです。
すぐ怒る人の特徴9. 意外と小心者で、内心では周囲からの印象を気にしている
すぐ怒る人は意外と小心者
本当は自分が怒られるのが怖い、周りからバカにされたり評価が落ちたりするのが怖い、と思っているのも、すぐ怒る人の特徴の1つです。
これは、臆病な自分を隠すために、自分よりも弱い立場の人にすぐ怒ったり怒鳴ったりすることで、自分の威厳や怖さを誇示しようとしているから。
逆に自分よりも立場の大きな人や、本当に怖い人には怒らないはずですよ。
すぐ怒る人の特徴
支配欲が強く、人よりも優位に立ちたがる
すぐ怒る人の中には、怒ることを人に自分の立場を誇示したり、マウントを取ったりする手段として用いている人もいます。
人よりも優位に立ちたがりますが、仕事で成果を出せなかったり、他の面で勝てる要素がなかったりします。
どうしても自分の立場を保つことに執着してしまうから、すぐ怒る手段にしか出られないのです。
支配欲が強い人の特徴・心理・原因とは|自分の思い通りにしたい男女への対処法も解説!
怒りっぽい人になってしまう主な理由や原因
怒りっぽい人は生まれ持った気質や性格だけでなく、実はその人自身を怒りっぽくさせてしまった理由や原因もあるのです。
どのような理由や原因で怒りっぽい人になってしまうのでしょうか。
具体的な理由や原因を知ることで、もっと怒りっぽい人とも上手に付き合えるようになりますよ。
怒りっぽくなる原因
周囲から怒られた経験がないため
ストレスをうまく発散できていないから
自己顕示欲が人よりも強いから
普段から人を見下しているから
怒りっぽくなる原因
今まで親や上司など、周囲から怒られた経験がないため
人は自分の経験から、「これをしたら人に嫌われるから止めよう」ということを学び、それを避けますよね。
ところが、すぐ怒る人は、すぐ怒るのは人に嫌われる行為であると分かっていないからこそ、すぐ怒ってしまう場合があります。
自分自身が親や上司などの周囲から怒られた経験があまりなければ、「怒られることはとても辛い事」というのが分からないため、怒ることに抵抗のない人になります。
怒りっぽくなる原因2
ストレスをうまく発散できていないから
どうにもならない慢性的なストレスが、実は怒りっぽさの原因になっていることがあります。
不満やストレスがたまると、寝不足や慢性疲労などの体の不調としても出てきます。さらに、不満やストレスの原因に対する憎しみや怒りもどんどん高くなってきて、気分もイライラして怒りっぽくなりますよね。
当然ストレスをためたままにしていると、より怒りっぽい状態が続くことになってしまうでしょう。
怒りっぽくなる原因3.
自己顕示欲が人よりも強いから
怒りっぽく徳仁は自己顕示欲が強い
自分がとにかく大好きで大切という人は大切な自分が傷つくのをとにかく恐れています。
普段は大好きな自分は素晴らしい人間だと周りの人にも伝えたいと思っているため、自分の成果や評判を誇示しています。
そんな大切な自分をおとしめたり、少しでもバカにしたりする人に対しては、大きな怒りをぶつけるでしょう。
「我が強い」とはどういう意味?
我が強い男女の原因・特徴・直し方を大公開!「我が強い」とはどういう意味?我が強い男女の原因・特徴・直し方を大公開!
今回は、我が強い男女の詳しい特徴から我が強くなってしまう原因、さらには我が強い人への対処法までご紹介していきます。
怒りっぽくなる原因4.
プライドが異常に高く、普段から人を見下しているから
プライドの高い人は、自分の立場や面子に強いこだわりを持っています。
自分の立場や面子をとにかく保つために必死なため、自分を上げるために人を下げることも日常茶飯事。
逆に、大切な自分の立場や面子をつぶされるような発言があれば、例え冗談だったとしてもすぐに怒るでしょう。
人は簡単に下げるにもかかわらず、自分が下げられるのは我慢できないのもすぐ怒ってしまう原因の1つでしょう。
急に怒る人は嫌われる?
感情的になりやすい人のデメリットとは
怒りっぽい人のデメリット
職場から日常生活まで、すぐに怒る人がいると男性、女性問わず雰囲気が悪くなってしまいますよね。
すぐ怒る人は嫌われる要素も多く、デメリットもたくさんあります。
もしも誰かに「あなたは怒りっぽいよね」と言われたときにチェックしたい、怒りっぽい人の3つのデメリットを紹介します。
すぐ怒る人のデメリット
周囲から怖いと思われ、距離を置かれてしまう
喧嘩やトラブルに発展する
感情がコントロールできない未熟な人と思われる
すぐ怒る人のデメリット1. 周囲から怖いと思われ、距離を置かれてしまう
人間が怒っている姿は、人に恐怖心を与えて周りの雰囲気も悪くなりますよね。さらに、口調も荒くなり物に当たったりすると、暴力的で粗野な印象も与えてしまい、何かトラブルに巻き込まれるかもしれないと思い、誰も近づきたくなくなります。
すぐに怒る人は、当然「怖い」と思われる回数が人よりも多く、さらに「近づかない方が良い」と思われてしまい、気が付くと自分の周りには誰もいなかった、ということも少なくありません。
すぐ怒る人のデメリット2. 他にも気が強い人が居た場合、喧嘩やトラブルに発展する
怒っている人が一人いるだけでも、周りの雰囲気は重く悪くなってしまいます。ところが、怒っている人に対してすぐに注意をするような気が強い人がいれば、この二人が衝突してしまう可能性が高くなります。
すぐに怒る人が実は小心者だった場合、誰かに注意されればそこで場が収まる可能性もあります。しかし、プライドが高かったり乱暴だったりすると、今度は喧嘩に発展してしまうかもしれません。喧嘩がヒートアップすると、大事故や警察沙汰になってしまうこともあるでしょう。
すぐ怒る人のデメリット3. 感情がコントロールできない未熟な人と思われる
怒りっぽい人は感情のコントロールが出来ない未熟な人と思われる
人間が社会に出て生活する上では、例え嫌な事や辛い事があっても表に出しませんよね。相手に不快な思いをさせないのも、社会人としての大切なマナーです。
つまり、仕事上のことですぐに怒る人がいれば、感情的になってはいけないという社会人としてのマナーが守られていない人ということになります。
大人や社会人として未熟だ、と思われるのもデメリットの一つです。
仕事上や職場など、すぐに怒る人と接するとめんどくさいと思ったり、付き合い方に悩んでいたりしませんか。