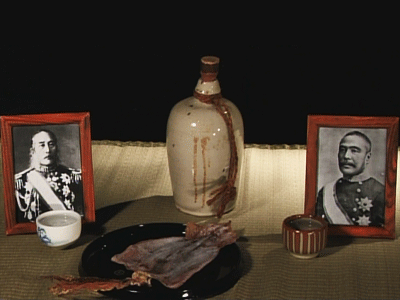仏教が誕生したインド社会は、カースト =ヴァルナ制度による厳しい差別社会であった。
人々の生活は、カースト=ヴァルナによっ て厳しく分断され、人間の尊厳も奪われていった。
そうした現実の中で仏教は、いのちとは 何か、人間とは何かを明らかにしていった。
いのちのつながりとその不可分性を大切にし縁 起思想を明らかにしていった。
差別は人と人を切り離していく。
いのちはつながりの中で存在するが、差別はそのことを 奪っていこうとする。
差別は人と人を分断し孤立させていこうとする。
人間とは何か、人間のいのちとは何か、私のいのちは他者のいのちとどのようにつながり、 無限のいのちとどのようにつながっていくのかといったことが大切な課題としてあったよう に思う。
それは、自己と他者、主体と客体、個人と社会の関係などの課題でもあると思う。
の尊厳と無我 人間は自立的・主体的存在であるとともに、他者とのかかわり、社会や環境とのかかわり の中で生きる存在である。
自己と他者、個人と社会は絶えずさまざまな緊張関係を生み出し、対立し葛藤しながら展 開していく。仏教は主に自己の側から他者や社会とのかかわりを見ていった。
自己の側の煩 悩やエゴイズム(利己主義)を主に課題としていった。
そして「我執」から解放された「無我」 の中に救い・解放を見ていった。
仏教の生命観
仏教の生命観と人権思想
仏教はいかに人権に関わるか
山岡政紀 書評集
〔書評〕『新版 日蓮仏法と池田大作の思想』 松岡幹夫著/第三文明社刊/2018年7月3日 発行/定価1400円/ISBN 978-4-476-06236-6 C0010
創価学会を「哲学」として見る視点
創価学会インタナショナル会長池田大作氏(以下、池田会長)は、1960年に創価学会第三代会長に就任して以来、60年近くにもわたり創価学会の活動を指導してきた。
その間、おびただしいほど多くの言説を著し、『池田大作全集』は既に150巻にも及んでいる。
ライフワークと定めた小説『新・人間革命』も去る2018年9月8日に全30巻の連載がようやく完結を見たところである。
池田会長は仏法者として日蓮の御書(遺文)や法華経など仏法哲学に関する講義を多く著述しているほか、歴史家トインビーをはじめとする世界の識者との対談、ハーバード大学をはじめとする世界諸大学での講演、平和・文化・教育をテーマに世界に発信する提言などが世界に多大な影響を及ぼしてきた。
そのいずれにおいても、仏法の生命哲学を普遍的な言葉に置き換えて現代の哲理に昇華して語っている。こうした池田会長の言説に触れたことを契機として池田会長との出会いを熱望し、実際に会見を果たした人々のなかには周恩来、ゴルバチョフ、マンデラといった世界各国の指導者も名を連ねている。
しかしながら日本国内においてはこうした池田会長の言説に対してまともな評価がほとんど行われていない。
ゴルバチョフ氏は2007年に来日した際、「日本人は池田会長を過小評価している。それは間違っているのではないか」、「池田会長とは対談集も発刊し、世界で読まれています。皆さんは、その対談集を読まれたのですか」と発言している。
その場にいた財界人たちはこの言葉に驚いたというが、実際に会って意気投合し、対談集まで出しているゴルバチョフ氏から見れば、なぜ日本人は池田会長の思想を知ろうとしないのか、対談を読もうともしないのかと驚いたことだろう。
かつて外交官としてゴルバチョフ氏と池田会長の出会いの場に関わり、それ以来、池田会長のファンになったと公言して憚らない作家・佐藤優氏は、講演のなかで「日本の社会には創価学会タブーがある。
創価学会の悪口であればどんなめちゃくちゃなことでも書けるが、創価学会の平和への貢献や池田会長の功績を書くとすぐに叩かれる」(佐藤優(2018)より、要旨)と述べている。
さらに日本の宗教学において、伝統的な仏教宗派に対してはその教理の「内側の」視点に基づく宗教哲学的な論考が見られるものの、明治期以降に成立したいわゆる新宗教に対しては教団の形成や社会との関わり等について「外側の」視点から分析した宗教社会学的な論考が大半である。
創価学会もまたそれらの新宗教の一つと見なされているうえに、排他性を持った教団との認識に基づく批判的な分析が多くを占め、創価学会の哲学の本質を「内側から」理解しようとする論考はいまだに希少というのが実情である。
池田文献への学術的アプローチ
前置きが長くなったが、こうした実情への問題意識が執筆の動機づけとなっていることは、本書『新版 日蓮仏法と池田大作の思想』を評するうえで不可欠な文脈なのである。
中国では北京大学を筆頭に20を超える諸大学で池田大作研究所が設立されるなど「内側」視点の池田思想研究が拡がりを見せており、その潮流は欧米にも拡大しつつある。
その一方で日本では池田会長の言説を学問的に整理し、分析し、その言説が持つ仏教哲学としての意義を正面から論じた研究が依然として少ない。
今後、日本における池田思想研究が興隆しゆくための先鞭となることを意図して書き起こされたのが本書である。
本書の著者松岡幹夫氏はかつて日蓮正宗大石寺宗門に僧籍を置くも、いわゆる第二次宗門問題の際に宗門を批判して離脱した人である。
宗門離脱に際しては大石寺の僧侶に顔面を殴られたとの逸話もある。怒号を浴び、暴力を振るわれてまで自らの信念を貫いて長年所属した宗門を離脱したというのだから腹が据わっている。
それこそは、いっさいの妥協を排して日蓮仏法の本義に忠実に生きようとした誠実な信仰の発露であったことを同氏はこれまでも度々述懐している。
氏はその後、本格的な学問の手法を修めるべく、東京大学大学院に進んで博士号を取得し、現在は大学教授として教鞭を執り、今日に到る。
本書には池田思想に対して学問的にアプローチするための研究手法が採られている。
その特徴の第一は池田会長の言説に忠実に基づいて考察している点である。
おびただしい池田会長の言説のテクストを収集・整理し、そこから解釈や一般化を行っている。
この点は文芸研究や歴史研究に求められる文献重視と共通の手法である。
第二の特徴は、そうして収集した池田会長の言説を表面的に捉えるのではなく、その理念の元となっている日蓮仏法の法理に淵源をたどって考察している点である。
つまり、池田会長が仏法の哲理を一般的な言葉へ普遍化した言説を、日蓮仏法の言葉へと再解釈しているのである。
このことがまさに本書の特徴である池田思想の「内側の」視点に迫る哲学的アプローチの中核にほかならない。
池田会長の言説は時代に即応した展開をしてはいるものの、その本質は約60年間全くぶれることなく一貫している。
それは池田会長が日蓮仏法の法理に一貫して忠実であり、その基軸がぶれないからであろう。
ゆえに池田会長の言説を日蓮仏法へと再解釈する作業は、池田会長の真意を確認するうえで重要な作業となる。
池田思想における「すべてを生かす」とは
本書は、序章「創価学会研究の現状と課題」、第一章「池田思想の五つの特徴」、第二章「池田思想に対する偏見を正す」、第三章「仏教哲学と池田思想」、第四章「現代仏法と池田思想」、第五章「人間主義の宗教」の全6章から成る。
第一章では池田思想の五つの特徴が記されている。これは池田会長が日蓮仏法を社会哲学としてどのように展開しているかをその言説をもとに整理したもので、①生命の復権、②自由自在の主体性、③すべてを生かす、④変化の信仰、⑤智慧に生きる、以上の五項目である。それぞれを端的に要約すると以下のようになる。
①生命の復権。
西洋近代の理性信仰に代わって、理性だけでなく、感情、直観、欲望等も含む全体的生命に尊厳を見出そうとする。
②自由自在の主体性。理性よりも根本的な生命次元の主体性の回復により、何ものにも囚われない自由自在の生き方を勧奨する。
③すべてを生かす。
根源的な主体性に基づくことにより、生死、善悪、苦楽など、二律背反的に現れる現象のすべてを無駄なく生かしていく。
④変化の信仰。人間が自身の宿命を真正面から受け止め、それを転換しゆく「人間革命」の可能性を信じ、そこに人間生命の尊厳観を見出す。
⑤智慧に生きる。個人の幸福と社会の繁栄が両立することを目的として、そのためには現実に即したあらゆる智慧を柔軟に生かしていくべきであるとする。
このうち、③「すべてを生かす」が特に繰り返し言及され、本書全編を通じてのキーワードとなっているので、ここを重点的に紹介したい。「すべてを生かす」は総合的概念で、この小節では池田会長が多面的に展開した池田会長の言説11件が典拠と共に引用されている。それらをさらに整理すると次の4項目に整理できる。各項1件ずつ引用を再掲する。
①人生のあらゆる経験を幸福境涯の確立のために生かす。
「仏界が基底の人生は、過去・現在の九界の生活を全部、生かしながら、希望の未来へと進める」(全集30-423)。
過去・現在のあらゆる苦難を未来の幸福のために生かしていく道を示している。
②すべての人を掛け替えのない人として尊重し、生かす。「あらゆる人を活かしていくのが、仏法」(全集97-369)。
人種、国籍、性別、社会的地位、宗教等、あらゆる外的側面を除去した生活者としての民衆をすべて尊極と捉え、生かす。
教育の根本精神にも通じる。
③あらゆる思想を生かす。
「歴史上の、あらゆる偉人の英知も(中略)現代に活かし、実生活のうえに活かし、価値創造していくことができる」(全集137-260)。
東西の万般の思想、哲学、宗教を活用しながら、社会の繁栄のために活かす。
④仏法の八万法蔵をすべて生かす。
「仏法では『序分・正宗分・流通分』、また『要・略・広』等と説きます。そのなかに、一切の知識、一切の善論を包含し、時に応じ、状況に応じて、最も価値的に表現するわけです。
大海のごとく、『すべてを生かす』のが仏法です」(聖教96.4.25)。
あらゆる一切経が法華経を説くための準備や法華経を広めていくための補助としての役割があって生かされるとする。
①~③は日蓮仏法の法理を普遍的な言葉で展開したものである。
そして、④が日蓮仏法における「三分科経(序・正・流通)」(注1)をかみ砕いて示したものである。日蓮の遺文「観心本尊抄」には、より本質的な「五重三段」(注2)の法理が展開されている。
詳細は略するが、要は根本の成仏の法である文底下種の法を中核に据えれば文上の法華経本門寿量品も生かされ、さらには法華経本門だけでなく迹門も生かされ、つまるところ法華経だけでなく爾前経や涅槃経も生かされ、八万法蔵の一切経すべてが生かされるという法理である。
そして、これを現代的に普遍化して展開したのが③と位置づけられる。なお、①は「煩悩即菩提」(注3)、②は「十界互具」(注4)の現代的表現である。
仏法そのものが全体包括主義的な思想であり、現象面の差異を乗り越えて本源的な法理への合一を目指す志向性が一貫しているため、どの部分を取っても「すべてを生かす」という全体包括的な一つの概念で表現することができる。
池田思想における「すべてを生かす」は、③に「東西の万般の思想、哲学、宗教を活用しながら」と記したように、他の宗教との対話姿勢も含まれている。本書にも池田会長の下記の言説が引用されている。
「仏教徒である前に、人間である。イスラム教徒である前に、人間である。キリスト教徒である前に、人間である。対話を通して、人間性という共通の大地に目を向け、友情が生まれれば、そこから互いの長所も見えてくる。学び合おうとする心も生まれるのだ」(名言100選120)
「仏教であれ、キリスト教であれ、イスラム教徒であれ、どの宗教も「生命の尊厳」を説いています。その共通の基盤の上に立って、人類の平和のために対話し、協調していくことは、宗教の当然の使命です」(全集141-400)
このことは本書では創価思想の排他性のイメージに対する反駁として特に強調されている。
創価学会・日蓮仏法は排他的か?
創価学会が日本社会で批判される理由は排他的、攻撃的、独善的とのイメージにある。
それは戸田第二代会長時代(1951~58)から池田第三代会長時代初期(1960~1970頃)までの間に強力な布教拡大が遂行された過程で他宗教の信者を大量に改宗させたことで他教団からの批判を招いたことや、一部の会員に強引で感情的な折伏があったことも本書で事実と指摘されている(p.94)。
しかし今日、聖教新聞を開いても他宗教を批判するような言辞はいっさい見られず、それどころか、平和、人権、環境などの社会的テーマを扱った啓発的な記事では、学会内外の専門家や有識者、あるいは他団体関係者のコメントを掲載するなど、社会貢献、社会との融和を目指す編集方針が明確となっている。今日の聖教新聞を見る限り、閉鎖的で排他的な印象は全くない。
ただ、このように現象や印象の次元で論じるのでは皮相的である。
本書は、そもそも日蓮仏法は排他的宗教なのかどうか、また日蓮仏法を語る池田会長の言説は排他的色彩を帯びていたのか、といった本質的な議論を文献学的、かつ哲学的に論じており、そのことが本書全編を貫く主題ともなっている。
これについて著者松岡氏は「日蓮仏法の折伏は決して排他主義ではない。
じつはその反対であり、排他性と戦うことが折伏なのである」(p.91)と述べている。鎌倉時代当時、浄土宗の僧・法然は『選択集』で法華経について「捨閉閣抛」(捨てよ、閉じよ、閣け、抛て)と誹謗した。
真言宗においては平安時代の開祖・空海が残した『十住心論』等で法華経を「戯論」と断じたことに依拠して法華経を排撃していた。
日蓮はこれらの諸宗による法華誹謗から法華経を護るための護法の戦いとしてその誤りを指摘し、『立正安国論』を著して幕府に上呈した。
つまり、日蓮の折伏とは護法の戦いだったのだという。
たしかに日蓮遺文における浄土宗や真言宗に対する折伏は法華誹謗の罪を糾弾するものであって、それら諸宗が依拠する観無量寿経や大日経そのものを否定してはない。
むしろ「すべてを生かす」の④で述べているように、それらは法華経の真実を部分的に補佐するものとして日蓮遺文の随所で肯定的に引用されている。
法華経は一切衆生の絶対平等と永遠の生命を説ききった経典であり、そこにはあらゆる人々の生命の尊厳を根本から見つめ、生かしきっていこうとする究極の人間主義が説かれている。
ゆえに日蓮は法華誹謗が厭世思想や差別思想など、何らかの形で生命の尊厳に対する毀損を含むものと捉え、人間主義を守るために諸宗の法華誹謗と闘ったのである。
世界の宗教紛争に見られる排他主義は、ナチス・ドイツのホロコーストに象徴的に示されるように他宗教の教徒を迫害の対象にするなど、人間性と生命の尊厳を毀損し、人間主義の対極にある人間疎外と言えよう。
いっぽう日蓮仏法における折伏は慈悲の行為であることを、本書では戸田第二代会長の言葉を引用して述べている。
「折伏は人類の幸福のためであり、衆生済度の問題であるから、仏の境涯と一致するのである。
されば折伏をなす者は慈悲の境涯にあることを忘れてはいけない。
けっして宗門論争でもなく、宗門の拡張のためでもない。
御本仏大聖人の慈悲の行を行ずるのであり、仏にかわって仏の事を行ずるのであることを忘れてはならない」(戸田全集3-99)
そうしてみると、創価学会員も隣人を幸福にしたい一心で折伏を行じているのであり、相手が他宗の信者であることを尊重したとしても、現に今苦悩に直面しているであれば、自らの信仰の幸福境涯と確信をもってその人と共に幸福を築きたいと願い、その思いを語ることは排他主義とは言えまい。
ここで、牧口常三郎氏が『人生地理学』で提唱した「人道的競争」が想起される。
本書でも加藤弘之氏の説を引いて、人道的競争は利他的精神の拡がりを意味するとして、その意義を主張している(p.244)。
つまり、一人の人を誰が真っ先に幸福にできるのか、各宗派が良い意味で競えばよい。
そのように個人救済のレベルでは健全な人道的競争を行いつつ、同時に教団としては平和や人権問題のために融和し協調することは矛盾なく両立できるはずである。
ただし先述のように、本人の意思に反して強引に入信させようとしたり、あるいは他宗教を信仰しているというだけで人格攻撃したり、現在は幸福であるのに不幸になると脅迫したりするのは人間主義とは言えず、日蓮仏法の本義に反する。
それは、自分は正しい法を知る者として高みに立ち、相手を無知と断じることから来る人格否定であって、ある種の差別思想となるからである。
もし、そのような折伏がかつての創価学会で行われていたのだとしたら、その歴史は創価学会が自らの取り組みと他宗教との誠実で真摯な対話を通じて乗り越えていかなければいけない。
それ以上に本書が主張する論点は、池田会長自身は会長就任以降、日蓮仏法の精神のままに人間主義の指導方針を貫いていて全くぶれていないことである。
『新・人間革命』には人間主義の折伏のあり方をすべての会員にいかに浸透させていくかについて苦慮する池田会長の姿も描かれている。
「学会が大きくなるにつれて、指導が徹底されていないため、布教の際などに、極端なものの言い方をして社会の誤解を招くというケースが見受けられます。
一家のなかであっても息子や娘を指導しきれないことが多いのに、毎月、何万世帯という会員が新たに誕生しているのですから、やむをえない場合もあるとは思います。
しかし、私としては、みんなが理路整然と、道理に則って、納得のいく、折伏や指導ができるようにしたいと念願しています」(『新・人間革命』第7巻「文化の華」の章p.18)
今日においてそのような前時代的な折伏を行う創価学会員がほとんどいなくなったのは、池田会長の指導がそれだけ行き届き、教団として成熟してきたことを意味する。
今後、そうした過去の残像に起因する排他性の古い偏見を意識しすぎることなく、創価学会が平和のため、社会のために積極的に他団体、他教団とも交流していくことが期待される。
そう考えれば考えるほど、創価学会員の活動実態に現れる現象を「外側から」分析することよりも、池田会長が目指す理想、その日蓮仏法上の意味を「内側から」捉えることのほうがより重要であることが認識されるのではないだろうか。
その視点をもってはじめて創価学会の未来像も展望できるし、世界で受容される理由もまた見えてくるからである。
その道標を示した本書を高く評価するとともに、第二、第三の同種の論説が続くことを今後も期待したい。
注
1)三分科経
経典を三つの科段に分ける考え方。①「序分」=序説としてその経典が説かれる由来や因縁を明かす部分、②「正宗分」=その経典の中心となる本質的な教説の部分、③「流通分」=その経典の功徳を説き、後世においてその経典を受持し広めていくよう弟子に勧めた部分。
2)五重三段
『観心本尊抄』に示される五重三段とは、①釈尊の一切経、②法華経全体、③法華経迹門(前半)、④法華経本門(後半)、⑤文底下種仏法、のどのレベルにおいても序・正・流通の三分科経に立て分けられることを示したもの。正宗分の重要性を示す意味もあるが、序分・流通分もまた正宗分を補佐する役割から包摂される。つまり、法華経以外のすべての経典も生かされるとする考え方である。ただし、序分・流通分が正宗分を排除・否定してしまっては自己否定となる。諸宗派の法華誹謗はこれに当たるとして誤りを指摘したのが日蓮の折伏であって、日蓮は決して序分・流通分に当たる経典それ自体を否定したのではなかった。
3)煩悩即菩提
煩悩に覆われ、苦悩にさいなまれた凡夫の身のままで、内心の仏界を覚知し、菩提(=仏の覚り)の智慧を発揮して苦悩の執着から解放され、自在の境地を得られるとする法理。法華経迹門において地獄界の衆生である提婆達多が成仏の記別を得ることが煩悩即菩提を表現している。創価学会では煩悩即菩提の法理を通して、現実の苦悩と格闘する勇気や智慧のなかに真の幸福境涯があるとしている。
4)十界互具
十界とは十種の生命境涯を表したもの。①地獄界・②餓鬼界・③畜生界・④修羅界・⑤人界・⑥天界・⑦声聞界・⑧縁覚界・⑨菩薩界・⑩仏界。法華経迹門に至るまでこれらはそれぞれに隔絶された生命境涯として固定的に描かれていたが、法華経によって十界のどの衆生もそれぞれまた己心に十界の生命境涯を備えており、固定的ではないことが示された。このことを「十界互具」という。そのことのなかに、地獄から菩薩までのすべての衆生の生命に仏界の生命が備わっていることが含まれている。創価学会ではこれを民族、人種、社会的地位、職業、性別などの外面的要素をすべて超えて、あらゆる一切衆生が平等に尊厳的価値を有する存在であることを示す人間主義の法理として示している。