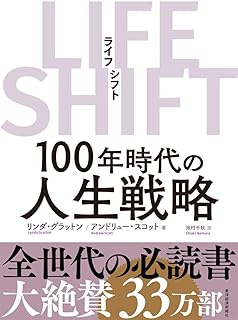野心家で屈折したエリート意識を持ち、世俗的な名声を求める面もあった「負」の顔をえぐり出している。
東京都立日比谷高校在学中に自己分析した「行動特徴」ノートや、大学2年の自殺未遂、夫人の心の病、さらには愛妻家で知られる江藤の「もう一人の女性」の存在など。
それらが、独自の文学世界が形成される背景として意味付けられる。
闘争心あふれる批評家は大岡昇平、大江健三郎さんらと論争を重ねた。
埴谷雄高、三島由紀夫ら、親しかった作家たちと後に離反するケースも目立った。
「小林秀雄に対しても、乗り越えるライバルだと思っていたのでしょう。江藤さんが影響を受けた人物や論敵を通して見ると、文学、論壇、ジャーナリズムの戦後史がよく浮かび上がってきます」
書きあげた後も、江藤は「複雑な人」だと実感した。
1980年代以降は「保守派」の論客のイメージが強く、文芸での活躍が薄れた。
没後、正当に評価されていないのを惜しむ。
「日米関係や憲法問題も<文学>の課題として本気で論じました。誤解されやすいが、面白い人です」と著者は述べる。
文・大井浩一さん
66歳で衝撃的な自死を遂げたのは20年前の1999年7月だった。
内容紹介
没後二十年、小林秀雄が後継者と認めた戦後を代表する批評家の決定的評伝! 「日本という国はなくなってしまうかも知れない」――「平成」の虚妄を予言し、現代文明を根底から疑った批評家の光と影。
二十二歳の時、「夏目漱石論」でデビューして以来ほぼ半世紀、『成熟と喪失』『海は甦える』など常に文壇の第一線で闘い続けた軌跡を、自死の当日に会った著者が徹底的な取材により解き明かす。新事実多数。
内容(「BOOK」データベースより)
「平成」の虚妄を予言し、現代文明を根底から疑った批評家の光と影―。没後二十年、自死の当日に会った著者の手による決定的評伝、遂に刊行!
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
平山/周吉
昭和27(1952)年東京生まれ。慶応義塾大学文学部国文科卒。出版社で雑誌、書籍の編集に従事した。
文芸誌「文学界」編集長に4月に就き、江藤の担当になって4か月目であった。
江藤の鎌倉の自宅を訪ねた当日のことで、当夜に自殺の報を聞き、「茫然となった」場面から本書は始まる。
現在、雑文家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)