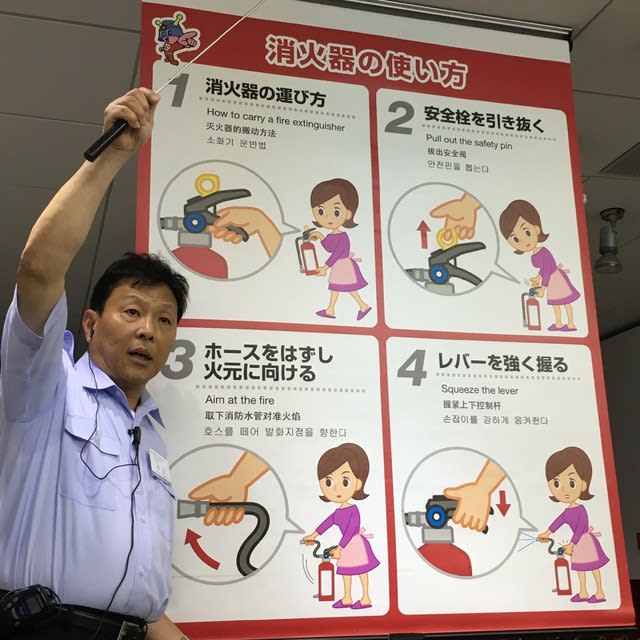JICA 中西部アフリカ幼児教育研修の一貫として、毎年東京おもちゃ美術館にて実施しています。
今年度は、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、コートジボアール、ニジェール、セネガル、
ガボン、ギニアの9カ国から計15名が来日。
中央または地方の視学官・教育官や、教育養成校の教師の方々です。

『アナログゲーム体験』では、どのテーブルでも大きな笑いと、悔しがる声が響き渡り、真剣に遊んでいる様子。
かえるを弾いてバケツに入れるゲームでは、いたるところで、空中落下するカエルが大量におり、捕獲するのがもう大変

身近な材料で自分だけの”おもちゃ”を作ろう!ということで、紙コップがパペット風に
おなじみ「ぱくぱく人形」に挑戦。独特の色使いやキャラクターを描かれるので、見ている側もとても楽しめます。

そして、東京おもちゃ美術館が推奨する木育について、赤ちゃん木育ひろばでの事例や、
木で育てる・木で育む という話しを、とても熱心に聞かれていました。
そして、フランスのブロック『KAPLA』や、プラスティック製のブロックなど、まずは自分が楽しむ、という体感を通して”遊び”の大切さを感じ取っていただいたようです。

また、日本の伝承遊び”わらべうた”を、お手玉や、自分の腕の広さの『マイあやとり紐』作りも体験。
昨年は「お・な・べ・ふ」がとても人気でしたが、今年はどうかというと…
あやとり紐で遊ぶ「糸ひけ ぶんぶん 豆引け がーらがら」が、大人気で写真を撮る時も、
「チーズ」ではなく「糸引けぶんぶん…」という人もいれば、「おなべふ」という人もいたり

歌いながら遊ぶことに、自然と体でリズムをとりアフリカンテイストが入った「わらべうた」はとても新鮮でした。

最後に感想として「今日、私達は子どもになりました。遊びの楽しみが感じられました。」と。
また、「昔の遊びを記録しておくなどの、まとまった資料がありません」という感想があり、
『でしたらなおさら、伝え続けていってほしい』、『大事なことを伝えることが”大事”』だと、日本わらべうた協会の田村理事(おもちゃ学芸員)もお話されていました。
絶対的貧困層の割合が他の途上国・地域と比較して高く、生活環境が厳しい国々では、幼児発達支援に関する政策を優先課題として、あげることができません。
また、専門の人材が不足している状況の中で、質の向上を一つの目的としている今回の研修にて、
東京おもちゃ美術館で体験したことが、お役に立つことを願いつつ、
みなさんと、またいつか何処かでお会い出来る日を楽しみにしています

はっち